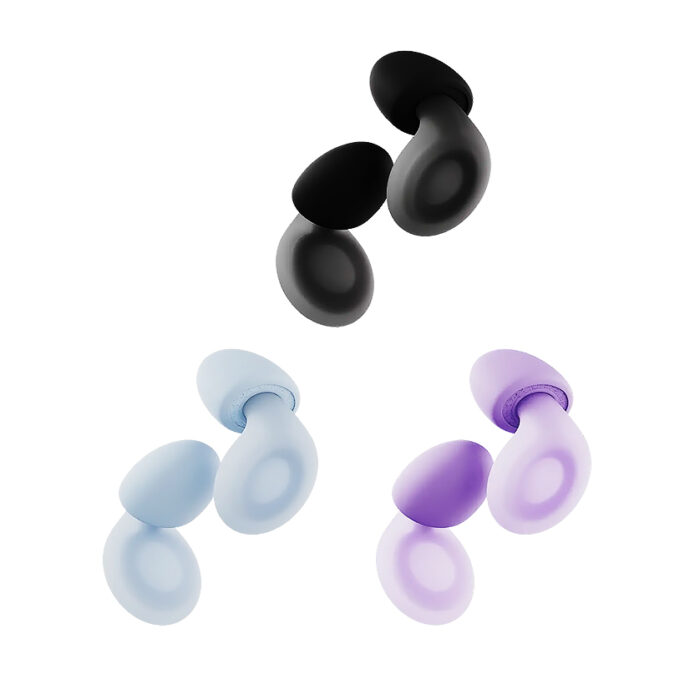子どもの脱毛はいつから?メリット・デメリットや年齢の目安を専門家が解説

“フェムケア”“フェムテック”という言葉を知っていますか?女性は毎月の生理や妊娠、出産、更年期などのイベントと共に体調の変化が起こります。ママの身体や心の変化を知り、正しいケアの方法を知ることで、家族の日々の幸福度をアップさせていきましょう!
助産師の石嶺みきさんによる最新“フェムケア”のコラム。今回のテーマは「脱毛」についてです。
脱毛は幅広い世代に広がっています
「脱毛」と聞くと、これまでは身だしなみを意識する大人の女性が行う美容施術というイメージが一般的でしたが、近年では男性の口ひげや胸毛の脱毛に代表される「メンズ脱毛」や、高齢者が自身の介護時に邪魔にならないようにと気遣って行う「介護脱毛」なども行われています。さらには小中学生が保護者と一緒に脱毛サロンや医療クリニックへ通う「キッズ脱毛」まで登場しています。
未成年のムダ毛に関する悩みは決して新しいものではありませんが、これまでは親から「まだ早い」とか「自然でいい」とか言われて、まともに取り合ってもらえないケースが多かったかもしれません。しかし、体毛の濃さにコンプレックスを感じる子どもは低年齢化してきており、友人関係や学校でのいじめ、引きこもりなどにも影響を及ぼすケースも出てきました。
脱毛サロンや医療クリニック側も、これまでは未成年はほぼ対象外としてきましたが、このように子どもたちの間でのニーズの高まりを受けて、子どもの肌や成長段階に合わせた「キッズ専用コース」を設けるようになってきています。
つまり、現代の脱毛に対する考え方は、美意識の高い大人のための美容行為から、年齢に関係なく、日常生活を清潔で快適に過ごすためのケアとして広く受け入れられるように変化してきているのです。キッズ脱毛は子ども版の身だしなみケアとして新しく定着しつつあるんですね。
キッズ脱毛が増えている背景
キッズ脱毛が増えている背景には、幼い年齢からSNSやYouTubeなどに触れることによって、「見た目」への意識が高まり、ルッキズム(外見至上主義)に影響されやすくなってきたことや、学校の制服や体操服などを通じて他人に肌を見せる機会が多いこと、さらに男の子も含めて「ムダ毛ケア=身だしなみ」の感覚が広がっていることなどが挙げられます。
私がこれまで聞いた中では、「まつ毛から下の毛は全部要らない」なんて言っていた男の子もいました。化粧品や美容クリニックのイメージキャラクターに男性のタレントやスポーツ選手などを起用した広告も、最近ではよく目にするようになりました。
キッズ脱毛のメリット・デメリット
キッズ脱毛のメリットは、体毛が濃いというコンプレックスを解消することのほかにも、毛の自己処理による肌トラブル(カミソリ負けや除毛クリームによるかぶれなど)の予防、成長期に合わせてケアすることで肌をきれいに保つことができることなどがあります。
逆にデメリットとしては、子どもの肌は大人よりも敏感なため、やけどや肌荒れのリスクが大人より高いこと、成長期はホルモンバランスの変化があるため、脱毛した毛が再び生えてくる可能性があることなどが考えられます。また、医療機関以外の脱毛サロンで施術を受ける場合は、万が一のトラブル時の対応体制を事前に確認しましょう。
キッズ脱毛は何歳から可能?
「キッズ脱毛は何歳からできるの?」というのは、保護者の方が最も気にする点のひとつですね。キッズ脱毛が可能な年齢についての正確な回答はありません。クリニックによっては6歳(小学生以上)から施術が可能なところもありますが、10歳以上を対象としているクリニックが多い傾向にあります。
施術自体はお子さんに施術希望のしっかりとした意志があり、施術中はじっとしていられることが前提ですが、ホルモンの影響を受けて脱毛した毛が再生してくるケースもあるので、検討する場合は、第二次性徴が終わる小学校高学年ごろからが良いのではないかと思います。
お子さんの肌や体に配慮しながら検討するようにしましょう
キッズ脱毛は見た目の悩みや清潔感をサポートするケアですが、成長段階の肌や体への配慮が最も大切です。お子さんが体毛を気にし始めたら、まずはお子さんの意志を確認したうえで、専門家にも相談しながら、選択肢の一つとして検討してみてもいいかもしれませんね。

次回は、皆さんから寄せられた「お悩み相談」にお応えします。
ナビゲーター
担当カテゴリー
美容・健康
助産師・看護師・栄養士 石嶺みき
助産師、看護師、栄養士。ミキズハウス助産院院長。株式会社FM BIRD所属。不妊治療中に献身的に励ましてくれた助産師に強い憧れを抱き、出産後に看護学校に進学。助産師専攻科を経て助産師資格を取得。卒業後は大学病院産婦人科外来・病棟に勤務し多くの出産に立ち会う。
その後、保健センター勤務に転じ、産後のメンタルサポートや妊娠SOS相談窓口、新生児訪問、乳幼児健康診査なども行う中で、フェムケア教育の普及活動を思い立ち独立。一般の方だけでなく、看護学校の教員や助産師、看護師などを対象とした講習会などを開講。現在は“全ての世代に、泌尿生殖器ケアを通して幸せになってもらいたい”という信念のもと、「フェムケア」「おちんちんケア(オムケア)」「思春期性教育」をはじめとする講演を広く行うなど、積極的に活動中。
「ぞうちんとぱんつのくに」原作・監修(2024年、KADOKAWA)