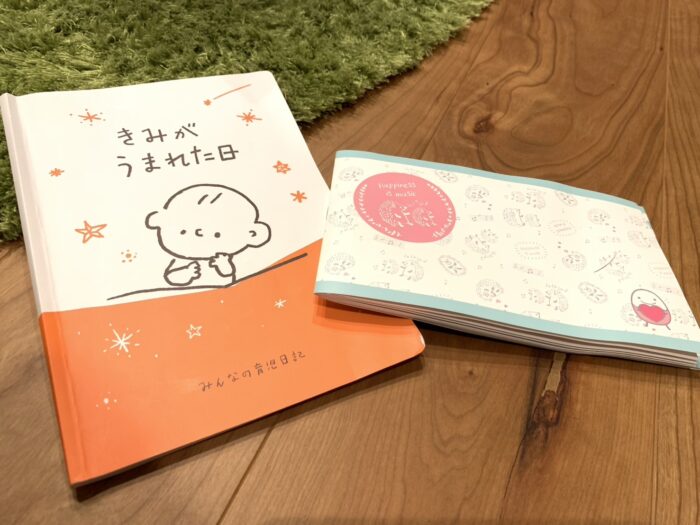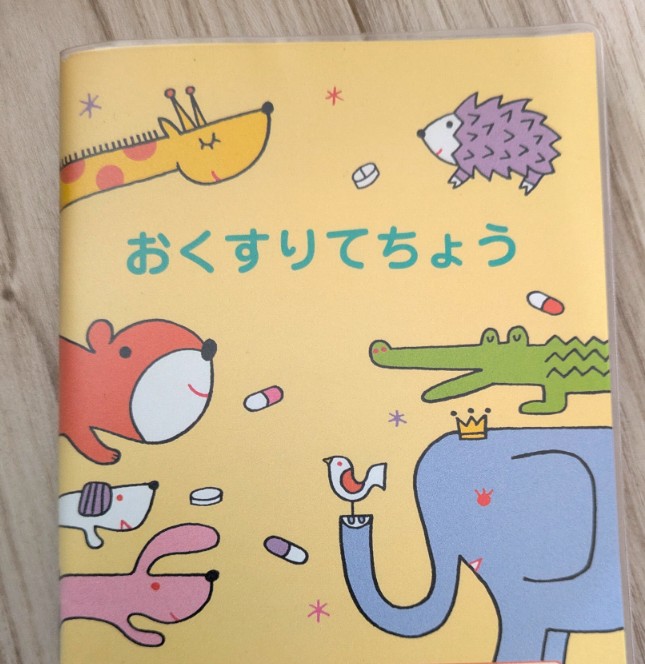更新 :
保育園のPTA役員をやったら、自分の仕事の価値が明確になった

多様性のあるコミュニティーで自分の力を再認識する

PTA役員募集は大抵、定員充足せずにババ抜きゲームになる
子どもを学校や幼稚園、保育園に通わせていると、多くの場合はPTAという組織に関わることになります。教育機関側で行われる行事などに対して、保護者側の支援が必要な時に活動を行う団体です。PTAを取りまとめるために、主に活動するメンバーとしてPTA役員が年度ごとに持ち回りで選任されます。
さてこのPTA役員、新年度に向けた時期になると募集が行われるわけですが、自発的な応募で定員が充足することはほとんどないようです。
最も大きい理由は「仕事が増えるから」となっています。それに加えて共働き家庭が多数派となっている現在では、PTA役員業務による追加負担はより敬遠されるようになっています。
そのため在籍期間中に最低1回は役員を経験することが暗黙のルールになっていたり、役員経験のない人を集めて地獄のじゃんけん大会が開かれることもあるようです。誰も欲しくないけれど誰かが抱え込まないといけない、トランプゲームのババ抜きのような扱いになっていることもしばしばあります。
PTA役員をやらないつもりが、急遽出番が回ってきた
この記事を書いているのは3人の子を持つ父親です。上の子2人は同じ保育園に通わせています。(末っ子は未入園、役員選任時は誕生前)子どもを通わせている保育園でも最低1回役員という暗黙のルールはありました。
一方で自発的に何年もPTA役員に立候補してくれる同学年の親がいたため、一番上の子では役員を求められることはありませんでした。2番目の子についても自分からやるつもりはなかったのですが、いろいろあって年度途中から急遽役員をやることになりました。
ここからは私が所属した保育園PTA役員会での経験談となります。
保育園のPTA役員の男女比は半々
PTA役員になってみて最初に感じたのは「男女比がほぼ半々」ということでした。保育園のPTAなので共働き家庭ということはあると思いますが、割と父親の参加率が高い印象でした。
保育園PTAの打ち合わせは最小限、オンライン会議主体で重要議題のみ集中討議

PTA業務が敬遠される大きな要因と思われる打ち合わせですが、私のケースでは無駄なく運営されていました。
まず定期打ち合わせはなく、行事の前だけセッティングされていて、平均すると1カ月に1回程度でした。打ち合わせ自体もオンライン会議ツールを利用して自宅で済ませることができました。
対面になると共働き家庭では仕事の調整、家事育児の前倒しもしくは後ろ倒しなどが出てきて非常に厄介なので、オンラインで済むとかなり負担が減ります。そして打ち合わせは事前に議題を決めて集中的に話し合いが行われていました。
打ち合わせの進行役や書記も割り振られていて議事録も作られ、フォローアップもしやすくなっていました。進捗はチャットで共有されるので、手の空いた時に確認して対応する形でした。これらは仕事での会議の進め方と同じで、さすが共働き家庭の集まりという感じでした。
ちなみに、行事の飾りつけや保育園の先生の手伝いなど、オンラインで対応できないものは手の空いた人で融通して行いました。
保育園のPTA役員をやったら、自分の仕事の価値が明確になった
私がたまたまやることになった保育園PTAが思いのほか取り組みやすかったことについて書いてきましたが、一番の経験がこれです。
通わせている保育園が同じでも、親の仕事は多種多様です。サービス業や公務員などの業種もそうですし、職種も異なってきます。普段の生活の中では直接の繋がりがない人が集まって、PTA業務を成功させるために協力します。そこで打ち合わせの場では、取りまとめが得意な人や細かいチェックが得意な人など、役割分担ができてきます。
そのような場に参加して感じたのは、「自分が仕事で培ってきた能力が役に立つ」ということです。普段は仕事で当たり前にやっている仕事が、実は世間一般では当たり前ではないという場面が出てきます。こういう経験は保育園PTAに限らず、仕事以外のコミュニティーに積極的に参加することで得られると知る、いい機会になりました。
この記事を書いた人