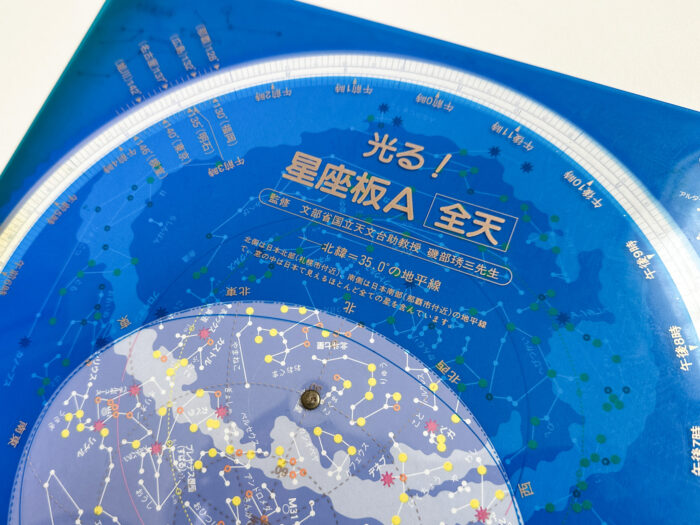公開 :
“スマホ育児”って本当にいけないの? 我が家が実践している上手な付き合い方5つ

「スマホばっかり見せてるとダメよ」「子どもが言葉を覚えなくなるって聞いた」そんな声に、心がチクッとした経験ありませんか?かくいう私も初めての育児に奮闘する中で、スマホに頼ったことが何度もあります。でも、ふと“本当に全部ダメなの?”と思い、上手な付き合い方を模索しました。今は「スマホ=悪」ではなく、「どう使うか」が大切な時代。本記事では、我が家で実践している即実行可能な“罪悪感ゼロ”のスマホ活用法を、5つご紹介します!
1.“ながらスマホ”はやめて、「一緒に見る」が鉄則
つい家事の合間に「動画でも見せておこう」と、スマホを子どもに渡してしまいがちですよね。でも、これが続くと子どもは“スマホ=1人で没頭するもの”という認識に…。
我が家では、“スマホは一緒に楽しむもの”というルールを作成。動画を見るときも、「これ見てみようか」「このキャラ知ってる?」と声をかけ、一緒にリアクションを楽しみます。すると、ただの動画がおもちゃのような役割を果たし、コミュニケーションツールに早変わり。親子の会話が自然と増えました。
2.タイマーで“時間を見える化” 子どもと約束してからスタート
子どもは時間の感覚がまだあいまい。つい「もっと見る!」とダラダラ見がちに。そこで我が家は、スマホを使う前にタイマーをセットすることを習慣化しました。
「今日は10分ね」と声をかけて一緒にスタート。タイマーが鳴ると「おしまいの合図だね」と一緒に画面を閉じます。最初はぐずることもありましたが、回数を重ねるうちに“時間になったら終わる”という感覚が身につき、今では自分で「ピピッてなったらバイバイする」と言ってくれるように。ルールを共有するって大事ですね。

3.子ども専用アカウントで“安全に興味を広げる”
YouTubeや知育アプリを利用する場合は、必ず子ども専用アカウントを作ります。おすすめ動画が自動表示される仕組みは興味の幅を広げる一方で、不適切なコンテンツに出会うリスクもあるためです。
子ども向けアプリやキッズモードを活用すると、動画のジャンルが狭まり安心できます。うちの子はアンパンマンが好きなので、キャラクター名を覚えたり、セリフを真似したりするのがブームになりました。興味のタネを広げるきっかけにもなります。
4.親の“スマホとの向き合い方”を見直す
子どもに「スマホばっかり見ないの!」と言いながら、自分はSNSをチェックしていた…。そんな矛盾、ありませんか?私自身も、自分のスマホ依存に気づいて反省した1人です。今は子どもが起きている時間はスマホをテーブルに置いたままにする、通知はオフにするなどちょっとした工夫で、“ながら見”を減らすよう意識しています。子どもは親の姿をよく見ている。だからこそ、自分の行動を見直すことがスマホとの上手な付き合い方への第一歩なのかもしれません。
5.“画面のあと”が本番。リアルな体験に広げていく
スマホで動画やアプリを見たあとは、リアルな世界につなげてあげる工夫をしています。例えば、動物の動画を見たあとに「図鑑で見てみようか」と誘導したり、絵本アプリで読んだ話を「ママにも読んで!」とリクエストしたり。スマホでのインプットを実体験につなげると、記憶に残るだけでなく親子の会話もぐっと豊かになり楽しめるようになりました!
我が家なりの「ちょっといい使い方」を見つけてみて
育児は正解がないからこそ悩むことばかりです。ゆえに、スマホとの付き合い方も「本当にこれでいいのかな…?」と迷いながらの日々です。でも、我が家なりのルールを見つけてからは、少しだけ気持ちが軽くなりました。
“完璧じゃなくていい”、その代わり“ちょっと工夫してみる”。それだけでも、スマホは忙しいママたちの味方になってくれるはずです!
この記事を書いた人