公開 :
学年代表にも選ばれた!わが家流の読書感想文サポート術を公開します
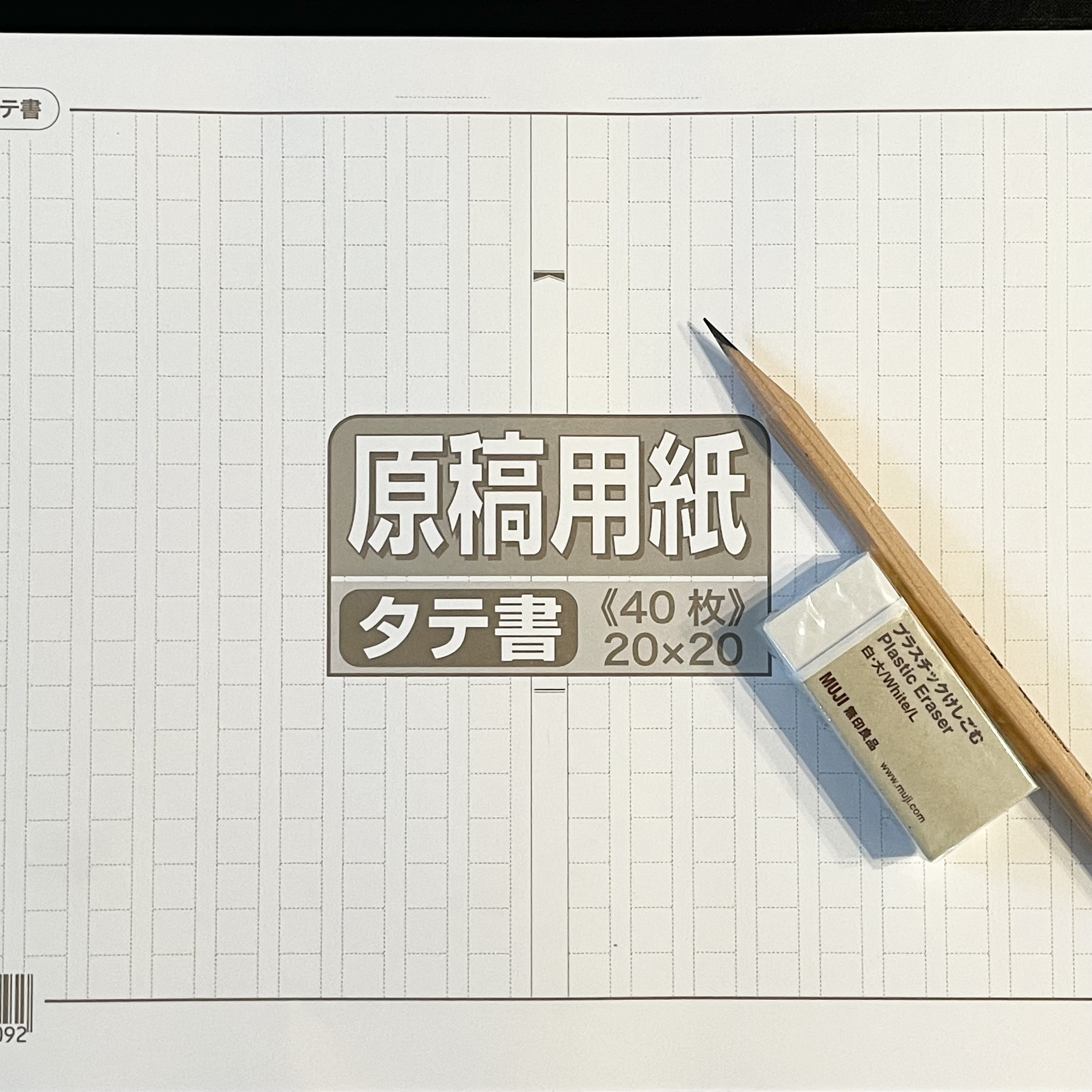
夏休みの宿題がやってきました~!ポスター、お習字、標語…いろいろある中で、一番の大物は「読書感想文」と感じる方がたくさんいるのではないでしょうか。
我が家は、長い夏休みにダラダラ生活に慣れないように毎年読書感想文に取り組んでいて、学年代表に選ばれたこともあり励みになっています。今年初めて読書感想文に取り組む親子もいらっしゃると思うので、我が家がやっている取り組み方や、私のオススメポイントをご紹介しようと思います。
絵本の選び方は?
我が子は好きな本で好きなように書きたいという意思があるので、図書館に行って自分と関係がある絵本を選んでいます。
<長男の場合>
幼稚園児の時に借りた「 くすのき しげのり」さんの絵本が大好きで、『ぼくのジィちゃん』という絵本で感想文を書きました。
出版社:佼成出版社 
出版日:2015年3月30日
定価:1430円
<長女の場合>
ミニトマトが大好きなので、トマトの絵本を探しに図書館へ行きました。トマトの絵本は思っている以上にたくさんありましたが、『おやすみなさい トマトちゃん』という絵本をたくさんある中から選んでいました。
出版社:きじとら出版 
出版年月日:2018年7月(7月10日初版発行)
文:エリーザ・マッツォーリ
絵:クリスティーナ・ペティ
訳:ほし あや
定価:1540円
一緒に読んでみよう
読書感想文の書き方の本が毎年たくさん出版されているので、ご存知の方も多いかもしれませんが、まずは一緒に読むことからスタート。
このとき大切にしているのは、読みながら「子どもの表情」を見ること!
聞いているだけでも面白い場面では微笑んでいたり、怖い場面では強張った顔をしていたり、感情の変化が表情に出てきます。それを見逃さないことが大切だと思います。
読み終えたらどうする?
読み終わったら「面白かった~」と言うよりも、「あ~ワクワクした~」と伝えてみます。
すると「〇〇なところが〇〇だった」と、一番印象に残っている場面が出てくるかと思います。出てこなくても大丈夫。そんな時は「どのページの絵が好き?」と聞くだけです!笑(付箋を張っておいてもOK)
1つ前のポイントに挙げた「子どもの表情の変化」とおそらく一致していると思います。ひとまずやることはここでストップ。
少し時間を置いてから声かけをしてみよう
お風呂の中や寝る前の落ち着いて話せる時に、「そういえばあの絵本に出てきた〇〇って(子どもの名前)に似てるよね~」とか、「絵本に出てきたうさぎさんと一緒にお出かけするならどこ行きたい?」などと、お話の流れと子どもが共感できることを見つけるように声がけをします。これが実際に感想文を作るときの中身の部分になり、情報が多い分だけ内容が膨らみ、スラスラと書くことに繋がるというわけです。
親のサポートがあることは承知済み
特に低学年の子どもは、親の手が加わっていることを先生も承知済みだと思うので、子どもから引き出した言葉やストーリーをうまく繋げることが親の役目だと思っています。
そして、子どもが最後に頑張ることは「原稿用紙2枚、3枚を第三者に読める字で、なるべく間違えないように書くこと」だと思います。疲れてきてるなと思ったら無理をさせずに、また後日にしてみるのもいいかもしれませんね。
低学年で使えるとっておきの技はコレ!!
ここまで読んでいただきありがとうございます。
最後に、代表に選ばれた理由はコレかな?と個人的に思っている技をご紹介します。それは「文末を『だよ』や『だな』にすること」です。
きちんとした文章を作らないとと思っていませんか?「思いました」や「感じた」と書くのももちろんOKですが、1年生はしっかりとした敬語で文章を作らなくてもOKなようです。
「〜とおもったよ」
「〜をやってみたんだ」
「おもしろそうでしょ」
おじいちゃんやおばあちゃんにお手紙を書いているようなイメージだとわかりやすいかな?
とっても柔らかくて可愛い感想文が出来上がりますよ!1年生にお子さまがいる方、ぜひやってみてくださいね。

誰かの役に立ちますように!
この記事を書いた人



























