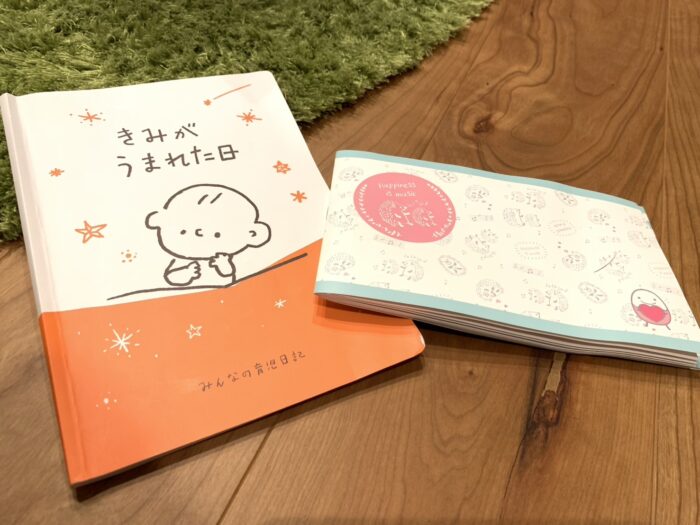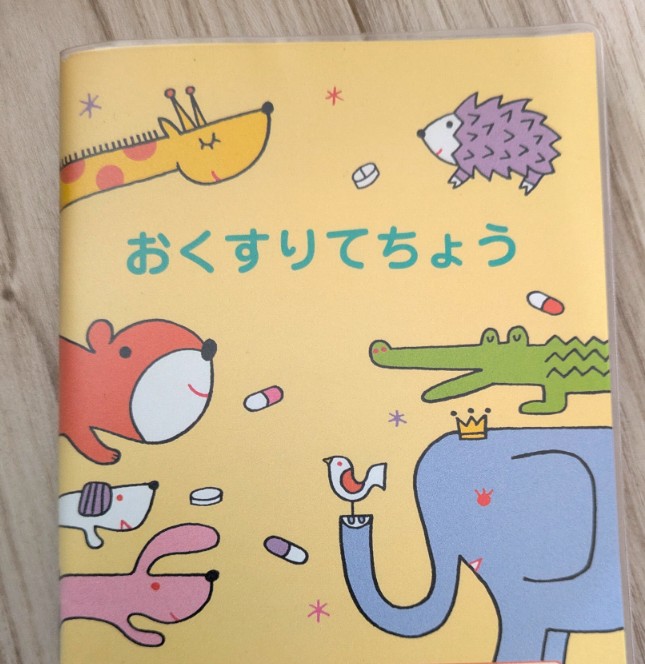更新 :
ベビーサークルで赤ちゃんを囲わない使い方。伸び伸び育てつつ安全は確保したい

ベビーサークルを逆転の発想で活用する

ハイハイ開始以降、赤ちゃんが動き回ることによる事故の対策が必要になる
1歳前の男の赤ちゃんを絶賛育児中の父親です。
生後半年を過ぎてからは、赤ちゃんが自力で移動するようになってきました。
そうなると周りにあるものに注意が必要です。
対策として、ベビーサークルが使われることが多いと思います。
ベビーサークルは赤ちゃんの安全を確保するうえで非常に重要な育児アイテムです。
ハイハイやつかまり立ちが始まると、赤ちゃんは好奇心のままに家中を動き回り、思わぬ事故につながる危険があります。
コンセント、家具の角、小さな物など、家の中には赤ちゃんにとって危険な要素が多く存在します。
そこでベビーサークルを使うことで、安全な範囲を確保しつつ、赤ちゃんが自由に遊べる環境を整えることができます。
また、家事や急な来客対応の際にも安心して赤ちゃんを見守ることができ、親の負担軽減にもつながります。
安全と安心、両方を守るために、ベビーサークルはとても役に立ちます。
ベビーサークルで赤ちゃんの行動を制限することのデメリット
ベビーサークルで得られる安心安全の代償として、行動を制限することによる不満足の可能性があります。
好奇心の赴くままに動き回って新しいものに手を伸ばすのは本能的な学習行動なので、発達という面でも万全とは言えません。
我が家の場合は性格的にスキンシップを通常より好むからか、ベビーサークルに入れておくと短時間で泣き出す場面が多くありました。
なるべく一緒にいてあげたいのは親心としても同じなのですが、赤ちゃんの相手をしながら家事をするのはとにかく時間がかかりすぎます。
うーん困った
ベビーサークルで赤ちゃんを囲わない、という使用方法
ベビーサークルの通常の使い方が我が子に合わないと分かったので、逆転の発想で使うことにしました。
赤ちゃんを囲わず、触ってほしくない物を囲う方法です。
実際に設置した状態がこちら

書類や上の子の持ち物を収納する棚などのスペースをベビーサークルで囲みました。
ハサミなど赤ちゃんにとって危険なものもこのスペースに集約しています。
ベビーがサークルの外にいるので呼び方はアンチベビーサークルになるのでしょうか…
この設置方法にしてからは、赤ちゃんが広いスペースを自由に動き回れるようになり、泣いて呼ばれることが少なくなりました。
この記事を書いた人