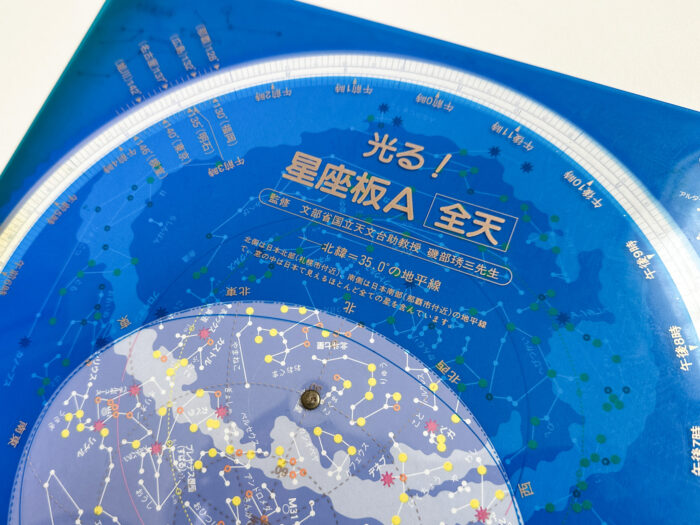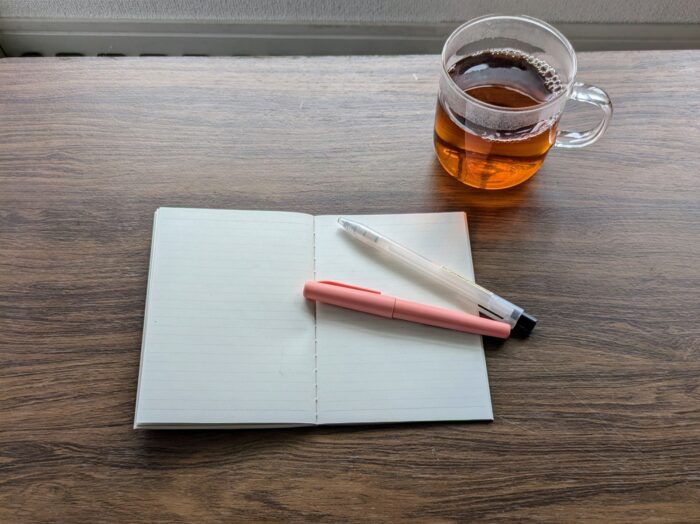更新 :
女性活躍推進について考える ― 私のモヤモヤと決意

こんにちは、ACOです。私はIT企業に勤めて営業職をしていますが、下期から人事部の女性活躍推進関連の業務も担うことになりました!そこで、今回は女性活躍推進について、私のもやもやと決意を記載します。
みなさんは「女性活躍推進」と聞いてどう思いますか?
「なんで女性だけがフォーカスされるの?」
「女性に下駄を履かせて昇進させるってこと?」
そんなふうに感じる方もいるかもしれません。私自身も、最初は同じような違和感を覚えていました。
私が女性活躍推進に関わりたいと思った理由
私が女性活躍推進に関心をもったのは、「女性のキャリア支援をしたい」という思いからです。個人を支えるだけでなく、組織の仕組みを通してより多くの人がキャリアの選択肢を広げられるのではないかと考えています。
「女性活躍推進」と聞くと、多くの人は「昇進」「管理職登用」といったイメージを持つかもしれません。でも、私が目指したいのはそうではありません。
むしろ大切なのは、キャリアの選択肢を増やし、女性が自分でキャリアを描けるようにすること。その結果として昇進を選ぶ人もいれば、別の形で自分らしいキャリアを築く人もいていい。そうした多様性が尊重される組織をつくりたいのです。
多くの会社の人たちは数字に追われて、女性管理職30%を目指したい、と思うようになっているかもしれないですが、そうではないということも伝えていきたいと思っています。
「女性活躍推進」って本当はどういう意味?
「女性活躍推進」という言葉は、政策や企業の施策のなかでよく耳にします。背景には大きく3つの流れがあります。
1.人口減少・労働力不足の解消
少子高齢化が進む中、女性の労働参加を促すことは社会の持続可能性に直結しています。
2.多様な視点によるイノベーション
同質的な組織では新しい発想が生まれにくいため、女性を含む多様な人材が意思決定に関わることが重要だと考えられています。
3.公平性・公正性の実現
これまで「男性が昇進しやすい構造」の中で機会が限られてきた部分を是正し、誰もが公平に挑戦できる環境を整える必要があります。
つまり「女性活躍推進」とは、決して「女性を特別扱いする」ことではありません。
本来は 性別に関わらず、一人ひとりが力を発揮できる環境を整えること が目的なのです。女性が働きやすい職場は、男性や他の属性の人にとっても働きやすい職場につながります。
現実に残る課題
しかし現実には、理想と現場のギャップが大きいと感じます。
1.家事・育児の負担の偏り
依然として多くの家庭で女性が主な担い手になっており、仕事との両立がハードルになっています。
2.「管理職像」の固定観念
長時間労働やフルコミットを前提とした管理職モデルが根強く、ライフイベントを抱える人が昇進をためらう要因になっています。
3.キャリア観の多様性が置き去り
「昇進を望まない女性」に対して、「意欲がない」と判断されがちですが、本当は別の形で貢献したいという思いがあることも少なくありません。
4.男性の家庭参画不足
男性の家事・育児参画が進まない限り、女性だけに負荷がかかり「活躍」のハードルは下がりません。
5.周囲の意識のギャップ
「女性活躍推進=女性だけ優遇」という誤解も根強く、取り組みそのものが抵抗感を持たれやすいのも現実です。
私が考える「これから」
私にとって「女性活躍推進」とは、女性を優遇することではなく、誰もが自分らしく力を発揮できる環境を整えることです。
そのためには、制度面だけでなく「文化」や「意識」に働きかけることが不可欠だと思います。
・制度を形だけでなく「実際に使いやすい」ものにすること
・長時間労働を前提にしない働き方を広げること
・「管理職=ひとつのモデル」という固定観念を壊すこと
・女性だけでなく男性も含めたキャリア支援を進めること
小さな変化を積み重ね、仕組みに落とし込むことが大切だと感じています。
私の決意
「女性活躍推進」を「女性だけの特別扱い」と誤解されないよう、本質を丁寧に伝えながら取り組みを進めたい。そして、一人ひとりが「自分のキャリアを自分で選べる」ようになる環境を少しずつ広げていきたい。
最終的には「女性活躍」という言葉自体が不要になる社会が理想です。その未来を信じて、まずは自分にできることから行動していきます。
女性活躍という言葉がいらない未来を目指して!
この記事を書いた人