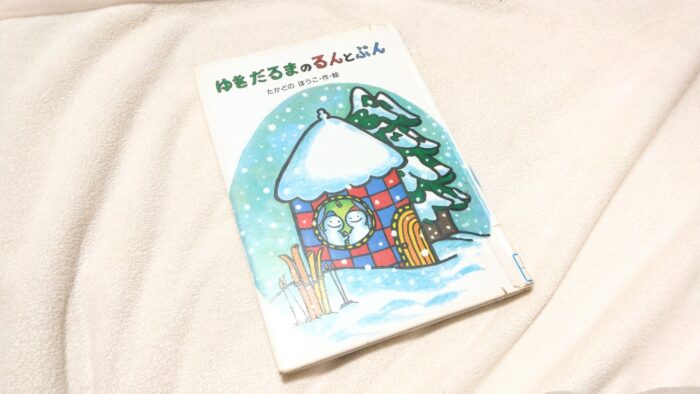公開 :
「きりん」が「ちりん」になる、側音化構音かもしれないと思ったとき

わたしが小学校に入学したとき、前の席だった男の子Kくん。普段から前後で話すことが多く、帰る方向も同じだったのでよく聞いていたKくんの声。Kくんは、「きりん」が「ちりん」になったり、「しんぶん」が「ちんぶん」になったり、母音の「い」が言いにくい「側音化構音」でした。それは今だからわかることで、小学1年生のわたしにはなぜそのような言い方になるのか、何の理解もできていませんでした。
そのことばの向こうに
ある日、国語だったか道徳だったか、「ことばづかいに気をつけよう」というテーマで授業がありました。「どんなことばに気をつけたらいいでしょう?」という先生の問いかけに、みんなが元気よく手をあげます。わたしも手をあげて、その場で起立。同じように手をあげた人たちが順に発言していくうち、自分の答えと同じものが出たら座る流れです。
わたしはたぶん、座りたくなくて、人とは違う答えを必死に探していたのかもしれません。順番がきたときに言ったのは、「Kくんみたいに、「き」が「ち」になること!」。
先生は「それは違います」と言い、さっと次の人に答えを求めました。わたしもすぐに席に座り、なんだかわからないけど、それが間違いだったということはそのとき理解したように思います。
わたしはこの出来事を、これまでの人生で何度となく思い出してきました。「なぜあんなことを言ったんだろう?」と今は思いますが、小学1年生のわたしにとってはそれが答えだったのです。先生の返事で、まちがいだと知れたのは幸いでした。それからも側音化構音の人に出会うことがあるたび、過去の自分を戒めるようにこの出来事を思い出しています。
最近になって感じはじめたのは、「自分がなぜそんなことを言ってしまったのか」というバツの悪さみたいなものより、Kくんはあのときどう思ったんだろうということ。
もしかしたら本人は気づいていなかったかもしれないし、気づいていてショックを受けたかもしれない。Kくんが家に帰ってお母さんに話していたら、きっとお母さんも心を痛めたはず。たしか1~2年のうちにKくんは引っ越してしまったけど、もしかしてこの出来事が原因だったらどうしよう、とまで妄想してしまいます。
先生がさらりと訂正してくれたから、Kくんの心には残っていない、そうあってほしいと願うようになっていました。それは、4歳になるわたしの息子も側音化構音かもしれなかったからです。

まだ4歳なので、これからうまく発音できるようになるかもしれません。でも、小学校に入学するときもこのままだったらわたしは不安になることでしょう。からかうつもりで言ったことではない、そう信じたいけど、もしかしたら小学1年生の自分にはそういう気持ちがあったかもしれない。からかうつもりがなくても、あの頃のわたしのように誰かが「何か変だな」「聞き取りづらいな」と思ったことを素直に発言して、それで息子が傷つく可能性もあります。
できればその頃には、治るようにしてあげたい。これから大きくなって、聞き取りづらいことが対人関係にマイナスになったり、自信をなくすきっかけにはなってほしくありません。
自然に改善した人もいれば、舌のトレーニングなどで克服した人もいるそうなので、判断は難しいところ。訓練に通うこと自体で息子が自信をなくす可能性だってあります。だけど何かあったらいつでも行動ができるように、いろんな選択肢から選べるように、知識だけは今のうちからもっておこうと思います。
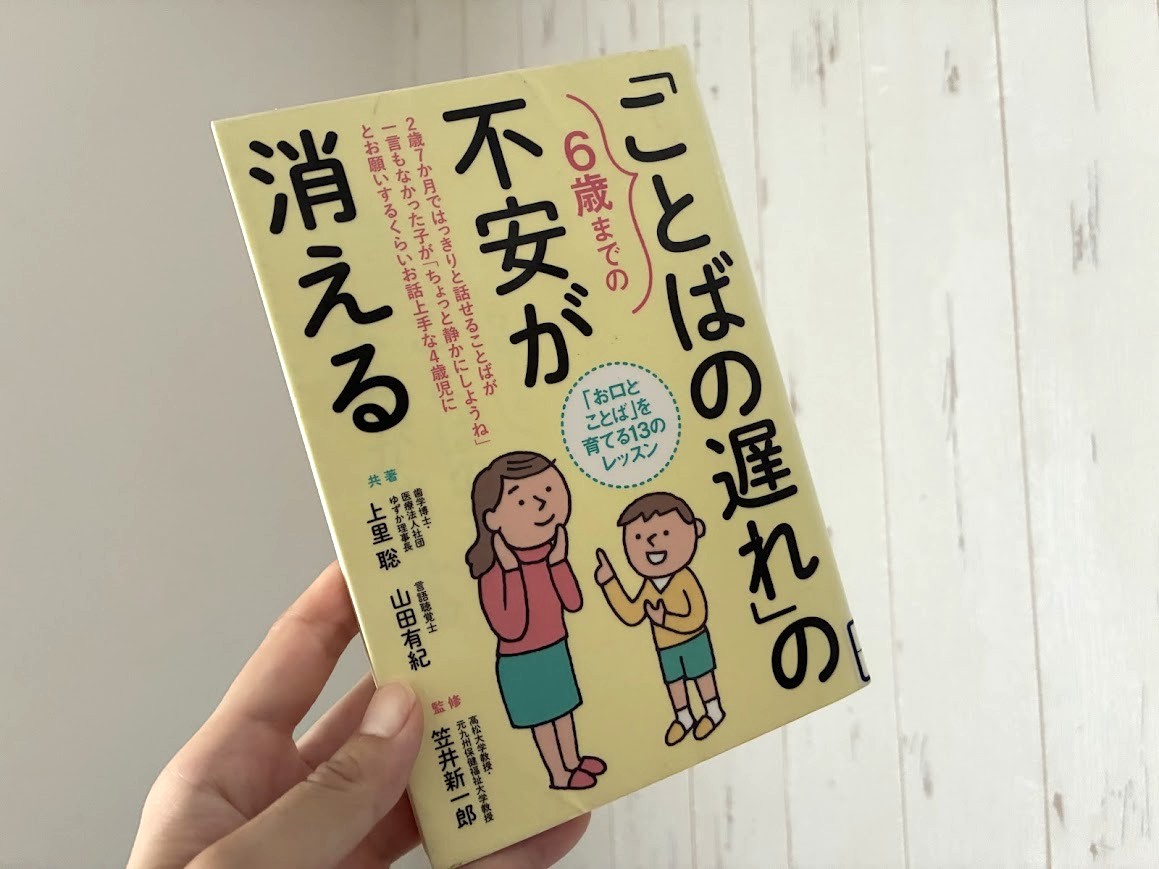
この記事を書いた人