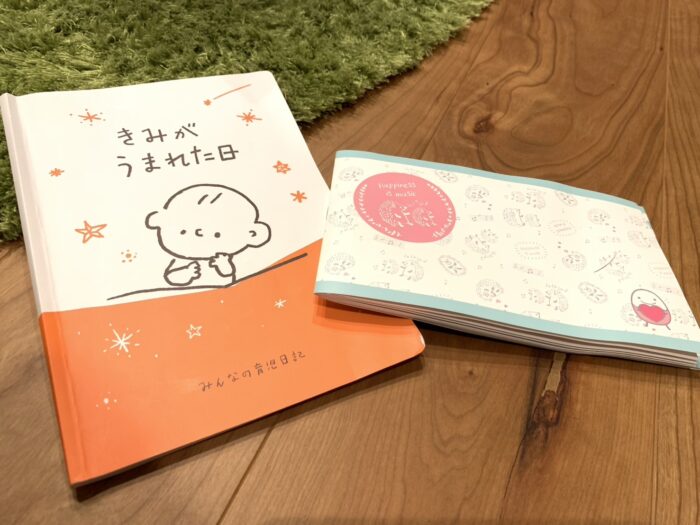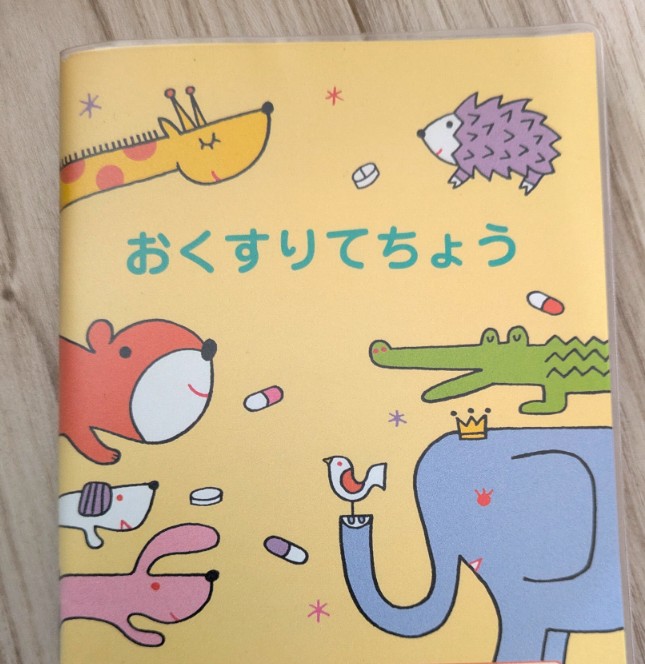公開 :
4日違いの誕生日、どう祝う?わが家の“きょうだいバースデー”工夫帖
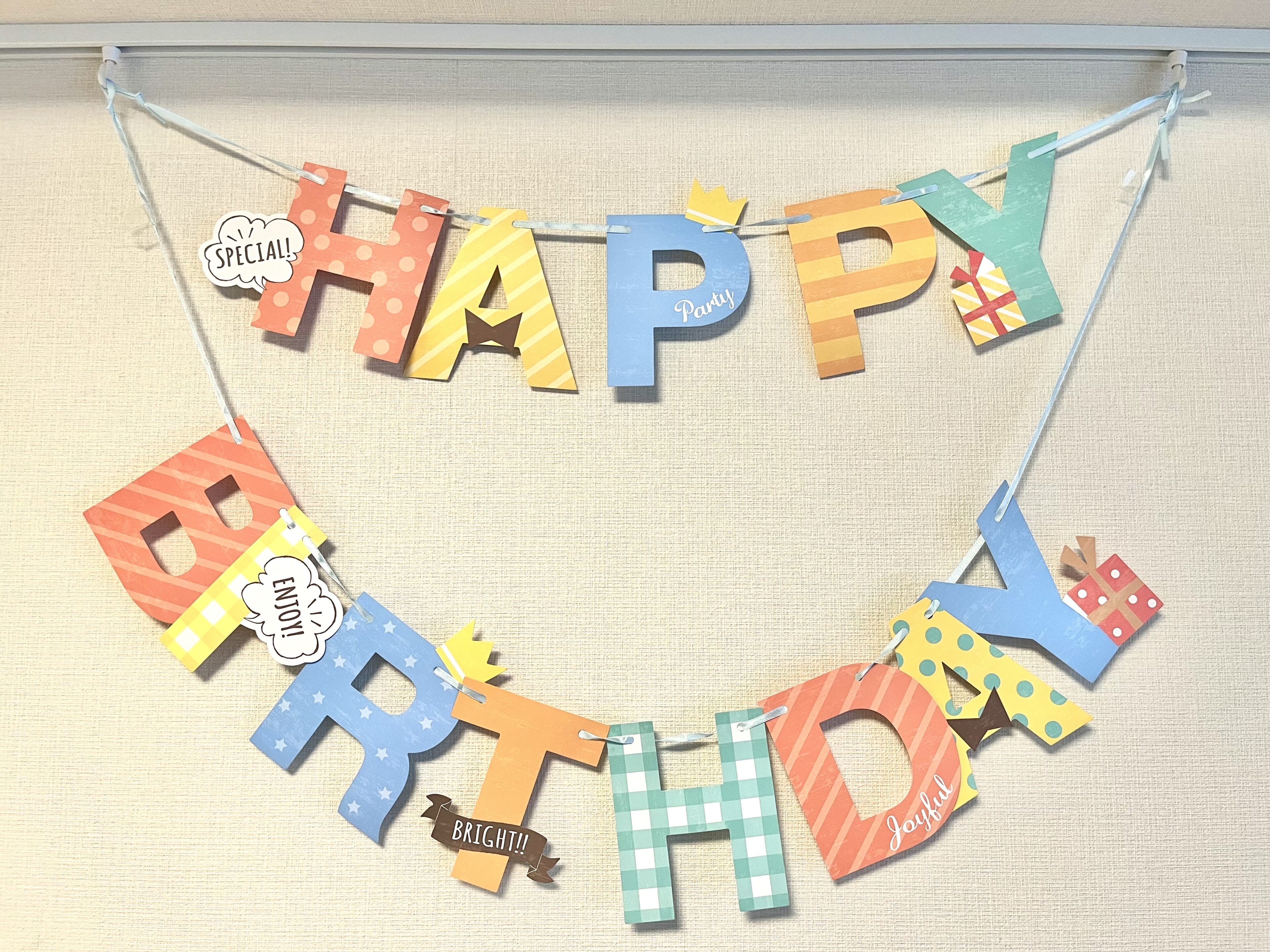
厚生労働省の人口動態統計によると、1995年〜2021年に生まれた人の誕生日で最も多いのは9月25日なのだそうです。
「誕生日」って、家族にとっても特別な日ですよね。わが家では、息子と次女の誕生日が4日違いでやってきます。毎年、どんなふうにお祝いするか、ちょっとした工夫が必要です。
そんな“きょうだいの誕生日”の過ごし方について、これまでの変化や子どもたち自身の希望、そして親としての思いをご紹介します。
小さい頃は、兄の希望中心に
次女がまだ小さかった頃は、誕生日をしっかり理解できるのは息子だけ。そのため、誕生日のお祝いでは、息子に希望を聞きながら、食べたいものやケーキを決めていました。
次女も一緒にお祝いはするけれど、実質的には息子の希望がメイン。そんなバランスでやっていた時期がありました。
今は2人それぞれに“希望”がある
次女も成長し、「誕生日=特別な日」という意識がしっかり芽生えてきました。
「自分の誕生日には〇〇(例えばハンバーグやお寿司など)食べたいな〜」
「ケーキはこういうのがいいな!」
そんなふうに、自分の希望を口にするように。それぞれにしっかり主張がある――これも、うれしい成長ですよね。
わが家のお祝いルールは“平等よりもみんなの納得”を大切に
平日は夫の帰宅が遅いため、お祝いは基本的に週末に。理想は2人の誕生日の間に週末があることですが、そう都合よくはいきません。
そんな中でも、どちらか一方だけが優遇されることがないように、2人が納得できる方法を模索しています。
・ケーキは1回だけ
・外食や好きなメニューで、2週連続“お祝いディナー”に
ケーキを1つにするときは、子どもたち同士で話し合って決める場面も。
ある年は、息子が「クリスマスは〇〇(次女)が決めていいから、誕生日は僕が決めさせて」と提案。次女も「うん!」と納得して、平和にまとまりました。
ちなみに長女の誕生日は2人と離れているため、すべての希望が叶う姿を見ている次女が、今年はどう感じるか…親としてはちょっとドキドキです。
自分だけの特別を大切にしたい
親としては、子どもたちの誕生日はどの日も、等しく大切で特別な日です。
「生まれてきてくれてありがとう」
「これからも元気に育ってね」
そんな気持ちは変わりません。でも、子どもにとっては「自分だけの特別な日」がちゃんとあることが、やっぱりうれしいもの。
だからこそ、ケーキやごちそう、過ごし方でちょっとした衝突があっても、それを一緒に乗り越えるのも大事な経験かなと思っています。
“公平”は難しいけれど、“納得”と“愛情”が伝わるように——これからも、言葉と行動で、子どもたちに気持ちを伝えていけたらと思っています。
その年ごとの“ベスト”を探して!
次女が生まれてから、息子と次女の誕生日を一緒にお祝いするのは、次で5回目。始めは「なんとかなるかな?」と思っていたけれど、工夫しながらその都度、楽しく過ごすことができています。
同じように、誕生日が近いきょうだいを育てているご家庭は、どんなふうにお祝いしているのでしょう?よかったらコメントでアイデアを教えてもらえるとうれしいです。

仲良く、すくすく、毎年ハッピーバースデーを迎えたいですね。
この記事を書いた人