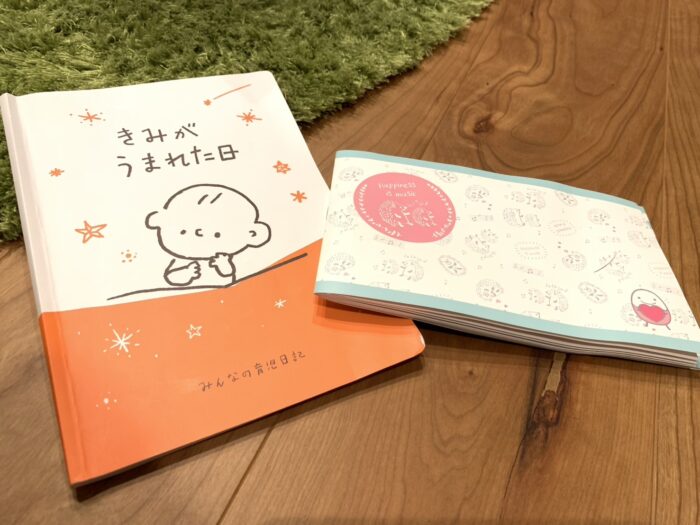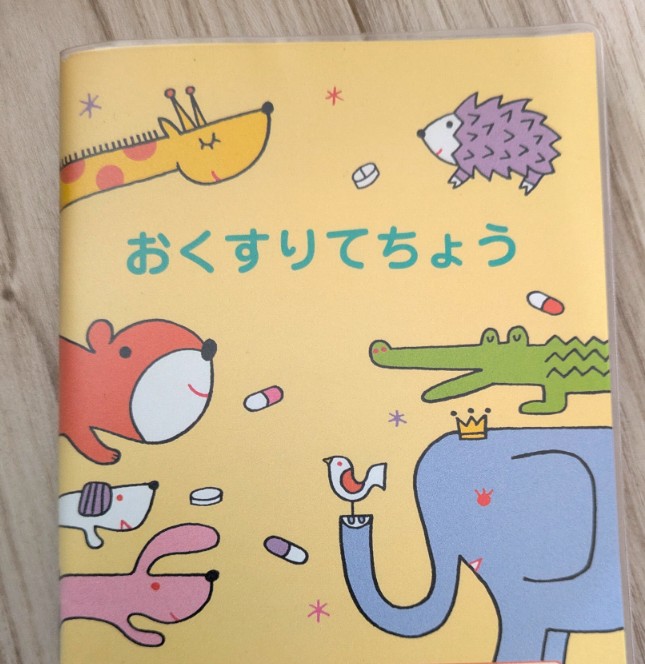公開 :
5人家族の引越し。段ボールは何箱必要だったのか。荷造りアウトソースの威力

ファミリーの引越しプランは段ボールが50枚、というのが多いがはたして…

こんにちは。3人の子どもを育てている5人家族の父親です。
先日、家族で引越しをしました。これがまた、想像以上に大変で…。
今回は、実際に私たちが使った段ボールの数、荷造りサービスを利用して感じたメリット・デメリット、そして小さな子どもがいる家庭にこそ荷造りサービスを強くおすすめしたい理由を、体験談を交えてご紹介したいと思います。
結局、段ボールは何箱使った?
まず結論からお伝えすると、引越しに使った段ボールの数は94箱となりました。
ちなみにこの数は、引越し後の1ヶ月間で廃棄した段ボールの数です。
その中には引越し前から段ボールに入っていて、今回の引越しで箱詰めしたものではない分もいくらかあります。
一方で引っ越してから段ボールのまま保管しているものもそれなりにあるので、実質的に必要な枚数はだいたい同じくらい、大まかに約100箱を使いました。
段ボールに入らない家具家電などは別でこの量です。
私自身、50箱くらいかな〜なんて甘く見ていたのですが、実際に荷物を詰め始めるとどんどん増えていき、最終的には段ボールの山に囲まれて生活する羽目に。

ちなみに、うちは夫婦+子ども3人(6歳、5歳、0歳)の5人家族。今回は2LDK(+S)からの引越しでした。
家族が多いと一人ひとりの荷物もそれなりにあるし、日用品や子どものおもちゃ類など「これはすぐ使うかも」という理由で捨てきれない物も多く、想像以上に段ボールが必要でした。
引越しの荷造りサービスを使ってみた
結果的に100箱近くの箱詰めが必要だったのは驚きですが、かなりの量になることは引越し前から感じていたので、荷造りサービスを引越しサービスのオプションに追加していました。
これが結果的に大正解でした。
メリット
・時間と労力の節約
荷造りは本当に大変です。特に子育て中の家庭では、日中にまとめて作業する時間がなかなか取れません。プロが来てくれて、テキパキと荷物をまとめてくれるのは本当にありがたかったです。
・梱包が丁寧
食器や割れ物、家電など、自分ではちょっと不安な梱包も完璧。あとで開けてみても、破損はゼロでした。
自力でこの量を箱詰めしたら丁寧にやっている時間はなく、皿など割れていたと思います。
・ストレスが少ない
引越しは心身ともに疲れるイベントですが、荷造りを任せることでかなり気持ちに余裕が持てました。これはかなり大きなポイントです。
デメリット
・費用がかかる
やはり一番のデメリットは費用面で、オプション料金として数万円かかりました。この部分はタイムイズマネーと割り切る必要があります。
・自分で何をどこに入れたか把握しづらい
荷物の大枠は箱の外側に書いてくれるのですが、細かい物の場所がわかりにくいことも。特に「引越し直後に必要な物(ハサミ・充電器・子どものおむつなど)」は、事前に自分でまとめておくと安心です。
小さな子どもがいる家庭こそ、荷造りサービスを使ってほしい
今回、我が家は0歳の赤ちゃんがいる中での引越しでした。
日中は授乳・おむつ・昼寝などの世話があるため、荷造りの時間が本当に取れません。夜や週末にやろうとしても、疲れて倒れ込む毎日。
そんな状況で、荷造りサービスは救世主でした。
特に良かったのは、子どもが在宅中でも安心して作業を任せられるという点でした。
小さな子どもがいる家庭は、とにかく日常がバタバタしています。そこに引越しのストレスが加わると、本当に心が折れそうになります。
だからこそ、「多少の出費をしてでもプロに任せる」ことが、家族全体の安心と安全につながると、今回の引越しで実感しました。
最後に
引越しは、家族にとって大きな節目。
楽しく、新しい生活を迎えるためにも、準備段階での負担はなるべく減らすべきだと痛感しました。
段ボールの数は94箱。見積もりより多かったですが、それでも荷造りサービスのおかげでなんとか無事に引越しを終えることができました。
これから引越しを控えている、特に小さな子どもがいるご家庭の方にとって、少しでも参考になれば嬉しいです。
この記事を書いた人