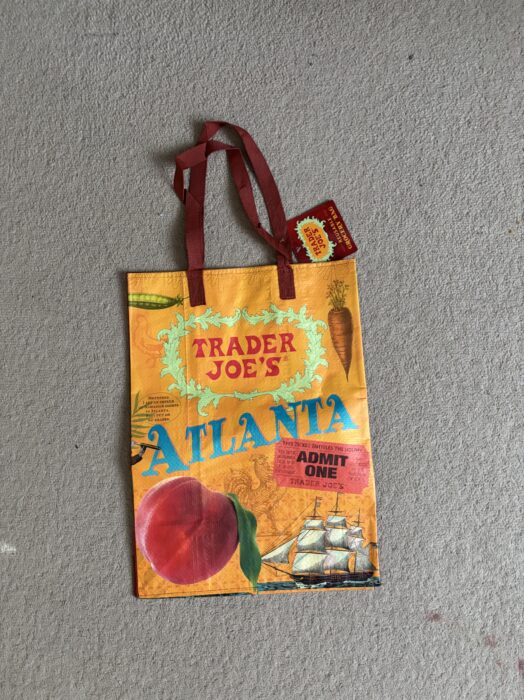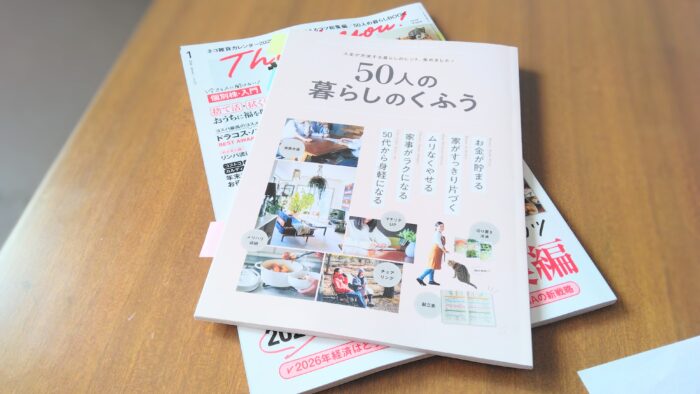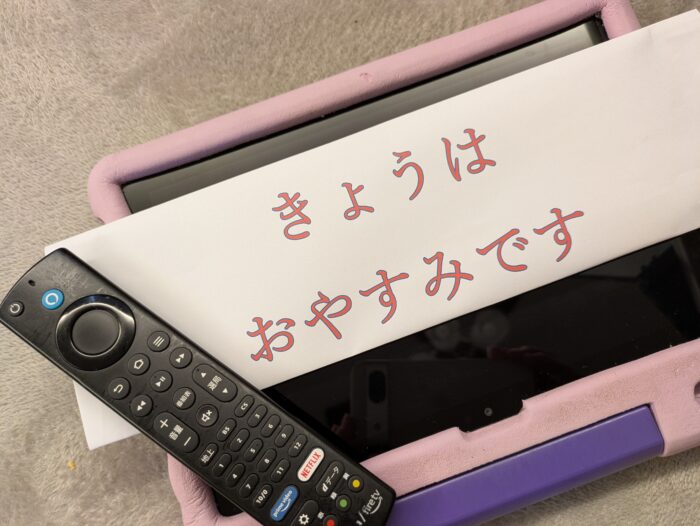公開 :
お米の「田植え」から「収穫」まで体験して感じたこと

少し前の話になるのですが、今年の夏休みの最終日は、子どもたちと一緒に「稲刈り体験」で夏を締めくくりました。
ゴールデンウィークに田植えを体験したお米を、夏休みの終わりに収穫できる貴重な機会でした。
「思い出作り」だけでなく、「食育」や「非認知能力の向上」にもつながる、とても良い体験になったので、今回のブログでご紹介します。
GWには「田植え体験」
お世話になったのは、酒々井町産コシヒカリ「酒水米」で知られる千葉県酒々井町の【酒々井町小さな米農家 サクラ咲ク農園】さん。
ゴールデンウィークに体験した初めての田植えでは、私も子どもたちも泥の感触に最初はドキドキ。
田植え機で植える場所もありますが、私たちが体験させていただいた田んぼは手植えでした。
田植え定規をゴロゴロ転がして十字の跡をつけ、その目印に沿って苗を手で植えていきます。
見た目は簡単そうでも、力加減が難しく、苗が浮いてしまうこともありました。
子どもたちは泥や水の中で自由に動き回り、途中からは泥遊びやカエル捕りを楽しむ場面も。
田植えという自然体験を通して、食べ物がどのように育つのかを肌で感じることができました。

千葉と長野の季節感の違いを体感
千葉では稲刈りの時期が非常に早く、長野育ちの私は「夏休みにもう稲刈りをするのか」と驚きました。
長野では、稲刈りは秋に入ってからの行事です。
夏休みも8月31日までなかったです(笑)!
その土地ならではの農業のタイミングや季節感の違いを、子どもたちと一緒に体感できたことも、学びのひとつになりました。
稲刈り!自分でやり抜く力を育む体験
稲刈り当日は真夏日!
次男は途中で離脱しましたが、長男は「自分が植えた場所は最後までやり抜く」と宣言し、最後まで稲刈りに取り組みました。
鎌の使い方も徐々に上手になり、自分の手で作物を収穫する喜びを味わう姿に成長を感じました。
また、ニュースで見ている社会の動きと結びつけ、農家さんに「今お米は値上がりしているから大切にしないと」と話す場面もあり、現実社会と農業のつながりを意識するきっかけになったことも印象的でした。
このような体験は、「やり抜く力」「責任感」「自己効力感」といった非認知能力を育む効果もあるのだなぁと感じました。
子どもが自ら考え、行動し、達成感を得るプロセスを体験できる点が大きな魅力です。

食べ物への感謝と食育
収穫したお米を家に持ち帰り、家族で味わったときには、その美味しさと同時に、食べ物への感謝の気持ちが自然と深まりました。
手間ひまかけて作られたお米のありがたみを知ることで、一粒一粒を大切にする心が芽生えるものですね。
こうした体験は、子どもの感性や思考力、心の成長にもつながる「生きた食育」と言えるのではないかと思います。
お米一粒たりとも残さず食べるようになりました!

米一粒には七人の神様が宿っている
食べ物を粗末にしないための言い伝えで、「米一粒には七人の神様が宿っている」という言葉があります。
これはお米を作る過程で必要な太陽、雲、風、水、土、虫、そして作り手(人)の七つの自然の恵みを指すと考えられています。
これらの神様への感謝の気持ちを持ち、お米を一粒残さず食べることで、豊作への感謝や、食べ物を粗末にしないという心を育むことができると言われていますが、実際に「田植え」から「収穫」までを体験させて頂き、本当にその通りだなと実感しました!

心を込めて…「いただきます!」