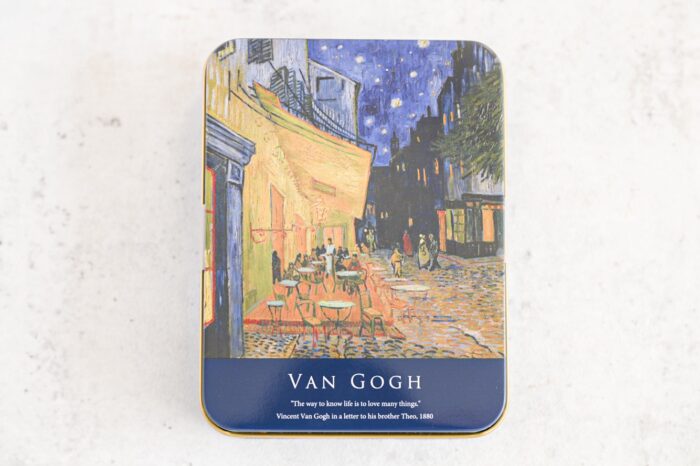公開 :
親世代の運動会と大きく違っていた、令和の小学校の運動会

子どもが小学1年生になって運動会が開催され、行ってみたところ親である自分の小学校時代とは様変わりしていて衝撃を受けました。
小学1年生の子どもを持つ父親です。
令和7年10月の秋晴れの日、我が子が通う小学校の運動会に行ってきました。
私自身は平成の前半に小学生として運動会に参加していた世代ですが、正直なところ「こんなに変わっているのか!」と驚かされることばかりでした。思い出の中にあるあの運動会とは、内容が様変わりしていました。
今回は、そんな令和の運動会と、親世代の運動会との違いを感じた点をいくつか書いてみたいと思います。
運動会が半日で終わる。弁当タイムなし
まず一番の驚きは、運動会が半日だけで終わるということです。
私たちの時代の運動会といえば、朝から夕方までの一大イベントでした。お昼には、家族みんなでレジャーシートを広げ、母親が早起きして作ってくれたお弁当を囲むのが楽しみのひとつでした。おにぎりや唐揚げ、卵焼き、そしてデザートのフルーツ。親戚が来てくれることもあり、まるでお祭りのような雰囲気でした。
しかし、我が子の運動会にはその「お弁当タイム」がありませんでした。全プログラムが昼過ぎに終了し、給食もなし。児童は親と、もしくは子どもだけで自宅に帰って昼食を摂るスタイルでした。
これは共働き家庭の増加や、熱中症対策などの理由もあるそうですが、親としては少し寂しさも感じます。家族で過ごす運動会の「特別な時間」が短くなった気がしました。
小学校の運動会と言えば親子競技…と思ったら無いの⁉

次に、親子競技がなくなったことも大きな変化です。
昔は親子で玉入れをしたり、借り物競争や綱引きに出たりと、子どもと一緒に体を動かす場面がありました。あの時の「親も子も本気」の雰囲気が楽しかったものです。
しかし今は、観覧エリアから静かに応援するだけ。親は参加しません。もちろんその分、運営はスムーズですし、安全面の配慮もあるのかもしれませんが、親としてはちょっと物足りない気もしました。平成に生きたおじさんとしては、子どもと一緒に汗をかいて笑い合う、あの一体感をもう一度味わいたいという気持ちも正直あります。
玉入れも綱引きもない運動会プログラム
全体的にプログラムの内容もコンパクトになっていました。
昔は学年ごとに競技が多く、運動会といえば玉入れ、綱引き、リレーなど盛りだくさんでした。
それに対して我が子の運動会は学年別種目が徒競走、演技(組体操)、リレーのみ、全学年の種目が大玉送りと応援合戦という構成で、事前に配布されたプログラムを見て驚きました。
「あれっ、運動会ってこれだけ⁉」
運動会を半日で終わらせるため、いろいろ省略されているようです。
学校側、特に教員の業務負荷低減という側面もあるので、致し方ないことなのかと思いつつ、自分の時代の運動会との違いが衝撃的でした。
都会の運動会はピクニックシート使用不可、全て立ち見
これは地域柄ということも多分にあると思いますが、観覧のスタイルも違っていました。
場所取りは一切禁止で、立ち見エリアが指定されており、順番に観覧します。シートを広げてくつろぐスペースはありませんでした。
私が小学生の時に住んでいたのは郊外で、我が子が通う小学校は比較的都会のエリアなので比較が難しいのですが、保育園児の兄弟を半日ずっと立たせておくことや、1歳になったばかりのベビーを抱っこしながらずっと立っているのはなかなか厳しかったのが印象に残りました。
運動会のノベルティとしてオリジナルグッズ配布
地味に驚いたのがこのオリジナルグッズです。
運動会後、我が子が見慣れない物を持ち帰ってきました。

ミニタオルでした。
写真は裏面で、表面には児童の1人が発案した、運動会のオリジナルキャラクターが描かれていました。
思わず、公立小学校で運動会のオリジナルグッズを配る時代になったんだなあ、と感慨深くなりました。
運動会のスタイルは変わっても、かけがえのないイベントであることは変わらない
昔と今の運動会の違いをいろいろ書いてきましたが、こうした変化を単純に「昔の方が良かった」とは思っていません。
先生方の負担軽減や、熱中症対策、家庭環境の多様化など、現代ならではの課題を考えれば、今の形が最適なのかもしれません。
短時間でも子どもたちは全力で走り、踊り、笑っていました。その姿を見ていると、どんな時代でも運動会の本質である「子どもの成長をみんなで喜ぶ場」というのは変わらないのだと感じます。
令和の運動会は、効率的で安全、そして現代社会に合ったスタイルに進化しています。そして、観客席から手を振る子どもの笑顔を見たとき、ふと自分が子どもだった頃の懐かしい運動会が頭をよぎりました。時代が変わっても、あのときの高揚感や誇らしさは、きっと今の子どもたちの胸の中にもあるはずです。
この記事を書いた人