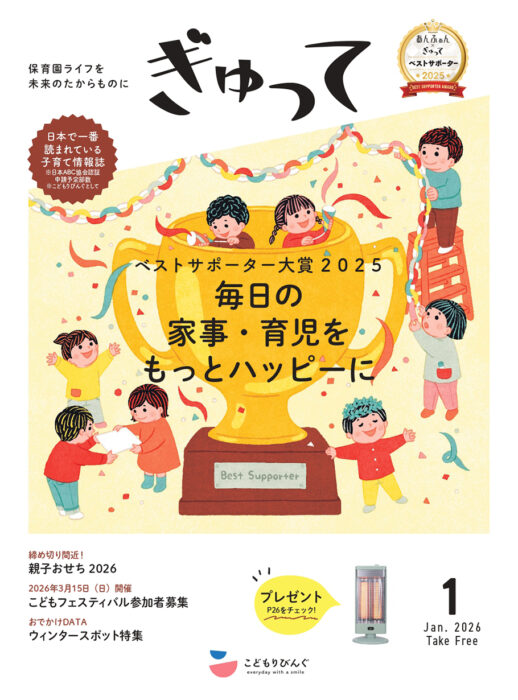公開 :
【発表会】「撮影不可の中央席」vs「撮影可能なサイド席」どっちを選ぶ?

以前通っていた幼稚園にて、12月に行われた生活発表会の観客席の仕組みになるほど〜!と思ったエピソードです。
わたしが選んだのは…
「撮影不可の中央席」でした。理由は、この仕組みを知ったときに、目に焼き付ける価値を考え直したからです。またクラス別開催で、指定された時間はそのクラスの保護者しか入れなかったので、混雑しないことが事前にわかっていました。結果的に中央最前列という特等席で鑑賞しました。
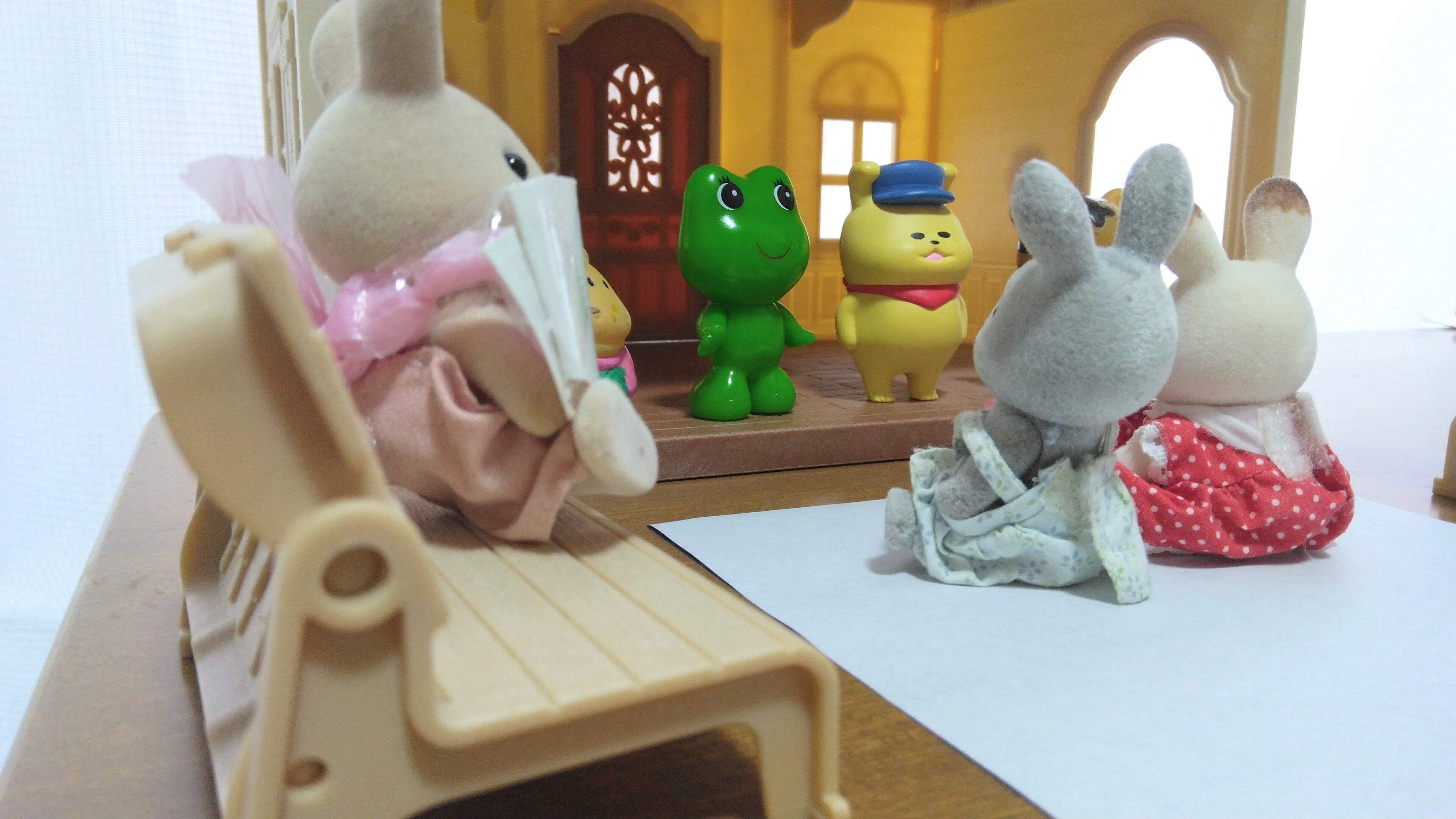
充実のアフターフォロー
とはいえ、きちんと映像で見返せるというシステムがあったことが何よりもの理由でした。当時通っていた幼稚園は平日開催だったということもあり、我が家も含め、家族そろって見られない家庭が多かった印象です。
・発表会後1週間、動画が限定配信されること。
・カメラマンが入り、後日写真注文ができること。
・DVDが700円であること。
※業者ではなく、幼稚園が撮影・作成したもの。
これらを前もって知っていたことから、「見ることに専念しよう!」と思えました。

決めた!撮影マイルール
おかげさまで、とても満足度の高いイベントになりました。意外と目に焼き付くもので、あの臨場感を昨日のことのように思い出します。この経験から、行事ごとはなるべく目に焼き付けるよう意識するようになりました。わたしは撮影が苦手なので、カメラ越しになると「上手に撮りたい、撮れない…」の繰り返しでかなり気を取られてしまいます。そのため撮影したいな、と思ったときは意図的に短くしています。動画は30秒以内に留めています。
DVDの価値を超える実体験
今の幼稚園での発表会は、業者が撮影に入るスタイルだったのでDVDは4000円ほど。あまりにも高額で目玉が飛び出そうになりましたが、逆に言えば、発表会は4000円の価値があるライブのようなもの。いや…換金なんてできない瞬間の数々。プロのカメラマンがいるにもかかわらず、素人(それも超不器用)が撮影に専念するなんてもったいない!と思うようになりました。わたしは今年も「見る」に徹する予定です。
まとめ
手軽に撮影できる便利な時代、また共有することも簡単です。遠方の祖父母に見せたいな、なんて瞬間も多々あります。けれども、きちんと見ることの価値を感じた経験が、わたしの中で今も生きています。ファインダー越しも良いけれど、肉眼で子どもの息遣いを感じながら、目に焼き付けることもおすすめです!
と持論を展開しつつも、願うことはただひとつ。
体調、崩しませんように…!