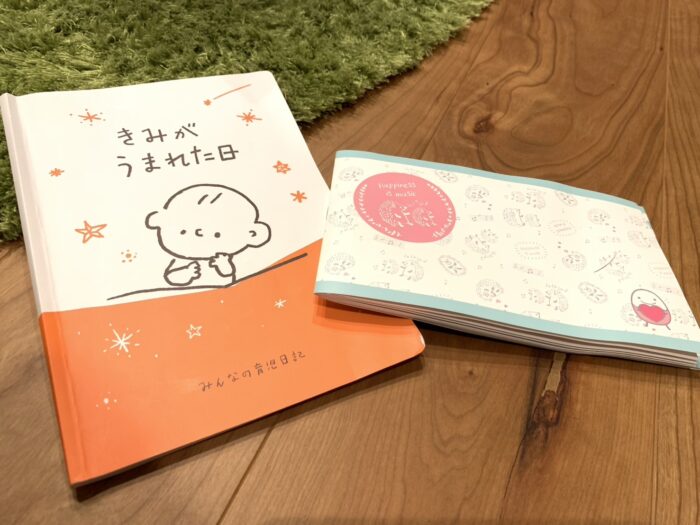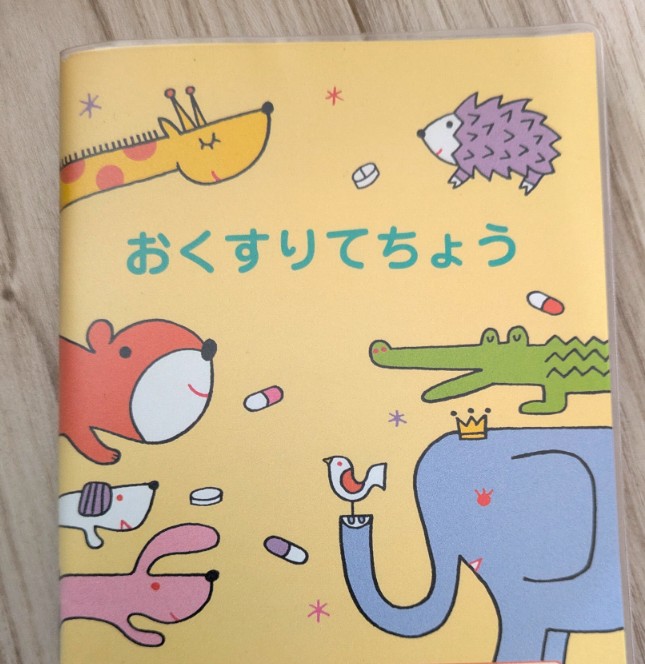公開 :
「怒らない声かけ」ママ友に学ぶ子どもとの向き合い方

「○○しないなら□□あげないよ!」「鬼が来るよ!」——気づけば、そんな言葉ばかり口から出ていませんか?
私もまさにそうでした。朝の支度でばたばたしたり仕事後で疲れたりしているときに、言うことを聞かないわが子にイライラして、つい「脅すような言い方」をしてしまっていました。でも、怖がっている子どもの顔を見て「こんなはずじゃなかった」と後悔するんですよね。
私だって怒りたくて怒ってるわけじゃない。でも、どうしたら「子どもを傷つけずに伝えられる」んだろう?そんなとき、ママ友の声かけがとても参考になりました。
今日は「ママ友に学ぶ、自己肯定感を下げない声かけの工夫」を紹介します。
ママ友の声かけがすごい理由
あるママ友の声かけを見ていると、共通点がありました。それは「子ども目線で、楽しく、前向きに伝えている」ことです。
たとえばこんな場面です。
子どもが目的地と違う方向へ走っていってしまったとき、あなたなら何と言いますか?
私ならつい「そっちじゃない!戻ってきて!」と大声で言ってしまいそうですが、そのママ友は、「こちらに曲がりま〜す!」と交通整理の人みたいに手をぐるぐる回して、ちょっと大げさに誘導していました。子どもも「は~い!」と笑いながら戻ってきていて、びっくりしました。
注意じゃなくて「楽しい誘導」に変えるだけで、伝わり方が全然違うと感じました。
叱るより「意味づけ」で納得させる
もうひとつ印象的だったのが、自転車のベルを鳴らされたときの対応です。
普通なら「ほら!危ないって言われたでしょ!」と言いたくなりますよね。でもそのママ友は、「あの人は○○ちゃんのことを思って『危ないよ』って教えてくれたんだね。ひとつ勉強になったね!」と伝えていたんです。
怒るでも、責めるでもなく、「相手の行動には理由がある」から「次に生かそう」という前向きな受け止め方をしていました。この一言で、子どもも「自分が悪い」ではなく「学びになった」と感じられるのではないでしょうか?
その違いは大きいなと思いました。
転んだときも、泣いたときも肯定から入る
子どもが転んで泣いてしまったとき、「泣かないでえらいね!」ってつい言ってしまいがちですよね。
でもママ友は違いました。「転び方上手だったね。これでまた一つ強くなれたね。ママもいっぱい転んで強くなったよ」と声をかけていました。
「泣かないこと」を褒めるのではなく、「転んだこと」も「頑張ったこと」も全部肯定してあげていたのです。痛かった気持ちも受け止めつつ、成長を感じさせる言葉にしていました。
こういう言い方なら、子どもの心にちゃんと届く気がしました。
私も実践してみた「子ども目線の声かけ」
私もさっそくマネしてみました。ドライヤーを嫌がる娘に、いつもなら「風邪ひくよ!」と言っていたのを、「ドライヤーしたら髪がさらさらになって気持ちいいよ」と言ってみたら…
「さらさら?」と、自分から座ってくれたのです。
「やらなきゃ」ではなく「やりたい」につながる言葉を選ぶことで、親も子も気持ちが軽くなりました。
怒らない声かけのコツは「子ども目線」
ママ友の声かけから学んだことは、たったひとつ。
「注意」ではなく「共感と意味づけ」で伝える。
子どもの行動を「どう止めるか」ではなく、「どう気づかせるか」「どう前向きに変えていくか」に意識を向けると、自然と優しい言葉が出てくる気がします。
私もまだまだ修行中ですが、子どもの自己肯定感を守る声かけ、これからも一緒に練習していきたいですね。もちろん、パパをはじめ、子育てにかかわる皆さんに参考になる声かけのヒントでだと思います。
余裕がないと難しいけど、百発百中でできるようになりたい!
この記事を書いた人