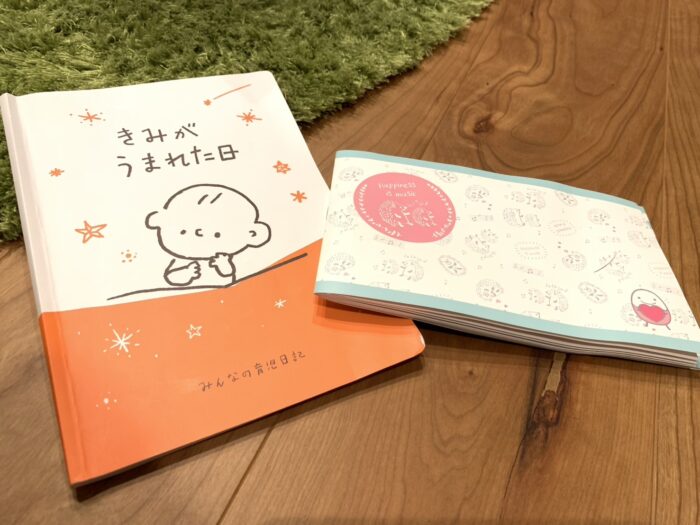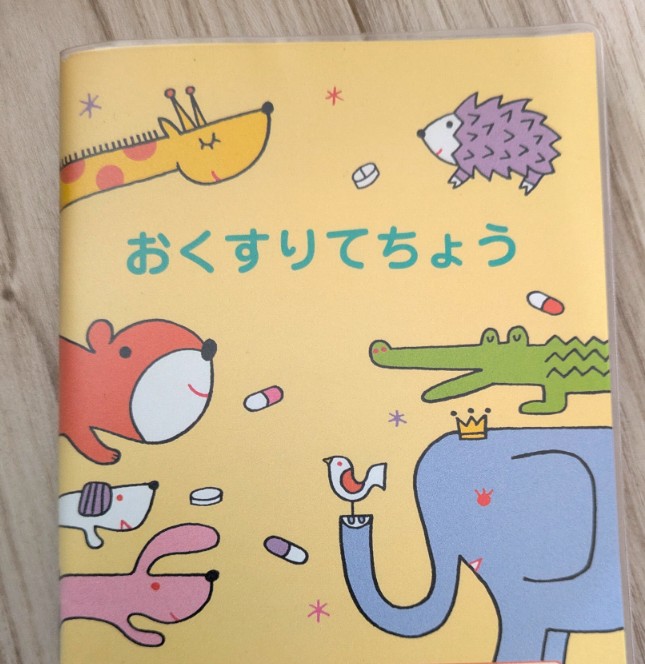更新 :
おひな様をすぐ仕舞えない時の裏技と豆知識-後編
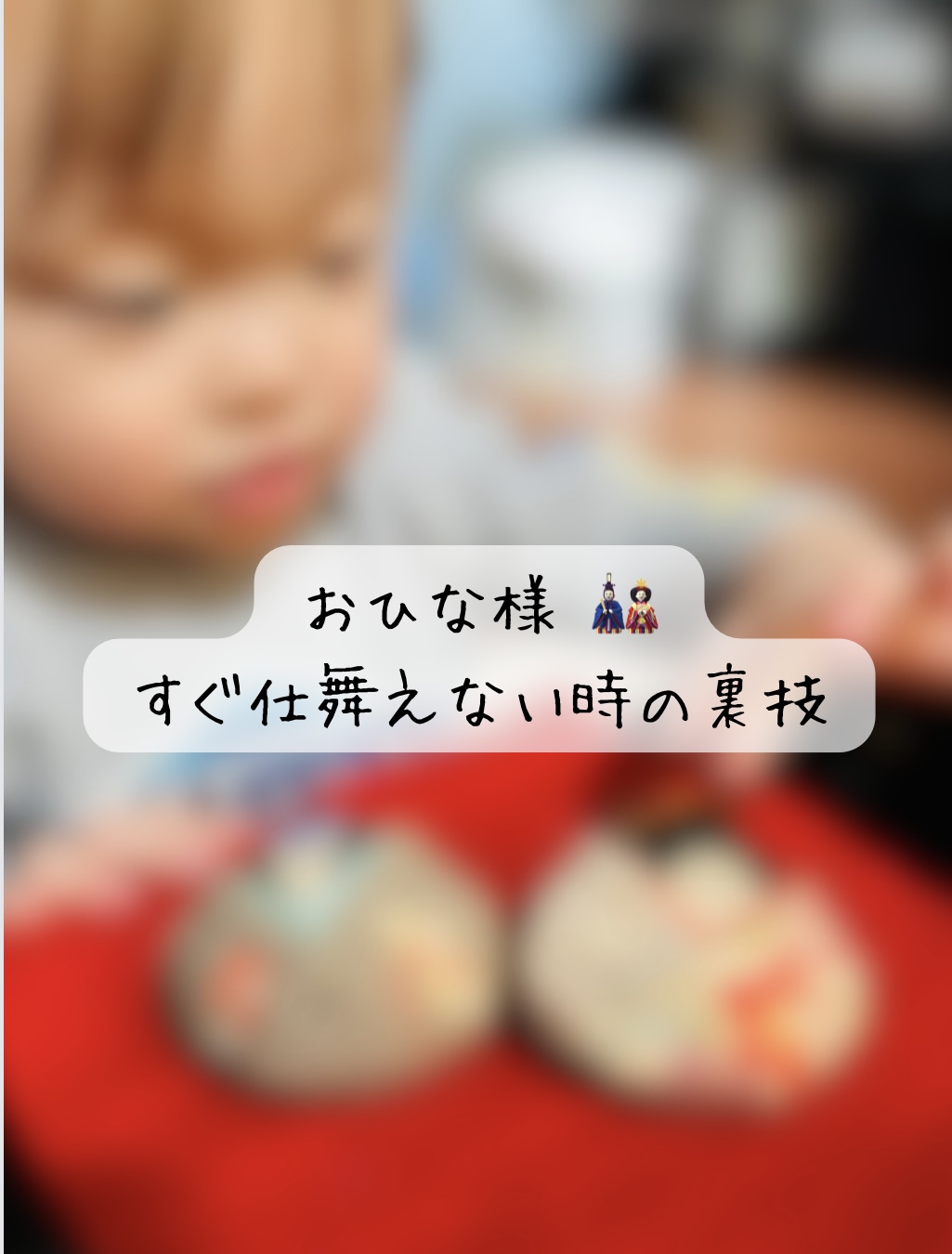
7段飾りのお雛様のボリューム感に、『蔵のある家にして良かった…』つくづく思う、インテリアコーディネーター通地陽子です。
ひな人形早くださなきゃと思いつつ、3年ぶり(産前産後で2年さぼりました)やっと出しましたが、出すべき時期ってご存知ですか?
⚫︎ひな人形を飾る時期は?
立春(今年2024年は2月4日)を過ぎた頃に飾り始め、ひな祭りがすんだ翌日には片付けるのが良いとされています。また、ひな祭りを旧暦で祝う地方は、旧暦の3月3日(今年は2024年4月11日)まで飾っておく地方もあります。
その中で、お雛様はすぐ仕舞わないと【お嫁に行き遅れる】という噂を聞いたことありませんか?
私の母や私の友人周辺では、都市伝説的に語り継がれていました。
そして自分が母になり、実家から引き継いで持ってきたお雛様を飾る役割となった今、そんな急いで仕舞ってもいられないんですよね。
そしてその都市伝説が本当なのか?ただの噂なのか?解説したいと思います。
この【お雛様はひなまつりが過ぎたら早く仕舞う】という言い伝えが出来た由来は、調べてみるといくつかありました。
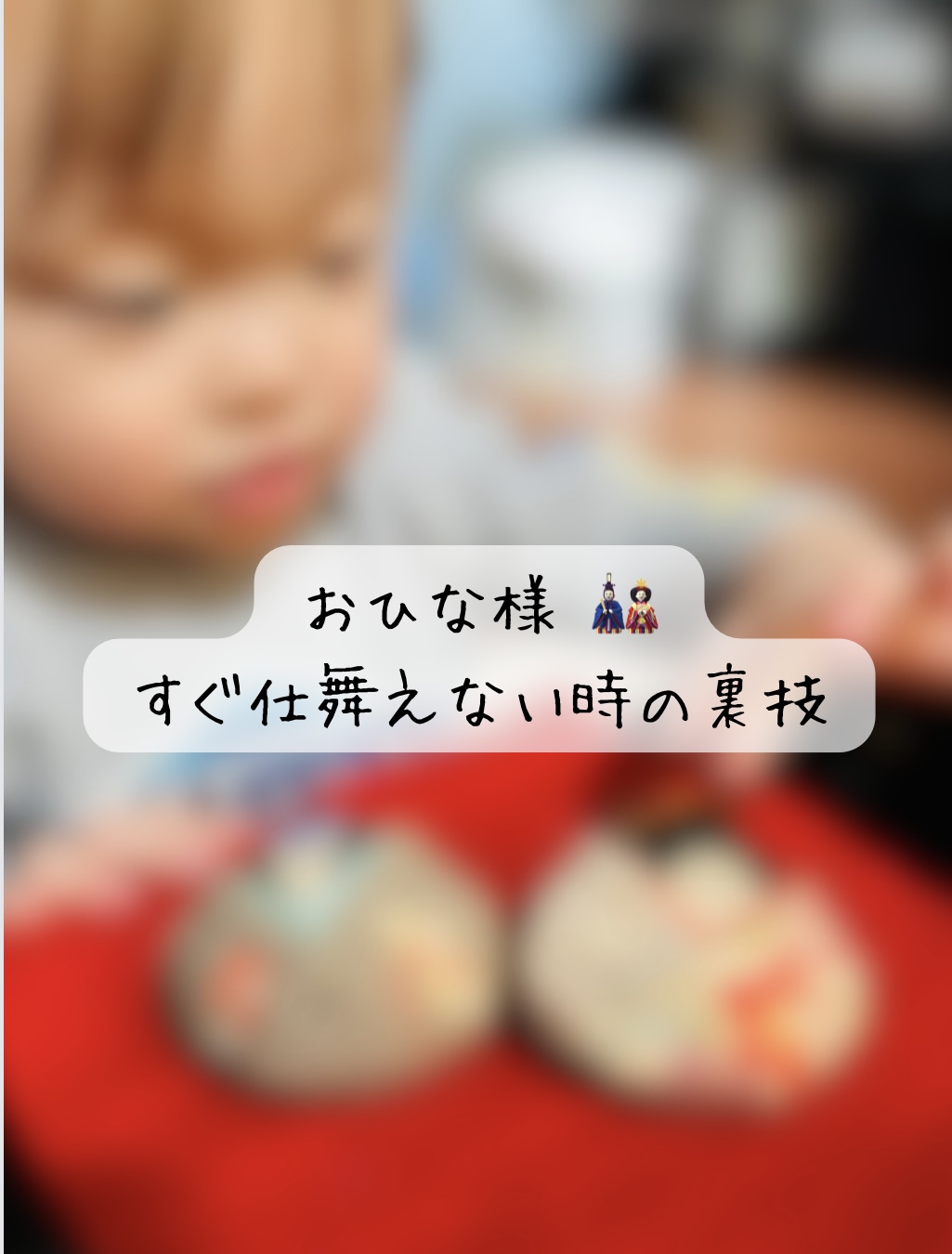
おひな様はすぐ仕舞わないと嫁に行き遅れるのか?!
言い伝えの3つの由来
・「将来いいお嫁さんになれるよう片付けができるきちんとした娘になるように」というしつけの意味
・厄を引き受けるお雛様を片付けて【不幸を遠ざける】という意味。
・婚礼の様子を模したひな人形を早く飾り出すと【早く嫁に出す】【早く片付く(嫁に行く)】ととらえ、娘の幸せな結婚を願う意味
また私が以前知人から聞いたものでは、昔偉い人が【庶民に贅沢な時間を与えて浮かれ過ぎないように】という思惑による噂話だという説もあると。
これに関しては、真偽不明ですが何となく理解できる説ですね。

ひな人形を早く仕舞えない時の裏技!
時間がないときや、湿気が多い雨の日は片付けに向きません。
そんなときは、
・【内裏雛を後ろ向きに飾る】=「おかえりになった」「眠っていらっしゃる」と解釈されます。
雨の日に慌ててしまうのでなく、お天気のいい日に大切にしまうようにしたいです。
冒頭のひな祭りが終わったらおひな様を早く仕舞わないと【嫁に行き遅れる】
というのは、あくまで通説というところ。
お子様の成長を喜び幸せを願うという大切な季節の行事として、その人形や道具も大切にしていこうと捉えていきたいですね。

この記事を書いた人