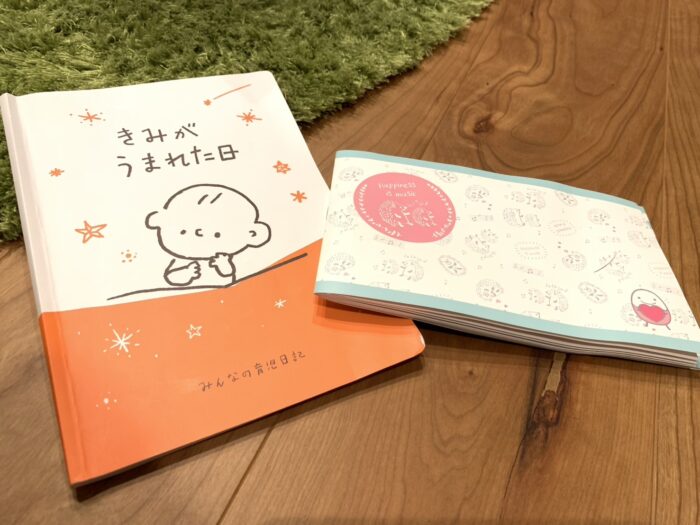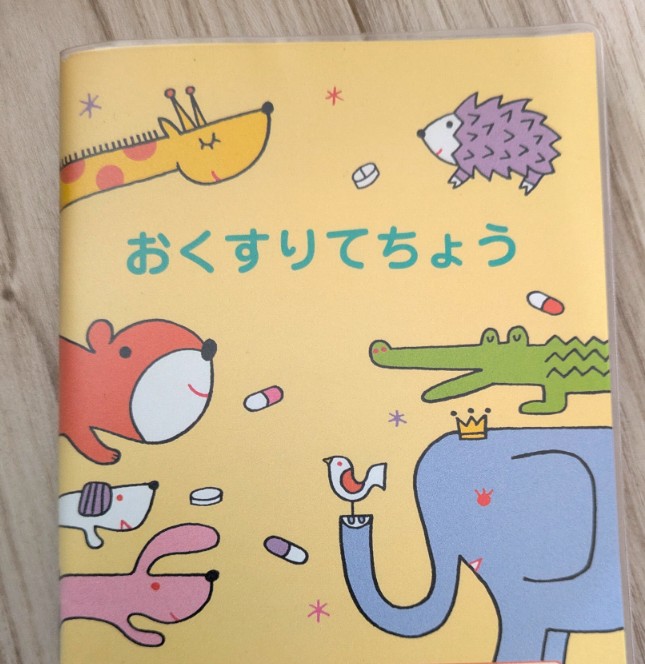公開 :
子どもの自己肯定感を高める10の魔法のことば(書籍レビュー)
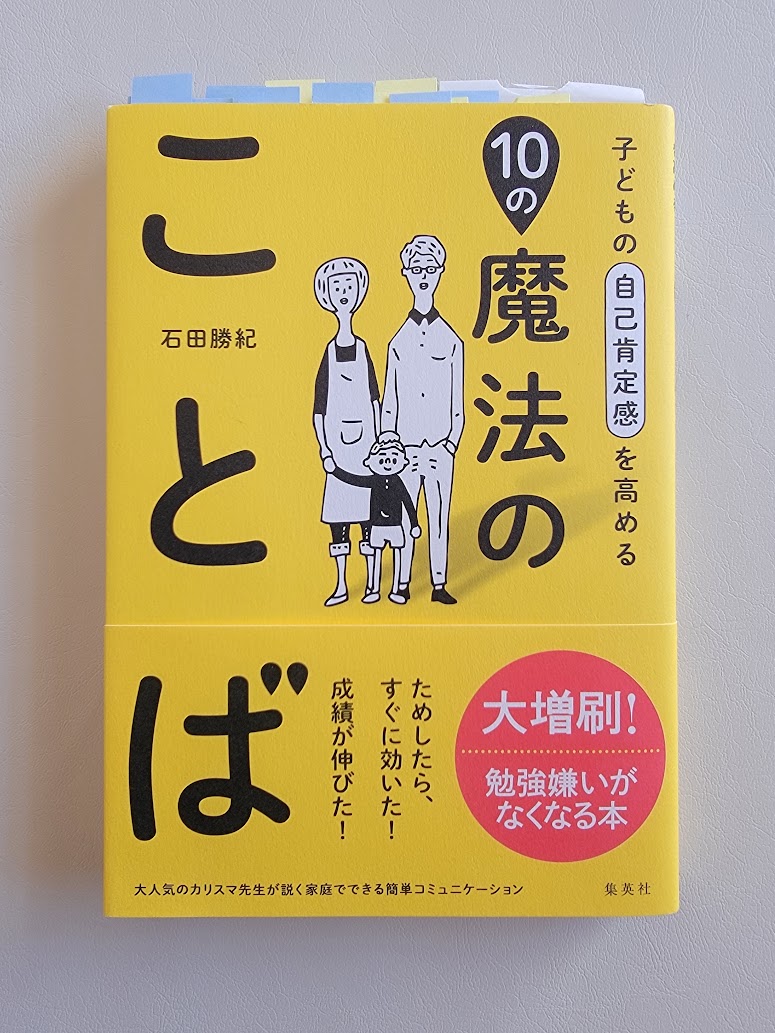
「自分でできるでしょ!」
「しっかりして!」
「やることやったの?」
みなさんはこんな声かけを毎日お子さんにしていませんか?
言いたいわけじゃなけれど、ついつい口からでてきてしまうこんなことばたち。
もちろん私も例外ではなく、これらのことばを毎日使ってしまっています。
こんなことばが子どもたちに届いていると思っていないけれども、
どんなことばで思いを伝えたらいいかわかりませんよね。
どうにかもっと良い声かけはないかと悩んでいるときに出会った今回の本。
著・石田勝紀 「子どもの自己肯定感を高める10のは魔法のことば」
これを読めば毎日の声かけに悩むことなく、しかもたった10種類の声かけでOKとのこと。
10種類なら、なまけものの私でもどうにかなると思い手にとりました。
読んでみると、納得できる内容がたくさんありました。
この本を読んで特に私が「ぐっ!」ときた内容に絞ってみなさんにお伝えします。
この本の内容をマスターして、私といっしょに魔法使いになりましょう。
ではいってみましょう。
自己肯定感を下げる3つのことば
自己肯定感を「高める」ことばを知る前に、自己肯定感を「下げる」ことばを理解する必要があると著者はいいます。
親が子どもにかけることばで、強力なネガティブワードのトップ3がこの3つです。
「早くしなさい」 「ちゃんとしなさい」 「勉強しなさい」
みなさんも心当たりがあるのではないでしょうか。
私も子どもによくこのことばを使ってしまっています。
では、この3つの声かけのどこが問題があるのでしょうか。
「早くしなさい」の問題点は、親の声かけがアラーム化し子どもをコントロールしてしまっている点です。
本来は自分で時計を見て、時間を確認して行動します。
しかし、親が時計がわりとなって「早くしなさい」と声かけするため、子どもが時計を確認するのではなく、親の声かけを受けてから行動する状態になっています。
私も、特に朝は「早く起きなさい」「早くご飯食べなさい」「早く着替えなさい」と「早く〇〇」のオンパレードです。
「ちゃんとしなさい」の問題点は、「ちゃんと」の定義が親も子どももわかっていない点です。
著者いわく、「ちゃんとしなさい」の裏側には「いい子でいるように」という親の無自覚で身勝手な希望と都合が隠されているそうです。
自分も子ども時代を振り返れば、何が「ちゃんと」しているのかわからず返事だけしていたように思います。
「勉強しなさい」の問題点は、子どもの行動を強制してしまっている点です。
本来子どもは放っておいても興味をもったことに対して積極的に学ぶものだそうです。
強制して行った勉強で一時的に成績は上がることもあるが、それは一過性のものとなることが多いとのこと。
私も勉強しなさいと言われて机に向かうものの、教科書のページをペラペラめくっていただけのような気がします。
これら3つのことばは、どれも「人から言われないとやらない」という本人の自主性を失なわせる言葉です。
そもそもこれらのことばは、自分自身も人からいわれれば腹の立つことばですよね。
だとすれば、これらのことばを使われる子どもの気持ちも前向きにはなりませんよね。
そのため、これらのことばを使わずに親は子どもとコミュニケーションを図る必要があるそうです。
子どもの才能を伸ばす3つの魔法のことば
さて、それでは先ほど紹介した自己肯定感を下げることばではなく、どういったことばを使ってコミュニケーションを取ればいいのかご紹介いたします。
まずは「子どもの才能を伸ばす3つの魔法のことば」、承認のマジックワードと著者が呼んでいることばがこちら。
「すごいね」 「さすがだね」 「いいね」
実にシンプルなことばだと思いませんか。
使い方はこんな感じ。
・水泳で潜水ができたとき → 「もう潜水できたの?すごいね!」
・食事の片づけを手伝ったとき → 「自分で進んで片づけるなんて、さすがだね!」
大人から見たら、ささいなことや大したことないと思えるシチュエーションこそがマジックワードを使う絶好のチャンスです。
親は何かあるとついくどくど言ってしまいがちですが、長い話は心に留まりません。
紹介した短いプラスのことばで、ことばが持つ「快」のエネルギーを心に浸透させる必要があります。
紹介したことばは、子どもを褒めて認めることができることばです。
褒められて認められたことにより心が満たされた子どもは、目の前にある「イヤなもの」がイヤではなくなります。
他人との関係や日々の出来事、加えて勉強においても「寛容」になり、必然的に成績も上がっていくというプラスの連鎖が起こります。
ぜひみなさんも、一見声かけしても意味のなさそうな子どもの行動でも、積極的に承認のマジックワードを使ってみてください。
子どもの自尊心を育てる2つの魔法のことば
続いて「子どもの自尊心を育てる2つのことば」、感心のマジックワードと著者が呼んでいることばがこちら。
「なるほど」 「知らなかった」
これもシンプルなことばですね。
これらのことばを子どもとの会話で使うと、子どもは自分が一人の人間として対等に扱われていること、一人前であることを意識します。
「親の知らないことを自分は知っている」という優越感は、子どもの自己肯定感にダイレクトに結びつきます。
そのため、親は子どもが親に何かを説明する機会を積極的に作る必要があります。
「これは何か知ってる?」「それはどうなってるの?」などと親がドンドン使って、子どもをその気にさせましょう。
マジックワードを使って子どもが話をしている間だけでも、子どもと同じ目線で会話をしてみるましょう。
対等に扱われていると子どもが感じると、親を信頼し、より深いコミュニケーションができます。
親の自己肯定感も高めよう
ここまでいくつかのことばを紹介してきました。
最後は、親に関する話も少し。
「親が幸せならば、子どもは幸せにある」と著者は言います。
人は自分が幸せであれば、他者に寛容になり他人の失敗を許せるようになるそうです。
まずは自分自身が、子育ても含めた人生を楽しむことを忘れないようにしなければなりませんね。
私もまだまだ未熟な父親ですが、自分が毎日を楽しく過ごし笑顔でいられるように心がけたいと思います。
私の話を読んで興味がわいた方は、ぜひ手にとって読んでみてください。
ほかにも今回紹介できなかった魔法のことばがたくさんのっていますよ。
これであなたも魔法使い!
この記事を書いた人