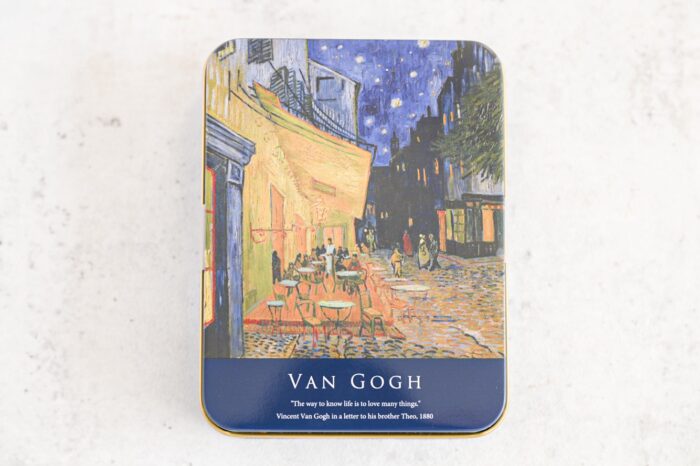更新 :
3人目ベビーを育てていて痛感したこと。何回目でも子育ては新たな発見がある

個性は人それぞれ。兄弟で似ているところもあれば、全く異なるところもある。
2回の育児経験があれば3回目は楽だと思っていたけれど
子供3人、核家族の父親です。子供は6歳と4歳と0歳で、育休取得中の身です。
父親として家事育児は妻と半々で行い、上の子2人が生まれた時から育児は一通りやってきました。
この2回の育児経験があるので3回目の乳児育児は同じようにやっていれば楽勝だと思っていましたが、そう上手くはいきませんでした。新生児から生後6ヶ月の育児で、上の子と違った点を書き出してみます。
3人目の育児で初めて感じたこと1:吐き戻しが多い子がいる
個人的に最も痛感しているのが、吐き戻し問題です。
上の2人が赤ちゃんだった時は困らなかったのですが、3人目は吐き戻しがすごいです。授乳後はおろか、2時間後でも吐くことがあります。
そのため少なくとも授乳後は絶対安静、しばらく抱っこで横にしておかないといけません。
最近は寝返りができるようになり、仰向けで一人にしておくとうつ伏せになって吐きます。
そしてまだ頭を上げ続けていられないので、吐瀉物まみれの床に顔からダイブしては顔面クリームまみれみたいになっています。
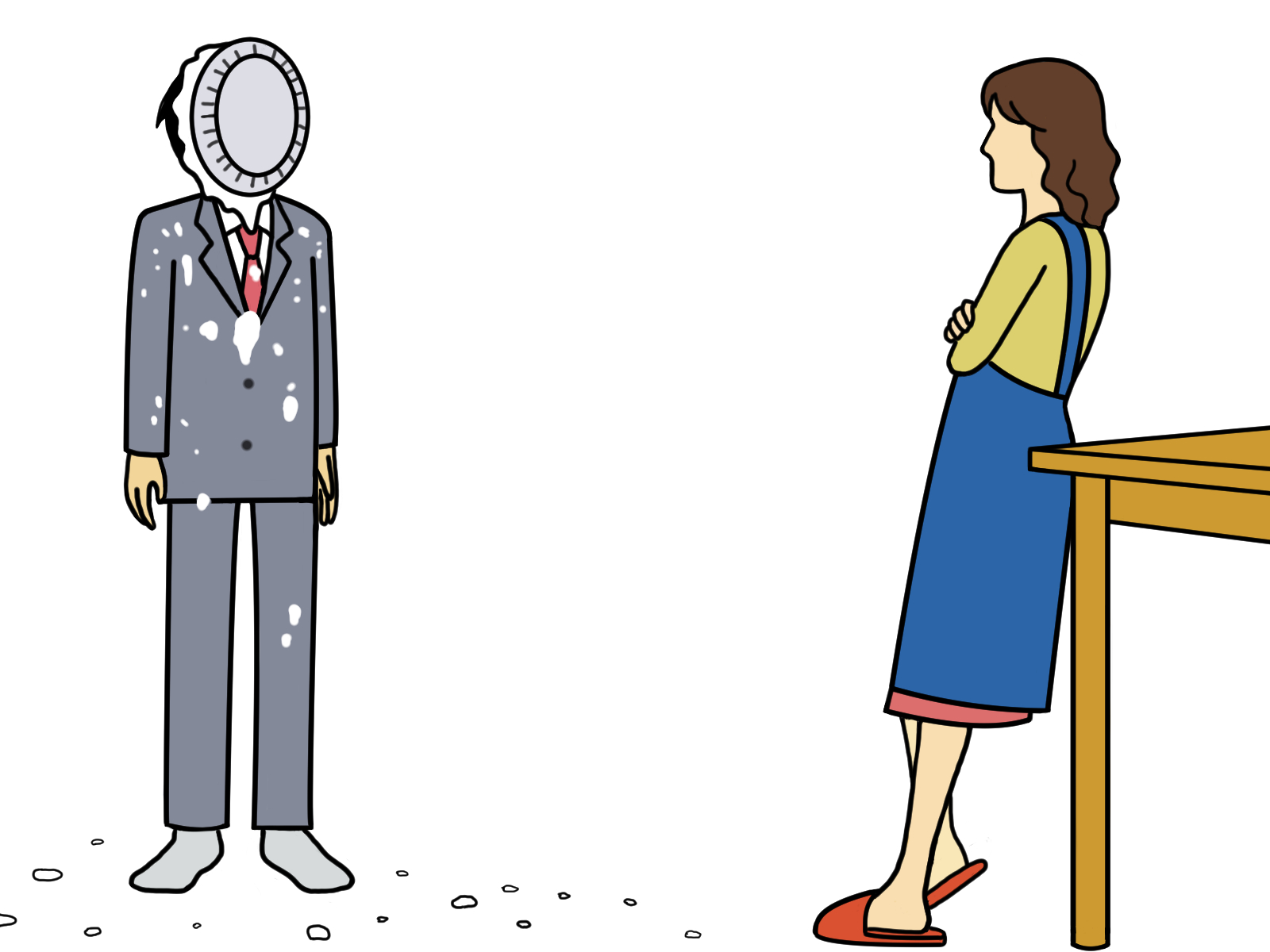
抱っこで散歩中に吐かれることもよくあります。
最終的に吐き戻しをなくすことは諦めて、後処理を楽にする方向に行きつきました。

敷物は布製のマットをやめて耐水性のマットに、そしておもちゃは汚れが染み込みにくい素材のものにしています。
汚れたらティッシュで拭き取って捨てられるようになったので、吐き戻しストレスがかなり減りました。
このような悩みは上の子の時にはなかったので、3人目で新たに学びました。
3人目の育児で初めて感じたこと2:寝る子は寝る、寝ない子は寝ない
夜通し眠れるようになるかは、生活リズムを整えることが大事ですが個人差が大きい部分でもあります。
育児記録アプリで同時期の夜間睡眠時間を比較したところ、上の子は生後2ヶ月を過ぎた頃には夜通し眠れるようになっていましたが、3人目は4ヶ月経過してようやく定着しました。
実は3人目の睡眠環境については、上の子での経験と最新の寝かしつけ理論を駆使して意識的に取り組んだので、この結果は意外でした。
それを踏まえて私の感覚的には「寝る子は寝る、寝ない子は寝ない」です。
とはいえ差があるだけでどの子もいずれ夜通し眠るようになるので、過度に気にせず個性を尊重して気長に子育てをしていくのが、精神的に楽なのかなと思います。
3人目の育児で初めて感じたこと3:早いうちに哺乳瓶慣れしておいた方がいい

赤ちゃんの個性というより育て方の話になりますが、哺乳瓶で授乳するには赤ちゃんの慣れが非常に重要ということを痛感しています。
我が家の場合は生まれてからしばらく直接授乳主体にしていたところ、哺乳瓶を嫌がるようになってしまいました。
生後3ヶ月から哺乳瓶で飲ませる練習を始めたのですが、慣れることなく生後6ヶ月になってしまいました。
哺乳瓶で授乳できないと、行動範囲が制限されます。
ある程度決まったタイミングで授乳しないといけないので、授乳室など授乳できる場所を確保しておかないといけなくなります。
哺乳瓶でミルクを与える場合は荷物は多くなりますが、比較的どこでも授乳ができます。
何より、母親が時間を気にせず一人で出かけることができるのは大きなメリットです。
また酒など食生活の面で、場合によってはミルク授乳が必須になることもあります。
完全母乳で育てる方針の場合でも、哺乳瓶で母乳を飲ませる練習は生後2ヶ月くらいまでにやっておく価値があると思います。
我が家の場合は上の子の卒園式や入学式があり、赤ちゃんが騒ぐと迷惑をかけるのでベビーシッターに預けたのですが、ミルク授乳できないので預ける方法を検討するのに苦労しました。
何回目でも子育ては新たな発見がある!
子育て経験は多い方といってもたった3回なのですが、結論はこれに尽きます。
加えて2人目以降を育てていると、親のステージも変わってきます。
具体的には体力面の変化や仕事の責任の大きさ、将来の見通しなどです。
そういったことも踏まえて、子供1人1人に対するオーダーメイドの育児方法を見つけていくのが親の務めなのではないかと思います。
この記事を書いた人