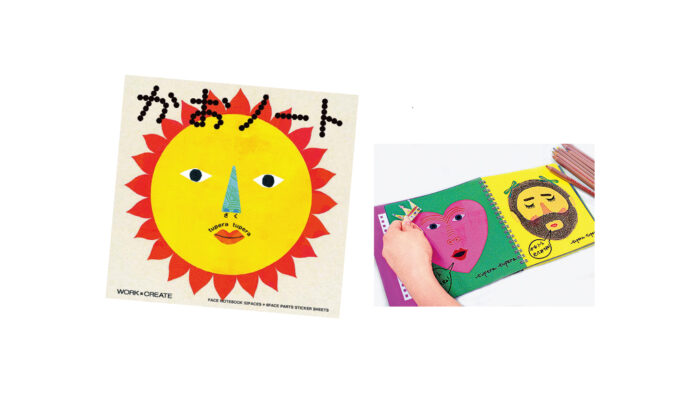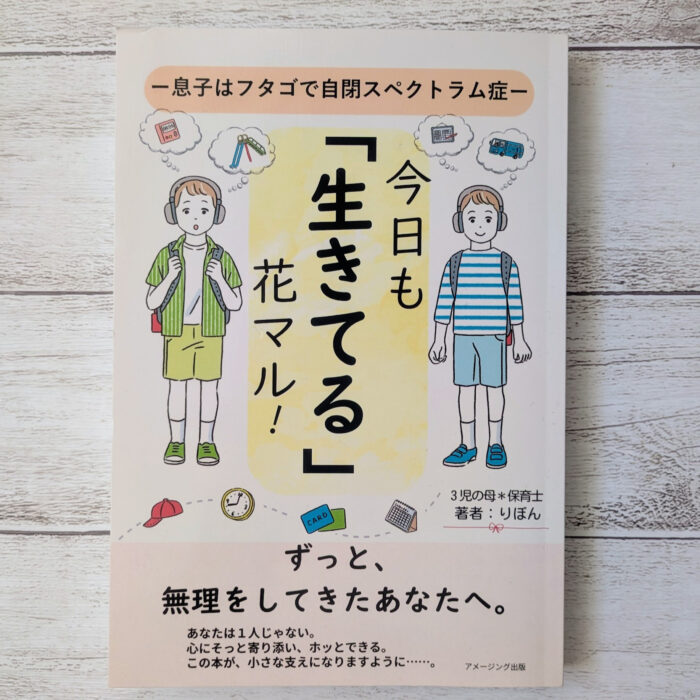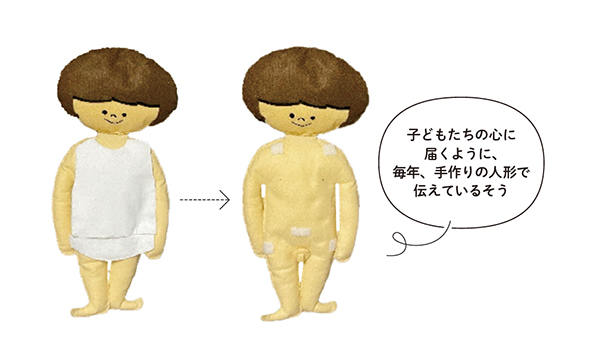「愛着障がい」ってなに?「愛着」の4タイプと2つの愛着障がいをやさしく解説【Part3】

近年「愛着障がい」という言葉が広く知られるようになりました。愛着に問題のある子の行動が、発達障がいの子どもの特徴とよく似ていることから「もしかしたらうちの子って、愛着障がいなんでしょうか?」、「愛着障がいにならないか心配です」という相談をいただくことがあります。今回は、「愛着」シリーズのまとめとして、愛着の4タイプと、愛着障がいの具体的な特徴について、スクールカウンセラー、発達凸凹コンサルタントの立場から、わかりやすくお伝えします。
関連記事:「愛着障がい」ってなに?発達障がいとの違いと「愛着形成」の基礎知識をやさしく解説【Part1】はこちら
関連記事:「愛着障がい」ってなに?「愛着形成」に大切な“三つの基地”をやさしく解説【Part2】はこちら
愛着の4タイプ
幼少期に形成された愛着は、その現れ方から安定型、不安型、回避型、無秩序型という4つのタイプに分けて考えられます。これらは「愛着のスタイル」と呼ばれることもあります。
ここでは、それぞれの特徴について説明します。
安定型
愛着がしっかり形成されている場合を安定型といいます。子どもは保護者や養育者に対して「安心できる」と感じており、困ったときには「安全基地」に戻って頼ることができます。
「安定型」というと、いつも穏やかなイメージがあるかもしれませんが、安定型の子でも保護者と離れる際に嫌がったり拒否することがあります。たとえば、登園時に離れがたくて泣いてしまうお子さんがいますよね。しかし、安定型の子は泣き続けるのではなく、先生の言葉に安心して遊びに参加し、落ち着いて過ごすことができます。また、お迎えの時に親の顔を見てうれしそうに喜び、今日あった出来事を話すといった姿がみられます。
不安型
このタイプのお子さんは、母子分離不安が強く、常に確認を求める行動がみられます。
具体的には、保護者と離れる時に強い拒否反応を示します。安定型の子も、離れることを嫌がることがありますが、不安型の場合は癇癪など、より激しいかたちで拒否をします。先生の声かけにも応じず、長時間泣き続けることもあります。さらに、お迎えの際にも激しい反応を見せることが特徴です。怒ったり泣いたりしながらお迎えに来た保護者を叩き、落ち着くまでに時間がかかることがあります。
回避型
感情表現が少なく、独立心が強い傾向にあります。
たとえば、親と離れるときに混乱することはなく、再会しても反応が薄かったりよそよそしいことがあります。一見すると落ち着いているように見えますが、「どうせ親に頼っても叶わない」と誤学習を重ね、内面には不安や孤独を抱えている場合があります。
無秩序型
このタイプの子は、一貫性のない混乱した行動パターンを示します。虐待経験があるなど、複雑な背景が関係している場合もあります。
つまり、保護者や養育者が子どもに恐怖を与える存在でありながら、同時に唯一の安心の対象でもあるのです。一貫して安心できる関わりを経験していないことが多く、対人関係にも混乱が生じやすい傾向があります。
愛着の4タイプについて知ると、「わが子は◯◯型かな?」と考えたくなるかもしれません。しかし、一部の行動が当てはまるからといって「自分の関わりが間違っていた」と責める必要はありません。
もし今後、お子さんが困ったりトラブルに直面している時に、この4タイプを思い出して関わりかたを見つめ直し「もっとできることはないか」を確認してもらえたらうれしいです。
愛着障がいの2タイプ
先に紹介した「愛着の4タイプ」は、愛着がある程度形成されていることを前提にしています。一方、愛着障がいは、初期の養育環境の不適切さなどを背景に、対人関係の結びつきや行動に特有の困難が現れる状態です。
さらに、愛着障がいは行動の現れ方をもとに2つのタイプに分類されます。
反応性愛着障害
困っていても人を頼れないタイプです。誰かに頼ることが苦手な人は多くいますが、反応性愛着障害の場合は、親や家族にさえ頼ることができなかったり、そもそも「頼る」という選択をせず、すべて自分で解決しようとします。
警戒心や恐怖心が強く、人を避けることがある一方で、「見捨てられないか」を確かめるために相手を試すような行動(試し行動)を繰り返して愛されていることを確認することもあります。
その他の特徴として、自傷行為、嘘をつく、自己評価が低い、人目を過剰に気にするなどが挙げられます。
脱抑制型愛着障害
人なつっこく見える一方で、協調が難しい場面があるタイプ。例えば、知らない人にも抱きついてしまう、居場所を求めて優しい人についていってしまうなどの行動が見られます。「自分を見てほしい」という気持ちが強く、相手の要求に過剰に応えてしまうこともあります。そのため、大人になってから恋愛や人間関係でトラブルにつながることもあります。
その他の特徴として、落ち着きがない、わがまま、空気が読めないなどが挙げられます。
愛着形成チェックリスト
愛着の4タイプや、愛着障がいの2タイプを詳しく知ると「うちの子にも当てはまる」と感じ、「もしかして愛着が形成できていないの?」と不安になる方もいるかもしれません。
次に紹介する愛着形成チェックリストは、普段のお子さんの様子をもとに、
・よくある行動 2点
・ときどきある行動 1点
・全くない行動 0点
と数え、合計するものです。ただしこれは医療的な診断を行うものではなく、あくまで参考に留めてください。気になる場合は、医療機関や相談機関、スクールカウンセラーなど専門家にご相談くださいね。
- 見知らぬ人に対して警戒心がなく、誰にでも懐く
- 目を合わせることを避ける
- 「嘘をつく」「盗む」などの行動が繰り返しみられる
- 強い不安や恐怖を示すことがある
- 夜、なかなか寝付けなかったり、悪夢にうなされたりする
- 自分の感情をうまくコントロールできず、癇癪を起こしやすい
- 「自分はダメな子だ」「誰も自分を好きではない」などと否定的な発言をする
- 新しい環境や変化に不安を示す
- 周りの注目を集めようとし、わざと問題行動を起こしたりする
- 同年代の子どもとうまく遊べない
- 褒められても喜ばなかったり、他者からの肯定的な反応に不信感を示したりする
- 過度に親や養育者に依存し、自分でできることでも助けを求める
- 食事の問題(極端な好き嫌い、過食、隠れ食いなど)がある
- 自分の身体を傷つける行為(頭打ち、爪かみ、皮膚をむしるなど)がある
- 特定の大人に対して極端に警戒的であったり過度に従順であったりする
合計点の目安
- ブルーゾーン(0〜10点)日常の範囲。経過を見守りましょう。
- イエローゾーン(11〜20点)気になる点が複数。家庭での関わりの見直しや園・学校への相談を検討。
- レッドゾーン(21〜30点)専門機関への相談をおすすめします。
これは、不安を煽るためのチェックリストではありません。愛着形成は、いつからでもやり直すことができます。
とはいえ、たくさんの項目に当てはまっている場合「どう関わったらいいかわかりません」という悩みが出てきますよね。
どうしたら愛着が形成できる?
さいごに、愛着を形成するための基本ポイントをお伝えします。赤ちゃんや幼児だけへの関わりに思えるかもしれませんが、中高生など年齢の高いお子さんにも有効です。
応答的な育児
泣いたときや「ねぇお母さん?」などの呼びかけに、できるだけ早く応じる。
スキンシップ
抱っこ、おんぶ、マッサージなど。反抗期の子には、ハイタッチや肩を叩くなど無理のないスキンシップも有効です。
アイコンタクト
目を見て語りかけることは、子どもの成長や発達にも大切です。お子さんが目を合わせることが苦手であっても、避けるのではなく少しずつ練習します。
感情の共有
喜びも悲しみも一緒に感じ、感情メーター(イラスト)や言葉のサポートで、自分の気持ちの言語化を支援します。
一貫した対応
ルールが曖昧であったり、子どもへの指導にブレがあると混乱するので、注意の基準や対応を揃え、予測できる環境を整えます。
特別な時間
毎日10〜15分、子ども主導の遊びを見守ります。勝敗のないゲームや、ブロック遊びなどの共同作業がおすすめです。
「こんな単純なことでいいの?」と感じるかもしれませんが、情緒的で一貫性のある対応を積み重ねていくことで子どもは「いつも自分を守ってくれる」と安心を抱きます。
「子どもとしっかり愛着を結びたい」「子どもにとっての“基地”になりたい」と考えているあなたなら、大丈夫です。
ナビゲーター
担当カテゴリー
子どもの健康・発達
公認心理師・スクールカウンセラー・発達凸凹支援コンサルタント 西木 めい
大学教育学部(特別教育専攻)卒業。小学校の通常学級の担任を8年、特別支援学校(小学部) の担任を5年、自治体の就学支援委員会(就学相談)の調査員、特別支援教育コーディネーターを経験。
「優秀な同僚の先生たちが、保護者と揉めて心を病んで、どんどん学校を辞めていく現状」を見て、専門職であるスクールカウンセラーになることを決意。現在は、小学校と中学校のスクールカウンセラーとして、親子や先生のカウンセリング、学校内の環境調整のコンサルティング、不登校や登校しぶりの再登校のサポートなどを行う。
一方で、SNSを通じた「発達凸凹支援コンサルタント」として、これまで2300人以上のママ・パパ、先生のお悩み解決コンサルを行いながら、発達凸凹っ子のママや、子どもの不登校・登校しぶりに悩むママに向けたオンライン講座、小学校の保護者100名以上が集まる子育て講演会などを開催。特別支援教育が「教育の一番の根本」であることを啓発している。2児の母。著書に『発達障害のある子を支える担任と保護者の連携ガイド 』(明治図書)がある。