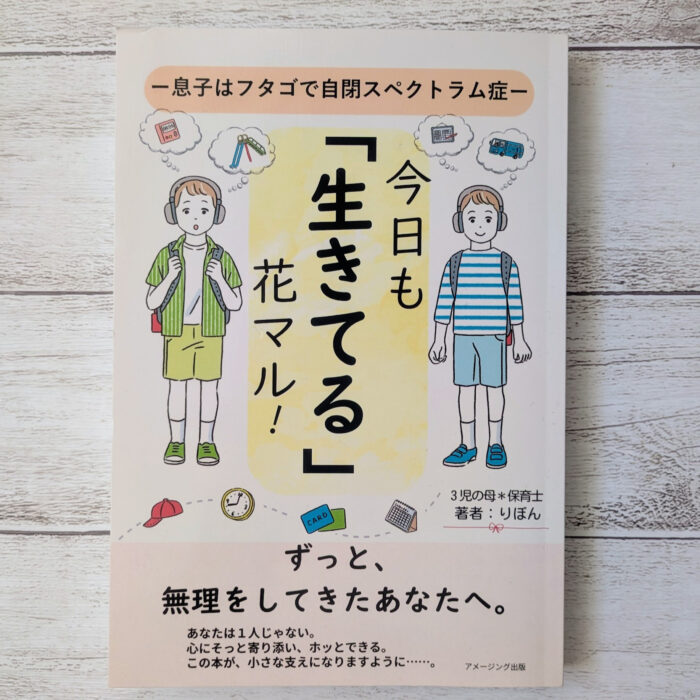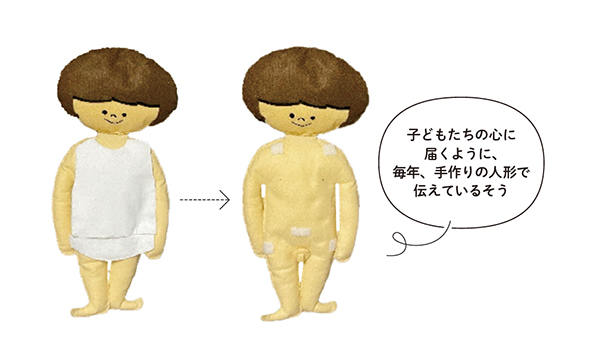HSPってなに?発達障がいとどう違う?自分や子どもが「繊細さん」かもと思ったら

「HSP」や「繊細さん」という言葉をご存じですか?発達障がいの特徴とよく似ていることから「うちの子はHSPなの?」、「発達障がいと似ているけれど何が違うの?」という相談をいただくことがあります。今回は、近年注目されているHSPについて、スクールカウンセラー、発達凸凹コンサルタントの立場からお伝えします。
HSPってなに?
「人の気持ちを考えすぎてしまってしんどい」「周りの人が気づかないような細かいことまで気になる」「いつもと違うことに敏感で疲れてしまう」。こういった悩みを感じ、原因や解決策を探ろうと調べ始めると「HSP」という言葉に出合うことがあります。
HSPとは、Highly Sensitive Person(非常に感受性の強い人)を略した名称です。子どもの場合は、HSC(Highly Sensitive Child)といいます。人口の5人に1人程度の割合で存在し、五感が一般より敏感になるという特性があります。日本では「繊細さん」という名称でも呼ばれることがあり、この名称が周知されるようになり、メディアで取り上げられるようになりました。
HSPってこんな感じ
なんとなく名前は聞いたことがあるけれど、「一体何が“繊細”で“敏感”なの?」という疑問がわいてきますよね。まずは、よく知られている特徴を挙げます。
・音や光、におい、温度などの刺激に敏感である
・周りの人の気持ちを察しやすい
・深く考えすぎてしまう傾向がある
・環境の変化に強く影響を受けやすい
発達障がいと似ている!?
実は、先ほど触れたHSPの特徴の一部は、発達障がいの特徴と重なるものがあります。例えば、感覚過敏や、コミュニケーションの困難さなどが代表的で、より詳しく説明すると以下のようなものが挙げられます。
・特定の音や光で極度の不安や恐怖を感じる
・集団活動で困難がある
・感覚の過敏さで日常生活に困りごとが多い
・年齢に応じたコミュニケーションの発達に困難さがある
要注意!HSPと発達障がいの違い
HSPと発達障がいは似ているところが多くありますが、ご自身で判断するのは禁物です。HSPは「特性」であって「障がい」ではないのです。HSPは一般よりも刺激に敏感な「気質」や「特性」、「発達障害」は医学的な診断名(脳の発達の特性に基づく診断)という違いがあり、HSPには医学的な診断基準がないのです。
自分や子どものことを「HSP」だと決めつけてしまうと必要なサポート、支援が遅れる可能性があります。
HSPの子どもの強み
「敏感」で「繊細」がゆえに、生きづらさを抱えているというイメージを持たれがちなHSPですが、その特性が強みになることもあります。
・イマジネーションが豊か
・繊細な気配りができる
・周りをよく見て、深く思考を巡らせる
・芸術的な感性がある
HSPという言葉が広がりを見せたのは、「わたしもそうかもしれない」と感じる人が多くいたことが関係しています。「繊細だけれど大丈夫」、「あなたは何も変わらなくていいんだよ」とHSPの特性をまるごと受けとめることが大切だという考え方が示されたことが、人々の共感を呼び、広まっていったからです。
ここで気をつけたいことは、HSPには強みがあるのだから「このままで平気」「強みを活かしていけるはず」というメリット「だけ」に注目してしまうことです。また、「うちの子は発達障がいではなくて、HSPだから大丈夫」という考えにこだわってしまうケースも見られます。重要なことは、障がいかどうかではありません。
もし「今困っている」という子どもがいたとして、そのアプローチが断たれてしまっては、困りごとの解決にはつながりません。
HSPの子どものサポート方法
では、どのようなことに気をつけたら、生きづらさや困り感を持っている子どもの負担の軽減につながるのでしょうか。取り組みやすいサポートの一部をお伝えします。
・刺激の少ない環境を整える
・予定の変更は早めに伝える
・休息時間を十分に確保する
・本人のペースを尊重する
実はこれらのサポートは、発達障がいの人に対するサポートと同じものになります。つまり、HSPであろうと発達障がいであろうと、できることは一緒だということです。
HSPの枠に当てはめないメリット
HSPは医療的な診断名ではないため、まだその取り扱いがあやふやなことがあります。そのため、自己診断のような形で「自分は(子どもは)HSPなんだ」と受け止めている人が多くいるのも事実です。ここではHSPという枠に、勝手に当てはめないことのメリットをお伝えします。
・医療的な診断に、素早くつながれる可能性
・より専門的な支援につながれる可能性
・福祉的なサービスにつながれる可能性
・より正しい自己理解ができる可能性
枠に当てはめるのではなく、社会で生きやすくなるためにはどうしたらいいか、その方法を探す気持ちを持ち続けることが重要なのではないでしょうか。
「HSPです」と伝えることのデメリットと伝え方
「わたしってHSPかもしれない」「うちの子はHSCの気質がある」と感じた時、自分の感じていることを周りの人にも理解してもらえたらうれしいですよね。ただし、単刀直入に「わたしHSPなんです」と伝えることはあまりお勧めできません。なぜなら、次のような理由があります。
・「じゃあどうしたらいいか」が相手に伝わらない
・「HSP」を「知ってるよね?」感(相手を置き去りにしがち)
・コミュニケーションを取りにくくする可能性
つまり、突然「わたしHSPなんですよね」とだけ伝えられると、相手の人は「どうしたらいいの?」と疑問を感じたり「何か言ったら傷つけてしまうかも」という不安を抱いてしまう可能性があるからです。
学校の先生に「うちの子はHSCなんです」と伝えたことがきっかけで、先生が過剰に気を使い、関わりが希薄になってコミュニケーションの分断が起きてしまったというケースもありました。自分のことを理解してもらいたくて勇気を出して話したのに、その意図がうまく伝わらないと悲しいですよね。
そんな時は「〜〜なところがあるから、△△してもらえるとうれしいです」「〜〜な環境が苦手なんです」と一言付け加え、関わりのヒントを添えるとよいでしょう。相手の人も安心してコミュニケーションをとることができます。
HSPと決めつけず、「生きやすくするためにどうしたらよいか」を考えよう
「HSP」かも?と思うことは、決して悪いことではなく、理解を深めることにつながります。ただし、「HSPだから」と決めつけてしまうことで、医療や福祉とのつながりや、困り感の解決につながらない側面もあります。
誰もが、苦手さや困難さは抱えていますが、「生きやすくするためにどうしたらよいか」を考えることが、子どもや自分自身への最大のサポートになるのではないでしょうか。
ナビゲーター
担当カテゴリー
子どもの健康・発達
公認心理師・スクールカウンセラー・発達凸凹支援コンサルタント 西木 めい
大学教育学部(特別教育専攻)卒業。小学校の通常学級の担任を8年、特別支援学校(小学部) の担任を5年、自治体の就学支援委員会(就学相談)の調査員、特別支援教育コーディネーターを経験。
「優秀な同僚の先生たちが、保護者と揉めて心を病んで、どんどん学校を辞めていく現状」を見て、専門職であるスクールカウンセラーになることを決意。現在は、小学校と中学校のスクールカウンセラーとして、親子や先生のカウンセリング、学校内の環境調整のコンサルティング、不登校や登校しぶりの再登校のサポートなどを行う。
一方で、SNSを通じた「発達凸凹支援コンサルタント」として、これまで2300人以上のママ・パパ、先生のお悩み解決コンサルを行いながら、発達凸凹っ子のママや、子どもの不登校・登校しぶりに悩むママに向けたオンライン講座、小学校の保護者100名以上が集まる子育て講演会などを開催。特別支援教育が「教育の一番の根本」であることを啓発している。2児の母。著書に『発達障害のある子を支える担任と保護者の連携ガイド 』(明治図書)がある。