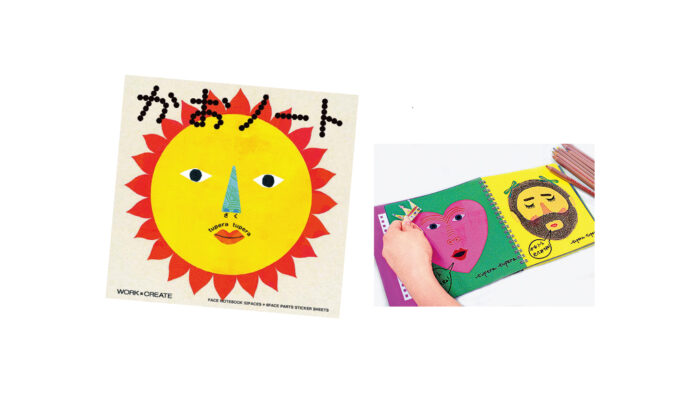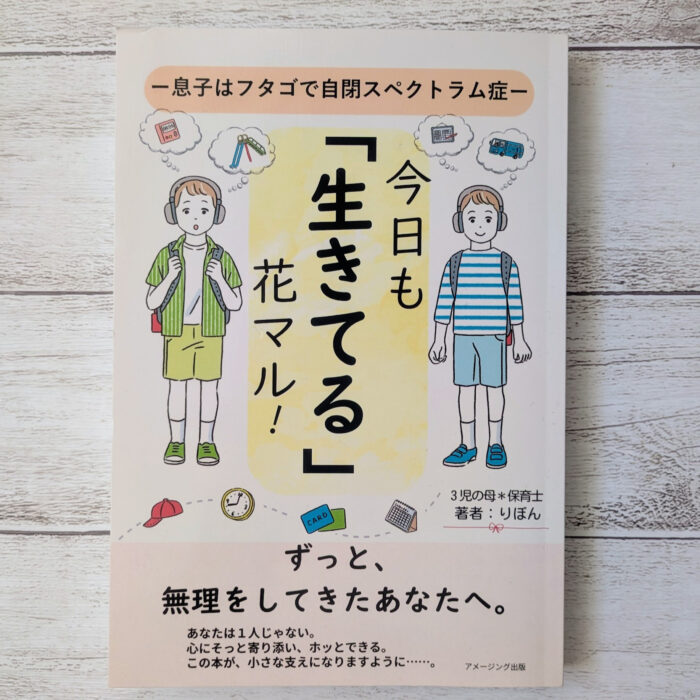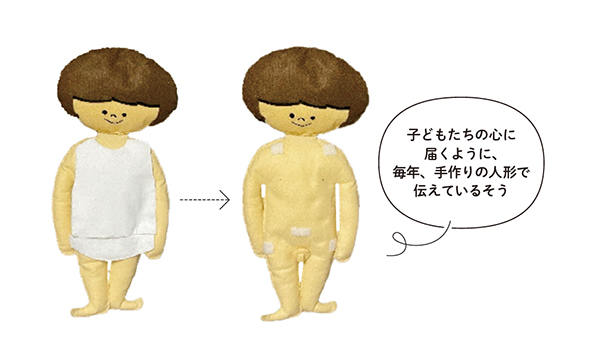上の子と下の子の睡眠リズムが合わない!きょうだいがいるご家庭の寝かしつけ方法

「上の子と下の子の眠くなる時間がバラバラ」「一人で二人を寝かせるのが大変で毎晩ヘトヘト...」など、きょうだいがいるご家庭ならではのお悩み、ありますよね。特にワンオペ育児の方は悩みが深いのではないでしょうか。
今回は乳幼児睡眠コンサルタントのねんねママが、きょうだいの睡眠リズムが合わないときの解決方法をご紹介します。
きょうだいの寝かしつけのコツは?
きょうだいの寝かしつけをラクにしていくコツは、下の子をねんね上手にすることです。なぜなら、お兄ちゃんやお姉ちゃんになった子は赤ちゃんがえりなど「ママを取られた!」というメンタルになりがちなので、そんな時期に「赤ちゃんを寝かせるからお兄ちゃんは一人で寝て」と言われると、寂しさが増してしまい、かえって親への依存が強くなることもあるためです。下の子は月齢が低い=まだクセも浅くて自我も少ないので、スムーズに練習をしやすいのです。
下の子がセルフで寝られるようになれば、きょうだい育児がぐんとラクになります。そんなきょうだいの寝かしつけ方には大きく分けて2つの方法があります。1つずつご説明していきます。
上の子の一人っ子タイム
メリット
時間差で寝かしつける最大のメリットは、上の子の「一人っ子タイム」を作れることです。下の子が眠った後、上の子とゆっくり過ごす時間があることで、上の子の寂しい気持ちを埋めてあげることができます。また、下の子の寝かしつけに時間がかかったり、ネントレなどで泣いてしまったりしても、(少なくとも就寝時は)上の子の睡眠に影響しないのも大きなメリットです。
※同室で寝る場合、夜中もネントレをするなら泣き声が上の子に影響します
デメリット
デメリットは上の子に待っていてもらう時間が必要になることです。
下の子がセルフねんねを獲得できているなら「おやすみ〜」と寝室でバイバイするだけで良いのですが、そうでない場合は多少なり下の子の寝かしつけに時間を要します。
その際、上の子がまだ1-2歳と小さいと一人で待機をしているのが難しいことも多くあります。寝室についてきて赤ちゃんにちょっかいをかけて起こしてしまったり、大きな声を出して寝かしつけの邪魔をしてしまったりすることもあり、そうなるとママのイライラにつながってしまいます。
上手に待機してもらうための工夫としては、お手伝い係として役割を与えるのが有効です。例えば「ごめん、ちょっとオムツを持ってきてくれる?」「ママの代わりにトントンしてあげてくれる?」などとおしごとをお願いすることで、意気込んでやってくれることも期待できます。自分も寝かしつける側の役割を担っていると思うと、静かにしてくれやすくなります。
同時に寝かしつけるには?
メリット
特に上の子がまだ小さい場合、一人で待っているのが難しいことがあります。そんなときは、同時に寝かしつける方法も効果的です。時間差だと下の子の寝かしつけを待っている間、どうしてもYouTubeを見ながら待機している上の子も多いのも事実。同時に寝かしつけをすれば、上の子に絵本を読みながら下の子に授乳など、二人を同時にねんねに導いていくことが可能になります。
一度に二人とも寝かせられるため、時間効率が良いのが最大のメリットです。
デメリット
同時寝かしつけのデメリットは、お互いが影響し合って時間がかかりがちなところです。 下の子に授乳をしていると、上の子が嫉妬してちょっかいをかけたり、ママの気を引くためにわざと大きな声を出したりすることもあります。
2人を同時に寝かしつけるコツは、ルーティーンを一緒にして部屋の電気を暗くして、心理的にも身体的(ホルモン分泌)にも眠りに導く状態を作っていくことです。
暗い状態になると人は眠くなるようにできているので、とにかく明かりを消して絵本を読んだり、お話をしたり、マッサージしたりなどリラックスできるようなルーティーンをして過ごしましょう。大きな声を出してママの気を引かなくても「上の子のことを見ていますよ」とアピールをするために 上の子だけにわかる秘密のハンドサインを作っても有効です(実際に我が家でやっておりました)。
まとめ
どちらの方法を選んでも、下の子がセルフで寝られるようになることが、きょうだい育児を楽にする鍵です。
生後6ヶ月まで:癖がつかない寝かしつけを意識
生後6ヶ月までは、本格的なねんねトレーニングはまだ早い時期。この時期はできるだけ癖がつかない方法で寝かしつけることを心がけてみると良いでしょう。
- 抱っこでうとうとさせた後、完全に寝る前にベッドに置く練習
- まずはベッドに置いて、2-3分だけトントンなどで待ってみる練習
- 授乳で寝落ちはさせずに、抱っこや見守りをしてみる練習
一度に大きな成果を求めず「今日はいつもよりちょっと抱っこの時間が短く寝られた」「今日は抱っこなしで寝られた」など、小さな成功を積み重ねることが大切です。
生後6ヶ月以降:段階的なねんねトレーニング
生後6ヶ月を過ぎると本格的なネントレのアプローチが可能になります。ファーバーメソッド(タイムメソッド)やS L S(フェイドアウトメソッド)などと呼ばれる方法が代表的ですが、泣いていても抱き上げずに見守り、自分で寝る力をつけていきます。この時、どうしても夜中は下の子の泣き声で起こされてしまいがちなので、もし別部屋があるのであれば上の子は別の部屋に避難する、もしくは夜中にどうしてもうるさくて眠れない時に避難できるように準備しておくと望ましいです。
完璧を求めすぎず、現実的にできるラインを見つけよう
一人で二人を相手にするのは本当に大変です。「今日は時間がかかってしまった」「思うようにいかなかった」という日があっても、自分を責めないでください。時間が遅くなってしまったり、上の子を待たせすぎてしまったり、下の子に手が回らず泣かせっぱなしになってしまったり…そんな日も、みんなあります。
ご家庭の中で無理なく運営しやすい寝かしつけ方法を、ぜひ見つけてくださいね。
ナビゲーター