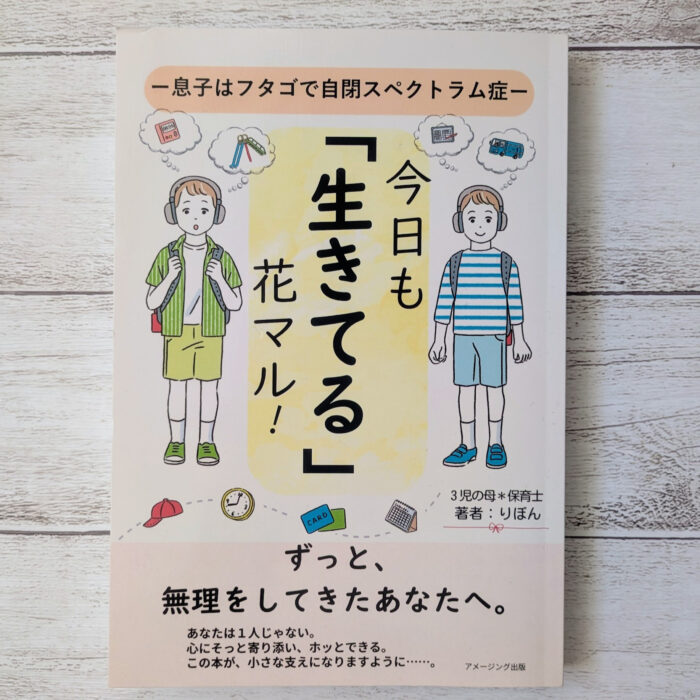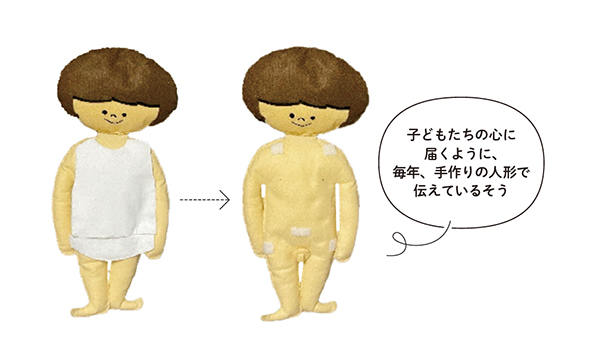完璧じゃなくてOK!子どもの心の声を聞く“がんばり過ぎない”子育てを精神科医に聞きました
毎日すくすくと育つわが子はかわいいけれど、ときにはイライラしたり、これでいいのか迷ったり……悩みは尽きないものです。毎月約400人の親子の診察を行う傍ら、SNS等での発信も人気の精神科医のさわ先生に、子どもの心に寄り添う子育てについて聞きました。
※この記事は小学館「ベビーブック12・1月号」の内容を掲載しています
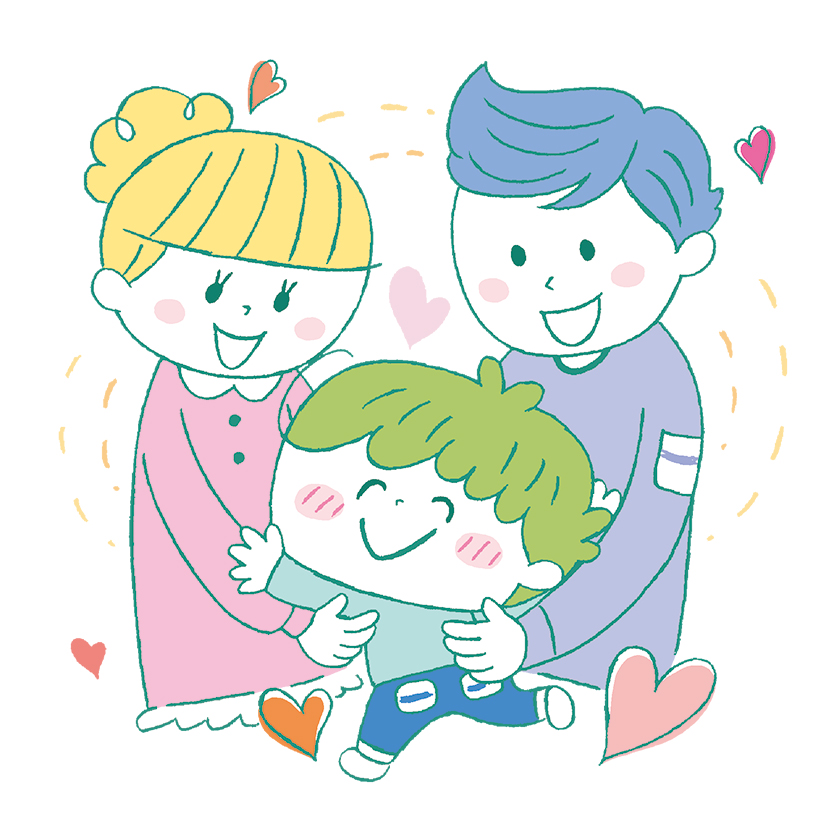
幼児期に形成された「愛着形成」 が将来の人間関係に影響
1歳から就学前は、「おうちの人との情緒的な結びつき」、つまり「愛着形成」が最も大切な時期です。これから生きていくうえで、幼児期におうちの人と築いた愛着形成のパターンを、人と関わる中で再現していく傾向があるからです。おうちの人との情緒的な結びつきが形成された子は、心理的な安心感を得ることができ、人への信頼感が芽生えます。
一方で、おうちの人から理不尽に疑われたり過度に叱責されたりし、適切な愛着形成がうまくいかなかった子は、将来的に他者を疑ったり、責める人間関係を築いてしまう可能性があります。
完璧を目指さなくていい 愛しく思う気持ちを育てよう
このような話を聞くと、自分の子育ては大丈夫だろうか?ちゃんと愛着形成ができているのだろうか?と不安になってしまうかもしれません。でも、完璧でなくてもいいのです。誰しも不完全な人間であり、完璧な親などどこにもいません。
まずは、わが子をただただ愛しいと思う気持ちを表現したり、「かわいいね」「大好きだよ」という声掛けをしたりすることが大切です。子どもはそれによって存在を祝福されていると感じられ、自己肯定感につながります。そこから、自分は生きていていいんだという当たり前の安心感が育まれていきます。
子どもの心はこう育つ
周囲の人たちとの関わりの中で子どもの心は育っていきます。どのような発達を遂げるのか、順番に見ていきましょう。
乳児~幼児期前半(0~3歳)
養育してくれる人と感情を共有し、信頼関係を築いていく中で、自己肯定感や社会性が育まれます。2歳ごろから自我が芽生え始め、自分の意思を通したいというイヤイヤ期に入ります。

幼児期後半~学齢期前半(3~10歳)
子どもは「自分が一番!」と思いたい時期があります。おうちの人にしっかり愛されることで、「自分はできる!」という大きな自信が育っていきます。

学齢期後半(10~13歳)
「一番じゃないこともある」と気づき、劣等感を抱くと同時に、自分のことを客観的に見られるようになります。自分は価値のある存在なのかを考え始めるので、ほめられることと叱られることのバランスが大事な時期です。

こんなことで悩んでいませんか?
この時期のお子さんを育てる人が抱えやすいこんなお悩み。どのように捉えればいいのか、さわ先生に聞いてみました。

他の子と比べてしまう
昨日より今日、今日より明日、自分の子どもの成長を喜んで
比較されて育った人は、子どものことも比較しやすい傾向があります。自分がされてきた子育てを無意識にしてしまいがちなのです。でも、発達は10人いれば10人スピードが違って当たり前。発達が速いからIQ が高いというわけでもありません。昨日より今日、今日より明日、過去と比べて自分の子どもが成長していることに目を向けましょう。
イヤイヤ期の自己主張が強すぎる
親子の役割を逆転させることで救われることも
イヤイヤ期の自己主張は、子どもが成長している証拠です。親として、子どもの成長はうれしいものですよね。「自我が芽生えてきたんだな」と捉えるといいでしょう。とはいえ、目の前でイヤイヤする子どもに腹が立つのも当然です。「親らしく」しようとせず、素直に「そんなこと言われたらママもイヤだ」と言ってみると、「ママもイヤなんだな」と、気持ちをわかろうとしてくれることもあります。
イライラして怒ってしまった
言葉が通じないのでイライラして 当たり前、責める必要はありません
子育てはしんどいこともたくさんあります。言葉がまだ通じないので、お互いの言いたいことが100%伝わらないというのは、人間にとって最大のストレス。イライラするのは当然ですし、それを責める必要はありません。怒ってしまったら、しっかりと愛情を伝えることをセットでするといいでしょう。
「〇〇すべき」に囚われてしまう
正解を探すより目の前のことを楽しむことを優先してみよう
がんばって生きてきた人ほど「べき」に囚われやすく、苦しくなってしまいます。結果として子どもの前で笑えなくなってしまうのはもったいないこと。何のために「べき」に囚われているのかを考えてみてください。きっとお子さんの幸せのためですよね。子どもにとって、おうちの人が笑っていることは、自分の存在が肯定されているのと同じこと。正解を探すより、目の前の子と楽しむことを優先してみてくださいね。
子どもが本当に思っていることって?おうちの人がよりそえること
子どもの心が健やかに育つためにおうちの人に心がけてほしいことは、実はとてもシンプルなことばかり。肩ひじ張らず自然体で、できることからまず取り入れてみましょう。
家庭を安心できる居場所に
家族がみんな笑顔で 穏やかに過ごすことが 心の豊かさを育む
心の土台を作る上で最も重要なのは、家庭が安心できる居場所であることです。生きる上での安心感につながり、自分が周りから喜ばれる存在だと感じることができます。将来、社会に出て生き抜く心の豊かさを育むために大切なことです。
家事や子育てにおいて完璧を目指すよりも、家の中のみんなが笑顔で楽しく穏やかに過ごすことを第一に心がけましょう。

子どものタイミングに合わせる
子どもの状況や気持ちを尊重しよう
親であっても子どもに話を聞くタイミングをうかがい、視線を合わせて話すことが大切です。子どもの状況を見ずに、一方的に話しかけたり促したりしていませんか。例えば子どもがおもちゃで遊んでいたら、「お母さん話したいことがあるんだけど、いつだったら聞いてもらえる?」と一言挟むこと。
一方的に指示するのではなく、子どもの状況や気持ちを配慮することで、お互いのストレスを減らすだけでなく「自分は尊重されている」という認識にもつながります。

子どもができていることに注目する
ダメな行動を叱るのではなく、できている行動に注目して言葉にして伝える
大人は「できていないこと」「やってはいけないこと」に目がいき、それを指摘しがちです。しかし、ダメな行動を叱るだけではなく、できている行動にも注目してみましょう。例えば、座ってご飯を食べない子どもに対して「歩き回らないで座りなさい」と言うのではなく、たとえ座って食べているのがわずか10秒だったとしても、そのときに「今日座って食べていてうれしいな」と伝えてみましょう。そうすると、その行動が増えやすくなります。

子どもを見て、聞いて、待つ
わが子を信じて、よく観察してみよう
心配性で不安の強い人ほど、わが子を「見ない、聞かない、待てない」傾向があります。見ていない、聞いていないと、子どもが何かをやりたかったり言いたかったりしていても気づくことができません。子どもを信じることも気づくこともできないため、不安で先走って「あれやりなさい、これやりなさい」と言いがちです。
しかし、待っていれば子どもは自分でできることもあります。子どもをよく観察すること。それだけでわが子の心の声が聞こえてくることでしょう。

正しい情報で正しく不安になる
過度な不安に陥らないよう情報リテラシーを身につけ、不安を客観視しよう
今は事実なのかデマなのかわからない情報があふれています。テレビやネット記事は不安をあおる傾向があり、SNSでは似たような情報が自動的に流れてくるので、ネガティブな情報ばかりを目にして、ますます不安になるという負のサイクルに陥ってしまいます。
根拠のない内容に振り回されるのではなく、情報リテラシーを身につけ、「何が不安なのか」を客観視しながら、正しい情報で正しく不安になることを心がけてみましょう。

ひとりで悩まず助けてもらおう
ひとりで悩んでいると、ますます不安が募るものです。そんなときは周りに助けを求めてください。迷惑をかけたくないと思うかもしれませんが、あなたが大切な人が追い詰められていて「助けて」と言われたら、「迷惑だ」とは思わないはずです。
初めての子育ては本当に大変です。精神科医である私も、子育てがあんなに大変だとは思っていませんでした。特に0歳、1歳、2歳のころは「助けてもらって当たり前の時期」だと言っても過言ではありません。ママ友、保健師さん、保育園の先生など、誰でもいいので遠慮せず助けを求めてくださいね。
イラスト/坂本直子 デザイン/平野晶 文/洪愛舜 構成/KANADEL

『ベビーブック12・1月号』の付録は2大完成品ふろく「アンパンマンときめきケーキやさんブロック」&「うたって おどろう♪DVD」

ベビーブック12・1月号のふろくは「アンパンマンときめきケーキやさんブロック」&「うたって おどろう♪DVD」。
「アンパンマンときめきケーキやさんブロック」は、アンパンマンとメロンパンナちゃんが、かわいいケーキやさんに大変身!
ベビーブックオリジナルの、ゆめかわパステルカラーデザインです。ポスターやケーキワゴンなど、一緒に遊べるアイテムもたっぷり!
「うたって おどろう♪DVD」は、歌とダンスがいっぱい。人気子役の永尾柚乃ちゃんと一緒に、童謡に合わせて楽しく踊れるオリジナル動画を収録。他にもアンパンマンをはじめとする人気キャラクターのお話や、乗り物・動物かんさつなど、楽しいコンテンツがもりもりです!
「ベビーブック12・1月号」 価格:1590円

この記事は小学館「ベビーブック12・1月号」の内容を掲載しています