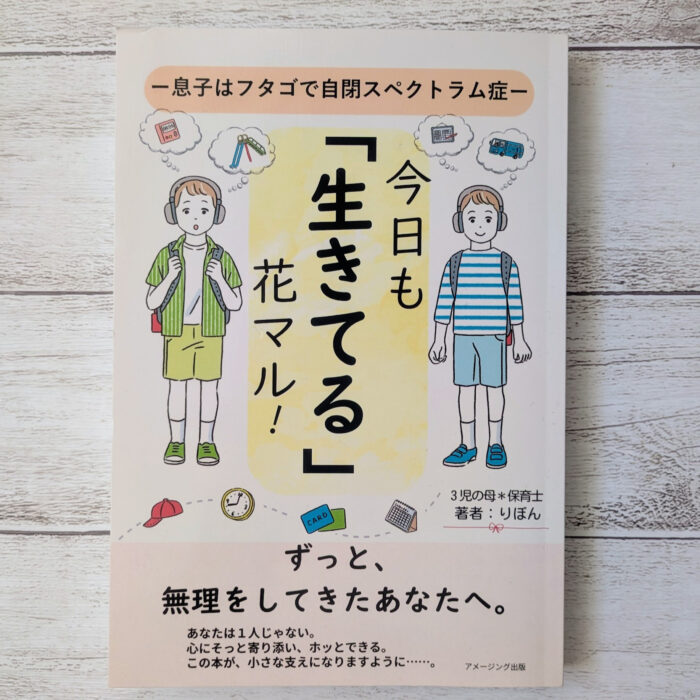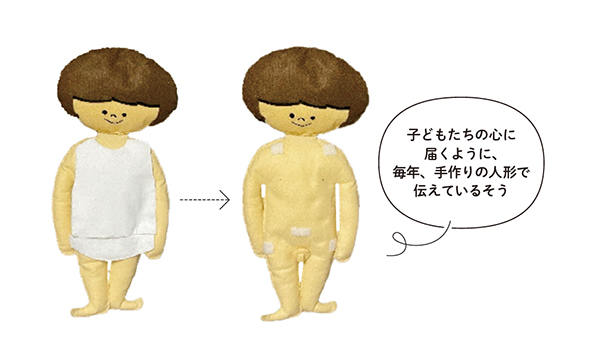【1年生の給食のリアル】好き嫌い&少食への対応は?練習できることはある?

こんにちは、ゆきこです。私は小学校教諭として9年間勤務し、現在は非常勤講師として子ども達とかかわっています。このコラムでは、「心の職員室」として、小学校の現状をお話しつつ、主に年長児のママ・パパを対象に、今から準備できることをお伝えしてきたいと思います。
小学校に入学する前、そして、入学してからの保護者の相談で多いのが「給食に関すること」です。自分ひとりで準備できるのだろうか、どれくらいのタイムスケジュールで給食時間を過ごしているのだろうか、うちの子は少食だけど大丈夫だろうかなど、さまざまな悩みがありますよね。
今回はそんな給食にフォーカスして、1年生の給食のリアルや学校での指導の様子、対応方法などをお伝えします。

1年生の給食のリアル
給食準備の方法は?
まず戸惑うのが「給食準備」。初めての経験という子どもほとんどです。そのため、どのような流れで準備をしていくのか、担任の先生がしっかり指導をしてくれます。また、しばらくは専科の先生や学校ボランティアさんが入りながらスムーズに準備ができるように指導や支援、人員確保をしています。最初のうちは、おかずをお皿によそっていくのは大人がやる学校が多いようです。また、6年生がお手伝いに来てくれる学校もあります。
しばらくは子ども達に戸惑う様子が見られますが、給食は週に5日間ありますから、1か月過ぎるころには、だんだんと要領をつかんでスムーズに準備ができるようになっていきます。
食べる時間や食べるときの席は?
食べる時間がどれくらい確保されているのかも、気になるところですよね。
4時間目終了から次の活動(昼休みの学校もあれば、掃除の学校もあります)に移るまでで考えると、1時間前後という学校が多いです。ただ、4時間目終了から白衣に着替えて、給食を運んできて、30~40人いる子どもたち全員に配膳して…という準備の時間は、早くても20分はかかります。給食を食べた後には、その食缶を給食室にみんなで運ぶ時間も必要です。そのため、実際食べる時間は20~30分程度です。
食べるときのシチュエーションは、コロナ禍は、みんな同じ方向を向いての“黙食”でしたが、最近は緩和されてきました。学級の方針やアレルギー対応などもありますので、グループにして食べるかどうかは学級や学校で違いますが、みんなで楽しくおしゃべりができるようになっていて、その様子に微笑ましさと懐かしさを感じています。
好き嫌いや少食、時間がかかる子への対応

好き嫌いが多い子や少食の子への配膳の配慮
保護者の心配で多いのは、「わが子が好き嫌いが多い、少食」ということです。
好き嫌いは誰にでもありますが、苦手なものが多い子どもや、少食な子どもにとっては、給食をハードルの高いものと感じている様子が見えることもあります。学校に行きたくない理由が「給食」と言う子どももいます。みんなで楽しく過ごしてほしい給食の時間が、しんどいものとなっていることは、悲しいことだと思います。そこで、教員である私たちは下記のように対応していることが多いです。
まず、配膳について。大きく2種類の考え方があります。ひとつは、「食べられる量を配膳する」です。この場合、苦手なものは極力減らして、その子自身が食べられる量に調整をします。その中で、苦手なものがあったとしても、「ひと口は頑張って食べようね」などと教員が声かけをします。
もうひとつが「基準量を配膳する」です。給食の供給量は、学年に応じて1人分の量(基準量)が決められていて、それをもとに提供されています。基準量を知ってもらうという観点や、給食費で払っていただいている分はしっかりと提供するべきだという観点から、そのような配膳方法をする学校や先生もいます。ただ、その中で、「食べられないものは残しても大丈夫だよ」と声をかけているようです。少食のお子さんに関しても同様の対応が多いです。
食べる時間がかかる子へのクラスでの取り組みも
食べるのに時間がかかる子どもへは、「量を調整する」か「時間を調整する」という対応をしている先生が多いです。量に関しては先ほどの通りです。時間に関しては「全体のいただきますより少し早めに食べ始める」という対応です。ただこれは、衛生面などにより、禁止している学校もあるようです。
そのほかには、「5分間だけは静かに給食を味わって食べようね」という時間をクラス全体で設けているケースも。楽しくてついつい食べることを忘れてしまうお子さんにとってはとても効果的です。
給食の悩みや対応については相談してください
「給食のことで相談をしてよいのだろうか…」と躊躇している保護者の話をとてもよく聞きます。教員側としては、ぜひ相談してもらえると嬉しいです。
給食がわが子にとってどれだけハードルの高いことなのか、分かるのは子ども自身と保護者です。年齢が上がってくると自分で言えるようになることも、1年生だとどうやって伝えたら良いか分からないことも多いと思います。だからぜひ、【お子さんが給食で悩んでいること】【学校でお願いしたい対応】は、直接担任に伝えてもらいたいと思います。
ただ、先生や学校の考えもあると思いますので“一緒に良い方法を考えていく”という方向でお話をしてもらえるといいと思います。個人面談や家庭訪問よりも、給食開始の方が先にあるところが多いので、流れとしては、「連絡帳で相談→あらためて個人面談などで詳しく話をする」というのがよいと思います。
入学前のこの時期に家庭でできることは
これまで保育園や幼稚園の給食でもたくさん練習をしてきていると思います。また配膳に関しては学校によって方法がさまざまなので入学してから身につけていけばよいでしょう。その上で、今家庭で練習できることと、保護者の給食への考え方についてお伝えしたいと思います。
まず練習ですが、基本的には必要はありません。ただ、少し余裕があり準備をしておきたいなという場合は、「20~30分で自分が食べられる量が分かる」とすごくラクかもしれません。それがわかっていれば、事前に「もう少し減らしてください」とお願いすることができます。お願いができることで、「残しちゃった」と自分をせめてしまうことも減ります。
あとは多くの自治体で行われている「牛乳パックを開く」という作業の練習でしょうか。リサイクルのために牛乳パックを開いて分別したり洗ったりする学校があります。ただ、パックの開ける部分って大人でも少し硬くて開けるのが大変なことがありますよね。それを練習しておくだけでも、少し心に余裕をもちながら片付けに臨めるかもしれません。
少食の娘から学んだこと
私の娘はとても少食でした(今も結構少食です)。苦手なものも多くて、給食はなかなかハードルの高い活動だったようです。減らしても減らしてもなかなか完食することができなかったようで、私が焦っていました。そう、私だけが。実は娘は、ちっとも焦っていなかったのです。その姿を見て、そうか、みんなと同じ量食べなきゃとか多く食べることが良いことだとか、苦手なものを克服できるようにしなきゃとか、そういうことに縛られていたのは、親である私だったんだなと反省しました。
そこからは、気長に娘の成長を見守ることにしました。すると時々、「モヤシが苦手だったけど、給食で食べられるようになったんだよ」「今日は完食した!」「今日はまさかのおかわりをしたよ!」ということが出てきたのです。彼女なりの成長があって、それを素直に喜んでいる姿を見ることができてよかったと感じました。
給食ってすごくわかりやすく差が見えるので、親も心が揺らぎますが、ぜひ長いスパンで、その子なりの成長を見守っていってほしいと思います。
食べることは生きること
食べることで、身体はどんどん作られていきます。大きく元気に成長するために、できるだけなんでもたくさん食べてほしいと願う親心はよくわかります。
でもそれよりも大切にしたいのは、子ども達が「食べるって幸せ!食べるって楽しい!」と感じることだと思っています。みんなと一緒に食べるものをおいしいと感じる、誰かと話しながら食べるのって楽しいなと思う、そんな日常がこれからの日々を支えるのではないでしょうか。そこを意識しながら、私たち教員も日々、指導をしていきます。
この記事を書いたのは

■ゆきこ先生
小学校教員として9年間勤務し、現在は非常勤講師。小学5年生と1歳児のママ。Instagramでは、「心がちょっと軽くなる職員室」として、学校がしんどい先生や繊細先生が少しでも自分らしく、心が軽くいられるように、先生のお仕事あれこれ、心を軽くする言葉、子どもと関わるときの考え方などを日々発信中。TCS認定コーチングスキルアドバイザー、キッズコーチングアドバイザー取得。Instagramのフォロワーは6.5万人