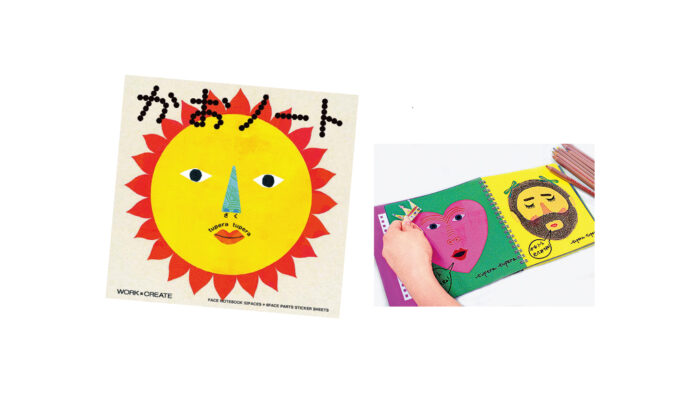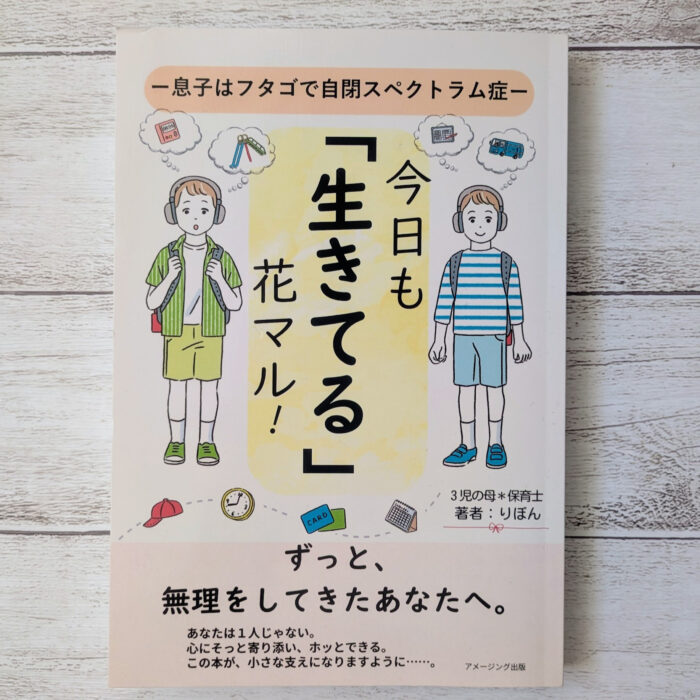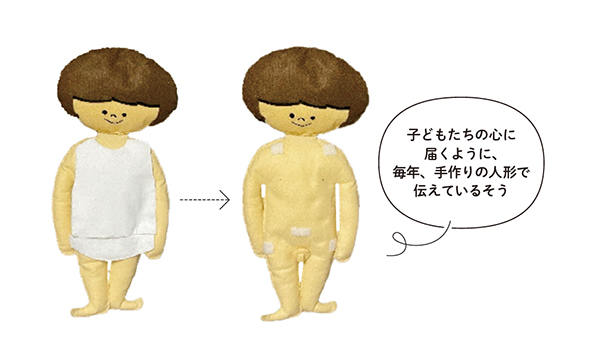小1に「早生まれだからしょうがないよ」と言うか、頑張らせるか、どちらがいいですか?

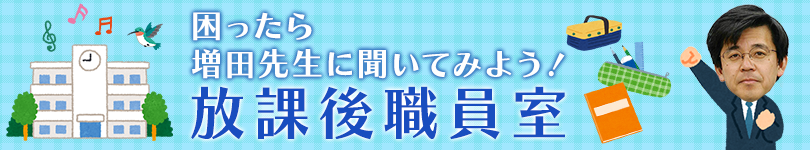
Q 早生まれな小1の息子。学校でついていけるか心配です。差がなくなるのは、いつぐらいですか?
一年生の男の子です。早生まれなこともあり、学校生活についていけるか心配です。早生まれの子と他の子との差があまりつかなくなるのは何歳くらいからですか? また、できないことに関して子どもに「早生まれだからしょうがないよ」と伝えるのと、頑張らせるのはどちらが良いでしょうか。(もち)
A 早生まれだが、小3の運動会で上位に!「負けない工夫が大事」と気づく

私も3月の早生まれなので、気持ちがよくわかります。今回は、私の体験から述べたいと思います。小学校1年生の時、体が小さかったこともあって、整列する時の「前へならえ!」は、いつも一番前で腰に手を当てていました。一度ぐらいは、手を前に上げたいものだと思っていました。もちろん、かけっこなどは遅い方でした。「4月生まれの人には、かなわない」といつも思っていました。
そんな私に大きな転機が訪れます。3年生の運動会の障害物競走の時のことです。「ヨーイ、ドン!」と一斉スタートします。もちろん私は抜かれました。しかし、網くぐりの時です。体が大きい友だちが、網に引っかかってモタモタしていました。体が大きいので、網を持ち上げた時に大きな隙間ができていることに気が付きました。その隙間に入り込み、スルスルと間をぬって網を出た時には1番になっていました。その嬉しかったことと言ったら、ありませんでした。その後、跳び箱を跳び、平均台を渡りました。残念なことに、最後の直線で1人に抜かれて、結果は2着でした。それでも、今までの自分にはないことでした。ものすごく嬉しかったことを、今でも鮮明に覚えています。
そのことから学んだのは、「体を小さいことや、早生まれを嘆いたりしても仕方がないんだな。それよりも、自分の体の小ささを長所ととらえて、大きな体の人に負けない工夫をすることが大事なんだ」ということでした。
それ以来、智恵を働かせるとはどうすることかと考え続けると同時に、「勉強なら体の大きさは関係ないんだから、ちょっと頑張ってみよう」と思うようになったのです。もちろん、そんなに急に成績は上がりませんでしたが…。
早生まれが「短所ばかりでない」ことを親子で理解する
こうした経験と、私が教師として見てきた実感から、早生まれが追いつくのは、だいたい3・4年生ぐらいのようです。なぜなら、小学校3・4年生の学習から、算数がぐんと難しくなり、面積・大きな数(億とか兆)・分数など、抽象的な概念が必要になってくるからです。知能面・体力面ともに、早生まれの子どもが追いつくのは、小学校3・4年生ぐらいと考えて良さそうです。
しかし大事なことは、そのまま自然に早生まれの子が他の子と差がなくなると考えるのではなく、それなりの働きかけが必要であることも忘れないでほしいと思います。なにしろ、4月生まれの子と比べれば、1年近くの差があるのですから。
ですから、ここで述べているように、抽象的な概念が育つように働きかけをしていくことで、その差がより一層早く埋まります。もちろん、このことは全ての子どもに言えることでもあります。面積などでは、「広いってどういうことだろう?」とか「すごく大きな数って、どう考えたらいいんだろう?」などということを、家庭で一緒に考えてほしいのです。
それと同時に、体が小さいことが長所になる場面を見つけてあげると良いかと思います。もちろん、早生まれでも体の大きい子がいると思います。その場合には、その子なりの長所を見つけて伸ばしてあげてください。どちらにしても、早生まれが決して短所ばかりではないことを、親子が理解していくことが大切だと思います。
【新刊】
新刊「子どものココロが見えるユーモア詩の世界-親・保育者・教師のための子ども理解ガイド-」(ぎょうせい、1980円)発売中。