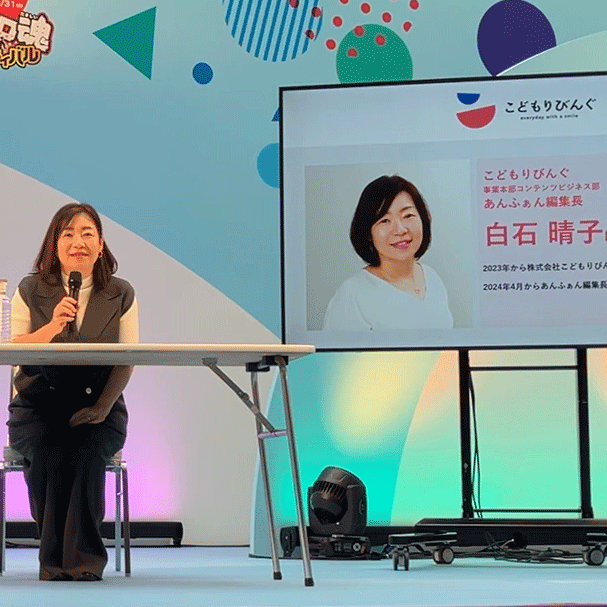あふれる情報に振り回されない!進学・習い事などの「教育情報」を取捨選択するコツ

情報を正しく読み取り、活用する力「メディアリテラシー」。さまざまなデジタルメディアが身近にある今、大人だけでなく、子どものうちから少しずつ育てていきたい力です。
このコラムでは日本メディアリテラシー協会代表理事の寺島絵里花さんが、「メディア」との上手な付き合い方について教えてくれます。今回のテーマは「情報の取捨選択」についてです。
情報があふれる時代…子どもの教育に関する情報をどう取捨選択すればよい?
新学期が始まってから約1カ月、家族の予定も落ち着く一方で、保護者にとっては「幼稚園・保育園の申し込み」や小学校受験・中学校受験のための入塾説明会が迫る時期でもあります。ネット検索をすると、教育方針、習いごと、進学に関する情報があふれていますが、その中には正確とはいえないものや、誤解を招きやすい情報も少なくありません。
今回は、膨大な情報をどう取捨選択すればよいのか、「教育情報」を例に考えていきましょう。
ネット上の情報は玉石混交
インターネット上には、先輩保護者の体験談、教育機関の公式サイト、まとめ記事、SNSでの口コミなど、膨大な情報があります。便利な一方で、情報の正しさや偏りには大きな差があります。 例えば「この園は絶対におすすめ!」や「この家庭学習が偏差値を上げた!」と書かれたブログがあっても、それはその人の価値観や家庭環境に基づいた感想にすぎません。反対に、悪い口コミも一部の体験だけに偏っている場合があります。大切なのは、ひとつの意見に引っ張られすぎないことです。
情報源をチェックする習慣を
情報を選ぶときは、「誰が発信しているか」を確認することが大切です。
● 公的機関や自治体の情報は信頼度が高い
● 園や学校の公式発表は一次情報として重要
● 個人のブログやSNSは「参考意見」として受け取る
このように、情報の「出どころ」を意識するだけで、判断の精度が上がります。
また、インターネットのアルゴリズムは「自分が見たいもの」を優先的に表示するため、検索結果が偏ることもあります。複数の検索ワードを使ったり、疑問があれば学校説明会や入塾説明会などで先生に直接話を聞いたり、学校見学をすることをおすすめします。
家族に合うかどうかを基準にする
教育情報を集めると、「この習いごとを始めたほうがいいのかな?」「やっぱり英語は早くやらせたほうが…」と不安になることもあります。しかし、一番大切なのは「わが子に合うかどうか」です。
同じ園や学校、塾、習い事でも「活発な子には合っていた」「おとなしい子には少し大変だった」など、家庭や子どもの性格によって感じ方が違います。見学や体験を通じて、自分の子どもがどう過ごしているかを確かめることが何よりの判断材料になります。
情報を整理するコツ
たくさんの情報を前にすると混乱してしまうので、次のような工夫で整理することがおすすめです。
● 気になった情報はノートやスマホにメモして「出典」を明記
● 「メリット」と「デメリット」を書き出して比較
● 家族で話し合い、優先順位を決める
この作業をすることで、情報が自分たちにとって「必要かどうか」を冷静に考えられます。

保護者に求められるメディアリテラシー
情報があふれる時代だからこそ、保護者には「取捨選択する力=メディアリテラシー」が求められます。大切なのは「すべてを信じる」でも「すべてを疑う」でもなく、情報の出どころを見極め、自分の家庭やわが子に合った形で取り入れることです。
情報との付き合い方を見直すことで、必要以上に振り回されず、子どもにとってより安心できる選択ができるはずです。
ナビゲーター
担当カテゴリー
ITデジタル
日本メディアリテラシー協会代表 寺島絵里花
一般社団法人日本メディアリテラシー協会 代表理事。高校時代に留学したカナダでメディアリテラシー教育に出合い、興味を持つ。上智大学文学部新聞学科卒業、ペンシルバニア大学留学。結婚、出産を経て、一般社団法人日本メディアリテラシー協会を立ち上げる。主な業務は、メディアリテラシー教育の普及を目的とする、保護者、教員、行政、民間企業などが対象のワークショップや研修、講演、出前授業など。
当協会立ち上げ後に東京学芸大学大学院教育支援協働実践開発専攻AI教育プログラム卒業。上海師範大学、北京師範大学での関連プログラム修了。2024年現在、JASSO 日本政府中国政府奨学金生(博士課程後期)として、華東師範大学大学院国際比較教育研究所所属。
メディアリテラシーに関する幅広い知見に加え、3児の子育てや日々の生活を発信するメールマガジンやブログが好評を博している。