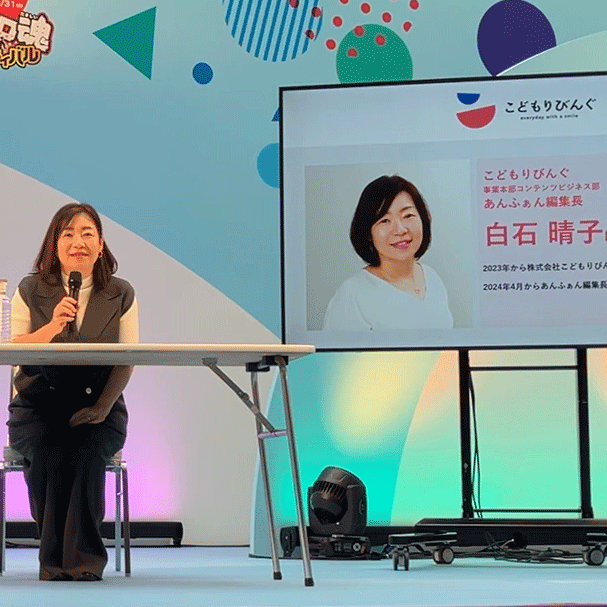未就学児でも要注意!?ネット広告との付き合い方と金銭感覚の育て方

情報を正しく読み取り、活用する力「メディアリテラシー」。さまざまなデジタルメディアが身近にある今、大人だけでなく、子どものうちから少しずつ育てていきたい力です。
このコラムでは日本メディアリテラシー協会代表理事の寺島絵里花さんが、「メディア」との上手な付き合い方について教えてくれます。今回のテーマは「ネット広告との付き合い方」と「お金の教育」についてです。
子どもにとって「お金」や「広告」は今や身近な存在
10月はハロウィンや秋のイベントが盛りだくさん。家族で買い物に出かける機会も増えますし、冬のボーナスや年末に向けて「欲しいもの」が頭に浮かぶ季節です。実は、子どもにとっても「お金」や「広告」は身近な存在になっています。スマホやタブレットのアプリ、動画サービスには広告が多く表示され、子どもが自然と触れるからです。
今回は、幼児期から始めたい「ネット広告との付き合い方」と「お金の教育」について考えましょう。
子どもは広告を「情報」として受け取ってしまう
大人にとって広告は「商品を売るためのもの」と理解できますが、未就学児など低年齢の子どもにはその区別がつきません。例えば、動画の合間に流れるおもちゃの広告を「おすすめ情報」として素直に信じてしまったり、ゲームアプリに出てくるキャラクター付きの広告を「ゲームの一部」と誤解してタップしたりします。
つまり、広告とコンテンツの境目を見抜く力=メディアリテラシーは、幼児期から少しずつ育てていく必要があるのです。
保護者ができるシンプルな声かけとは
未就学児には難しい理屈は不要です。日常の中でシンプルな声かけを心がけましょう。
●「これは買ってほしい人が出している宣伝なんだよ」
●「見ている動画とは別のものだよ」
●「欲しいと思っても、すぐに買わなくてもいいんだよ」
こうした言葉を繰り返すことで、子どもは「広告は特別なもの」と理解しやすくなります。小学生であれば、テレビや子ども向け新聞、インターネット上にある広告と記事の違いについて家庭で話し合う機会をぜひ作ってほしいものです。

課金対策とお金の感覚の身につけ方
アプリやゲームの中には、広告を見せたり「課金」を促したりする仕組みがあります。未就学児や小学生でも誤って購入ボタンを押してしまうケースは珍しくありません。
保護者ができる対策は以下の通りです。
●スマホやタブレットに「親の承認なしでは購入できない設定」を入れる(※)
●課金画面を見せないようにする
●「お金を払う=数字が減る」ことを絵やコインで視覚的に伝える
遊びの延長で自然に「お金には限りがある」という感覚を学べると、今後の金銭教育にもつながります。また、小学生ですでに子ども専用のスマホを持っている場合は、料金が毎月いくら発生しているのか、それは誰が支払いしているのかを明確に伝えましょう。
※設定方法はデバイス等によって異なります。使用するデバイスに応じて検索を
・iOSデバイスの場合:承認と購入のリクエスト
・Google Playの場合:Google Playでの購入の承認
ハロウィンや買い物を教材にする
10月〜年末年始にかけてはイベントが多い時期。お菓子や仮装グッズを選ぶときに「予算を決めて買う」「広告に出ていたものと実物を比べる」など、体験を通して学ぶチャンスです。
「今日は500円までね」「チラシで見たかぼちゃのお菓子は売り切れていたね」といった会話を重ねることで、広告をきっかけに「選ぶ力」と「待つ力」が育ちます。
リスクから子どもを守りながら、メディアリテラシーと金銭感覚を育てましょう
子どもにとって広告やお金はまだ抽象的な概念ですが、日常生活やデジタル体験の中で自然と触れるものです。だからこそ、保護者が「広告は特別な情報」「お金には限りがある」と伝えることが、早すぎることはありません。
ネット広告や課金のリスクから子どもを守りながら、買い物やイベントを教材にしていく。そんな小さな積み重ねが、これからのデジタル社会で必要なメディアリテラシーと金銭感覚を育てていきます。
また、兄弟姉妹がいる家庭は、子どもの年齢にあった設定が必要です。上の子と下の子が同じデバイスを使用する場合は、それぞれのアカウントを作って、それぞれにカスタマイズした設定を行いましょう。
ナビゲーター
担当カテゴリー
ITデジタル
日本メディアリテラシー協会代表 寺島絵里花
一般社団法人日本メディアリテラシー協会 代表理事。高校時代に留学したカナダでメディアリテラシー教育に出合い、興味を持つ。上智大学文学部新聞学科卒業、ペンシルバニア大学留学。結婚、出産を経て、一般社団法人日本メディアリテラシー協会を立ち上げる。主な業務は、メディアリテラシー教育の普及を目的とする、保護者、教員、行政、民間企業などが対象のワークショップや研修、講演、出前授業など。
当協会立ち上げ後に東京学芸大学大学院教育支援協働実践開発専攻AI教育プログラム卒業。上海師範大学、北京師範大学での関連プログラム修了。2024年現在、JASSO 日本政府中国政府奨学金生(博士課程後期)として、華東師範大学大学院国際比較教育研究所所属。
メディアリテラシーに関する幅広い知見に加え、3児の子育てや日々の生活を発信するメールマガジンやブログが好評を博している。