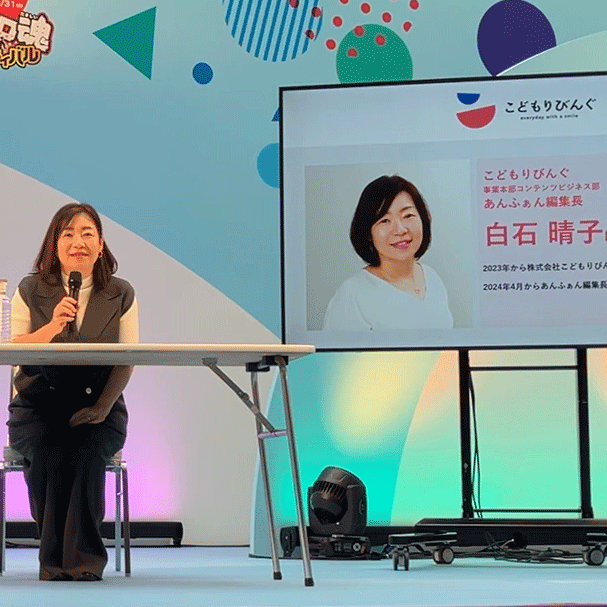クリスマスにデジタルデバイスがほしいと言われたら?メリットとリスクを知っておこう

情報を正しく読み取り、活用する力「メディアリテラシー」。さまざまなデジタルメディアが身近にある今、大人だけでなく、子どものうちから少しずつ育てていきたい力です。
このコラムでは日本メディアリテラシー協会代表理事の寺島絵里花さんが、「メディア」との上手な付き合い方について教えてくれます。今回のテーマは「デジタルデバイスの選び方」についてです。
11月に入ると、街中はクリスマスムード一色。子どもから「サンタさんにプレゼントをお願いする!」という声が聞こえてくるご家庭も多いのではないでしょうか。プレゼント候補に「タブレット」や「スマホ」「Nintendo Switch」を考える保護者も増えています。けれども、子どもにデジタルデバイスを渡す際には注意が必要です。今回は「プレゼントとしてのデジタルデバイスの選び方」について整理してみましょう。
1. デジタルデバイスのメリット
知育アプリや絵本アプリ、動画コンテンツ、オンラインゲームなど、子どもの学びや興味を広げてくれる点は大きな魅力です。長時間の移動や雨の日などに活躍し、子育てをサポートするツールとしても役立ちます。 また、タッチ操作は直感的で、未就学児でも使いやすいのが特徴です。
2. 気を付けたいリスク
一方で、使い方を誤ると視力低下や姿勢の悪化、睡眠リズムの乱れ、さらには依存のリスクもあります。特に小さな子どもは「やめ時」を自分で判断することが難しく、保護者のサポートが欠かせません。 また、インターネット接続がある場合、思わぬサイトや動画にアクセスしてしまう危険もあります。
3. プレゼント選びのポイント
デジタルデバイスを検討するなら、次の点を意識してみましょう。
●対象年齢に合ったモデルか(キッズ向けタブレット、フィルタリング機能があるものなど)
●使用時間を管理できる機能があるか(ペアレンタルコントロールや時間制限)
●学びや創造性につながるアプリを選べるか(ただ見るだけでなく、考えたり作ったりできるもの)
「安いから」「周りが持っているから」ではなく、子どもに合った環境を作れるかを基準にすると安心です。とくに、兄弟姉妹がいる場合は、年齢によって使用範囲やルールを変化させることが大切です。そのため一度決めた設定やルールは、少なくとも半年に1回は見直し、それまでの使い方の反省点や改善を話し合いましょう。
4. プレゼントは「約束」もセットで
デジタルデバイスを贈るなら、プレゼントと一緒に「使い方の約束」も準備しましょう。
●1日の使い方
●食事中や寝る前は使わない
●家族と一緒に使う時間を大事にする
サンタさんからのプレゼントとして「楽しいけれど、ルールもあるもの」という意識を育てると、長く安心して利用できます。
まとめ
クリスマスは子どもの笑顔を見られる特別なイベントです。タブレットやスマホも工夫次第で、学びや遊びの幅を広げてくれる贈り物になります。ただし、与えるのは「モノ」だけでなく、「安心して使える環境」と「家庭でのルール」も一緒に贈ることが大切です。とくに、ルールについてやインストールする新しいアプリは年齢とともに変化します。定期的に見直す必要があることを保護者がリードしていきましょう。

ナビゲーター
担当カテゴリー
ITデジタル
日本メディアリテラシー協会代表 寺島絵里花
一般社団法人日本メディアリテラシー協会 代表理事。高校時代に留学したカナダでメディアリテラシー教育に出合い、興味を持つ。上智大学文学部新聞学科卒業、ペンシルバニア大学留学。結婚、出産を経て、一般社団法人日本メディアリテラシー協会を立ち上げる。主な業務は、メディアリテラシー教育の普及を目的とする、保護者、教員、行政、民間企業などが対象のワークショップや研修、講演、出前授業など。
当協会立ち上げ後に東京学芸大学大学院教育支援協働実践開発専攻AI教育プログラム卒業。上海師範大学、北京師範大学での関連プログラム修了。2024年現在、JASSO 日本政府中国政府奨学金生(博士課程後期)として、華東師範大学大学院国際比較教育研究所所属。
メディアリテラシーに関する幅広い知見に加え、3児の子育てや日々の生活を発信するメールマガジンやブログが好評を博している。