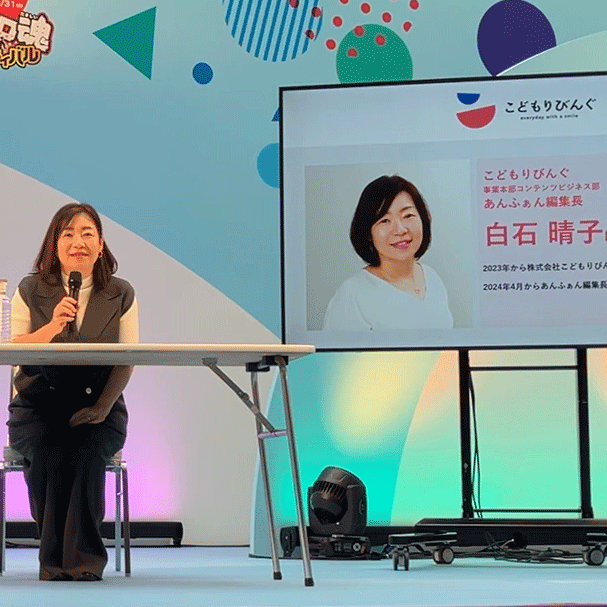デジタルは“悪いもの”と決めつけてない?デジタルと外遊び、どちらも大事にする工夫を専門家が教えます

情報を正しく読み取り、活用する力「メディアリテラシー」。さまざまなデジタルメディアが身近にある今、大人だけでなく、子どものうちから少しずつ育てていきたい力です。
このコラムでは日本メディアリテラシー協会代表理事の寺島絵里花さんが、「メディア」との上手な付き合い方について教えてくれます。今回のテーマは…?
5月は、さわやかな気候が気持ちよく、外遊びにぴったりの季節です。公園や広場で元気に体を動かす子どもの姿を見ると、自然と笑顔になりますよね。一方で、家の中ではタブレットやスマートフォンに触れる機会も増えています。
「外遊びも大切だけど、デジタル機器も上手に使わせたい」――そんな悩みを抱える保護者の方も多いのではないでしょうか。
デジタルは悪いものじゃない
まず伝えたいのは、デジタル機器は決して悪いものではないということです。最近では、未就学児向けの絵本アプリや知育ゲーム、教育系動画など、成長をサポートしてくれるコンテンツがたくさん登場しています。上手に活用すれば、言葉を覚えたり、好奇心を広げたりするきっかけにもなります。
また、家事で手が離せないときや、移動中の待ち時間など、親子双方にとって助かる場面もありますよね。
デジタルを「悪いもの」と決めつけず、場面に応じて味方にすることが大切です。
でも、体を使う遊びもすごく大事
一方で、未就学児期は、心と体を育む大事な時期でもあります。外遊びには、体力や運動能力を育てるだけでなく、社会性や想像力を伸ばす効果もあります。自然にふれたり、友だちと一緒に遊んだりする経験は、デジタルでは得られない豊かな体験です。特に、走る・跳ぶ・転ぶといった全身を使った遊びは、成長に欠かせません。
スクリーンを見る時間(スクリーンタイム)が長くなりすぎると、姿勢が悪くなったり、睡眠リズムが乱れたりするリスクもあります。外遊びとデジタル、それぞれの「いいところ」を意識して、バランスよく取り入れていきましょう。

バランスがカギ!わが家のルールを作ろう
大切なのは、「外遊びもデジタルも、どちらか一方を排除しない」こと。わが家なりのルールを決めて、無理なく続ける工夫をしましょう。たとえば、
● スクリーンタイムの機能を最初は親が把握することが鍵!
子どもは、生まれたときから、親がスクリーンを見ている姿をずっと見続けています。子どものスクリーンタイムを決める前に、保護者が1日どれくらい見ているか把握しましょう。
● 午前中は外遊びの時間、午後はお昼寝やデジタル学習の時間にする
● デジタル機器を使うときは、できるだけ親子で一緒に楽しむ
など、シンプルで守りやすいルールがオススメです。子どもと一緒に「今日はどんな外遊びをしようか?」「どのアプリを使おうか?」と話し合うのも、よい習慣になりますよ。
スクリーンタイムは、iPhoneなら設定画面から把握することができます。Androidなら設定から「デジタルウェルビーイング」というところをみてくださいね。
iPhoneの場合…設定→「スクリーンタイム」を選択 詳しくはこちら
Androidの場合…設定→「Digital Wellbeing と保護者による使用制限」を選択 詳しくはこちら
※OSのバージョンや機種によって、機能は異なる場合があります
最後に
デジタルも外遊びも、子どもの成長を支える大切な「道具」です。どちらかを否定するのではなく、バランスよく、楽しく取り入れていきましょう!
ナビゲーター
担当カテゴリー
ITデジタル
日本メディアリテラシー協会代表 寺島絵里花
一般社団法人日本メディアリテラシー協会 代表理事。高校時代に留学したカナダでメディアリテラシー教育に出合い、興味を持つ。上智大学文学部新聞学科卒業、ペンシルバニア大学留学。結婚、出産を経て、一般社団法人日本メディアリテラシー協会を立ち上げる。主な業務は、メディアリテラシー教育の普及を目的とする、保護者、教員、行政、民間企業などが対象のワークショップや研修、講演、出前授業など。
当協会立ち上げ後に東京学芸大学大学院教育支援協働実践開発専攻AI教育プログラム卒業。上海師範大学、北京師範大学での関連プログラム修了。2024年現在、JASSO 日本政府中国政府奨学金生(博士課程後期)として、華東師範大学大学院国際比較教育研究所所属。
メディアリテラシーに関する幅広い知見に加え、3児の子育てや日々の生活を発信するメールマガジンやブログが好評を博している。