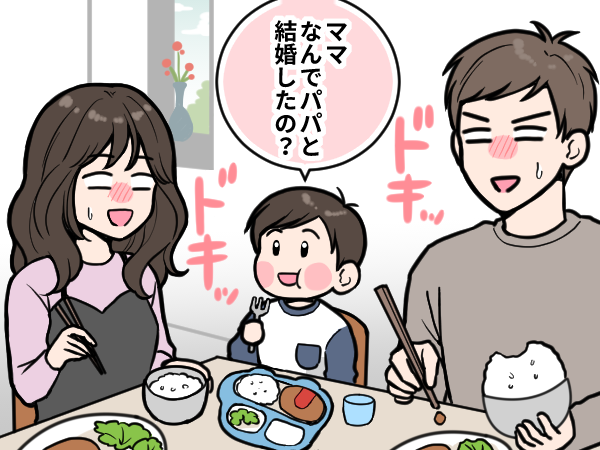子育て中こそ大切にしたい「自己肯定感」、親も自分を好きになるヒントとは?
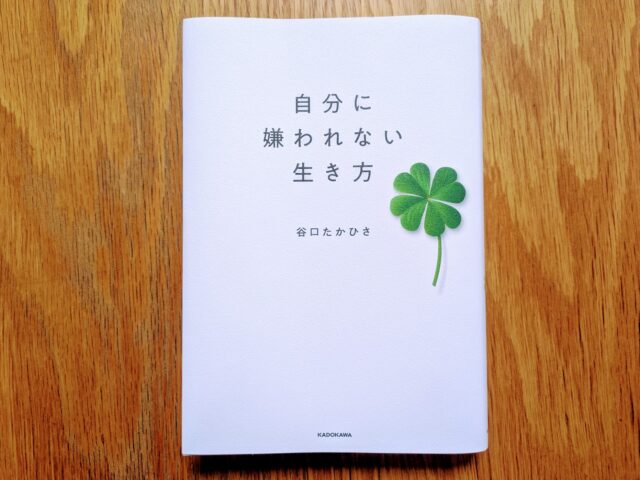
子ども中心の毎日、自分のことはつい後回し…。でも「人生でいちばん長く付き合うのは自分自身」。だからこそ、自分を好きでいられる選択を少しずつ増やしてみませんか? 世界100か国を旅した谷口たかひささんが見つけた、幸せのヒントをのぞいてみましょう。
※この記事は、谷口 たかひさ『自分に嫌われない生き方』(KADOKAWA)の一部を再編集したものです。
不幸になりたくなかったら、やめるべき2つのこと
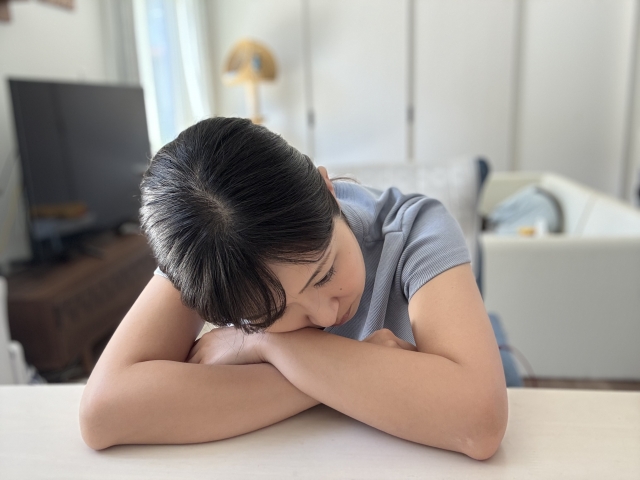
どうしても人の目が気になってしまう…そんなときは、どうしたらいい?
「幸せになる理由があるのではなく、不幸になる理由がある」
人間というものは、そもそも幸せになる力が自然に備わっている生きものだと思うのです。であれば不幸だということは、不幸になるべくしてなっている理由があるということ。つまり、「どうやったら幸せになれるか」ではなく、「どうやったら不幸にならないか」が大切だということです。
そして、「不幸になる理由」を突きつめて考えていくと、シンプルに次の2つのことが諸悪の根源だという結論に至りました。
①人と自分を比べること
②人の目を(過度に)気にすること
(もちろん最低限の生活水準を満たせているか、といった要素も大切だと思いますが、その上で精神的な話として)
この2つのことによって、自分から不幸をつくり出してしまっている人が、特に日本にはとても多いと思ったのです。
「人と比べないこと」が大切
① 比べることをやめるために、「私は私(俺は俺)」を口ぐせにしてみましょう。人は自分が思っている以上に自分の言葉から影響を受けます。
② 人の目を気にすることをやめるためには、そもそも人は自分以外の人のことをそれほど気にしていないと理解しましょう。
集合写真を見たときに確認するのって、自分の顔ぐらいですよね。みんな同じです。あるアメリカの電話会社の分析でも、最も多く使われていた言葉は「私」だったそうです。人はそれぐらい、自分のことに夢中で、人のことをそれほど気にしていません。
「批判」だけでなく「賞賛」も真に受けすぎない

どうやったらブレないで、自分軸で生きていくことができますか?
「賞賛」そのものが目的になったり、過度な「期待」に応えたりしようとすると、「自分軸」を失ってしまいます(これは子どももそのようです)。
人の身勝手な「賞賛」や、過度な「期待」に応えることを目指して生きることは、不安定この上ないと思います。
また「期待」には、「自分がやりたくないことや、やりたくてもやれなかったことを、他の人にやってもらおうとする」という側面があります。他の人の人生を生きなくていい。親や先生、友達や恋人からの過度な「期待」に応えようとして、心が壊れてしまった人をいくらでも見てきました。
僕のお母さんは「元気でいてくれさえすればそれでいい」と言い続けてくれました。生まれてくる前は、「健康に生まれてきてくれさえすれば」と誰もが願うのに、いざ生まれてきて、成長するにつれ求めるものばかり増やしてしまう。
「批判」や「失望」だけではなく、「賞賛」や「期待」も真に受けすぎないように心がけましょう。
お父さんとお母さんの立場を交換したらわかること

〇〇を精一杯やっているのに、何でわかってくれないんだろう
僕がイギリスにいたときに教わった方法をお伝えします。それは、「自分の立場」と「相手の立場」を交換して話し合ってみるということ。あなたが「A」という立場で、相手は「B」という立場であれば、あなたが「B」という立場になり、相手は「A」という立場になって話し合う、というふうに。
こんな話があります。
お父さんは外に働きに出ていて、お母さんは家でずっと家事をしていました。お互いに、「自分のやっていることのほうが大変だ」と思い、ケンカを繰り返していました。そこでこのお父さんとお母さんは、3日間、お互いのやっていることを交換してみることにしました。そうして、お母さんが外に働きに出て、お父さんが家でずっと家事をすることになりました。お互い、相手のやっていることの大変さを知り、それからは感謝し合うようになりました。
立場を交換して行うこのディベートの目的は、「論破すること」ではなく、「理解を深め合うこと」。これをイギリスで毎日のようにやらされました。ディベートというのは、自分の本当の立場で、相手をコテンパンに論破するものだと思っていた僕。最初は、「何でやねん」と思っていましたが、今では、この経験が本当にありがたかったなぁと。「相互理解」「ロジカルシンキング」「クリティカルシンキング」「コミュニケーション能力」「(信頼性の高い)データを押さえておく力」などが、一挙に身についたんですね。
そして、自分の立場でならスラスラとモノが言えるのに、立場を交換した途端、何も言えなくなる人が少なからずいます。これは「頭が偏っている」証拠。「頭が偏っている」状態になると、ダマされやすく、また違う意見にストレスを感じやすくなります。そして、立場を交換して話し合うと、「A」か「B」でなく、両方を和えた「C」ができたりします。「〇〇の話になると、いつもパートナーと意見が対立する」という人は、1度試してみてください。
「正義」の反対は「悪」ではなく、「もう1つの正義」。その人にはその人なりの正義があるのだから。
相手に自分の好みを演じさせている?

ウチの子どもは〇〇が好きだと思う。
親が子どもに対して、「この子はこう」と思っていることは、実はその子が空気を読んで、親の好みを感じ取って行動している可能性があります。そしてこれは、親子という人間関係に限った話ではないと思います。自分が相手に対して、その人らしさだと思っていることは、相手が空気を呼んで自分の好みを演じてくれているだけなのかもしれないということです。
子どもの前でも、「ウチの子にはこうなってほしい」と口にする親をよく見ます。親としては、当然のように抱いてしまう気持ちなのかもしれません。だけどその上で、同じようなことをパートナーに言われたとしたらあなたはどう感じるでしょうか?「あなたにはこうなってほしい」と言われたら、場合によってツラい気持ちにならないでしょうか?今の自分を否定されたような気持ちにならないでしょうか?
僕のお母さんは「あなたはあなたのままでいい」と、いつもそう言ってくれる人です。自分のことを1人の人間として尊重し、信頼してくれる人に、人は好意を寄せるものなのでしょう。人は好意を寄せる人のことは、キズつけたくないし、喜ばせたいと思うものなのでしょう。
自分の背中で魅せる

子どもにどんな声がけをしたほうがいいですか?
先生でも、他の大人でも、その人が尊敬できる人であれば、僕は言うことを聞いていました。「尊敬できる人」というと、いわゆる「偉人」のような人を思い浮かべるかもしれません。だけどもっとシンプルなことです。
・口で言っていることと、実際にやっていることが一致しているか
・ 誰にでも平等に接しているか(目上の人には媚びへつらい、そうではない人に威張るような人は尊敬できません)
・感謝をして、それをちゃんと口に出して伝えているか
・ 自分が間違ったと思ったら、(相手が子どもであっても)ちゃんと謝罪をしているか
・人の幸せを喜び、人の不幸を悲しむことができるか
これらが、その人を尊敬できるかどうかに関して、最も大きな要素だったように思います。人として最も大切なことだと、子どもながらに感じていたのだと思います。「〇〇が言うことを聞いてくれない」という言葉をよく聞きます。〇〇は、子どもだったり、パートナーだったり、部下だったり、同僚だったり、様々です。子どもだったら思春期など、難しい年頃なども確かにあるかもしれません。
だけどまずは自分が、人に言うことを聞いてもらえるような、尊敬される人であるのかどうか。完璧にはできなくても、少なくともそうあろうとする努力をしているのかどうか。それが1番大切なことなのだと思います。
自分に問いかけてみましょう。
「自立」とは依存しないことではなく、依存先が多いこと
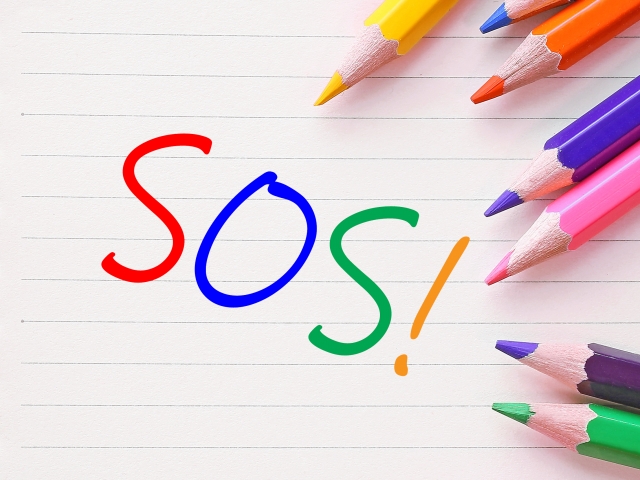
人に頼れず、自分がしっかりしなくてはいけないと思う
「1番勇気がいる言葉」って何だと思いますか?
それは、「ごめんなさい」でもなければ、「ありがとう」でもない。「好き」でもなければ、「愛してる」でもない。「1番勇気がいる言葉」は、「助けて」だと僕は思います。今の日本には、人を頼れず、自分ですべてをやろうとして余裕がなさすぎる人がとても多いように見えます。僕自身もそうでした。
人に頼るときに気をつけたいことがあります。それは、「余裕がゼロになる前に頼る」ということです。本当に余裕がゼロになったときは、「助けて」という余裕もなかったりします。また、仮に「助けて」と言えても、助けたいと思ってくれた人から見たら、もうどうしようもない状況に陥っているときもあります。
「もっと早く言ってくれたら……」
僕自身、「助けて」と言うのが遅くて、こういう言葉をもらった経験が何度かあります。1番勇気のいる言葉、「助けて」。これが言える、自立した人になりましょう。依存先を増やしていきましょう。
命も使わないと意味がない

やりたいことがあるけれど一歩が踏み出せない
命を使わないというのはどういうことかというと、「〇〇したらどうしよう?」と、まだ起きてもいないことや、リスクをこわがったりして、行動しないこと。
自分の人生を変えられる人や、社会を変えられる人は、保証などなくても行動できる人。こんな混沌とした社会においても、行動する人を僕はたくさん知っています。そしてその何十倍も何百倍も、行動しない人がいることも事実でしょう。だからそんな中で大切なのは、「あなた」はどうありたいのか。これに尽きるのだと思います。
とはいえ、ほとんどの人はこの「自分自身の本当に望むもの」がわかっていないかもしれません。とっかかりとしては、「自分がワクワクすること」からスタートしてみるのがいいと思います。世界が何を必要としているかなんて、いったん考えなくていい。自分がワクワクするものを追い求めればいい。世界が必要としているのは、ワクワクしている人なのだから。
「自分を好きでいる」 人生でそれ以上に大切なことなどない
『自分に嫌われない生き方』は、自分を大切にするためのヒントが詰まっています。子どもの自己肯定感を育てたいなら、まずは親自身が「自分を好きでいること」から。疲れたとき、イライラするとき、張りつめた心をゆるめてくれます。子育て中の今だからこそ、手にとってほしい一冊です。
※記事内のリンクから商品を購入すると、売上の一部が当社に還元される場合があります