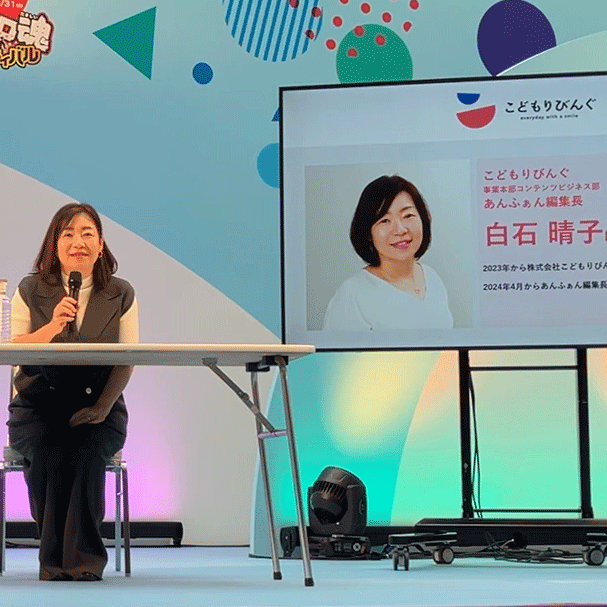子どものスマホ・タブレット依存を防ぐ!家庭でできる効果的なルール作りのヒント

情報を正しく読み取り、活用する力「メディアリテラシー」。さまざまなデジタルメディアが身近にある今、大人だけでなく、子どものうちから少しずつ育てていきたい力です。
このコラムでは日本メディアリテラシー協会代表理事の寺島絵里花さんが、「メディア」との上手な付き合い方について教えてくれます。今回のテーマは「子どものデジタル依存を防ぐ、家庭でのルール作り」についてです。
梅雨の時期や真夏の暑い時期、外で遊べない日が続くと、つい子どもたちのスマホやタブレットの利用時間が長くなりがちです。天候のせいだからこそ、「まあ仕方ない」と思ってしまうのは、大人も同じ。ですが、今のうちにルールを整えておくことが、長期的な“依存”の予防につながります。
スマホ・タブレット依存の兆しとは?
まず、依存の兆しにはどんなものがあるでしょうか。たとえば、時間を区切ってもやめられない、取り上げると強く泣いて反発する、他の遊びに興味を示さなくなってきた――こうした様子が見られたら、少し立ち止まって様子を見てみましょう。夜更かしをして朝が起きられず、食欲が落ちたりする子もいます。大人が早めに気づくことが大切です。
効果的なルール作りと失敗するルール作りのポイント
では、どんなルールが「効果的」なのでしょうか。基本はシンプルです。「スクリーンタイム(※)のセルフコントロールの醸成」と「使う場所」のルールを決めることです。
※スクリーンタイム…スクリーンを見る時間
失敗するルール作りとは
失敗するルール作りとして、「1日〇分まで」と時間で区切ってしまうことです。この場合、見たかった動画、したかったゲーム、会話が続いている最中で連絡が取れないといったことになり、「また使いたい」といった欲求が起きやすくなるからです。大人でも、お気に入りのドラマのラストシーン5分前にいきなりテレビの電源を切られてしまったらいやな気持ちになると思います。
ルールを一方的に押し付けない
「夕食後は使わない」「寝室では使わない」といった、わかりやすく守りやすいルールがよいのですが、ここで大切なのは、ルールを一方的に押しつけないことです。「どうしてそのルールが必要なのか」「体や心にどんな影響があるのか」を、子どもと一緒に話しながら決めていくことがポイントです。
さらに、「破ったときはどうする?」という“罰”ではなく、“次にどうするか”を一緒に考える姿勢が大切です。
18歳までに習慣づくりを!失敗しても責めない
実際の場面では、子どもがどのような動画、ゲーム等をしているか、内容に関心を持つことも大切です。各動画やゲームには、1本、1ゲームにかかる時間が予想できるので、時間を決めるのではなく、何本見るのか?何回遊ぶのか?という回数の約束をした上で、その回数の上限に達したときに、子ども自身でやめるという習慣を18歳までにつくることを目標にします。
この18歳までというのは、自動車の運転免許でいうところの教習期間であり、失敗しても責めないことが大切です。今の子どもたちは、スマホやタブレットを今後一生涯使う可能性があり、セルフコントロールを身に付けることは重要ですが、すぐに身に付けることはできません。長い目で見ていきましょう。
また、視覚的に時間の流れを確認できると、子ども自身が「終わりの時間」を意識しやすくなります。
大人の関心と安心が依存予防につながる
子どもの使いすぎを心配するあまり、「もうやめなさい!」と感情的になってしまうこともありますよね。でも、そこでガミガミ言うのではなく、「なにを見てたの?」「それ、そんなに面白いの?」と声をかけてみると、子どもは自分の“好き”を理解してもらえたと感じ、素直になれることがあります。大人の関心と安心が、依存予防の土台になります。

親子で一緒にルールを作り、デジタルと上手に付き合おう
スマホやタブレットは便利な道具です。でも、使い方を誤ると、子どもの発達や親子関係にも影響を与えてしまいます。だからこそ、今の時期は「一緒にルールをつくる」絶好のチャンス。家族で向き合い、考えることで、画面と上手につきあう力が育っていきます。
ナビゲーター
担当カテゴリー
ITデジタル
日本メディアリテラシー協会代表 寺島絵里花
一般社団法人日本メディアリテラシー協会 代表理事。高校時代に留学したカナダでメディアリテラシー教育に出合い、興味を持つ。上智大学文学部新聞学科卒業、ペンシルバニア大学留学。結婚、出産を経て、一般社団法人日本メディアリテラシー協会を立ち上げる。主な業務は、メディアリテラシー教育の普及を目的とする、保護者、教員、行政、民間企業などが対象のワークショップや研修、講演、出前授業など。
当協会立ち上げ後に東京学芸大学大学院教育支援協働実践開発専攻AI教育プログラム卒業。上海師範大学、北京師範大学での関連プログラム修了。2024年現在、JASSO 日本政府中国政府奨学金生(博士課程後期)として、華東師範大学大学院国際比較教育研究所所属。
メディアリテラシーに関する幅広い知見に加え、3児の子育てや日々の生活を発信するメールマガジンやブログが好評を博している。