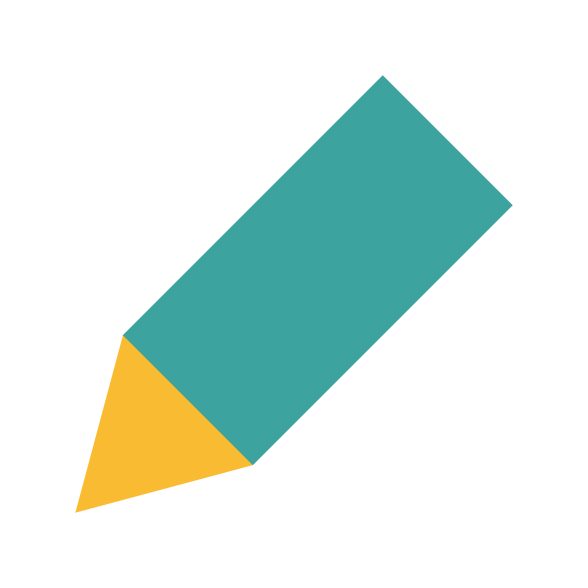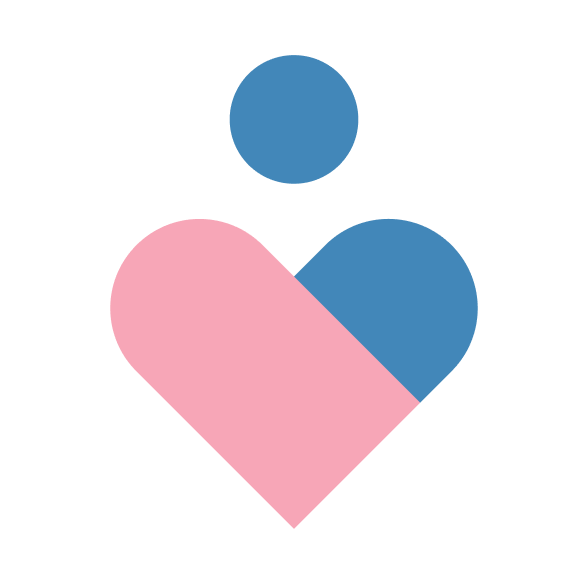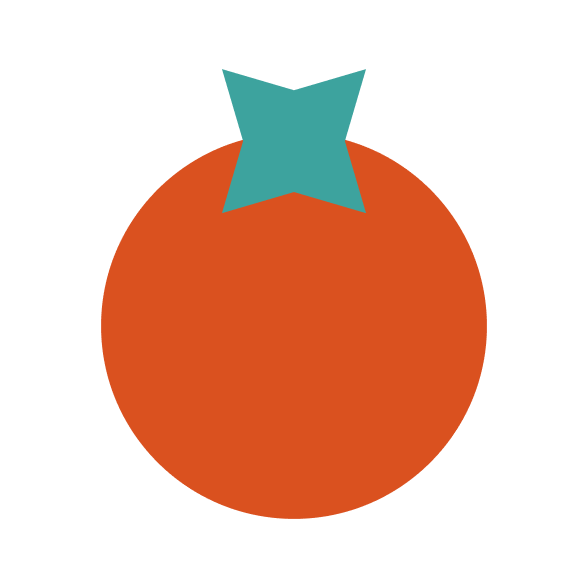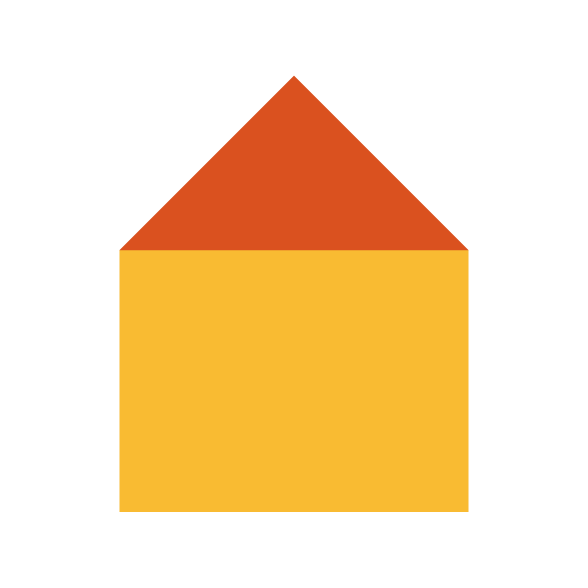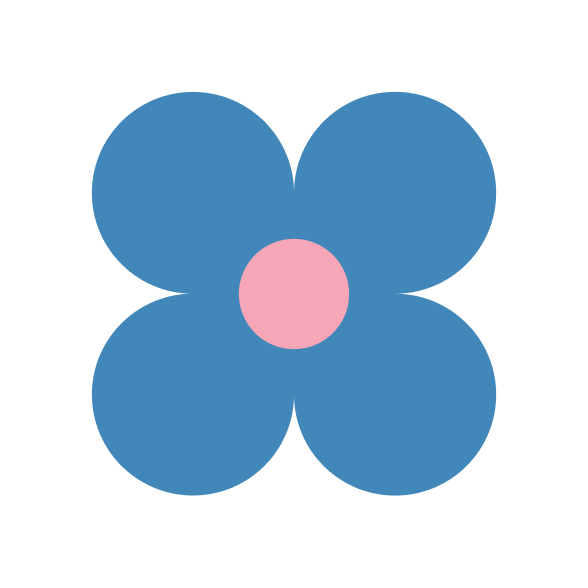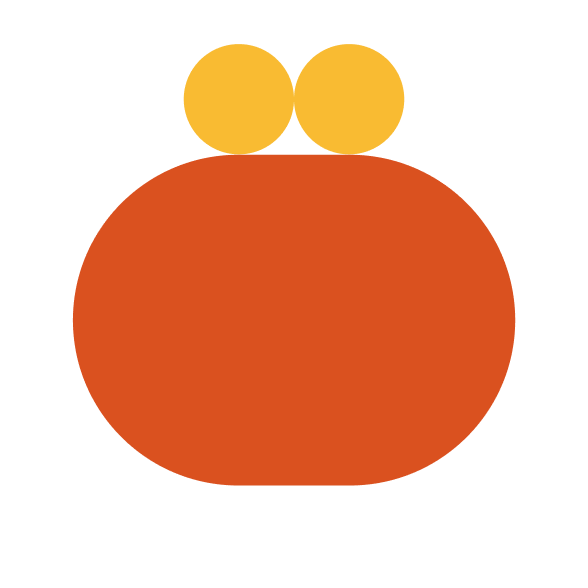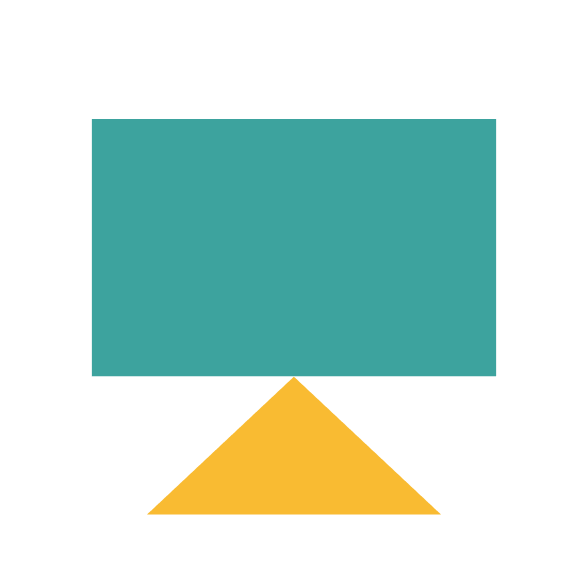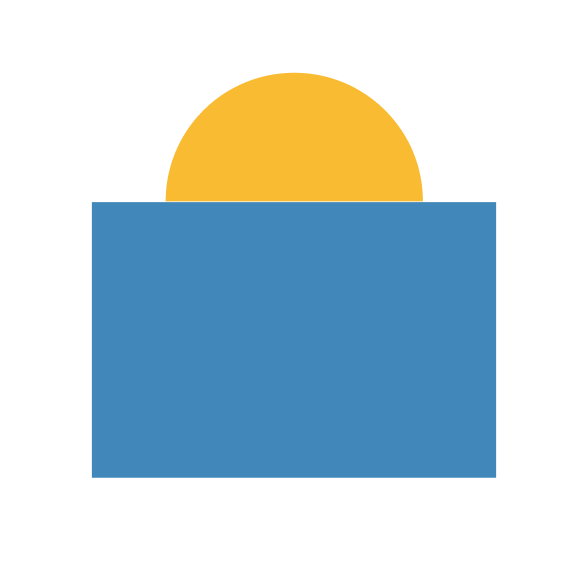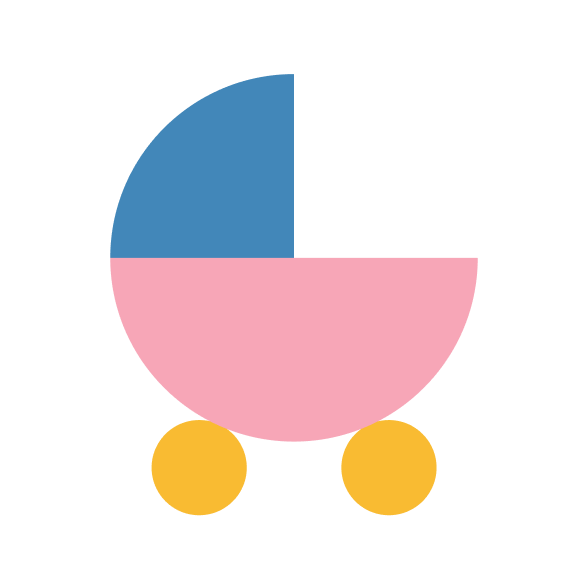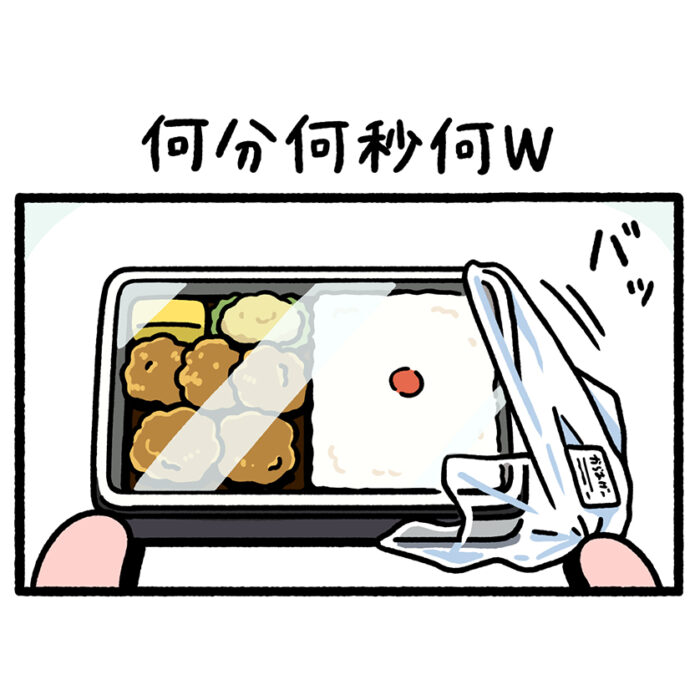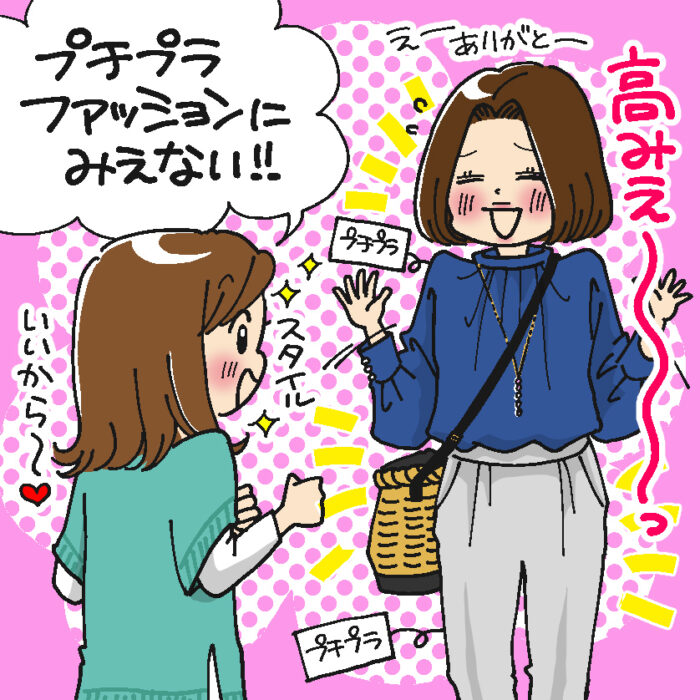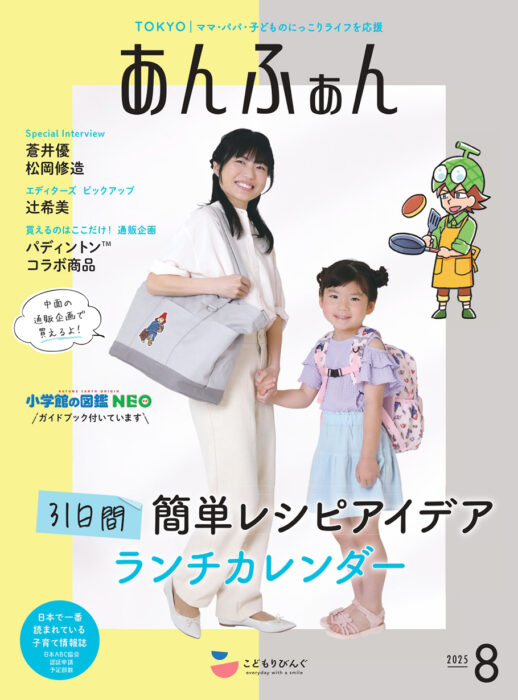更新 :
子どもが「自分で」宿題&支度をするようになる部屋づくり3つのコツ

子どもが自分から、宿題や学校の準備に取りかかるのはなかなか難しいもの。親も「宿題は終わった?」「明日の準備は?」など、何度も同じことを言わなければならず、なかなか気が休まりませんよね。
そこで今回は、わが家で実践している、子どもが「自分で」宿題や次の日の学校の支度をするようになるコツを紹介したいと思います。
小学生の子どもとの暮らしで最優先に考えていること
わが家が小学生の子どもとの暮らしで、優先的に考えていることは、「動線」と「簡単に」ということです。この2つを心掛けるだけで、子どもは暮らしやすく、また学校の支度など、自主的にできるようになると考えています。この2つをふまえて、コツを紹介していきます。
1.子どもの「移動」はできるだけ少なくする
子どもが「自分で」物事を進めていけるようになるには、子どもが「どういう動きをするのか=動線」を意識することがとても重要だと考えています。
家の中を何度も行ったり来たりすることになると、子どもは疲れて、宿題や学校の支度をすることも面倒になってしまいます。しかし、子どもの生活動線をできるだけ少なくすることで、それが改善します。
そこで重要になってくるのが、「ランドセル置き場」です。ランドセルを置く場所は、子どもの「動線」を考えて決めると、全体の流れがスムーズになります。
■やめた方がいいランドセル置き場
例えば、1階に玄関、リビングがあり、2階に子ども部屋がある場合。子ども部屋で宿題をする場合は、そこにランドセル置き場を作ってもいいのですが、リビング学習をする場合は不向きです。学校から帰ってきて2階にランドセルを置きに行き、また1階に宿題をしに戻ってくるのは、時間も手間もかかります。そうすると、学校から帰ってきて、そのままリビングにランドセルを放置してしまうことになりかねません。また、移動している間に面倒になって宿題もしないままに…なんて場合も出てきてしまいそうです。
■「動線」を考慮したランドセル置き場
わが家の場合は、子どもの動線を考え、ランドセルは登下校の際に必ず通る「玄関」に置いています。帰宅したら、まず玄関のランドセル置き場にランドセルを置き、宿題や学校からの手紙はリビングに、洗濯するものは洗面所へ運ぶようにしています。そうすると、子どもの移動が短くてすみ、リビングにランドセルの中身などが散らかることもありません。また、リビングが狭い場合にも「玄関」をランドセル置き場にすると、場所をとらなくてすむのでおすすめです。
明日の準備をする際は、玄関に行くことになりますが、リビングと玄関の往復のみと、移動も短いので、面倒になることもないようです。しかし、玄関からリビングまでの距離が長い間取りの場合は、ランドセル置き場をリビングなどに作ったほうが、子どもも面倒にならずにすむと思います。

■リビングをランドセル置き場にする場合
リビング学習をする場合、リビングにランドセルを置き場があると、動線も少なくすみます。ですが、その際は必ずランドセル置き場の位置を決めておかないと、リビングにポンとランドセルが置きっぱなしになってしまうことも。そうなると、リビングが散らかってしまう原因にもなるので要注意です。
また、ランドセル置き場は、なるべく「置くだけ」など、子どもが簡単に、1回の動作だけで済むように作ってあげると◎。簡単にできることが、習慣化にもつながるのではと思います。
2.宿題や勉強に取り組みやすい環境を整える
子どもが「自分で」宿題に取りかかれるようにするためには、環境がとても大切だと思っています。わが家は動線や環境を考えた上でリビング学習をしていますが、環境を整えるために気をつけていることを紹介します。
■宿題に必要なものは必ずそばに
リビング学習において、私が気をつけていることは、“宿題や勉強をする際に必要な勉強道具やテキストなどは、必ずテーブルのそばにまとめて置いておく”ということ。勉強道具を遠くまで取りに行かなければならなかったり、必要なものがバラバラの場所においてあると、それだけで集中力が切れてしまいます。また、毎回違うところから持ってこなければならない状況だと、「面倒だから後にしようかな」「もう宿題やりたくない」という状況になりかねません。
必要なものがすぐ届く状況であれば、効率もよくなり、子どものやる気にもつながります。また、勉強道具などを収納する場所は、子どもが自分で簡単に取り出せてしまうことができるようにしておくことも大事なポイントです。
■リビングでの勉強道具の収納場所
「勉強道具を収納する場所がリビングに見当たらない」「どこを収納場所にしていいのか分からない」という場合もありますね。わが家では、もともとリビングに置いていたラックの一角に、100均の収納アイテムを使用して、子どもの勉強道具コーナーにしています。まったく収納する場所がない場合は別ですが、わざわざ購入しなくても、リビングに置いてある棚やカラーボックス、本棚などの一角を専用のコーナーにするというのもひとつの方法ですよ。

■用意したけれど不要だったもの
リビング学習をすると決めた時に、子どもが少しでも勉強しやすいようにと、リビングに勉強専用の机を取り入れてみたことがあります。しかし、その机の上には、どんどんモノが増え、その時に使わないモノなどが置かれるように。結局、勉強専用の机を置くのはやめ、ダイニングテーブルで勉強するようになりました。勉強机を取り入れたのが、子どもが年長の時だったので、年齢がもう少し上がってからであれば違っていたのかもしれません。
3.親の「目線」が必ず届くようなレイアウトにする
リビング学習において、親の「目線」が届くように環境をレイアウトすることは、とても大切だと考えています。
その理由として以下が挙げられます。
・子どもが宿題や勉強で分からないことがあった時に、すぐに親に声をかけることができる
・親が家事などをしているときでも、子どもの様子が分かる
・いつでも、親から「見守ってもらえている」という安心感につながる
子どもは、親から「見守ってもらえている」と感じることができるだけで、安心して宿題や学校の支度をすることができるのではないでしょうか。そしてそのことが、「自分で」「自分から」に繋がるのではと感じています。
子どもの「自主性」を考えた工夫で「暮らし」がよりよいものに!
子どもが低学年のうちは、ひとりで宿題をやって明日の学校の準備をするというのは難しいですよね。しかし、少しでも「動線」や「環境」を変えてみると、「自分で」できるような習慣が、だんだんとついてくるはずです。親が見守りながら、「自主性」を育んでいけると、子どもの暮らしもよりよいものになるのではないかと思います。