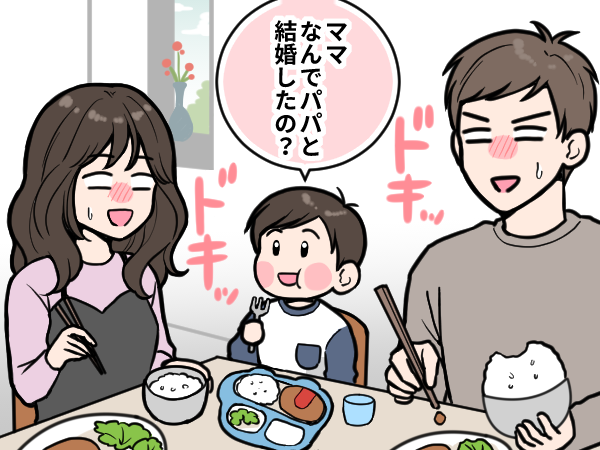わが家に合うのはどっち?小学校受験と中学受験の違いと考え方

「中学受験って本当に必要?」「小学校受験とは何が違うの?」──将来の進路を考えるうえで、一度は気になる“受験”の話。今回は、小学校受験と中学受験の違いをふまえ、メリット・デメリットを整理しながら、家庭で話し合いたいポイントをご紹介します。
小学校受験と中学受験、どう違う?
小学校受験と中学受験には、どのような違いがあるのか比較します。
受験準備期間
まず違うのは受験する子の年齢です。小学校受験と中学受験では、受験準備期間に違いがあります。小学校受験では新年中から通塾する家庭が多く、塾選びなど年少頃から小学校受験を意識します。
中学受験では新小4からの通塾が一般的です。入塾テストや先取り学習を意識して、低学年から家庭学習を始めるケースも多いです。そのため受験準備期間は中学受験のほうが長い傾向にあります。
親の関与度
中学受験と比較して、小学校受験の方が親の関与度が大きいという違いがあります。中学受験では子ども自身の学力や思考力が問われるのに対し、小学校受験は学力だけではなく家族を含めた「人」が評価されます。
小学校受験では、子どもの協調性や指示の聞き取り・待ち時間の態度など、一つ一つの言動すべてが評価対象となります。
また、子どもだけでなく親も、面接や願書を通じて人格や家庭の価値観を観察されます。通塾や受験にも親が付きっきりで対策をする必要があり、親の負担は大きくなります。
受験理由
受験理由にも違いがあります。小学校受験では、以下のような理由で受験する家庭が多い傾向にあります。
・学業も大事だが人格形成に重きを置きたい
・座学よりも体験活動を重視したい
このように、私立小学校は心の教育を重視する傾向があるため、学力だけではない人格形成を重視する家庭が多いです。
中学受験を目指す理由では、
・子どもの学力や個性がはっきりしてから学校選びをしたい
・学校選びの選択肢を幅広く持ちたい(小学校受験に比べ、中学受験では受験対象校が多いため)
といった理由が挙げられます。子どもの個性に合った進路をじっくり選びたいと考える家庭が中学受験を選んでいます。
比較して分かること
このように違いを比較してみると、小学校受験は「親の意思と準備」が大きく影響し、中学受験は「子どもの意思」が伴ってくる点が大きく違うことが分かります。とくに中学受験は準備期間も長いため、本人の意思とやる気がとても大切になります。
中学受験のメリットとは?
中学受験をするメリットは、子どもが自分の意思を持って「学びたい」「伸ばしたい」と思える環境を選べる点が大きな魅力です。
学力や価値観が似ている子と切磋琢磨しながら質の高い授業を受けることができ、人間関係が安定した状態で大学受験に臨めるのは、大きなメリットと言えます。
高校受験を回避して安定した6年間を過ごすことで、自分のペースを築いたり、仲間と強い結びつきができたりすることもメリットとして挙げられます。
中学受験のデメリットや注意点
中学受験にはデメリットもあります。一つは受験競争の激化に伴い、親子ともにストレスを抱えやすいことが挙げられます。小学校高学年の時期に勉強量を増やさなければならず、遊ぶ時間や習い事との両立をどうするか考える必要があります。親の期待や試験合格へのプレッシャーが子どもにとって精神的ストレスになる場合もあります。
費用の負担が重いこともデメリットと言えます。塾費用は小6になると月4〜6万円と高額になるほか、模試・実力判定テスト・合宿・特別講習の費用も必要です。家庭教師や算数専門塾を併用するケースも珍しくありません。中学受験は小学校受験より通塾期間が長い傾向があるため、受験にかかる合計費用が高額になりやすい点に注意が必要です。
このようなデメリットも考えながら、本当に中学受験が必要かどうか冷静に判断することが大切です。「受験=絶対に必要な選択ではない」という考え方を頭の片隅に置いておくことで気持ちに余裕を持つことができます。
「受験に正解はない」家庭で話し合いたいこと
小学校受験と中学受験のいずれにしても「受験する・しない」どちらがいいかは家庭ごとに答えがあり、決まった正解はありません。 子どもの性格、家庭の教育方針、学びに対する姿勢について、夫婦、親子で話し合い、 早い段階からコミュニケーションを取れる状況を作っておくことが重要です。
また、どちらの受験を選択する場合でも、学びの土台作りとして「自ら考える習慣」を幼少期から作っておくとよいでしょう。
まとめ:「進路の選択肢」は、家庭の数だけある
今回は、小学校受験と中学受験について、違いと考え方を解説しました。受験をする・しないに関係なく、受験はあくまで通過点であり、子どもの力を伸ばすことが本来の目的であることを改めて確認しましょう。 将来どんな進路を選ぶにしても「自分で考えて決められる力」が何より大切であることを忘れないでください。
ナビゲーター
担当カテゴリー
学び・遊び・教育
算数教材「RISU」代表取締役 今木智隆
RISU Japan株式会社代表取締役。京都大学大学院エネルギー科学研究科修了後、ユーザー行動調査・デジタルマーケティング専門特化型コンサルティングファームの株式会社beBitに入社。金融、消費財、小売流通領域クライアント等にコンサルティングサービスを提供し、2012年より同社国内コンサルティングサービス統括責任者に就任。2014年、RISU Japan株式会社を設立。タブレットを利用した小学生の算数の学習教材で、延べ30億件のデータを収集し、より学習効果の高いカリキュラムや指導法を考案。国内はもちろん、シリコンバレーのハイレベルなアフタースクール等からも算数やAIの基礎を学びたいとオファーが殺到している。