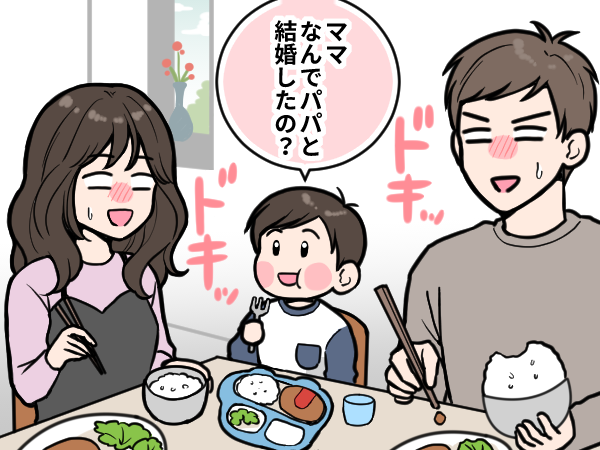「国立小学校ってどんなところ?」受験しなくても知っておきたい、子どもの育ちにつながるヒント

小学校受験では一般的に「公立か私立か」の選択を考えることがありますが、「国立小学校」も一つの選択肢です。「国立」と聞くと特別な子が行く学校というイメージがあるかもしれません。しかし実際は、少し準備をすれば誰でも受験を検討できる学校です。今回は国立小学校とはどのようなところか解説します。
「国立小学校」ってどんなところ?
国立小学校は、一般的な公立(文部科学省が定める各地域にある学区の小学校)でも、私立でもない、第3の選択肢ともいえる学校です。国立大学に附属しており、教育や保育に関する研究に協力したり、付属する国立大学の教育実習が実施されたりする特徴があります。
学費については、公立小学校と同様に無料です。その他、学区の小学校と同じで、給食費や修学旅行の積立金などが必要です。ただし、学校により制服の有無や後援会費、寄付金などプラス必要になる費用があるため、一概に公立並みの学費とはいえません。
国立小学校の受験は、私立小学校と比べ特殊であるため、試験の特徴や合格の傾向を理解しておく必要があります。
国立小学校の試験って?家庭でできる5つの準備
「試験」と聞くとハードルが高いように感じるかもしれませんが、国立小学校入試の倍率や試験内容は、地域によりさまざまです。
試験では、親子面接や行動観察(集団も含む)、ペーパーテストなどが一般的に行われる場合が多いです。お子様の基本的な生活態度や思考力をチェックするような内容が多いのが特徴です。
また多くの国立小学校では、事前または考査後に抽選が行われます。高倍率校では事前と考査後の2回抽選があるケースもあり、国立小学校受験では運も必要になります。
私立の小学校受験対策には、基本的に通塾が一般的ですが、国立小学校の場合は、家庭での取り組み方によっては通塾なしでも受験対策が可能です。
ここからは、特別な塾通いがなくてもできる「5つの準備」をご紹介します。
話を聞いて考える力を育てる「ペーパー対策」
国立小学校のペーパーテストでは、お子さまの「聞く力」「思考力」「基礎的な知識」を問う問題が出題されます。
●お話の記憶:短いお話を聞き、質問に答える
●図形:図形同士を重ねた形や、回転した形を答えるなど
●数:計数や簡単な足し算・引き算(答えの数だけ丸を書くなど)
●言語:しりとりなど
●常識:花や生き物の名前、季節、マナーなど
家庭では基礎的な小学校受験用問題集で対策します。
試験は音声で発問され、一問ごとに時間制限があります。また「記号で答えましょう」など、学校により独自のお約束があるため、一度で聞き取れるよう練習しましょう。
遊びながら育つ「体の使い方&集中力」
国立小学校の運動考査では、ただ単に運動神経を測るだけではありまなく、お子様の「体の使い方」と「指示を聞く力」を総合的にチェックする傾向があるようです。
たとえば、クマ歩き(4足歩行)、ケンケン、立ち幅跳び、ケンパー、スキップ、平均台歩行、ボールキャッチなどがおこなわれます。さまざまな運動を通して、学校側は次のような能力を観察しています。
●体幹
●基礎的な運動能力
●体をコントロールする力
●集中力 など
また、ルールや指示を理解する力や、待ち時間の姿勢や言動も同時に見ています。
ご家庭では、まずクマ歩き(4足歩行)から練習ししてみましょう。公園や帰り道でケンケンやスキップを取り入れるなど、遊びながら基礎的な運動能力を育てましょう。
折り紙や工作も効果アリ!手先を動かす「巧緻性(こうちせい)」
巧緻性(こうちせい)とは、ズバリ「手先の器用さ」のことです。
この課題では、単に器用さだけでなく、集中力や指示を理解し最後までやり遂げる力が観察されます。
・はさみで切る・のりで貼る(指示通りの形を正確に再現する力)
・ちぎる・塗る(指先の力加減、集中力、丁寧さ)
・紐を通す・むすぶ(両手の協調性、生活に必要な基本技能) など
家庭では、折り紙、ちぎり絵、塗り絵、工作など、手先を使う遊びを積極的におこないましょう。
お友だちとの関わり方「行動観察」
行動観察は、4〜6人ほどのグループで協力して製作やゲームをおこない、その言動を観察します。
この考査で重要しされるのは、製作物の出来やゲームの勝ち負けは重要ではなく、協調性や目的・指示の理解、勝敗後の言動が見られています。
ご家庭での対策としては、家族で勝敗のつくゲームをおこなったり、思いやりや優しい気持ちを育む絵本を読むなどしてコミュニケーションを取ります。
ゲームで負けたときに癇癪を起こしやすい場合は、「負けて悪い言葉を使うお友達と、負けて悔しいけど相手におめでとうと言えるお友達では、どっちが素敵かな?」と伝えてみるなど、子ども自身が言動を客観視できるような声掛けをしましょう。
日常の会話で自然に対策!「親子面接」準備
面接では、言語力や思考力、コミュニケーション能力はもちろん、性格なども観察されます。
たとえば、
「お名前を教えてください」
「誰ときましたか」
といった基本的な質問のほか、
「お母さんに褒められるのはどんなときですか」
「迷子になったらどうしますか」
など、答えのない、自分の考えや意見を求められる質問もあります。
家庭で対策するときは、絵本を読みながら「こういうとき、あなたならどうしますか?」と問いかけるなど、自分で考えて話す機会を増やします。
また「それはなぜですか?」と質問を掘り下げ、理由も説明できるようにしておきましょう
受験しない家庭にも役立つ「受験準備の考え方」のポイント2つ
国立小学校の受験対策で求められる力は、すべてのお子様の成長に役立つ、将来の土台となる力です。受験の有無にかかわらず、小学校入学までにぜひ身につけておきたい「生活力」と「思考力」として捉えましょう。
改めて受験で評価されるポイントをまとめてみましょう。
1.自分の考えを言葉にする力(思考力・表現力)
国立小学校の考査では、自分の意見をはっきり発言できることが合否に影響されやすいです。
これは、単に知識があるということではなく、「自分の頭で考え、それを整理して言葉にできる力」が評価されているためです。日頃から、「あなたはどう思う?」「なぜそうしたの?」と問いかけ、お子様が自分の考えを持てるような関わり方をしておくことが大切です。
2.自立した生活を送る力(生活習慣・精神的な自立)
あいさつ・着替え・持ち物の管理など、基本的な生活習慣が身についているお子さんは合格しやすいとされています。基本的な生活習慣が身についているということは、精神的にも自立が進んでおり、自分で考えて行動できると評価されるためです。
このような力は、小学校入学後に先生の話に集中し、スムーズに学校生活がスタートできることにも繋がります。
これらの力は、基本的にどの進路を選ぶ場合にも必要な力といえます。「小学校入学に向けた思考力」や「生活力」の育成にもつながりますから、国立小学校の受験の有無にかかわらず伸ばしておくとよいでしょう。
中学受験ともつながる?知っておきたい進路の話
子どもの進路についてさまざまな選択肢があるなかで、親の心構えとして大切なのは「さまざまな選択肢があることを知っておくこと」です。
たとえば、小学校へ進学する時点で国立小を選んだ場合、その後の進路変更が難しくなるかといえば一概にそうとはいえず、中学受験率が高い学校もあります。
逆に小学校受験を見送り公立小へ進学しても、中学受験への対応は十分可能です。
つまり、進路をどう選ぶかについて決まった正解はないのです。
子どもの性格や能力は個々に違うため、小学校受験を選ぶか・選ばないかよりも、将来子どもの選択肢を広げたいと思ったときに「情報を持っているか」が大きな差になります。
選ばないであろう選択肢を除外するのではなく、常に「情報として持っておく」ようにすると、親子で有意義な選択ができるでしょう。
小学校受験と中学受験の違いや考え方については、こちらの記事も参考にしてください。
引用:わが家に合うのはどっち?小学校受験と中学受験の違いと考え方
まとめ:「選ぶ・選ばない」より、まず知っておこう
今回は国立小学校について、その特徴や考え方を解説しました。国立小学校は「特別な場所でわが家に関係ない」と思いがちですが、案外に身近な存在であることを感じて頂けたのではないでしょうか。
お子さんがまだ進路を決める年齢でなくても、情報として知っておくことで、子どもに合った教育環境を選ぶ判断材料になります。今後の学校選びの参考に、選択肢のひとつとしてお役立てください。
ナビゲーター
担当カテゴリー
学び・遊び・教育
算数教材「RISU」代表取締役 今木智隆
RISU Japan株式会社代表取締役。京都大学大学院エネルギー科学研究科修了後、ユーザー行動調査・デジタルマーケティング専門特化型コンサルティングファームの株式会社beBitに入社。金融、消費財、小売流通領域クライアント等にコンサルティングサービスを提供し、2012年より同社国内コンサルティングサービス統括責任者に就任。2014年、RISU Japan株式会社を設立。タブレットを利用した小学生の算数の学習教材で、延べ30億件のデータを収集し、より学習効果の高いカリキュラムや指導法を考案。国内はもちろん、シリコンバレーのハイレベルなアフタースクール等からも算数やAIの基礎を学びたいとオファーが殺到している。