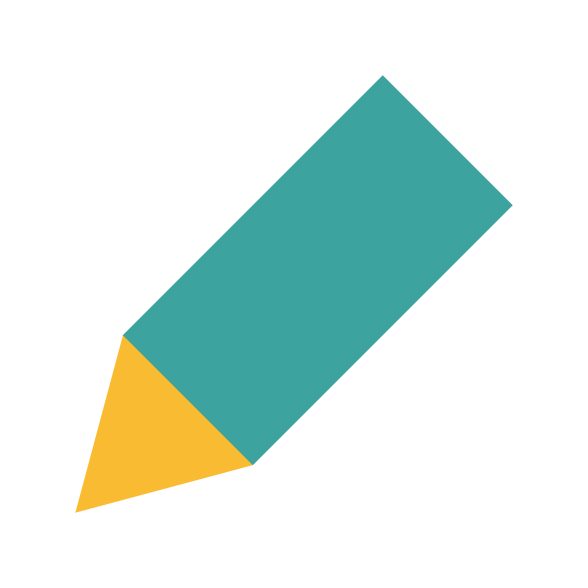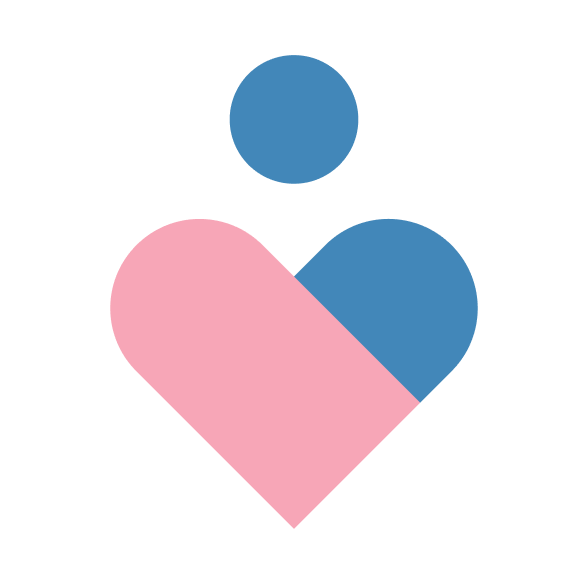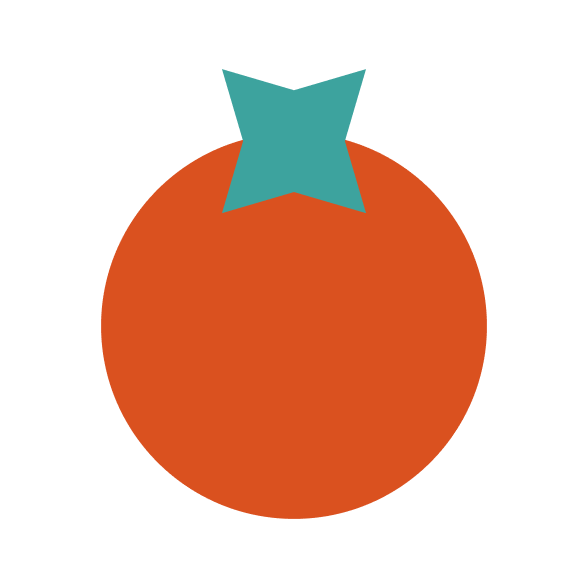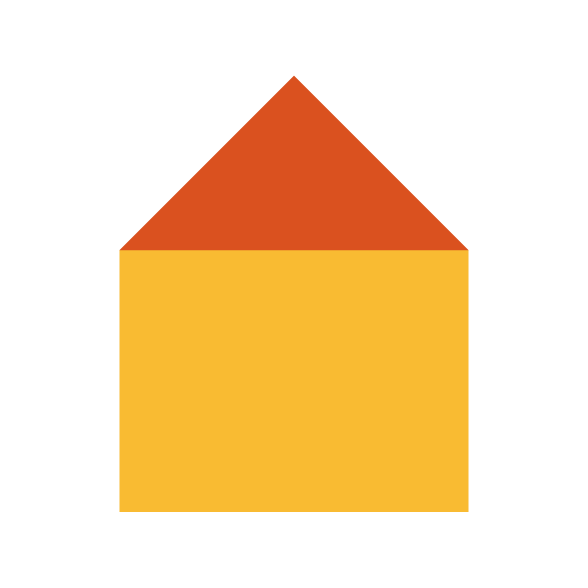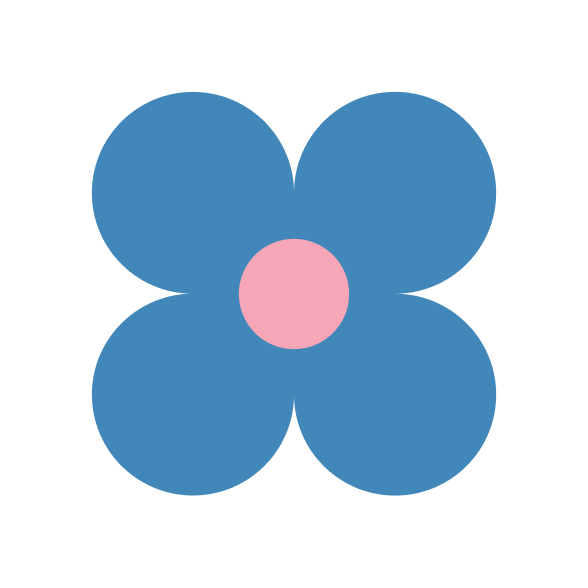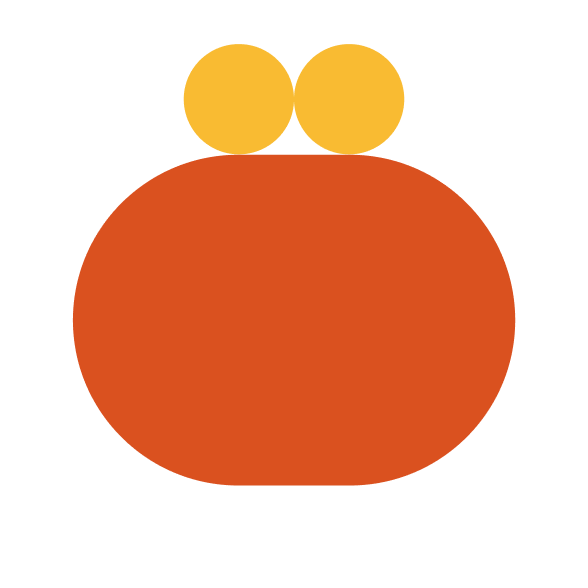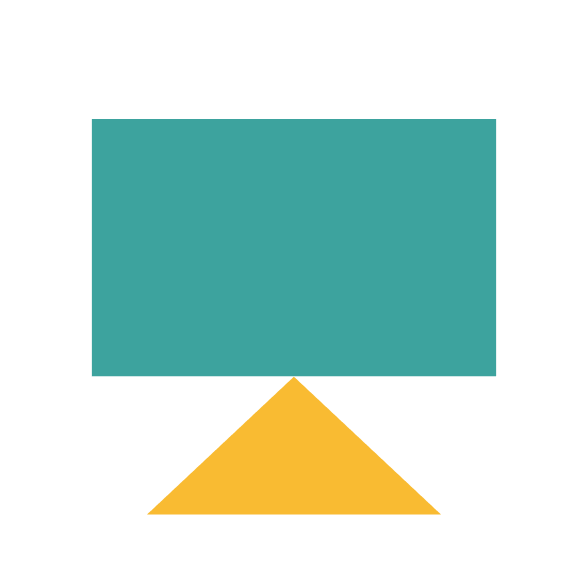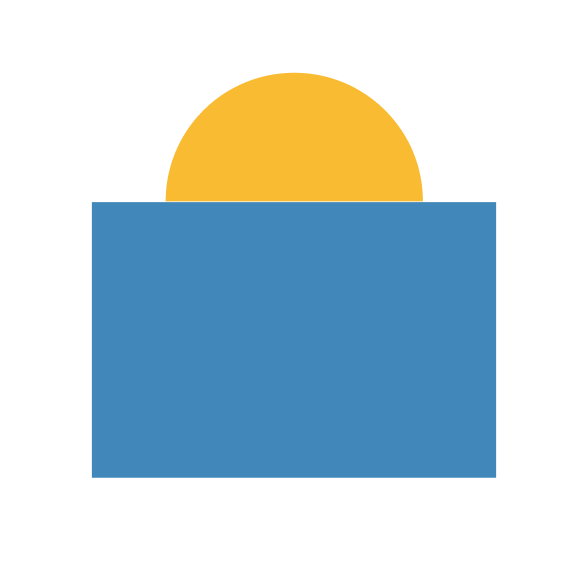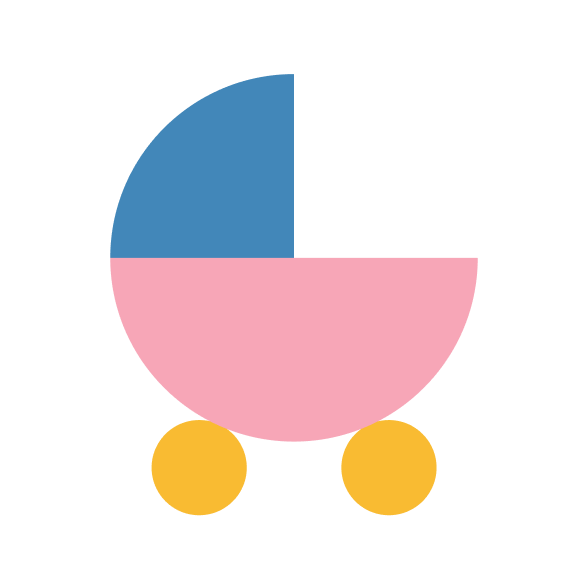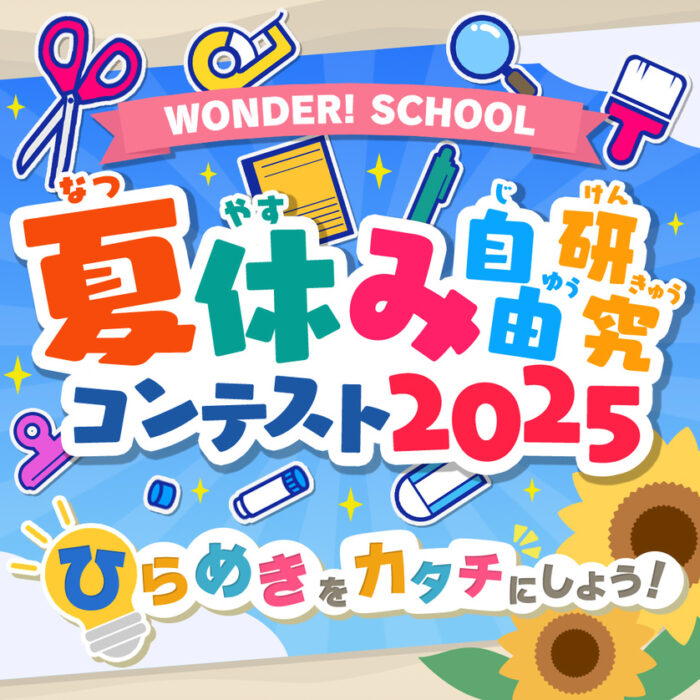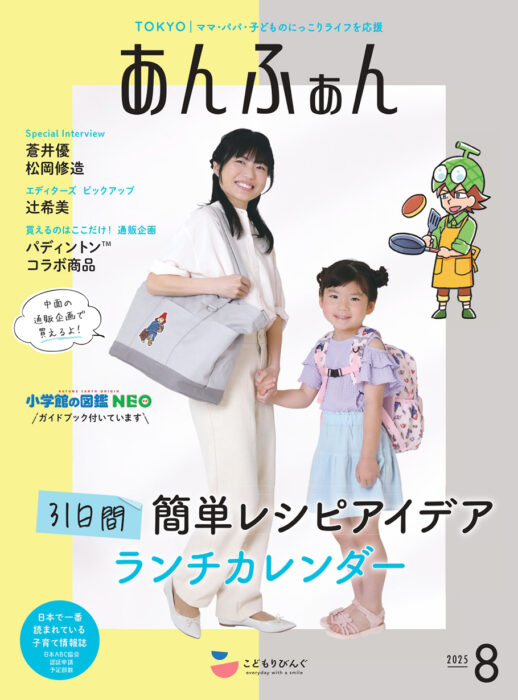モンテ流・自立心を育てるお掃除タイム。今年の大掃除は子どもと!

年末が近づくにつれ「大掃除、そろそろやらなくちゃ」と少し億劫ですが、今年は「子どもと一緒に」早めのお掃除を始めてみませんか。子どもと掃除するなんて非効率!と思われるかもしれませんが、実は子どもの自立心を育てるチャンスなんです。
子どもは大人のまねっこが大好き!
大人のまねっこが大好きな子どもたちは掃除用具にも興味津々、「私も同じようにやってみたい!」という気持ちでいっぱいです。普段から子どもに邪魔されてお掃除できない…という状況ならば、いっそ子どもを掃除に巻き込んでしまうという逆転の発想はいかがでしょう。
モンテッソーリのプログラムでもホウキや雑巾での掃除を取り入れていますが、私の勤務園には子どもたちによる「食事当番」があります。まずはこの当番の内容から、子どもがどんなことを学べるのか紹介していきましょう。
モンテッソーリの教室で行われている「食事当番」
「食事当番」の内容は、エプロン・帽子をつけて、バケツに水をくむ、布巾を絞って机を拭く、テーブルクロスを敷く、花を活けた花瓶を飾る、コップにお茶を注いで配る…などです。
3〜5歳の縦割りクラスでの活動はそれぞれの発達段階でできることを分担して行いますが、子どもたちがすっかりやり方を心得ているので、保育者は口出しせずに任せて見守っています。
全体の流れを把握して作業をリードする年長児は現場監督のようでもあり、年少の子どもにやり方を教える頼もしい先生でもあります。エプロンのひもを後ろ手でさっと蝶結びにするやり方もサマになっています。
年中児はスムーズに作業を進めます。バケツに水をくみに行き、布巾をしっかり絞ってからテーブルを拭きます。ふたりで机の両端に立ち、端から中央へと布巾を両手で押さえて拭いていきます。
ちょうど机のまんなかで布巾同士が「ごっつんこ!」となるようにすると拭き残しがありません。それからテーブルにクロスを広げます。

年少の子どもがテーブルに花を飾ると、皆がお茶を入れたコップを運びます。年長児が各テーブルのコップが座席の数と同じになっていることを確認したら、作業は終わりです。
お当番は一見すると単なる作業ですが、実はこんなことを学んでいます。
- 体の動かし方を学ぶ…布巾を絞るような小さな動作、バケツやコップを(こぼさないようバランスをとりながら)運ぶなどの大きな動作
- 作業の順序や段取りを考える
- 人に教える…相手の能力や理解度を推し量る
- 自分の役割を持つ、誰かの役に立つ
布巾を絞る動作は「手首を捻って回す」という練習になり、お茶の入ったコップをお盆で運びながらバランス感覚を養います。年中以上の子どもにとっては、順序や段取りを考える訓練や、相手の能力を考えながら教えるという体験が得られます。
そして、誰かにお茶を用意したり花を飾ることで「ありがとう」と言われる体験から自信をつけていきます。このような体験は子どもの成長に重要なエッセンスであり、おうちでもできることがあります。
おうちで子どもと掃除してみよう
子どもサイズの道具を用意して、親子でやってみてください。具体的なやり方はこちらです。
- ゆっくりした動作でやり方を見せる
- 子どもにまねしてもらう
- うまくできないところを助ける
というステップです。遊びと同じく気長にお付き合いする感覚で、大人が「急がない」ことがポイントです。
雑巾がけ
年齢目安:2歳半〜
子どもの手の大きさにあった道具を用意します。小さめ雑巾なら8×15cm程度が目安。

雑巾絞りのやり方
- バケツに水をくみ、雑巾を入れます。雑巾を絞りやすい大きさに畳み、水滴が出なくなるまで絞ります
- 「やってみせるから、見ていてね」と声をかけます。動作を見せている間は喋らず、子どもによく見えるようにゆっくりと手を動かします
- 「次は〇〇ちゃんがやってみて」と子どもに雑巾を渡します。初めはうまくできないので、子どもの手を握って絞る動きを一緒にやってみるといいと思います
- 絞り終わったら「お水がポタポタ落ちないかな?」と子どもと一緒に確認します
雑巾がけのやり方
- 子どもの雑巾がけは両手を使って行います。両手を使うと腕だけでなく体全体を使った動きになり、体重をかけることで掃除しやすくなります。大人は普段片手で拭いているかもしれませんが、やり方をみせる場合は両手で行なってください
- 2歳以下の小さい子どもの場合は、大人が水拭きしたところを乾拭きしてもらうのが良いと思います。「ここを拭いてください」「ここもお願いしまーす」と場所を伝えると、一生懸命拭いてくれると思います
掃き掃除
年齢目安:2歳半〜
子どもの手の大きさにあった道具を用意します。卓上用のホウキとちりとりなら子どもにも使えそうです。

- ちりとりとホウキの持ち方をみせる
- 手首を動かしてホウキでゴミを集める、ちりとりに入れる。この動作は子供にとって想像以上に難しい動きなので、雑巾がけと同様に初めに大人がしっかりやり方を見せましょう
- ちりとりに入れたゴミは落とさないようにそっとゴミ箱まで運んで捨てます
1〜2歳でも「ゴミ箱にポイ」ならできる!
使い終わったティッシュなどの軽いゴミなら、子どもに捨ててもらいましょう。ゴミ箱の場所を教えてから「このゴミをポイしてきてくれる?」とお願いすれば、遊びのように楽しんでやってくれると思います。場所を忘れてしまったら、「あそこだよ」と教えてあげてください。
日常的に繰り返し行なって「自分のゴミは自分で片付ける」を習慣にしていきましょう。
自分が使ったものを片付ける
おもちゃや絵本など、出したものは自分で片付ける習慣もつけてみましょう。いつも大人が片付けていると、それが当たり前になってしまいます。物の定位置を決めておくと、子どもが自分で元に戻しやすくなります。お片付けタイムを決めて、片付けるようにしましょう。
やり方を覚えたら、日常的に掃除しよう
一度やり方を覚えたら、日常的にたくさん掃除の機会を取り入れてみてください。あらかじめ子ども用雑巾の置き場所を決めておいて、子どもが自分で取りに行けるようにしておくと自発的な行動につながりやすいです。
食事の後にテーブルを拭いたり、何かをこぼしてしまったときは大人と一緒に拭くなどはどうでしょうか。こぼしたときの応急処置は大人の出番かもしれませんが、「〇〇ちゃんも雑巾をとってきて」と子どもを促すのも良いですね。掃除が終わったら「お部屋がきれいになってうれしいね」と声がけをしてみましょう。
子どもだからといって大人が全てやってあげるのではなく、成長度合いに合わせて家事に参加してもらいましょう。子どもにとってはどんな小さな作業でも「信じて任せてもらえる」ということが大きな喜びになりますよ。