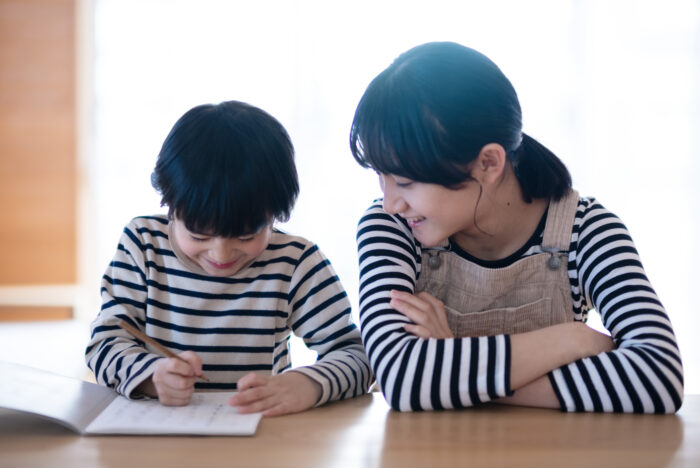更新 :
「自分でできる」がどんどん増える 生活習慣スイスイ大作戦

新生活が始まった春。特に入園まもないご家庭は、わが子の生活習慣が気になりますよね。
まだひとりでできないあれこれについて、親はどう関わるとスイスイできるようになるのでしょうか?
テレビやYouTubeでも人気のカリスマ保育士てぃ先生に聞きました。
読者ファミリーのお悩みにアドバイス シーン別・スイスイ大作戦
読者アンケートで「まだできない生活習慣」として多く挙がったシーンについて、てぃ先生にアドバイスをもらいました。
寝起きが悪い
大人でも朝起きられない人はいますよね。子どもでも多くの子は朝が苦手で、きちんと起きられる子は少数派。だから「寝起きを良くしたい」でなく「寝起きが悪くても登園に間に合うようにしよう」と考えましょう。
●少し早く起こして、親の時間と心に余裕を
寝起きが悪くて親が困るのは「子どもが起きないから」でなく「起きないことで時間がなくなるから」がほとんど。この場合は5~10分早く起こすだけで困ることを減らせます。
●スキンシップで機嫌を良くする
「起きて」と言葉だけで起こすと子どもは不機嫌になりがち。寝ている子どもに寄り添ったり、ハグをしたりして、1分だけでもスキンシップをすると、心が安定して機嫌良く起きられるでしょう。
●自分で目覚ましをセットしてもらう
目覚ましのタイマーを、前夜に自分でセットしてもらいましょう。朝は、子どもがタイマーを止めるまで待って。「自分で決めた起床時間の約束を、自分でちゃんと守った」という成功体験が大切です。
時間が来ても遊びをやめられない
子どもにも子どもの予定があります。親の都合で急に「おしまいだよ」と言えば、ごねるのは当然。先の見通しが立てられるように予告して、心の準備をしてもらいましょう。
●終わりの時間を可視化する
砂時計を使う、時計の文字盤にシールを貼るなど、終了時間を見て分かるようにしましょう。また、事前に決めた時間は親も必ず守って。親の都合で「もう少しいいよ」と延長するとルーティンになりません。
●「取っておいてまた遊ぼう」とする
片付けがイヤで遊び続ける子もいます。特にブロックやおままごとなど、遊び始めてから面白くなるまでに時間がかかる遊びは、「そのまま取っておいて、また遊ぼう」とすると納得しやすいでしょう。
食事に集中できない
座った位置からおもちゃなど楽しそうなものが視界に入ると、集中力が切れやすくなります。食事に集中しやすい環境を整えましょう。
●立ち歩かない約束を
食事中に飽きて立ち歩く場合には、「立ったらごちそうさまね」と事前に約束を。それでも立ったら、有無を言わさず食事を下げましょう。
食事中に遊ぶことを許してしまうと、親だけでなく子どもも食事を取れずに困ります。ルールは親も守ることが大切です。
●テレビは消す
大人でもテレビの面白いシーンでは箸が止まります。食べることに集中できるように、テレビは消しましょう。静かな環境がイヤなら、ラジオなど耳だけで楽しめるものを。
●足を置く位置にマークを
テーブルの上に足を乗せる、椅子の上に立つなど、足癖がよくない場合は、正しい姿勢を保てるよう、椅子や床など足を置く位置にマークを付けてみましょう。
食事を時間内に食べ切れない
まず見直すのは量。いつもの1/4でもいいので、「自分で食べ切れた」という自信を付けることが大切です。この成功体験を積めず、毎回怒られていると、食事への意欲が下がって悪循環。園ではちゃんと食べていたり、お腹が空けば食べられたりすることも多いので、「親が食べてほしい量を食べる」にこだわらないようにしましょう。
●食べたい量を子どもが決める
子どもも大人と同じでお腹が空いていない時、食欲がない時があるので、食べる量は子どもに決めてもらいましょう。最初は「自分のお腹の具合」と「食べられる量」が合致しないので、食べ切れないことも多いはず。ですが、この練習を繰り返していくと、いずれ適切な量を見極められるようになります。
●時間が来たらおしまいにする
食べ始めから20~30分たつと、食べた量が少なくても血糖値が上がって満腹感を感じてしまいます。すると集中力が途切れて、さらに食べるのが遅くなります。食事の時間は30分(長くても40分)と決めておき、時間が来たら食べ切れなくても切り上げましょう。
遊んだ後、片付けない
自発的に「次の行動に移る前に片付ける」ことは、未就学児にはまだ難しいことも多いもの。幼児期には片付けやすくするサポートが必要です。片付けやすい環境作りと、片付けがイヤにならない工夫をしましょう。
●物の定位置を明確にする
物をしまう定位置を決め、イラストや写真を付けるなど、子どもにも分かりやすくしましょう。
●一つの箱にしまうところから
片付けが苦手な子の場合、物を細かくカテゴリー分けするとハードルが高まってしまいます。まずは1つの大きな箱に全部入れればOKとし、あとは親が分類して片付けましょう。箱に入れる習慣が定着したら、「ブロック」と「その他」などと箱を2つに分け、それができたら3つに…とスモールステップで進めて。
●親子で役割分担する
「ひとりで全部片付けて」はハードルが高すぎ。おもちゃを集める係と箱にしまう係など、親子で分担しましょう。子どもが主役なので、役割を決めるのは子ども。親が選択肢を用意して選ばせてもOKです。
脱いだ靴をそろえない
「ちゃんと」「きれいに」は子どもに伝わりにくい言葉。「靴をちゃんとそろえてね」ではイメージできません。「次に履くときに便利だよ」「玄関が汚いとイヤだよね」と教えても、子ども自身は不便を感じないでしょう。
●靴を置く位置にシールを貼る
靴を置くべき位置を可視化しましょう。シールを2枚貼り、「シールにかかとを合わせて置いて」と教えてみて。
お風呂に入りたがらない
目に見える汚れが付いていないと「汚れたからお風呂に入ろう」では伝わりません。入る目的を“自分ごと化”してもらいましょう。
●お風呂での役割を設定する
「ママのシャンプーを出してほしい」「パパの背中を洗ってほしい」など、家族を助ける役割を決めてみて。入る目的が“自分ごと化”され、「自分は役に立っている」という自己有用感(自分が人の役に立っているという気持ち)も得ることができます。
“その場しのぎ”のテクは乱用しない
「お風呂で遊ぼう」と誘えば、動いてくれる子は多いですよね。同様に、やってほしいことを「○○屋さんごっこ」などの遊び風にすると、子どもは動きやすくなりますし、ルーティンを崩さないためには役立ちます。ただ、これらはあくまでも“その場しのぎ”。
「遊びでないとやらない」となると困るので、乱用はしないほうがいいかもしれませんね。
【読者アンケート】今回の特集、いかがでしたか?
抽選で10人に1000円分のAmazonギフト券をプレゼント!
私たち編集部では、皆さんの感じたことを大切に、あんふぁんを作っていきたいと思っています。下の応募ボタンよりアクセスして、感想を教えてください。