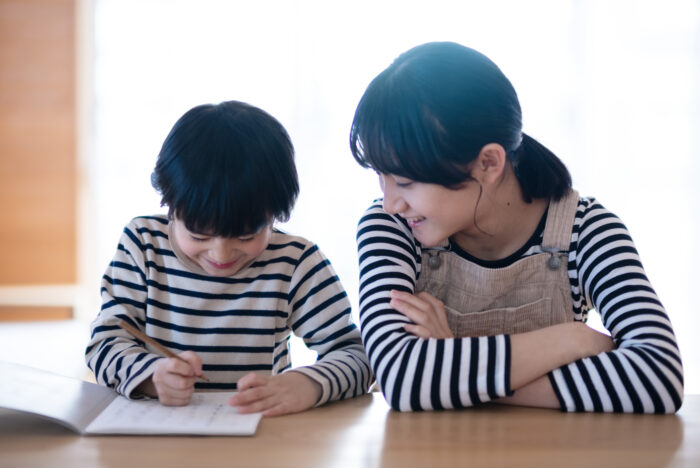更新 :
子どもの「好き」から見えてくる わが子の得意を発見!

子どもの得意なことは、見つけて伸ばしてあげたいと思うのが親心。
実は意外なところに、子どもの素晴らしい能力が隠れているかもしれません。
それを見つけるカギは、「子ども自身が好きなこと」にありました。
“好き”の見つけ方Q&A
さまざまな種類の知能があることを知ったら、次に気になるのはわが子の「得意」は何なのか、ですよね。子どもの「好き」をどう見つけ、親としてどのように関わったら良いかを、岡田先生に聞きました。
Q. きょうだいでもタイプが違うのはなぜ?
A. 同じ家庭でも環境は異なるから
「同じ家庭で育ったきょうだいなのに、上の子と下の子で好きなことが全然違う」という声がありますが、それは当然のこと。親としては「きょうだいで同じように接しているのに」と思いがちですが、上の子は“妹・弟がいる”、下の子は“姉・兄がいる”という時点で環境が違いますし、共に過ごしている幼稚園の先生や友達も違います。そういった環境の違いによっても、育つ知能は変わってくるのです。
ちなみに、得意なことが似ている子同士だと話が合いやすい一方で、得意なことが違う子同士で補い合うこともあります。例えば、「博物的知能が高く恐竜に詳しい子の影響で、自分も恐竜が好きになった」「言葉が苦手な子に代わって、言語的知能の高い子がママに言いたいことを伝えてくれた」なんてこともあるのです。
Q. 子どもの知能は親からの遺伝?
A. 遺伝+環境・経験の組み合わせ
知能は遺伝的な要素と、生まれてからの環境・経験との組み合わせで決まるものとされています。「遺伝的要素がどれくらいの割合か」というところは議論があり、まだ結論は出ていません。
遺伝的に優れた能力があっても、それを発揮する機会がなければ能力が表に出ることはありません。多重知能理論は、「いろいろな視点で、人の良さを見つける」という考え方です。遺伝に着目するより、今の子どもの良さを見つけて伸ばしてあげましょう。
Q. “好きなこと”の見つけ方は?
A. まずはいろいろなことに触れる機会を作って
前述のように、能力があってもそれを発揮する機会がなければ、その力は表には出てこないもの。まずはいろいろな経験ができる環境を作り、子どもの反応をよく観察してみましょう。
世の中にはチェックリストで能力を数値化するものもありますが、チェックリストに回答すること自体が言語的知能や論理的数学的知能を使うので、正しい能力を測ることは難しいと言われています。ぜひ普段の生活の中で、子どもが夢中になっていることに注目してみてください。
絵本やおもちゃがあり、他の子どもがいる幼稚園での過ごし方は、とても参考になると思います。可能なら幼稚園での様子をのぞいてみたり、先生に子どもの様子を聞いてみたりするのも良いかもしれません。家では気付かなかった子どもの「好き」が、見つかるかも。
Q. 能力を伸ばすにはどうすればいい?
A. 今よりちょっと上の段階を見せましょう
まず原則として、子どもの興味があることを認めて追求させてあげることが大事。大人が子どもの好きなことに良し悪しをつけて中断させることなく、できるだけ温かく見守ってあげましょう。
その上で少しサポートするなら、自分よりちょっと上のレベルを経験させてあげることがおすすめです。心理学では「最近接発達領域」と言いますが、“今一人でできること”と“他人の助けがないとできないこと”のギリギリ境目を目指すことで、物事が上達するとされています。例えば、空間的知能が高く絵を描くのが好きな子には上手に絵を描く様子を見せてあげる、身体運動的知能が高くサッカーが好きな子には「こんなすごいキックがあったよ」と上手な人のプレイを見せてあげる、などは良い刺激になると思います。方法を直接教えるのではなく、目で見て気付かせることが大切ですよ。
岡田先生からメッセージ 子どものをすごいところを見つけよう
好きなことに夢中になっているとき、きっと子どもはとても楽しそうにしているはず。“こうあるべき”“こうなってほしい”という思い込みはやめて、ありのままの子どもの様子を見て「へーすごいなぁ!」と思うところを見つけてあげましょう。
大きくなると、好きなことも「テストの役に立たないから…」などとやらなくなってしまうことがあります。小さな子どもはそのような忖度(そんたく)がなく、好きなことにとことん熱中できるとても貴重なとき。ぜひ思い切り楽しませてあげてください。場合によってはママ・パパも一緒に楽しむと良いですね。