更新 :
作文を上手に書くコツ!小1から育てたい「書く力」
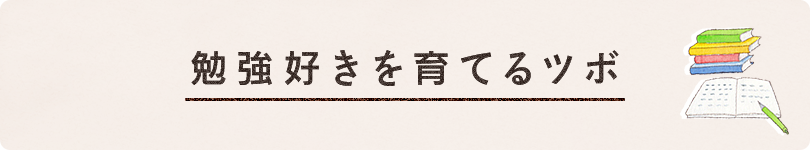
こんにちは、いしびきです。
7月に入りましたね。多くの小学校や園で通常のカリキュラムになって、やっとクラス全員がそろう!と喜んでいるお子さんも多いでしょうね。
さて、外出自粛期間中に新1年生のママから、「作文の宿題が出て困った」とメールをいただきました。
お困りの気持ち、すごくわかります。低学年に作文を書かせるのは本当に大変!
なにしろ、ひらがなで言葉を書いたり読んだりするのだってままならず、言葉の意味すらよくわかっていないのに、「作文を書け」っていうのは厳しいですよね。
それでも小学校では、1年生の夏休みくらいから感想文などの宿題が出るので、親はどうやって教えたらいいのか悩むのは当然だと思います。
私もわが子が1年生のときの作文が一番苦労をしましたし、もっとも記憶に残っています(笑)。
低学年の学習で苦労するのは、算数ではなく…

わが子が1年生のとき、たった400文字の作文用紙2枚を書かせるのに、4日も5日もかかりました。まさに親子ともどもヘトヘト…。
言葉の意味や使い方をまったく学習していない子どもに、作文を書かせるのは無茶だ!と感じた思い出があります(笑)。
以前、国語塾の先生に取材した際に、「小学校の低学年の学習でいちばん苦労をするのは、実は算数ではなく国語の作文なんです」とおっしゃっていました。
算数は答えがあるので、論理的に説明すれば家庭でも教えやすいと思いますが、国語の場合、教え方のルールがないと思っている人が多いからだそうです。
特に、作文は「センスがないとダメ」と思い込んでいるママたちが多いように思います。だから最初から「教えられない」と諦めてしまうのでないでしょうか。
国語はセンスではなく「要約力」が必要です
でも実は、「国語はセンスがないとできない」と思っているのは間違いなんだそうです。
国語塾の先生は、「国語は、たとえば音楽で楽器を鳴らすのと同じように日々の積み重ねで力がついていくもの。そして、読解力や思考力は要約力があってこそ」とおっしゃっていました。
とくに、国語の長文のテストで何が書かれているのかを読み解くためには、要約力が必要です。
この「要約力」は作文を書くのにも大事だと思います。自分が考えていることをまとめるのにも要約力がいりますよね。
でも、小学校の低学年生の場合は、文章のクオリティを上げる前に言葉をつむぎ出すことが求められます。
ところが、語彙もあまりなく言葉の意味がわからない低学年生が、自分で言葉をつむぎ出すことはできません。
ここで、ママやパパの力が必要になります!
「作文を上手に書く」には、ママやパパとの「会話」がポイントになってくるのです。ママやパパがお子さんにする質問の仕方に、作文を上手に書くポイントがあるのです。それは、「細かくたくさん聞くこと」です。
根掘り葉掘りのインタビューで内容を聞き出す
たとえば、今朝なにを食べたかということを細かく聞いてみてください。
パンを食べたなら…。
パンの種類や大きさや見た目の形、色などを聞いてみましょう。それからどれくらい食べたのか。その味はどうだったか。だれがどのようにして作ったのか。
できあがったときにどう思ったのかなど、対象物の様子はもちろん、それに対しての行動なども聞くと面白いですよ。
ほかには何を口にしたのか、それはどういう様子のもので、味はどうだったのか。今朝の朝食についてどう感じたのか。明日はどうしたいのかなど、お子さんに、根掘り葉掘りインタビューしてみましょう。
そして、よりよい作文にするには「気持ちも聞く」こと!
食べる前と食べている最中、食べ終わったときどう思ったのかを聞いてみましょう。これが「個性」となってほかにはない作文に仕上げてくれます。
小学校1年生の男の子に、根掘り葉掘りインタビューをしてみたら、こんな言葉が出てきました。
ぼくの朝食はパンケーキ。
パンケーキはおかあさんが作ってくれた。
土ようびの朝ごはんによくつくってくれる。
ふわふわであまくて、まるでおふとんみたい。
少しちゃ色くてこげめのにおいがする。
パンケーキに手をあててみるとあたたかい。
フォークをさして、「ごめんね」とこころでおもいます。
ぼくはお兄ちゃんだから、いもうとのパンケーキより少し大きいからうれしい。
ぼくはパンケーキが大すきです。
毎日パンケーキを食べたいな。
誕生日には、パンケーキをタワーみたいにしてクリームやチョコやお菓子をのせて何かをつくってみたい。
作文を面白くするなら、テーマをひとつにしぼってみる
作文のテーマを考えるときに、「海に行ったことについて書こう」と考える場合があります。でも、あまりにもテーマが大きすぎると、
海に行きました。貝を拾って楽しかったです。お弁当もおいしかったです。帰りに車が混んでいてとっても疲れました。
と、ちょっと面白みに欠けてしまいがちです。
より面白い文章にするコツは、「ひとつのことを集中して書くこと」だと思います。つまり、テーマをひとつのことにしぼるのです。
前述のように、1日のうちでも朝食だけにしぼって書くほうが、子どもの気持ちをより深くとらえることができますし、何を見て・考えて・行動しているのかをまとめたほうがユニークな発見があるはずです。
「個性」を出すには「気持ち」を書くこと
今回は朝食の話で、パンケーキが出てきたとき、色や形などの様子を細かく聞いてみました。
それからそれに対する「気持ち」も聞くと、その子だけの作文ができあがります。状態を書くだけだと、ただの解説ですが、それに「気持ち」「考えたこと」が入ることで、個性が生まれてきます。
小学校の先生が作文を添削するときに重きを置いていることがあります。
それは、自分ならではの視点で書かれているかです。
作文は、言葉の意味はもちろん、自分の気持ちや考えを整理して表現する学習なので、同じテーマであっても、「自分だけのことば」「自分だけの切り口」を使った方が点数は上がるのです。
さきほどのパンケーキの聞き取りをつなげる作業は、ママやパパがお手本を見せるといいと思います。
つなげるときのテクニックは、絵本や童話などをマネしてみるといいですよ!
大学受験にもつながる「書く力」を少しずつ
親子の細かい質問(記者のように取材する)をして出てきた言葉を子どもに書かせます。それをつなげる作業までは、やっぱり親が教えなければいけないなと私は思っています。
それを1回や2回ではなく、何度も続けなければいけないのです。
子どもはすぐにはひとりで作文を書くことはできないでしょう。
なかにはひとりで書きたい子もいるので、そういうお子さんはどんどん書かせてください。書けば書くほど、文章は上達していきます。
でも、やっぱりひとりではなかなか作文が書けなかったら、親が子どもの頭から言葉を引き出して、その引き出し方を身につけさせてください。
時間はかかって当然! ここは親が根気強く、けっして頭ごなしに叱らず!
昨日よりもひとつ何かを覚えてくれたらOK。階段を1段ずつ登りましょう。
作文を書く力は、2020年からの大学受験につながっています。
小学校のうちに、書くことへの興味を持たせることが大切です。




























