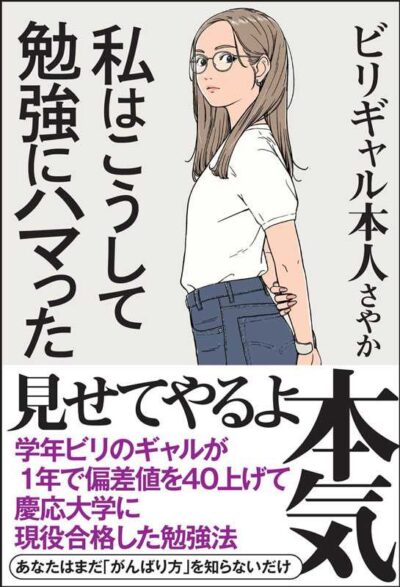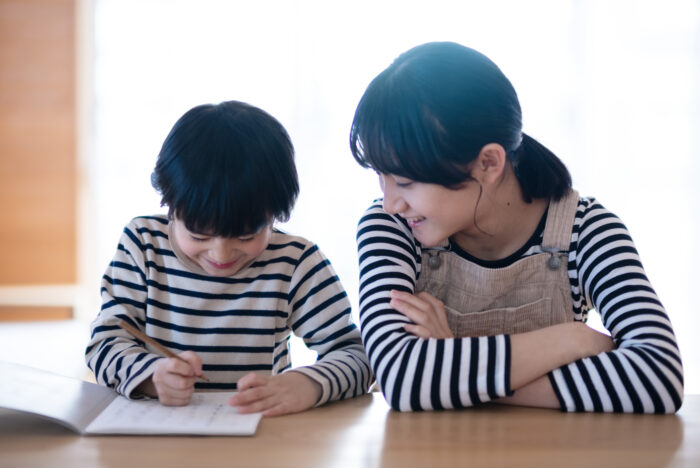なぜ勉強するの?“ビリギャル本人”が語る、幼少期に知っておきたい親の関わり方

『学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話』通称“ビリギャル”の主人公、小林さやかさんが、人はどうすれば勉強にハマれるのか?どうすれば「勉強ができる人」になれるのか?をわかりやすく解説した『私はこうして勉強にハマった』を7月に発売。
小林家の子育てや勉強との向き合い方、子どもの勉強をサポートする心構えなどについて、お話を聞きました。
「ビリギャルの本当の主人公は母」小林家の子育てとは?
ビリギャルの本当の主人公は母だと思っていて、ビリギャルの物語の根っこにあるのは母の子育てだと思っています。母は、私に「ワクワクできることを自分で見つけられる人になってほしい」ということを大切に子育てをしてくれました。なので、いい大学に行ってほしいなんて母は思っていなかったし、何かを強制されたことも一度もありません。
挑戦することを大きく捉えずに、些細なことでもすごく褒めてくれて一緒に喜んでくれる人だったし、何かつまずいたり、望んだ結果が得られなかったときも結果に焦点を当てるのではなく、そのプロセスを見て声がけをしてくれたので、私の中で失敗したという経験がありません。
ビリギャルの著者である坪田先生に「慶應大学を受けてみる?」と言われたときに、「楽しそう、やってみたい!」と当時の自分の学力を考えずに挑戦してみたいと思えたのは母の子育てのおかげです。
学ぶことは誰でも好きなはず
勉強は“興味がなくても詰め込む”というイメージがありますが、それだと苦しいですよね。本来、子どもは知らないことを知る、学ぶことに関しては絶対に好きなはずなんですよ。けれど、これがだんだん「勉強」となると、興味がないものもテストのために覚えるという作業になってしまう。
学びがいつからか勉強になった瞬間に私も嫌いになったし、みんな多分そこで勉強が嫌いになってしまうのだと思います。だから捉え方や考え方が変われば勉強(学び)が好きになるはずです。
私にそれを教えてくれたのが坪田先生で、先生に出会った瞬間に学ぶことに対してのイメージが変わりました。受験も勉強とイメージが近い言葉だと思いますが、当時の私の場合は慶應大学はキラキラしたところというイメージがあり、「慶應に行ってみたいから、勉強してみる!」と勉強に興味が湧きました。
私が受験に挑戦しようと思ったのは、ただのギャルバイアスで行きたいと思っただけで、勉強の楽しさに気がついたというよりは自分の人生が楽しくなりそうだなという感覚でした。違う世界に行くための切符を手に入れるために受験をしてみよう!と思ったのがきっかけです。
モチベーションを保つのに大切なのは、「I can do it!」自分ならできると思えること
勉強を続けるモチベーションを保つために大切なことが2つあります。1つは「I can do it」、これだったらできるとイメージできる範囲のタスクの難易度にすること。つまり難しすぎることをやらないことです。
私は高校2年生の夏に坪田先生に出会ったのですが、そのときにやっていたのは小学校4年生のレベルでした。当時の偏差値が28だったので、そんな子にいきなり高校生だからといって高校生のレベルをやらせたら、次の日塾に来なくなるんですよね。どこまで戻ればこの子ができると思えるか、つまりモチベーションが湧くかというのを先生がしっかり見定めてくれたのです。「6割マルがとれるところまで戻る勇気を持つ」、まわりの大人もそこからやらせる勇気を持つことが大事です。
2つめは、「やってみたい」と思う気持ちです。「こんなのやって何になるんだろう」と思うとモチベーションが下がりますが、「これはやる価値があるな」など、情熱や興味を持った瞬間にモチベーションが上がります。
また、自己肯定感や自己効力感が極端に低い人は「I can do it」と思えるハードルが高く、意欲が湧きにくくなります。例えば、「私が慶応大学に合格するのは無理です」と思っている人を慶應に入れることは無理です。ですが、まわりが絶対に無理だろうと思ったとしても、私みたいに「行けるかも」と言えるくらい楽観的な方がうまくいくのです。

「自己効力感」を育むことで、「自己肯定感」を補える
「自己肯定感」は大人になってから自分で意図的に育てるのは本当に難しいということを私自身感じています。幼少期の声がけや文化、親の育て方、環境である程度決まってしまうものだと思うので、親御さんは子どものいいところを伸ばしてあげることを心がけてあげてください。
「自己肯定感」は自分にはどのくらいの価値があるのかという自己評価で、意識を変えることは難しいけれど、「自己効力感」は「自分ならできる」という根拠のある自信で、これは意図的に育てられるものです。自己肯定感が低くても、この分野では自己効力感が高いぞ、ということがあり得るので、自己効力感を意図的に上げていくことで自己肯定感を補えると思っています。
自己効力感の育て方
1.ロールモデルの存在
他者の代理経験と言うのですが、他者の活躍や成功事例を見てモチベーションや自己効力感が高まります。
2.生理的情緒的状態の解釈
晴れた日はやる気が出るけど、雨の日は気分が落ち込むというように環境要因によって自己効力感は自然に上がったり下がったりします。
例えば、受験など大事な試験の前に手が震えてきたとして、この状態をどのように捉えるかで自己効力感が変化します。ポジティブに受け止めて、「手が震えるほどパワーが溢れてきた」と思えば自己効力感が上がりますが、ネガティブに「緊張してきた。もっと勉強すればよかった」と考えてしまうと自己効力感もパフォーマンスも下がります。
3 .言語的説得
これは坪田先生が私にやってくれたことで、今から慶應大学を目指すなんてみんなは無理だと言ったとしても、「あと1年半もあるから、間に合うよ」と、やれそうな気がする!と思えるような言葉がけも自己効力感を育てます。
4.成功体験
目指していることとちかい分野で成功体験があることは、自己効力感を高めます。成功体験を積み上げることは自信にもつながります。
学びをコンテンツ化すれば、自然と勉強をするようになる!?
「子どもが勉強をしないから困っている」という悩みをよく聞きますが、親御さんが子どもの頃に「勉強しなさい 」と言われて、やる気になったのか思い出してみてください。大人になってから勉強の大切さや必要性に気がついたと思いますが、子どもたちは「なぜ勉強しなくてはいけないのか?」ということを教えてもらう機会がないですよね。
それを伝えるには、まず大人が勉強している姿をみせることが重要なポイントです。言葉だけではなく、親御さんが学ぶことを楽しんでいるところを見せて、勉強をコンテンツ化して家族で共有すればいいと思います。
子どもの教材選びのポイント
感覚的に6割くらい答えられるような内容の問題集から挑戦する。そしてワーキングメモリをあまり使わないものを選ぶことがポイントです。
ワーキングメモリとは、情報を一時的に記憶する能力のことで、基本的に必要ではない情報は長期記憶できずに忘れるようになっているのですが、勉強は一時的に記憶したものを長期記憶にする作業になります。繰り返し覚えようとすることで脳が大事な情報だと認識し、長期記憶になるという感覚です。
このワーキングメモリが重要で、これをいかに効率的に使うかがポイントになります。例えば、文字がぎっしり埋まっているプリントをみると情報量が多すぎてワーキングメモリがパンクして、読む気にもならなくなってしまう。けれど、イラストや図形などを使って説明されたものだと頭に入りやすくなるというように、教材を選ぶ時はシンプルでわかりやすいものを選ぶのがおすすめです。
結果だけでなく、プロセスを大事にしながら見守ってほしい
私が好きなことわざが、「人事を尽くして天命を待つ」です。どれだけ努力をしても実力があっても結果は天にしかわからないということなんですよね。つまり、プロセスに光を当てているわけですね。
私は、結果だけに光を当てることがものすごく怖いことだと思っています。挑戦して頑張ったけれど結果が出なかったからダメではなく、努力したことに意味があって、それは今後の人生で大切な経験になるはずです。
そして、努力をするなら正しい努力をすることが大切です。勉強でもなにかを学ぶにしてもある程度法則があります。間違ったやり方で頑張っても、成果は出ないですよね。これは、まわりの環境が大切になります。
努力しても報われないと思っても仕方ないじゃないですか。もし、結果が出なかったとしてもそのときに掛けられる言葉次第で子どもたちは次も頑張ろうと思えるようになるので、プロセスを大事にしながらお子さんの成長を見守ってほしいと思います。
取材・文/やまさきけいこ
※記事中のリンクから商品を購入すると、売上の一部が当社に還元される場合があります