トラブルメーカーのクラスメイト、どう距離をとればいい?
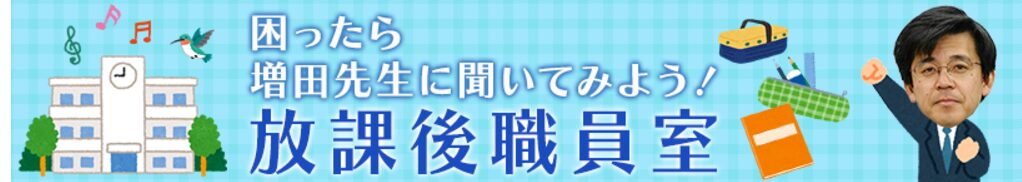
【Q】同じクラスのトラブルメーカーの女の子に困っています。2年生で別のクラスにしてもらうようにお願いしてもよいでしょうか?
小1の娘がいます。共働きのため放課後は学童に通っています。そこには同じ学年で、違うクラスのトラブルメーカーの女の子がいます。心ない言葉をあびせるのは日常茶飯事。娘のスカートをハサミで切ろうとしたこともありました(学童の先生に確認済)。
娘には、その子に近寄らない、関わらないことを徹底するよう教えています。2年生にあがる際にクラス替えがあります。その子とは同じクラスになってほしくないので、学年末の懇談会で先生にお願いしようと思っています。やりすぎでしょうか?
(おつまみ)
【A】トラブルメーカーの子どもへの対応

私も自身も小学校教員時代、トラブルばかりを起こす子どもを担任したことがあります。いや、担任しなかったときがないといってもよいかと思います。
毎年のように、頻繁にトラブルを起こす子どもを2~3人担任しました。そうした子どもを担任することは、苦痛ではありませんでしたし、むしろそうした子どもがいるのは普通のことだと考えていました。
当時、子ども達にはこんなことを言っていました。
「相手が『イヤだ!』とか、『やめて!』と言ったときには、必ず一度やめて、相手の様子を見ること。そう言っているのに続けるのは『いじめ』になるよ。やめてほしいことは、人によって違うからね。自分がよいと思ったことでも、相手がイヤだと思うことがあることを知っていこうね。それが学校で一緒に生活する意味だよ」
トラブルメーカーの子どもに共通しているのは、「相手がイヤだと思うかもしれない」という想像力に欠けていることです。発達に困難さがある子の場合には、ていねいに対応していくことが必要ですが、そうした困難さがない子どもの場合は、相手への想像性を育てていく「声がけ」が必要です。
ただし「そんなことをしたら、相手はどう思うかな?」とか、「相手の気持ちを考えてごらん」とか、「相手の気持ちになって考えてみて」という言葉は、何の効果ももたらしません。それがわかるようならトラブルメーカーにはならないからです。
ご相談の中で出てくる女の子は悪口や、イヤなことを言ってくるようですね。そうした場合には、その言葉を先生にメモしてもらったり、ほかの子どもから聞き取って、メモしておくことです。メモしたことを、トラブルメーカーの子と一緒に分析すると効果的です。「これは相手の欠点を言っている」「こちらは相手の家族のことを言っている」という形で、パターンにわけていくのです。そうした作業をすることで、自分の言葉がどのような形で相手を傷つけているかがわかっていくようになります。
「あの子と同じクラスにしないでください」という言葉は、学年末になると、親御さんから聞くことが多いのですが、クラス編成は子ども同士の相性、クラスの力量の平均化などを中心に決めていきますので、言ったとしても実現するかはわからないことを理解しておいてください。
トラブルを起こすには理由がある
すき好んでトラブルメーカーになる子はいません。「悪いことをして嫌われよう」とか、「意地悪をして楽しんでやろう」と思っている子どもはひとりもいないのです。そうした子どもには、必ず理由があるのです。
娘さんのスカートを切ったのは、きっとうらやましかったのだろうと思います。とてもかわいいスカートだったので、「自分もほしいな!」と思って、ついやってしまった行為だと思うのです。何らかのさみしさを抱えているのかもしれません。そこの根っこの部分を共感してくれる大人が必要です。
私が担任した男の子で、毎日トラブルを起こす子がいました。親はシングルマザーで、看護師をしていました。そのさみしさから、ほかの子に手を出したり、遊びをわざと邪魔していました。そのことをお母さんと十分に話し合いました。
あるトラブルを起こしたとき、ほかの子ども達が耐えかねたので、クラスで話し合いをしました。まわりの子から批判されてつらそうでしたが、ある程度、クラスのみんなが抱えているストレスを、本人にわからせることも必要だと判断しました。
そうした話し合いの最後に、(彼の)お母さんはひとりで子どもを育てていること、看護師をしていて、夜遅くならないと帰ってこられないこと、そうしたさびしさから、みんなに意地悪をしてしまうことなどを、噛んで含めるように話をしました。
翌日、本人が「増田先生が自分の気持ちを話してくれてうれしかったし、すっきりした。こんなにみんながイヤな思いをしていることに気がつかなった」「これからは気をつける」といった内容の作文を持ってきました。これ以後トラブルを起こさなくなりました。
トラブルメーカーの子どもの気持ちを理解し、寄り添ってくれる大人がいれば、子どもは変わることができるのです。
担任の先生や、学童の先生に頼んでみることがよいと思います。今回の記事を担任の先生や、学童の先生に見せて、一緒に考えてもらえたらとてもうれしいです。
【新刊】
新刊「子どものココロが見えるユーモア詩の世界-親・保育者・教師のための子ども理解ガイド-」(ぎょうせい、1980円)発売中。

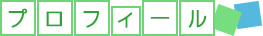

増田修治先生 あんふぁんサポーター
白梅学園大学子ども学部子ども学科教授。
1980年、埼玉大学教育学部を卒業後、埼玉県の小学校教諭として28年間勤務。
若手の小学校教諭を集めた「教育実践研究会」の実施や、小学校教諭を対象とした研修の講師なども務めている。
「笑う子育て実例集」(カンゼン)、「『ホンネ』が響き合う教室」(ミネルヴァ書房)など、著書多数。



























