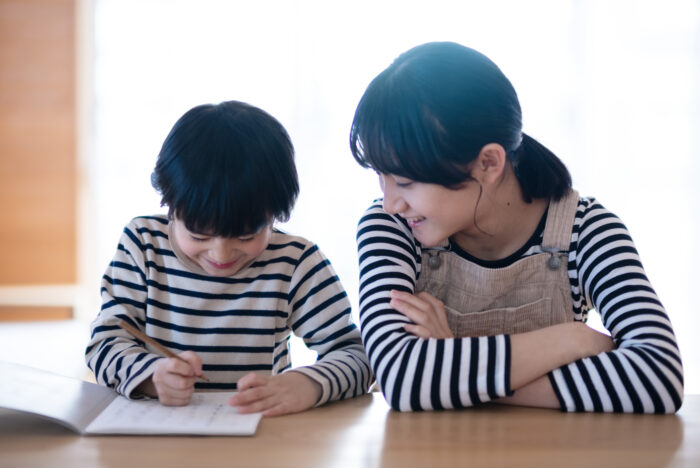更新 :
園生活の中にヒントがこれからのSDGs


SDGsって何?

「SDGs(持続可能な開発目標)」は、2030年までに達成すべき世界共通の目標。2015年の国連サミットで、全ての加盟国が合意して採択されました。貧困や気候変動、感染症など数多くの課題に対処しながら、誰一人取り残すことなく、持続可能でより良い社会の実現を目指す17の目標が掲げられています。
大和山王幼稚園のSDGsへの取り組み
SDGsの活動に力を入れている、大和山王幼稚園(神奈川県大和市)。園生活に散りばめられた工夫について、副園長の小倉賢人先生に聞きました。

使い終わった段ボールや紙箱、失敗した折り紙などを捨てずに活用。子どもの製作の素材にすれば、元は廃材だから失敗を恐れることなく使えて、イマジネーションがふくらむのでは。園内には先生の作ったものもあり、それらが身近なものでできていると気付くと、園児の創作意欲が刺激され、「やりたい!」となることもあるそうです。

先生からのポイント
「青色が好き!」「風で揺れているね」と、子どもは興味津々。家庭では並べて遊ぶだけでも十分楽しめると思います。


SDGsを園児たちに言葉で説明するのは、なかなか難しいもの。「知的好奇心を刺激する絵本だと比較的理解しやすい」と先生。園児が自由に出入りできる図書室には、健康やジェンダー、資源の大切さなど、SDGsにつながる考え方をやさしく教えてくれる絵本がそろっています。

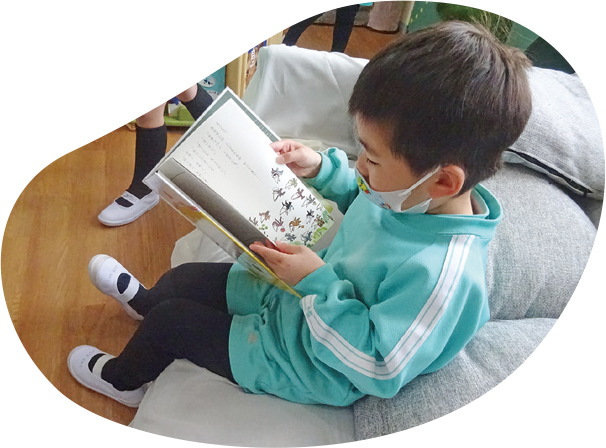
先生からのポイント
無理に読み聞かせるのではなく、自然と手に取れるような環境にしておくことが大切です。

園庭は植え込みや花壇に加え、あえて野草の種をまいて緑化。空気がきれいになる、虫や鳥を呼び寄せる、目に優しい、転んだ時クッションになるなどのメリットがあります。野草を摘んでおままごとをしたり、花冠を作ったり、遊びのバリエーションが増えるきっかけにもなっています。

先生からのポイント
野草と植え込みの花の区別がつかない子もいます。公園であえて野草と触れ合うのも良い体験になると思いますよ。

食育は実体験を大事にしています。園で行う料理体験では、スーパーで材料を買うところからスタート。年長さんにはグループごとに「牛乳を買う」「麺を買う」などのミッションを与え、年少さんには商品の写真を見せながら「これを見つけてきて」とお願いし、ワイワイと楽しみながら買い物をします。

先生からのポイント
普段親が買っているものを子どもが選んでくることも。食材選びを手伝ってもらうと自然と食育につながります。


先生からのポイント
トマトや枝豆など、子どもの目の高さに実がなる野菜は変化が分かりやすく、おすすめです。
楽しみながらTRY 幼稚園のSDGs
DGsを意識した取り組みを行う幼稚園は他にもたくさん。子どもたちが楽しく実践できる工夫がいっぱいです。
ワカバ幼稚園(東京都中野区)

読み終わった新聞紙を職員が持ち寄り、みんなでかぶとを作って、5月5日の子どもの日をお祝いしました。園児には「きれいな紙を用意しなくても、新聞紙でいろいろなものが作れるんだよ」と説明。大きな紙を折ることに多少苦戦していましたが、かぶとができると歓声が上がりました。

西山幼稚園(京都府京都市)

園児の体操服は男女ともに同じ、白いTシャツとショートパンツ。カラー帽子も男女で色を変えるのではなく、クラスごとの色分けです。性によって役割を決めつけず、男女が入り交じってさまざまな遊びや活動を行っています。


牛乳パックやティッシュの箱など、職員が生活の中で出た廃材を持参し、廃材室にストック。子どもが自ら何を作るか考えて製作します。「トイレットペーパーの芯出して〜」とリクエストもあり、不用品を楽しみに変えています。子どもが楽しむ姿を見て保護者からも廃材が集まるようになり、自然とSDGsに取り組めています。

稚竹幼稚園(東京都板橋区)

都心に住み、植物を育てた経験のない園児たちと花や米、野菜を育てています。園児には、植える時に「植物を育てることは人や地球に優しいこと」と説明。無意識に花をちぎっていた子が、花を大事に扱うようになりました。花を植えやすい5月・10月がおすすめです。育てた花を卒園式の花道に飾ったり、米や野菜を収穫時にみんなで食べたりしています。

若草幼稚園(東京都目黒区)

SDGsについて話し合う機会を積極的に設けています。例えば、茶道の時間に鮎の形のお菓子を食べながら、鮎はきれいな川にしか住めないことなどに触れ、川や海を汚さないためにできる具体的な対策を話し合い。また、年中組はSDGsの17の項目から興味のあるものを選択し、自分でできることを絵に描いてポスターを作って発表しました。


家でもチャレンジ SDGs

子どもは大人の行動をよく見ていて、私が園で作業に熱中していると一人また一人と集まってきます。まずは親御さんが、簡単なことからSDGsに取り組んでみてはいかがでしょうか。その姿を見た子どももきっと興味がわくはずです。たとえその時は関心がなくても、子どもはいつ興味のスイッチが入るか分からないので、“興味の種”を散りばめていきましょう。背伸びしすぎず、楽しみながら持続できることにチャレンジしてみてください。