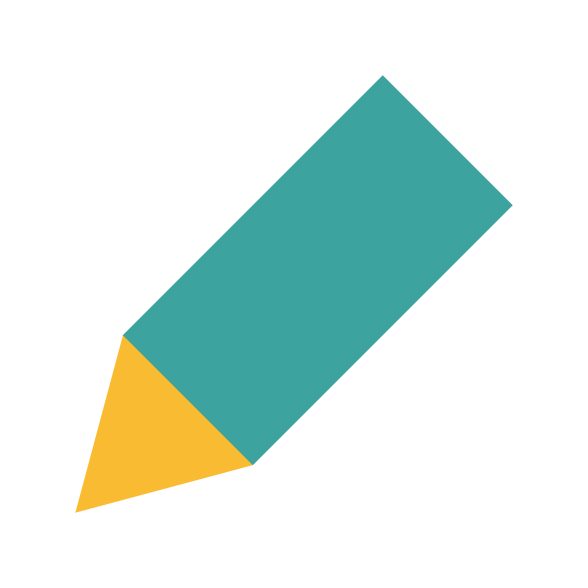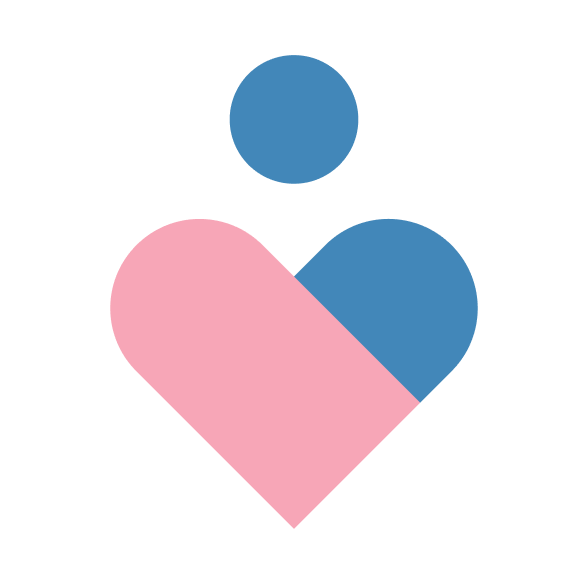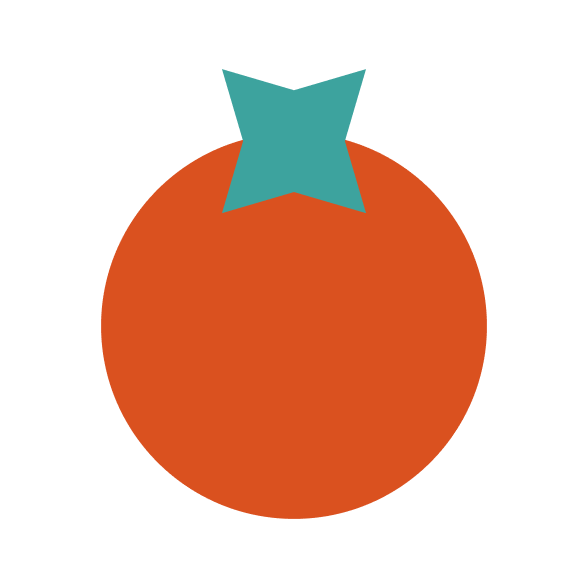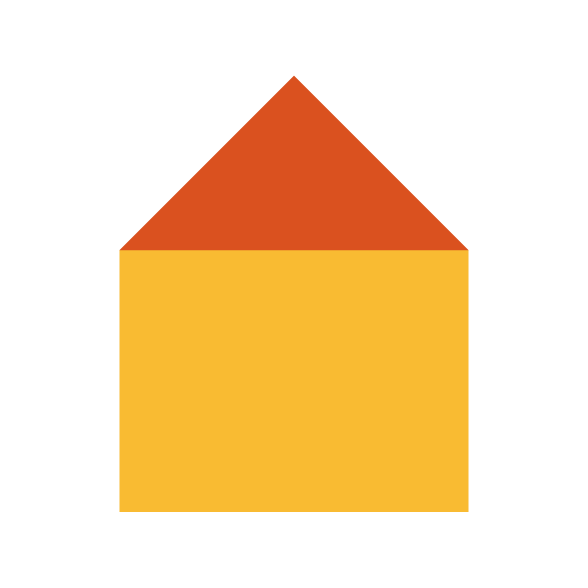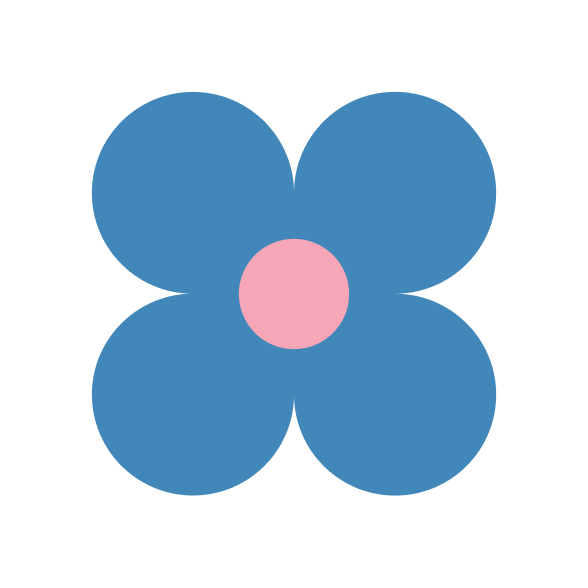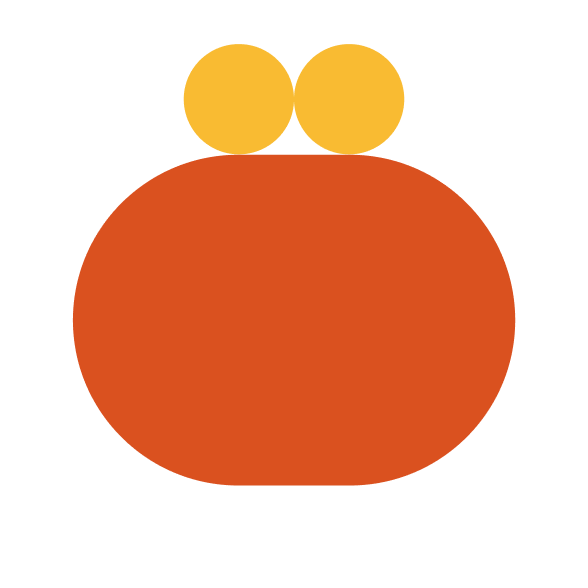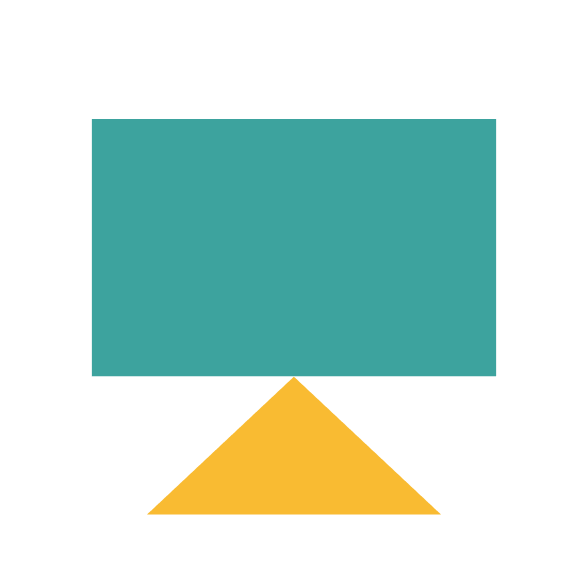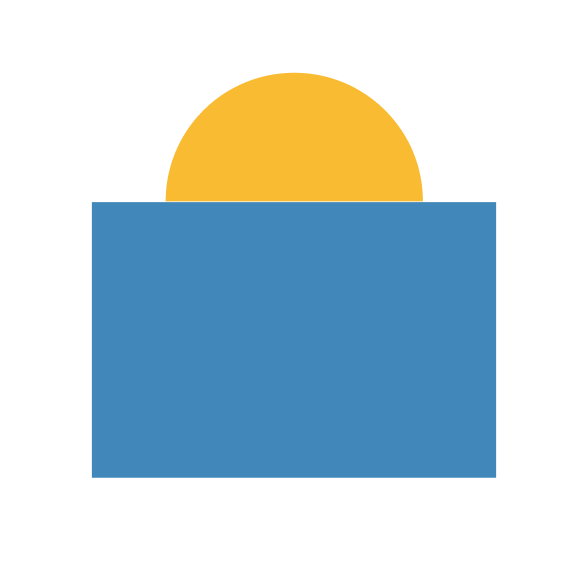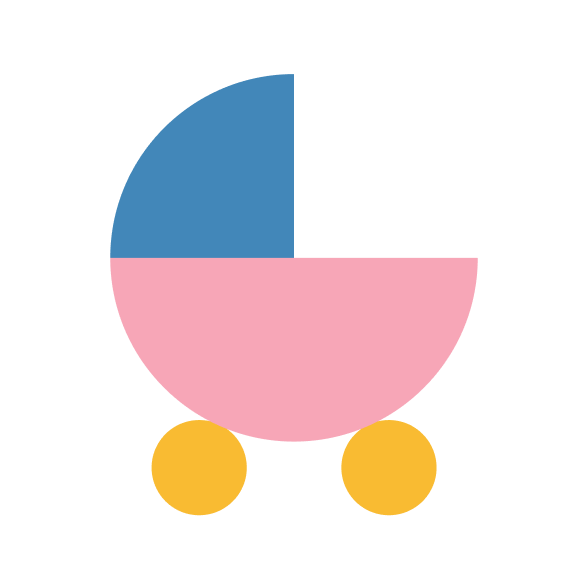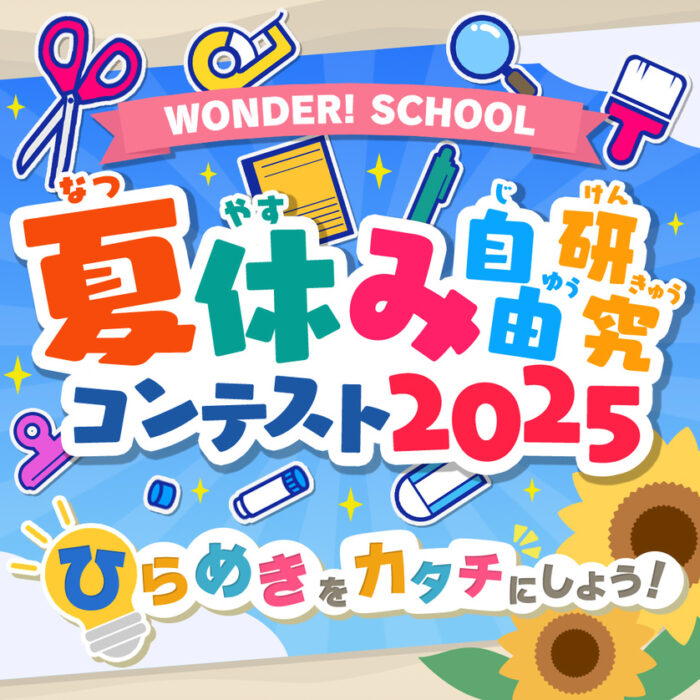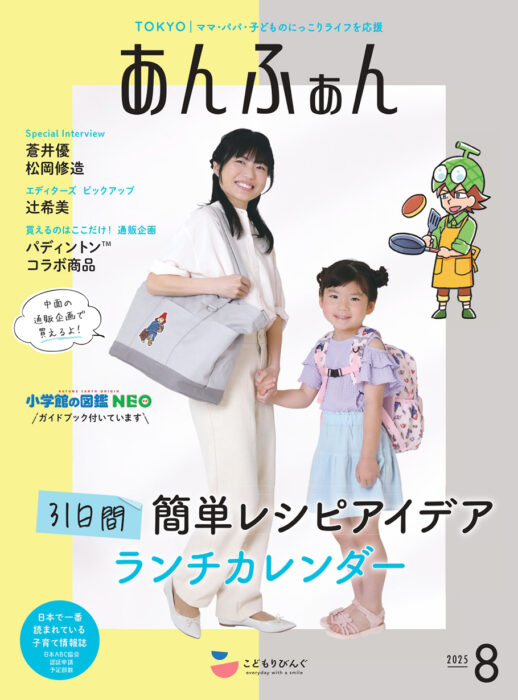更新 :
子どもの自尊心を傷つけていませんか?気をつけたいNGワード

今回は、最近よく耳にする「自尊心」について掘り下げてみたいと思います。
「自尊心」は自信をもって根気よく物事に取り組み、充実感のある人生を送るために、幼少期から必要だと言われています。それを知って、「わが子の自尊心を育てなければ」と思っても、具体的にどうしたらいいかわからないという人も多いのではないでしょうか。
そこで心理カウンセラーの立場から、自尊心の正体や育て方、そして気をつけたいNGワードについてご紹介します。

自尊心とは?
自尊心とは、突き詰めると「自分を好きだと思う気持ち(考え方)」のことです。自分で自分のことを好きだと思えるということは、自分はいろいろなことができる!と自信をもっているということでもありますし、自分に価値があると感じられるということでもあります。
欠点さえも自分の長所と捉えるのが自尊心
自尊心が低いと、自分の欠点は「悪いところ」としてだけ認識されます。もちろん欠点というのは、欠けているところという意味なので、多くは「悪いところ」と解釈されるでしょう。しかしそれは裏を返せば「個性」です。
この欠点は「自分の魅力で長所でもあるのだ」と考えられたり、この欠点があるから「自分のほかのいいところや他人の魅力が引き立つのだ」と思えたりすることで、「欠点があってもいいんだ」と自分を肯定的にとらえることができるのが「自尊心」です。
自尊心の高さの秘密は、目標の低さ!?
通常、自分の子どもを育てる時に、多くの親は「高い目標をもって、才能を伸ばし、よい人生を送ってほしい」と思うものです。しかし実際には、高い目標をもつことが才能を伸ばすことにつながるとは限りません。
例えばスポーツの大会で、幼い頃から全国大会1位というような好成績を狙っていても、それはなかなか達成できることではないでしょう。すると子どもは「自分は目標を達成できないダメな子だ」と自己評価をし、自尊心は低くなります。
反対に、まずは楽しめばよい、頑張るだけで充分!というような育ち方をしていると、どんな成績が出たとしても自分の評価には影響しませんし、むしろ楽しんでいたのだからよし!と自分を認めることができ、自尊心は高くなる傾向にあるのです。
落ち込みにくく、あきらめにくい性格を育むことが大切
幼少期に、たとえ失敗したとしても、とにかく頑張ったことがエライ、頑張ることのできる自分は素晴らしい!という価値観で生活をしていると、成長してどのような壁に直面したとしても、落ち込みにくく、あきらめにくい性格でいることができます。
結果的にさまざまな局面で、失敗をしても挫折することなく頑張り続けることができるので、根気よくものごとに取り組むことができ、成功率も自然と高くなります。
自尊心の高い子に育てるために気をつけたいNGワード
わが子を自尊心の高い子に育てるために、親が気をつけたいNGワードを挙げてみましょう。
何気なく口に出してしまいがちですが、多用すると子どもの自尊心が低くなりますので、日常的に自分が言っていないか見直してみるといいですね。
「1番になれなかったの?残念」
わが子に対して「よくできる」と評価している親が言いがちな言葉です。
子どもの頃にとても成績がよかった子が、思春期で挫折したり、大人になって自尊心が低くなったりすることがありますが、このような言葉が引き金になっていることも。
子どもは親から、「成績がよければ褒めるけれど、悪ければ悲しい顔をしたり、けなしたりする」というような扱いを受けることで、「1番になれない自分には価値がないのだ」と判断するようになります。
そこに至った本人の努力を褒めてあげることが大切
たとえ小さい頃に難しい問題が解けたり、小学校低学年で成績がよかったとしても、「それができたこと」自体を褒めるのではなく、そこに至った本人の努力を褒めてあげることが大切です。
「頑張ったから解けるようになったんだね!」「順位は関係なく、努力できたことがすごいんだよ」という言い方をすると、子どもは「次もまた頑張ろう」と思えますし、もし失敗したとしても「また頑張ればいいや」と考えられるようになります。
「〇〇ちゃんはできているんだから、あなたもやりなさい」
当然のことですが、わが子とよその子は別の人間です。同じわが子であっても、きょうだいもまた別の人間です。Aさんができることは、必ずBさんもできるということはないはずです。それなのに、「〇〇ちゃんができているから」「お兄ちゃんにできたのだから」ということを理由に「あなたもやりなさい」「あなたにはなぜできないの?」と言うことはNGです。
他者と自分との間に一線を引くことが重要
自尊心を高めるには、他者と自分との間に一線を引くことが重要です。「他人は他人、自分は自分、他人がどうであっても自分が自分の基準で頑張ればよい。他人にできることが自分にはできないのと同様、自分にできることが他人にはできないこともある」。
このような現実をしっかりと認識することで、自尊感情は高まります。反対に他者と自己とが同化していると、他人にできることが自分にできなければ劣等感を抱き、自分にできることは他人にとっては非常に簡単なことに過ぎないのだろうと物事を悲観するようになります。
「お友達はお友達、あなたはあなた」
子どもが「〇〇くんはゲームを持っているからボクもほしい」と言ったら、親は「よそはよそ、うちはうち」と言いたくなりますよね。
それと同じように、すべてのことに関して、「お友達はお友達、あなたはあなた」であることを教えてあげてほしいと思います。
「〇〇ちゃんができることを、あなたはできないかもしれないけど、あなたにはこんなことができる」と、大人の目線でわが子のできることを見つけ、「そうか、自分にはこんなことができるんだ!」という「発見」をさせてあげてください。
よい意味での「適当さ」をもつことが子どもの自尊心を高める

なんでもいい加減に考えるのは困りますが、よい意味での「適当さ」をもつことは、子どもが自尊心を高める過程で大切です。
幼児教室の成績からスポーツまで日常のさまざまなことについて、大人は高い目標を持ち、子どもに結果を求めてしまいがち。しかし、本当の意味での子どもの成功や前進を願うのならば、幼いうちに目覚ましい成績を残さなかったとしても、本人の興味や頑張りをできるだけ、ありのままに認めてあげることが大切です。
そのことが成長する過程で高い自尊心につながり、結果、人生のどんな局面でも自分を伸ばす努力を続ける人に成長していくことができるでしょう。