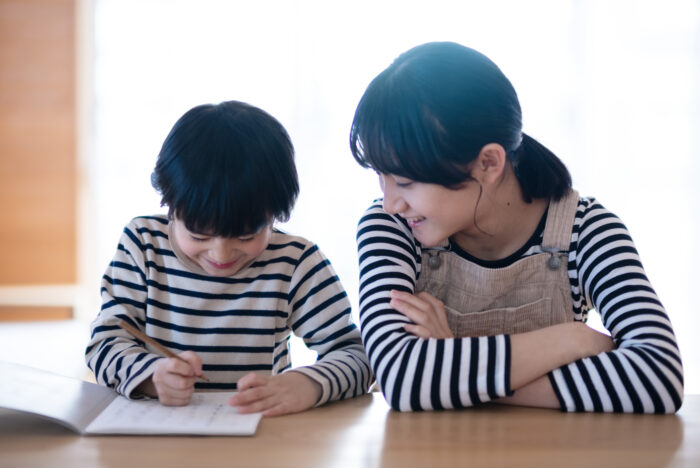算数は得意なのに、数学でつまずくのはなぜ? 小学生のうちに育てたい「考える力」

「算数は得意だったのに、中学に入って数学でつまずいた…」そんな声をよく耳にします。
実は、計算中心の「算数」と、論理的な思考力が求められる「数学」との間には、大きなギャップがあるのです。
このつまずきを防ぐカギは、小学生のうちから「考える力=数学的思考力」を育てることです。とくに、中学受験を検討しているご家庭では、小学校低学年から数学を意識した取り組みを始めることで、思考力や表現力を磨き、入試問題や将来の学びにもスムーズに対応できる力が育ちます。
今回は、低学年のうちから取り組める論理的思考力を育てるメリットや「好き」「おもしろい」をきっかけに始められる、学びのヒントをご紹介します。
「算数」と「数学」の違いとは?
小学校で学ぶ「算数」は、計算や図形の基本的なルールを学ぶことが中心ですが、中学校から始まる「数学」では、それらの知識を使って考えたり、説明したりする力が求められます。
つまり、答えが出せるだけではなく、どうしてそうなるのかを論理的に理解し、説明できる力が必要になるのです。
そのため、「算数は得意だったのに、数学でつまずく」というケースが起こりやすくなります。とくに文章題やグラフ、関数などは考え方の柔軟性が問われるため、早いうちから考えるトレーニングに触れておくことが重要になります。
小学生のうちに数学的思考力を育むには?
中学受験を検討しているご家庭はもちろん、そうでない場合でも、小学生のうちから「考える力」を育てることは、中学以降の学びをスムーズにする大きな支えになります。
たとえば、「この問題はなぜこの式で解けるのか?」「ほかの方法はある?」といった問いかけを日常的に取り入れたり、図や表を使って整理する習慣を身につけることが、将来の数学に直結する力となります。
最近では、小学生向けに数学的思考力を自然に育める教材も登場しており、中学数学の基本を中心として先取り学習ができる教材も増えています。こうした教材を活用することで、無理なく「算数から数学への橋渡し」ができる環境が整いつつあります。
小学生でも「数学」にふれられる時代「論理的思考がこれからの学びを支える」
「数学は中学生になってから学ぶもの」と思われてきましたが、最近では小学生のうちから数学的な考え方に触れられる教材が少しずつ増えています。
計算ができることだけでなく、「なぜ?」「どうしてそうなるのか?」と道筋を立てて考える力=論理的思考力の重要性が見直されていることが背景にあります。
こうした力は、算数や数学の学習にとどまらず、将来社会に出てからも必要となる「自分の頭で考える力」として、多くの場面で役立つものです。
最近では、子どもの興味や理解度に合わせて、学習が進められる教材も登場しており、「おもしろい!」「もっと知りたい!」という小さな成功体験が、思考力を育てるきっかけになっています。
昨今の“考える力”重視の流れを受けて、RISUでは小学生向けに新たな学びのステージとして「数学モード」を新設しました。
基礎はもちろんのこと、代数・図形・統計など、興味のある分野を選び、自分のペースで数学的思考力を育むことができる構成となっています。
RISUの「数学モード」について詳しくはこちらのサイトをご覧ください。
https://www.risu-japan.com/gakuryoku/mathematics.html
考える力を育てる「RISU数学」ならではの工夫
RISUの「数学モード」では、小学生でも無理なく数学的思考力を育めるよう、わかりやすい解説・興味を引き出す構成・論理的に考える仕組みを丁寧に設計しています。
楽しみながら論理的に考える力を育てるヒントとして、他の教材選びにも役立つポイントになりますのでぜひ参考にしてください。
小学生でも取り組める、やさしく丁寧な解説つき
中学数学で学ぶ「文字式」や「図形の証明」などは、保護者が説明するには難しいこともありますが、RISUの数学モードではすべての問題に小学生向けのわかりやすい解説を用意。自分の力で理解しながら進めることができます。
「論理的に考える力=数学的思考力」を育てる構成
単なる正解・不正解ではなく、「どうしてそうなるのか」「別の考え方はないか」を考えながら進めることで、論理的に考える力=数学的思考力が育まれていきます。将来の中学受験や数学学習においても土台となる力です。
「もっと知りたい!」を引き出す仕掛け
数学Basic・代数・幾何・統計といった分野を自由に選べる構成や、数学の偉人の紹介ムービーなど、子どもが「おもしろそう!」「自分でやってみたい!」と思える仕掛けが豊富。興味から入って、自分のペースで深めていけるのが魅力です。
このように、小学生のうちから“数学的思考力”にふれることで、「考える楽しさ」と「学ぶ意欲」が自然に育まれていきます。
次のセクションでは、小学生のうちに「数学」に触れておくことがもたらす3つのメリットをご紹介します。
実際に役立つ!小学生のうちに学ぶ「数学」先取りの3つのメリット
1. 中学数学への“つまずき”を防ぐ、スムーズな橋渡しに
2. 自分で考える“思考力”を鍛えるきっかけに
先取りの問題には、ただの計算ではなく「なぜこの解き方になるのか」を考える要素が含まれます。早いうちからこうした問題に触れることで、論理的に考える力=数学的思考力が自然と育っていきます。
3. 「もっと知りたい!」を引き出す、学びのモチベーションに
先取り学習では、子どもの興味や得意に合わせて代数・図形・統計などを選ぶことができるため、「図形が面白い!」「この先もやってみたい!」という前向きな気持ちが生まれます。この“楽しさ”の積み重ねが、学び続ける力につながります。
こうした考える力を育てる環境の中で、「これ知ってる!」「もっとやってみたい!」という声が出てきたら、それは学びへの好奇心が芽生えたサイン。
算数が好きなお子さんや、「もっと難しい問題にも挑戦したい」と思い始めたタイミングは、まさに数学的思考に一歩踏み出すチャンスと捉えるとよいでしょう。
論理的思考を育てることが、未来の学びを広げる力に
中学校で学ぶ「数学」では、ただ計算するのではなく、「なぜそうなるのか?」を自分で考え、説明する力=論理的思考力が求められます。
この力は数学に限らず、国語の記述問題や社会の因果関係の理解、さらには日常生活の中で自分の考えを整理する場面でも大いに役立ちます。
だからこそ、小学生のうちから「考えるっておもしろい!」という経験を重ねることが、将来の“つまずき”を防ぐ準備になります。とはいえ、難しい内容を無理に詰め込む必要はありません。大切なのは、お子さんの「やってみたい」という気持ちを出発点に、興味に合ったテーマで楽しく学ぶことです。
自分のペースで、学年にとらわれず論理的に考える力を育てていくことは、子どもたちの未来の選択肢を大きく広げるきっかけになります。
考えるって楽しい!と思える経験を、日常生活のなかから積み重ねていけるといいですね。
ナビゲーター
担当カテゴリー
学び・遊び・教育
算数教材「RISU」代表取締役 今木智隆
RISU Japan株式会社代表取締役。京都大学大学院エネルギー科学研究科修了後、ユーザー行動調査・デジタルマーケティング専門特化型コンサルティングファームの株式会社beBitに入社。金融、消費財、小売流通領域クライアント等にコンサルティングサービスを提供し、2012年より同社国内コンサルティングサービス統括責任者に就任。2014年、RISU Japan株式会社を設立。タブレットを利用した小学生の算数の学習教材で、延べ30億件のデータを収集し、より学習効果の高いカリキュラムや指導法を考案。国内はもちろん、シリコンバレーのハイレベルなアフタースクール等からも算数やAIの基礎を学びたいとオファーが殺到している。