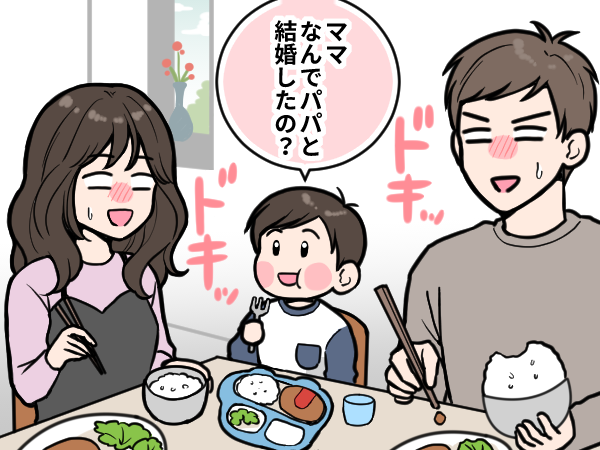「子どもが笑えば世界が笑う」と信じる大和田美帆さん、俳優と保育士の二択から生まれた子ども支援活動のストーリー

俳優として活躍する一方、今年の2月に「子どもが笑えば世界が笑うプロジェクト」を立ち上げ、「はじめのいっぽ」を踏み出した大和田美帆さん。支援活動をはじめたきっかけや、自身の子育てについて語ってもらいました。
「子どもが笑えば世界が笑うプロジェクト」立ち上げの原点は
子どもが大好きで保育士と演劇の二択となった本気の大学選び
もともと、子どもが大好きで、将来保育士になるか役者になるかの二択でした。大学も、保育科と演劇科を受験していて、あの時保育科だけが受かっていたら、今ごろ保育士になっていたんじゃないかなと。
ですが、見事に落ちまして(笑)。日大芸術学部に合格したので、その道に進み大好きな演劇に集中することに。そんな中でも、自分が卒園した保育園のボランティア活動をしたり、2015年の私の出産を機にどんどん子どもたちと関わる時間が増えていきました。
がんばりすぎない育児をさらけ出すことでみんなが集まってきた!
「子どもが笑えば世界が笑うプロジェクト」は、2025年2月に一般社団法人として立ち上げて、芸能活動とは完全に分けて、しっかりやっていこうと決意しました。子どもたち向けの音楽会「ミホステ」を主催したのも、自分が行って楽しい子ども向けのコンサートがなかったのがきっかけですね。子どもは楽しいけど親は寝ているみたいなのはイヤで、親も行きたくなるようなコンサートを、自分でやってしまおうと思ったんです。
10~15人くらいのお客さんで、小規模ではありますが、子どもも楽しい手遊びや、大人も楽しめるミュージカル、あとみんなで輪になって子育ての相談をしたりなど、ママ友感覚で身近に感じ「また今日から、子育てをがんばる!」と言ってくれるので私も励まされて、活動を続けています。
2015年に出産した自分の子どもに試して、喜んでいたものを披露したり、自分の子と同年代の子たちが遊びにきてくれたので、みなさんと一緒に子育てをしている感じも良かったですね。
出産前からやっていたブログは、同世代の方たちが読んでくれていたんですけど、同じように子育てをしていて、私のがんばりすぎない育児で、適当に楽しんでいることを発信すると「見ているだけで元気が出ます!」「楽しみにしています」という声をいただけて、みんなで一緒に歩んでいる感覚がうれしいんです。育児をしている3年間は舞台を減らしていたので、その間になにかやりたい、そこが原点ですね。
ばくみほ:父であり、俳優の大和田獏と大和田美帆が立ち上げたユニット
コロナ禍の2020年、母(岡江久美子さん)が亡くなってから、父と「奥さんを亡くすこと、母を亡くすことはとてもつらいけど、お子さんを亡くすってどんなにつらいだろう」と考えるようになり、いつかコロナが明けたら病院訪問などをして、紙芝居や朗読ができたらいいねと話していたら、引き寄せの法則じゃないですが、現在NPO法人の理事をされている、かつてお世話になったプロデューサーさんから、「入院中の子どもが大変な思いをしている、オンラインでミホステをやってもらえないか?」と2020年6月にオファーがあったんです。
まだそのころ、友人との連絡も躊躇する時期。そんな時に連絡をくださったので、ちょうどできたらいいねと話もしていたし、父も誘って「ばくみほ」として出演。それが原点ですね。合計4回、入院中の子どもたちに歌や朗読をオンラインでお届けしたのがきっかけ。もともと、私は障がいのある子どもたちとキャンプをしたりしていたんですけど、小児がんの子どもたちと会うのは初めて。調べてみるととにかく大変で、その後もっと詳しく、子どもホスピスのことを調べ始めて、現在は、横浜にある子どもホスピスさんのアンバサダーをするようになりました。
5/5開催、『こどわらフェス〜子どもが笑えば世界が笑う〜』について
イベント出演の方とのつながりやエピソード

5/5(祝・月)14:00-17:00に、東京都世田谷区「玉川区民会館せせらぎホール」で、「こどわらフェス」を初開催します。ゲストの渡辺えりさんは、今まで3度共演をさせていただいたことがあって、えりさんの歌声は魂が歌うような力強さと包み込むような優しさがあり、同時にばくみほをいつも応援してくれていたので出演をお願いしました。
あと、私は音楽療法士という資格を2019年に取得したのですが、その時同じクラスだったのが川越亮くん。彼は全盲なのですが、聞いた音をピアノで弾けるという特技が!今回は、私たちが出会った中で、素敵な人、思いのある人を知ってもらいたいというイベントなのです。
イベントのスペシャルダンサーかほちゃん&ももちゃんは、子どもホスピスで出会った子たち。治療法がない心臓病とたたかっているのですが、生きることをあきらめていない、だからこそ濃厚な時間を生きていているんです。私たちは彼女たちから学ぶことがたくさんあると思ってご紹介したいなと。二人とも若いのに、社会貢献がしたいと言うんです。今も緊急入院したり、体調が安定しない中でも、5/5の当日を目標にがんばると話してくれました。他にも、同じような思いを持った方たちとイベントがしたくて、子どもの笑顔を大切に思っている人だけでおこなうイベントです。
第一回目のイベントは、自分が生まれ育った等々力から
気心知れた仲間と、アットホームな雰囲気の中、当日までワクワク、楽しみです。これを機に福祉、チャリティーイベントがもっと身近なものになればいいなと思います。みなさん、患者さんの当事者にならないとわかりにくいのですが、明日当事者になる可能性があることをみんなで想像できたら。決して他人事ではないんですよね。
そう思えたら、もっと優しい世の中になるのかなと。自分もいつか老人になるし、障がいは明日にでも自分や周りの人に起こる可能性がある。もし自分だったら、と考える力が必要になってきます。まずは子どもの指針となる大人の私が、想像力を豊かに、多様性について考えて行動していく姿を見せられたらなと思います
みんな子どもが笑っていればいいと願っているはずなのに、どうやったらいいのか
「ばくみほ」の活動はわかりやすくて、病気や障がいのある子どもたちのところに行って、歌や朗読をするということなのですが、「ここから」というワークショップは、演劇のメソッドを使ったもので、心が開放されて想像力や発想力、コミュニケーション力が育まれるものですが、演劇という言葉が非日常的だからか、なかなか体験しないと想像しにくいワークショップなんです。
でも、世界で見ても、演劇の授業がないのは日本だけ。小学校から当たり前のように授業にあって、読解力や発想力、みんなでおこなうコミュニケーション能力とか、人間に必要な要素が含まれているんじゃないかと。ほとんどの先進国ではすでに取り入れられていて、きっと5年10年後、日本でも自己表現の習い事がある、なんてことになるのかなと思っています。プールやピアノのように、何級になったからよくできました!ということはありませんが、目に見えないものこそ大事だということも。
楽しみ方に正解はない!感じるままでいい
演劇は、舞台背景やセリフの意味を考えるだけでなく、他人を演じることで、他者の気持ちを想像して理解する気持ちが育まれます。誰にも会わずに遊べる今の時代、コミュニケーション力が落ちている懸念点を、演劇の力でサポートできると信じています。
こどわらフェスは誰でも参加できますか?
はい、車いすスペースもありますし、あと、できないものはやらなくていい、できることに参加をして楽しければいいなと思います。とにかく座っていなきゃいけない、静かにしなきゃいけないということはないんです。
プロジェクトの将来的な展望
福祉のイベントと言えば「ばくみほ」だよね!と言われるようになりたいですね。「ここから」も幼稚園や塾とのコラボという展開も見えてきています。自信を持って表現できる人が増えるように、オンラインも使って活動したいと思っています。
子どもホスピスって、日本に2つしかないんです。イギリスにはどの州にもあって、プロサッカーチームが協賛していたりするんです。日本はまだまだ子どもホスピス自体が知られていないので、まずは子どもホスピスとはなにか、ということをイベントを通して知ってほしいし、世田谷にもホスピスができたらいいですね。そのお手伝いをしたいです。
ご自身の子育てについて
娘は今9歳、個性的で自立していますね。私は、子育てのゴールだけ決めていて、それは自立をさせること。私なしで生きていける子にしたいというのが目標です。
私自身、母を亡くして感謝しているのが、母が亡くなっても生きる力は残っていたこと。悲しいけれど、泣き続けることはなかったし、前を向いて新しいことに出会い、実行に移せる力は両親がつけてくれたと思っています。社会が不安定で、どうやったらいいのかと、不安がっているのは大人だけ。それが子どもに伝わらないようにしたいなと思いました。不安だからこそ、子どもにレールを引きがちですが、子どもの生きていく力を信じて、少しずつ選択肢をあたえて、自分で決められる子に育って欲しいと願っています。
自己決定ができる環境というのは、幸せなことだと知ってほしいですね。何事も自分で選ばなかった人生を後悔している人や、親に言われた人生を歩いている人、誰かに言われて選んだ人生は、たとえ素敵でも本当の幸せと感じられないような気がします。
反抗期真っ最中!毎日ケンカから始まる
もう反抗期に入っておりまして、毎日のようにケンカをしてはハグして、大好き!って言いながら寝て、朝ケンカしての繰り返しですね。学力も大事ですが、人に愛される子に育ってくれればそれで十分です。
最近、私の背中を押してくれるような頼もしくもあり、まだまだ子どものところもたくさんありますから、引っ張ってしまいがちですが、振り返ったら私がいるという状態がベストですよね。娘が歩いている道の小石たちをどけてあげたい気持ちはありますが、そこはあえて転ばせるということが大事かな。
私は何の制約もなく育ち、少しさみしい思いをしていたのですが、今思えばあの自由な時間が、今の私を育てたと思っています。まあ、もっと勉強しなさいと言ってくれたら良かったのに、と思うこともありますが(笑)。
昨年、娘が1人でタイの冬キャンプに行きたいと言ってきたんです。私が仕事だから今年は行けないと伝えたら、「空港まで送ってくれればいい」と。私はすごく悩んで、行きたいという気持ちがそこまであるならと、行かせました。その時私はサポート役、どうやったら安全に行けるか、忘れ物はないかなど、完全な裏方に徹しました。子どもを手放すことの大変さがありますが、親から離れて行動するワクワク感も大切にして、育ってほしいと思います。
自己決定できるって幸せなこと
先日娘に、1000円でどうやって1日遊ぶか考えてごらんと言って、一緒に出かけました。いろいろ考えて、クレーンゲームもやりたい、100均で買いたいものもあると。もっと小さい時は先に全部使い切り、後悔していましたが、今回はちゃんとクレーンゲームは300円までとか予算を決めていましたね。
ひとつビックリしたのは、「ママこれ取れそうじゃない?」とクレーンゲームを私にやらないかと言って来たこと。お菓子がいっぱい取れるやつです。「ママなら取れるよ」の一言でその気になっちゃって(笑)。1回やってみなよと言われ、まんまとハマってやったんです。そしたら取れなくて、でも取れそうなんですよ。待って、両替してくると追加で払ってしまい、結局300円で取れたんですけど、子どもはお金を払わずにお菓子をゲットするというワザ。頭を使ってくるところも「やるなー」と思いました。他のもやったら?という誘いは断りましたけど。本当にちょっとした日常の自己決定ですね。その積み重ね。
未就学や小学生のお子さんを持つママ・パパへ
先輩ママさんからも聞いていましたが、ここまでの育児は本当にあっという間でした。先日、子どもの体操着の学年を替える時に、もう1年経った?早いな、と思いました。子育ての時間は有限なんです。だからこそ、私は「楽しんで喜んで、感謝して」を合言葉にしています。理想ではありますが、なんでも楽しんで喜んで、感謝して毎日過ごしたいなと思います。
もっとこうしておけばよかった、それは、やってもやってもそうなんでしょうけど、とにかく子育てができることに感謝しています。今まで「ばくみほ」で出会った子の中にはすでに亡くなってしまった子もいます。子どもとケンカできたり笑ったりハグできる当たり前のことに感謝なんです。こどわらフェスに来て、ささいな日常こそが大きな幸せなのだと感じてもらえたら嬉しいです。
小さい力でも集まれば大きな力になる!自分ができることから始めてみませんか?
企画:&あんふぁん編集部、取材・文:森岡陽子