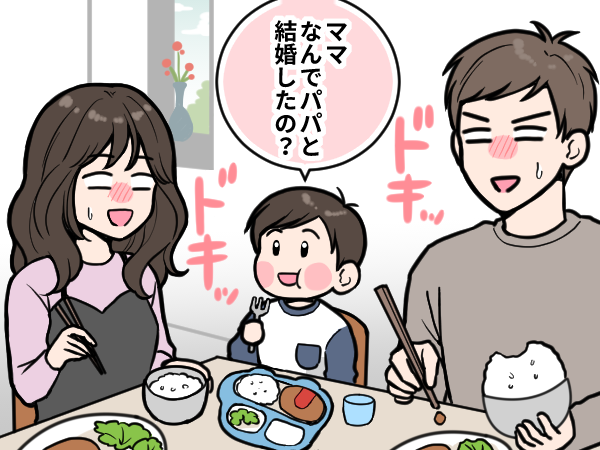中学受験の経験ママ対談②わが家の中受物語【塾選びの本当のところ・合格者の必勝技】

【中学受験連載】第9回/近年、都市近郊で増えてきている中学受験。「気になるけれど、実際どうなの?」「うちの子どうする?」未就学児〜小学生のママ・パパへ、焦ることなく、無知でもなく、「自分たちらしい選択ができるようになるための知識」をお届けします。
中学受験経験者の先輩ママの対談第2弾。リアルな体験から見えてくることもたくさんあると思いますので、ご家庭の選択の一つのご参考にされてください。
※内容はあくまでお二人の個人的な経験に基づくご意見です。
【前回の記事】中学受験の経験ママ対談①わが家の中受物語【やると決めた理由・通塾のリアル】
(お話を伺った方)
フルタイム勤務ママA(東京都在住)
兄:公立小学校→ ※中学受験なし/都立中学 →都立高校へ進学→大学生。
妹:公立小学校→ 私立女子中・高一貫校へ進学。※好きなことが学べる私学一択
フルタイム自営ママB(東京都在住)
姉:公立小学校→ 女子教育で有名な私立女子中・高一貫校へ進学。
弟:公立小学校→ 進学校として有名な私立共学中・高一貫校へ進学。

塾選びは、実際どう選んだ?早稲アカ・日能研・SAPIX・四谷大塚etc…
Bさん(以下B):うちは、四谷大塚に2人とも行ってました。 とりあえずSAPIXはハードル高く感じて、無理かもしれない、と。 噂で、「SAPIXは家で親が宿題を見なきゃいけない」とか、「 超難関校狙いだ」などと聞いていたので。 じゃあ早稲田アカデミーか四ツ谷大塚か日能研かな?と思って、 通える教室に見学に行ったんですけれど、四ツ谷大塚は、駅からの道のりも安全そうで、綺麗な校舎だったんですよ。なので四谷大塚に決めました(笑)。
塾帰りは夜遅く、学年にもよりますが、夜の8時半とか9時とかに。私は働いていたので、 家が近所の子と一緒に通って、そのお母さんと協力して当番制で送り迎えをしていました。それはすごく助かりました! 夕方に一度家に帰って、お弁当を作って持たせて、また家で続きの仕事を少しするという感じでしたね。6年生時は、 マックス週4で塾に通っていました。
また、うちはそれに加えて、2人とも塾の復習をするために、個別教室にも週1で通わせていたので、ダブルスクール! 本当にフル課金でしたね。
Aさん(以下A):うちのケースは相当変わっています。本格的に受験勉強を始めたのは、最後の1ヶ月くらい。受験年の12月20日から、家庭教師さんを個別指導でフルでつけまして。1ヶ月60万円しましたが、短期集中で課金しました。それ以前は、5年生の頃から、東大生の家庭教師をつけていて、週に1回国語と算数と社会の問題集を渡されて、何度も同じ問題集を解く、ということをしていました。なので、トータルでも2年間くらいの受験準備期間。
もともと、行きたい学校が1つに決まっていたので、その学校だけを狙って、それに必要な勉強に絞ってやったという感じなので、成立したことです。無理だったら公立に、と腹を決めていたので。
B:集団塾に行かず、家庭教師と個別だけを利用するという方法は、中学受験では珍しいですけれど、志望校が明確に絞れている場合はアリなのかも。
A:家庭教師は、子どもとの相性が最も大事だと思います。優しい先生がいいのか、厳しめの先生がいいのか、男の先生、女の先生がいいのか、など。
あとは、子どものやる気を継続させるために、志望校に足を運ぶ機会を作ることは、努力してやりました。私立中学は、年に何回か文化祭や体験授業など学校へ見学に行ける日を設けています。ネットで募集をするのですが、これが募集スタートと同時に席が埋まるほどの熾烈な争いなんです!
仕事の合間にも、ちゃんと応募タイミングを忘れないように気をつけていました。医者や教師の友達は、これができないと悩んでいましたね。模試の成績が落ちた時には、娘を希望学校の門まで連れて行って「あの制服を着て、ここに通うんだよ〜」と声をかけたりもしていました。
B:涙ぐましい努力! でも、本当に体験授業予約は、争奪戦ですよね。私も、ネット予約するのに苦労したことを思い出します。
塾については、学校の子が多く通っている塾だと、塾のクラス分けのヒエラルキーが、学校でも反映される、っていうのも聞きます。なので、うちはあえて少し離れた塾に通っていました。
A:電車の中で、大人の男性が「α(アルファクラス:塾のクラスのトップ)にいたアイツが、XXX企業に入ったよ」みたいな会話をしているのを聞いて、「この人たちは東京出身者で、大人になって就職しても、中学受験の頃の競争意識が、今だに続いているんだな〜」としみじみ思ったことはあります。それほど強烈な体験なんでしょうね。だからこそ、中学受験をネガティブな経験にしてしまうことは、親として避けるべきだなと思います。
志願校はどう選んだ?
B:最終的な成績によって、受けられる学校は自ずと絞られてくるので、あまり最初から決め込みすぎない方が良い気がします。特に「絶対に共学」などと絞っていると、意外と選択肢が少なく、偏差値が高い学校が多いので。
A:逆に、うちの子みたいに好きなことがはっきりしている場合は、早期に親がリサーチして決めてしまって、そこだけ受験をするのもアリだと思います。
塾選びから志望校選びまで、両極端なお二人の例ですが、どちらにしても保護者も様々な努力と実務が必要な中学受験の様子が垣間見えます。第3弾は、意外と知られていない受験当日のリアルや合否発表の現実などをお聞きします!