更新 :
【東京都】こどもの事故情報を“見える化”して事故を防ぐ!こどものために知っておきたい「こどもセーフティプロジェクト」とデータベースの活用法
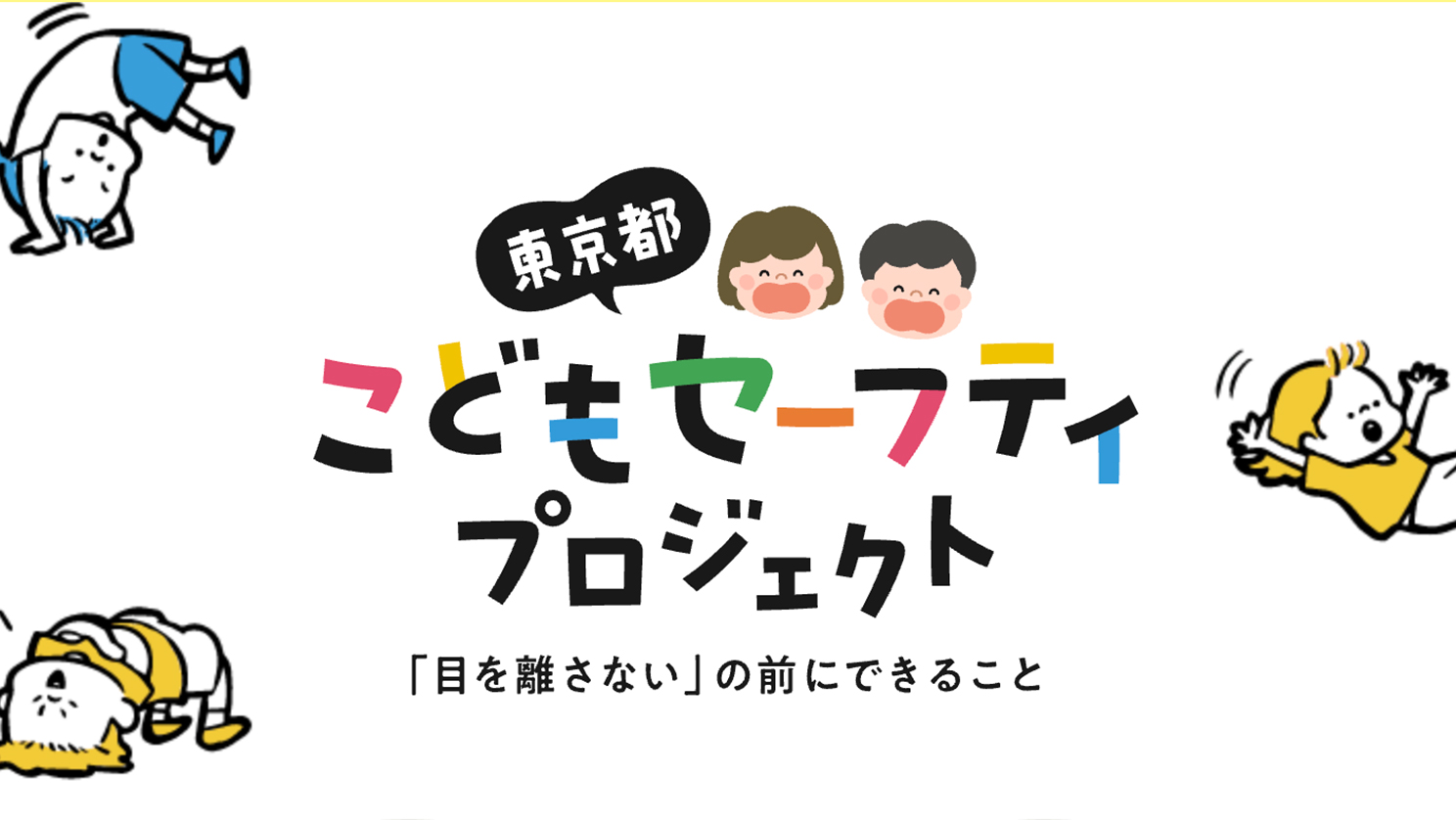
東京都では、こどもを事故から守り、思いきりチャレンジできる環境を整える「こどもセーフティプロジェクト」が進行中です。2025年3月には子どもの事故に関するオープンデータベースが開設されたほか、毎年1つのテーマを選んで事故予防策を深掘りする取り組みとして、「睡眠環境」における事故予防策が発表されました。
今回はこのプロジェクトに取り組んでいる、東京都 子供政策連携室 企画調整部 企画調整担当課長の添野宏さんにお話を聞きました。
こどもを事故から守る環境を整える「こどもセーフティプロジェクト」とは?
――東京都が進める「こどもセーフティプロジェクト」の取り組みについて教えてください
添野さん:日常の中でこどもの事故を防ごうとすると、こどもに危ないことをしてほしくないのが親心ですよね。だからこそ「危ないことはやめてね」と、こどもが「やりたい」という好奇心やチャレンジ精神に抑制をかける声かけをしてしまいがちだと思うんです。でもこどもたちの自然な成長や発達の段階を考えると、興味関心や好奇心を持ってチャレンジする姿が望ましい。
だからこそ、防げる事故は確実に防いで、こどもたちが安心してチャレンジできる社会を実現したいという目的で「こどもセーフティプロジェクト」は始まりました。
東京都内の子どもの事故で119番通報により救急車が駆けつけた件数というのは、実はずっと概ね横ばいなんです。親御さんは皆、神経を使いながら子育てをされていますけれど、事故は長年減っていないんですね。そして事故の種類別に見ても、転落や誤飲による窒息など、同じようなことが同じような件数でずっと起こっていてあまり変化がない。
そういうデータを検証した上で、やはり今まで通りの「見守る」「注意喚起」だけでは、事故の傾向は変わらないだろうと考えました。何か別のアプローチが必要なのではということからスタートし、「変えられるものは変える」という視点で安全な環境を整え、重篤な事故を食い止めるという理念で取り組んでいます。
――命に関わるような事故の起こりにくい環境を事前に整えるということですね
添野さん:はい。たとえば川遊びを例にすると、「川で溺れて死亡する」という事故を防ぎたい。でも川は自然のものなので、流れの速さや、水の量は人間ではコントロールできません。では変えられるものってなんだろう?と考えた時に、必ずライフジャケットを着用すれば、防げる事故がある。「こどもセーフティプロジェクト」は、このようなところにフォーカスして、保護者の方々に実践していただくための発信を行う事業なんです。
事故予防のサイクルを回すデータベースのプラットフォームを開設
――事故情報の検索データベースが開設されたり、睡眠中の事故防止策の取りまとめを発表されていますね
添野さん:はい。データベースを立ち上げた狙いは、大きく2つあります。まず1つ目はこども向けの製品・サービスの開発や改良を行っている事業者の方、保育事業者やこどもの事故予防に関する研究者の方などからのニーズがあったことです。また、保護者の方やこどもたちからも事故の情報を調べられるプラットフォームがあると良いという声もありました。
これまでは学校や保育所関連での事故はこども家庭庁、製品関係の事故であれば消費者庁といったように、それぞれの機関でそれぞれのデータベースが作られていました。そのデータを使いたい方々からすると、1カ所にまとまっていると便利ですよね。
もう1つは、ここで集めた情報を使って調査研究をし、事故の予防策をつくること。この予防策を多くの方に広報することで、「変えられるものを変える」視点を持つ方が増え、事故予防のサイクルを回していけるのではないかと考えました。
この2つの観点からデータベースを立ち上げて、ようやく2024年度末に公開ができました。
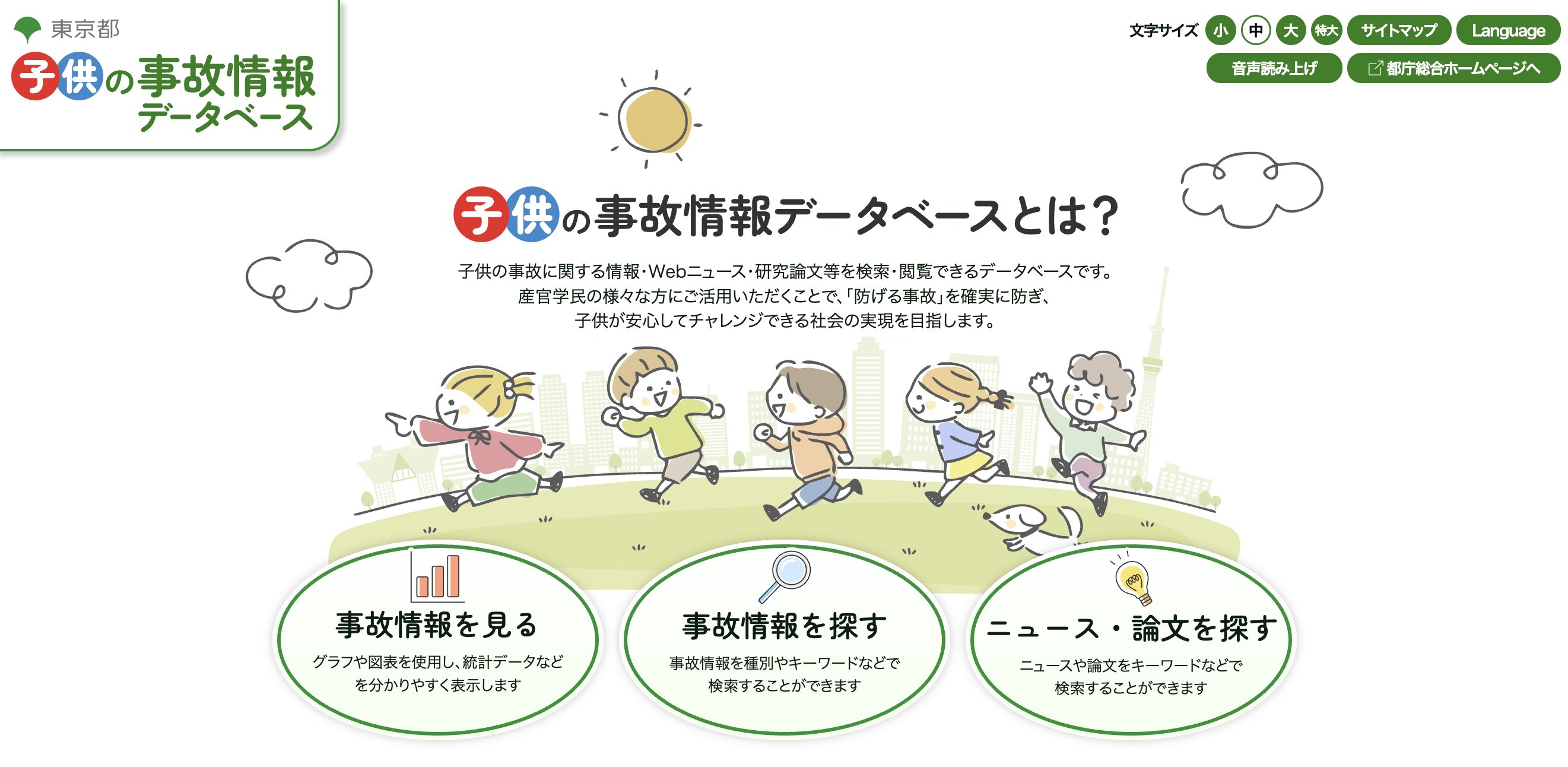
保護者にも事故予防策の参考にデータベースを活用してほしい!
――今後、このデータベースをどのように活用してほしいですか?
添野さん:やはり安全な製品がどんどん広まって、事故を減らしていくために企業の方や研究者の方に使ってほしいというのもありますが、実際にこどもたちと接している親御さんたちにぜひ活用していただきたいです。
データベースと聞くと、とっつきにくい印象を持たれると思うのですが、事故の種類別や年齢別などで検索できるので、お子さんの年齢だとどんな事故に遭いやすいのかな、どういうところに気をつけたら良いのかなというように、必要な情報のみをピックアップしてもらうことができるんです。
これからの暑い時季には熱中症が気になりますが、お子さんの年齢によっても気をつけるポイントが変わってきたりしますよね。それに夏休みなどで海や川に遊びに出かける前に、予備知識としてどんな事故に気をつければ良いのかを「海」や「川」などに絞って検索することができます。
また、こどもの事故を報道するネットニュースも簡単に調べていただくことができるので、手軽に活用していただけるのではないかと考えています。
例えばこどもの自転車事故などは警視庁でもデータが公開されていますが、「こどもセーフティプロジェクト」のサイトでは、何月ごろにどんな時間帯で事故が増えるのか、グラフを使って視覚的にわかりやすいように工夫しています。雨の時季である6月ごろや、日が短くなってくる秋頃、そして夕方の時間帯に事故が多いということをグラフから見て、感じ取っていただけるのではないでしょうか。
――キャンプに行く前に念のため検索してから行こう、というような使い方ができるということですね?
添野さん:そうですね。安全な製品が増えるだけでは事故は無くなりません。やはり使う方の意識にかかっている部分もあるので、ぜひデータベースを日常的に活用して事故予防の知識を深めていただきたいです。
“知らなかった”を回避する事故予防策が保護者向けのデジタルブックに
――データベースと同時期に、睡眠環境での事故予防策の取りまとめも発表されていますね
添野さん:1年に1つのテーマに着目して取りまとめをしています。2023年度は転落事故をテーマに、2024年度末には睡眠環境での事故をテーマにまとめました。
この取り組みでは実態をしっかりと調査した上で、エビデンスとともに予防策をお伝えしていくということを大事にしています。机上のデータだけで分析をするのではなくて、自分たちで実態を調査して情報を集めているんです。
例えば119番通報の情報だけだと、重篤な事態になったケースしか見えてこないので、ちょっとヒヤッとした、いわゆる「ヒヤリハット」について、保護者を対象にアンケート調査やインタビューなどを行い、情報を集めています。また大学の研究室と共同で、実際のお宅で調査をさせていただいて得た情報なども元にしています。
睡眠環境に着目した理由は、家庭や保育所などでも睡眠中の事故が後を立たないという点があります。どうしても睡眠中に起こる事故なので、保護者も寝ている時間帯に発生することが多いんですね。ということは、どんなことが原因で、こどもがどんな寝方をして、どんな動きをしていたか、現場を見ていた人がいないので分かりにくい。
そこで、実際の家庭でお子さんがどのような部屋で、どのような寝具で寝ているのか、また寝ている間にどのような動きをするのかというところまで調査しています。その調査結果を踏まえて予防策を取りまとめています。
――詳細な調査報告書のほかに、保護者でも読みやすいポケットブックも用意されていますね
添野さん:特にポケットブックは保護者の方に、こどもにどんな睡眠環境を整えてあげれば良いのか参考にしていただけると思います。例えば大人の寝具を使った場合の危険性についても記載しています。
こども向けの寝具は比較的固くできているので、万が一うつ伏せになっても窒息しにくい設計がされているのですが、ベビー布団を使っていても、その上に大人用の寝具を敷いてしまうと危険な環境になってしまうことがあるんです。実際に寝具の硬さを計測できる装置を使って、どのくらいの割合で危険な状況になっているかなども調査し、記載しました。
またこどもは寝ている間に15mも動くので、落ちないところに寝かせるとか、10cmの隙間でも挟まってしまうので、家具の配置を工夫するとか。知らずにいたり、良かれと思ってしたことが、かえってこどもを危険にさらしてしまう前に、悲しい事故を防ぐポイント集になっています。

「睡眠環境における事故」報告書(ポケットブック)はこちらから
保護者にこそ活用してほしいからホームページも随所に工夫
――「保護者に活用してほしい!」という思いはサイトの構成からもうかがえます
添野さん:保護者向けと事業者向けにページを分けたのは工夫したポイントです。事故を減らすという観点では、こどもに近い保護者の方に気をつけてほしいところと、事業者に知ってほしいところという点が違ってきますので。
また保護者の方が読みやすいように、専門的な内容であっても親しみやすいイラストを入れたりして気軽に読んでいただける雰囲気・デザインを大切にしています。
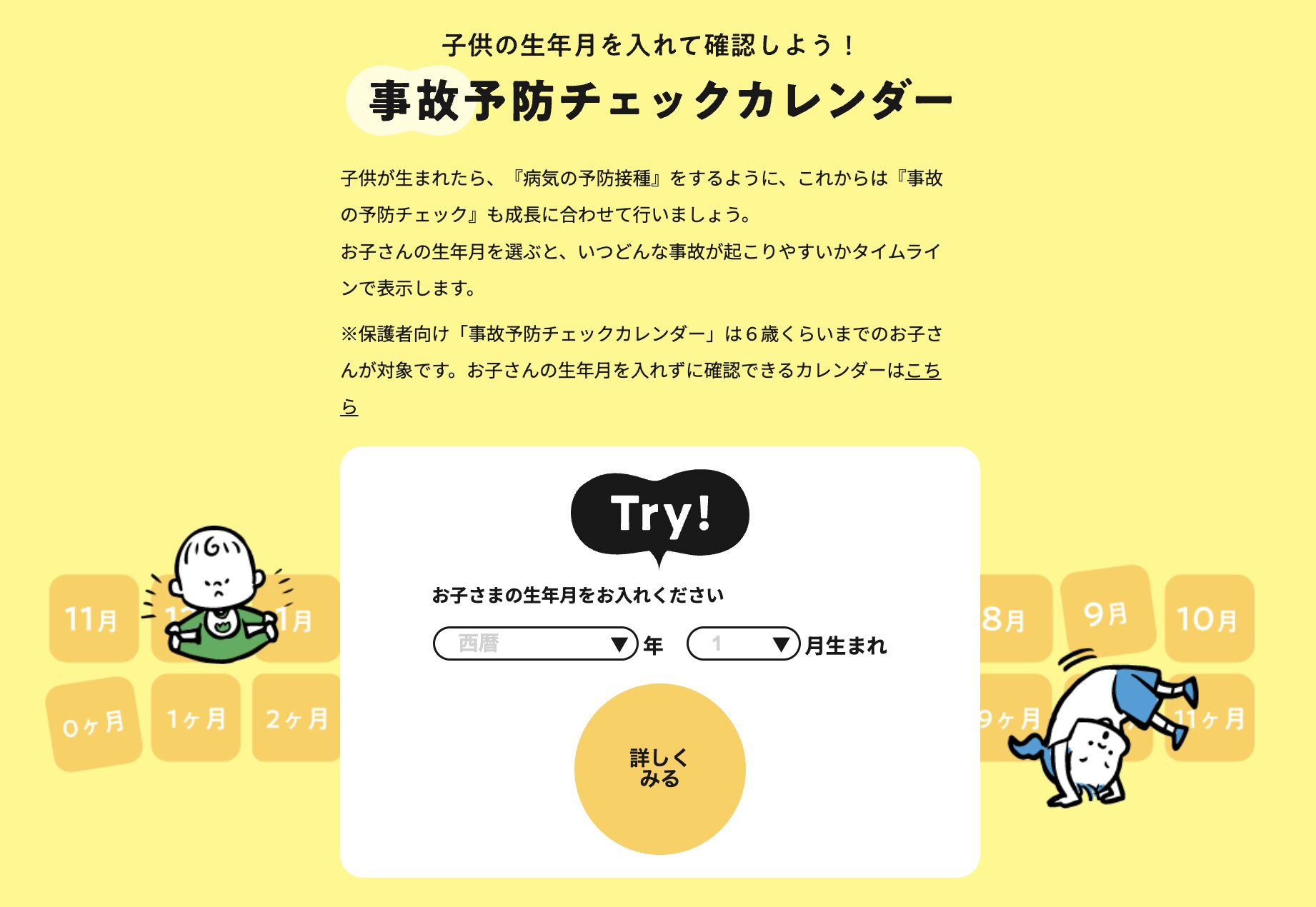
――より多くの方に知ってもらうために、広報の工夫などはされていますか?
添野さん:熱中症、水難事故など、季節性があるものはSNSや東京都のLINEアカウントを利用して、タイムリーに、なるべく切れ目なく発信するようにしています。
また、昨年度は都営地下鉄の駅に啓発用のポスターを掲示したのですが、この駅広告を見て「こどもセーフティプロジェクト」のサイトを知っていただいた方が、サイトで掲載しているデジタルブックをご自身の病院に置きたいと問い合わせをいただいたり、メールなどでも反響をいただいていて、とてもうれしく感じています。
――今後はどのような展望を考えていらっしゃいますか?
添野さん:保護者の方にデータベースをなるべく使いやすく、使い勝手を良くするために、今年度は利便性のバージョンアップをしようと動いています。より親しみやすい話し言葉でも検索できるように、AIの活用を検討しています。
また、たくさんの予防策を発信していきたいですね。書いてあることは当たり前のことかもしれないですが、「そんなことならやってみようかな」と思ってもらえるような“取り組むハードルの低い”予防策をどんどん発信して、なるべく実践していただけるとありがたいなと思っています。
まとめ
こどもの事故が起こらない未来を目指して、「こどもセーフティプロジェクト」のホームページは「知ってよかった!」と感じる事故予防策のヒントが目白押し。ぜひお子さんの成長とともに、事故予防の情報やヒントをチェックして、ご家庭の予防策をブラッシュアップしてみてくださいね。
企画・編集/&あんふぁん編集部、文/山田朋子



























