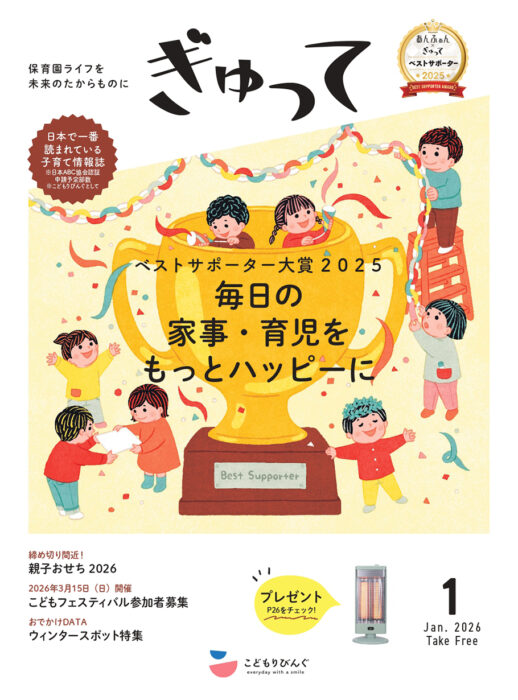更新 :
「すごい」「えらい」の多発はNG!見直したい日常のほめ方

「子どもの自己肯定感を高めましょう」と言われる昨今、ほめてわが子を伸ばそうと考えている保護者は多いことでしょう。しかし、ほめるという手法は使い方を間違えると、子どもの自己肯定感が低くなってしまったり、過度な反抗につながったりすることもあります。
今回は心理カウンセラーの立場から、実は難しい「ほめ方」について、効果的な方法を紹介します。
逆効果を招くこともある!NGなほめ方
まずは、NGなほめ方を確認してみましょう。以下に挙げるようなほめ方をしている場合、少しずつやり方を変えてみることを意識してください。
●「すごいね」「えらいね」が多発されている
ほめ言葉の代表格ともいえるものが、「すごいね」や「えらいね」といったものです。
「えらいね」は、お手伝いをしたときや、ルールを守ったとったとき。「すごいね」は、成績が良かったとき、スポーツなどで記録が出たとき、人に勝ったときなどに使われやすい言葉ではないでしょうか。
実際、3、4歳までの子どもには、「えらい、すごい」と連発したいことがよく起こります。成長がいちじるしく、少し前の自分と比べてもできることが増えているので、子ども自身もこの言葉を素直に受け止められます。ですから、小さいころのほめ方としては、「えらいね」「すごいね」でも問題はありません。ただ、これらは「何かができた」という、結果に対するほめ言葉になりやすいのも事実です。
成長に伴い、結果を残すことは徐々に難しくなってきます。やってもできないこと、チャレンジしても失敗してしまうことが増えてくるでしょう。10歳前後になると、結果に対するほめ言葉だけを受け取ってきた子どもは失敗する自分に価値を感じられず、心が折れてしまうことがあります。5、6歳を過ぎてからも。「すごい」「えらい」という言葉を多発しているようであれば、ひと工夫が必要です。
●「ほめる」が「おだてる」になっている
子どもが徐々に成長すると、大人のほめ言葉を「勉強してほしいから、ほめている」「手伝ってほしいから、ほめている」と深読みすることがあります。実際、ほめることで相手を動かそうと思っているなら図星ですし、そうでなくても子どもが勝手に、違った方向からの見方をするかもしれません。
こうなると、ママやパパが、自分をほめ言葉によってコントロールしようとしていると感じるため、かえって反抗する、暴言を吐くといった結果につながりやすいのです。
誰しも、自分をコントロールしようとする人に対しては反発します。親として、子どもをほめているのか、おだてているのかを、少し立ち止まって考えても良いのかもしれません。
子どもが素直になるほめ方のポイント

では、子どもが素直にほめ言葉を受け取り、子ども自身の糧にしていけるようなほめ方とは、どのようなほめ方なのでしょうか。効果的なほめ方のポイントを紹介します。
●「頑張ってえらかったね」「努力の結果だね、すごいね」に置き換える
「すごい」「えらい」と単純にほめていた幼児期を超えたら、ほめ言葉を「すごいね! 努力したんだね」「頑張ってえらかったね」とグレードアップさせてみましょう。これは結果そのものよりも、「頑張った」「努力した」という経過に焦点を当てたほめ方です。
注意したいのは、大人が努力をほめたつもりで「えらいね」と言っていたとしても、それを言葉にしなければ子どもは「結果をほめられた」と思ってしまう、ということ。わざわざそんなところまでと思うかもしれません。しかし子どもにとっては、将来的に結果を出せないときにも自分自身を認め、さらなる努力につなげられるようになるか、それとも結果を出せないことで落ち込み、自分を責めてしまうかの分かれ道となります。
●結果が出なかったときも、頑張っていた分だけほめる
誰もが、いつも良い結果を出せるとは限りません。結果が出なかったときも、子どもが努力をしていたのであれば「すごく頑張っていたの見てたよ」「全力出している姿がかっこいいと思ったよ」「頑張りは必ず力になっているよ。すごかったよ」とほめることで、子どもの肯定感は高められます。
ただし子どもが頑張っていない場合は、同じようにほめることはできません。たとえばわが家では、事前に頑張るよう指導していたにもかかわらず努力をせず、テストなどで結果が悪かったときは、「ちょっと頑張ったのはえらかったけど、足りなかったね」「ちゃんとやれば結果は出る。次までに頑張ろうね」と言います。頑張らずに結果が出せなかったときは、子ども自身が最もそれを感じていますから、生半可に褒めても、あるいは叱っても効果はありません。冷静に、努力が足りなかったことを自身で再確認してもらいます。
ただ、頑張りがゼロではなく、忙しい日々のなか子どもなりに頑張ったところはあったはずなので、全否定はしないことにしています。それまでの指導によっては努力のやり方がわかっていないこともあるため、結果を出せないときは原因を一緒に探り、頑張り方を模索することも大切です。
●「ありがとう」「助かったよ」はほめ言葉と心得る
子どもが家事を手伝ってくれたときなど、「えらかったね」ではなく「ありがとう」「助かったよ」という言葉を使うと、子どもは喜びます。“何かをしたからえらい”という概念ではなく、大切な人に感謝される喜びを感じられる言葉選びです。これらは厳密に言えば、ほめる言葉ではなく感謝の言葉ですが、子どもを伸ばしてくれる言葉という観点から見れば、ほめ言葉と同様に使えます。
またこれらの言葉は、大人が子どもに対して「私は、あなたに感謝しているよ」という「アイメッセージ(発言する人を主体としたメッセージ)」です。「(あなたが)えらいね」というほめ言葉は、時として「期待されているから、もっと頑張らなくちゃ」といったような意識で子どもを押しつぶしてしまうことがありますが、アイメッセージは子どもに喜びをあたえ、その喜びによって、即効性はなくとも、将来的には自然に人から感謝される行動をとったり、人に感謝できるようになったりすることが期待できます。
子どもへの共感と推察を大切に、素直な心を伝えましょう
ほめることによって子どもを伸ばそうと考えるのは、そもそも下心のあるほめ方なのかもしれません。ただ相手を賞賛したい、自分の心を伝えたいと思う気持ちがあれば、子どもにもそれが伝わっていくのかな、と感じることがあります。そして、子どもの自己肯定感を高めるのは、最後はそのような大人の、純粋な気持ちなのではないでしょうか。
幼児期、何ができてもすごいと感じられた小さなころ、きっとパパもママも子どもの「できた!」を純粋に、一緒に喜んでいましたよね。いつの間にか大きくなってしまって、生意気な!と思うことは増えたかもしれませんが、親子ともにいくつになっても、わが子の努力を推察する感受性と、日々を頑張るわが子に対する尊敬の気持ちをもちたいものです。
何かができたときに共に喜び、できてもできなくても日々の努力を認め、役に立つことをしたのなら、ありがとうって言ってくれるだけでいい…という気持ちは、大人も子どももずっと同じ。子どもを伸ばそう!と肩肘を張らなくても、純粋に寄り添い共感してもらえることが、子どもにとってもっとも心強く、そうして培った心の基盤が将来の役に立っていくのではないかと思います。