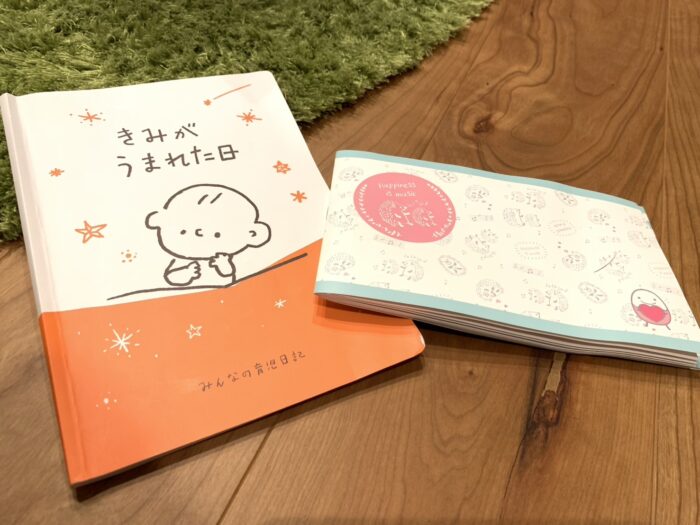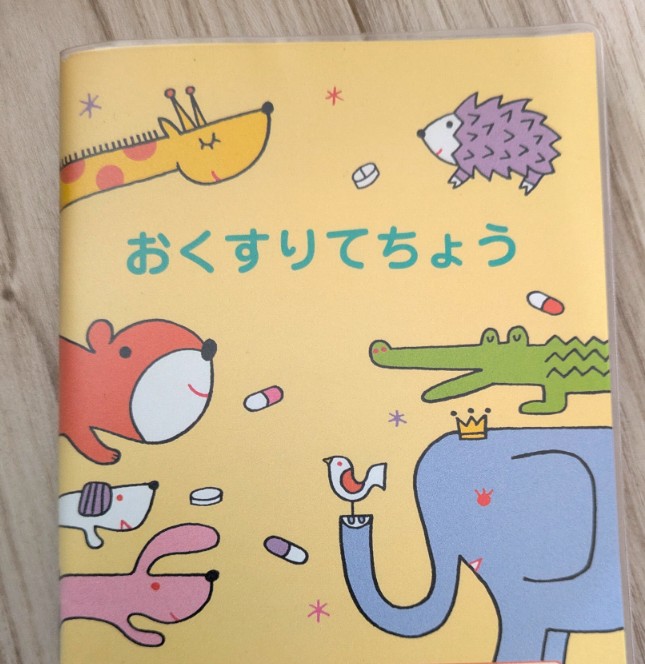公開 :
手洗いのタイミング合ってる?インフルエンザ流行期に見直したい感染予防の基本

子どもから感染症をもらって辛かった…という経験、みなさんはありますか?
子どもの看病中はどれだけ予防しても感染してしまうことはありますが、基本の手洗いを意識するだけでもリスクを減らすことができます。
すでに10月初めには全国的にインフルエンザの流行期に入り、ワクチン接種も始まりました。
私自身もこれを機に家庭での感染予防を見直してみようと思いました。
今回は、看護師である私が医療現場で実際に行われている手洗いのタイミングをもとに、家庭でも続けやすい形でご紹介します。
医療従事者の「手洗いのタイミング」は?
初めに、医療現場で実際に行われている手洗いについて少しご紹介します。
医療従事者は、WHO(世界保健機関)のガイドラインで定められた「手指衛生の5つのタイミング」に基づいて、手洗いや手指消毒を行い感染を予防しています。
「手指衛生の5つのタイミング」とは以下の通りです。
【1】患者に触れる前
【2】清潔・無菌操作の前
【3】体液に曝露された可能性のある場合
【4】患者に触れた後
【5】患者周辺の環境や物品に触れた後
家庭内感染を予防する手洗いのタイミング
「手指衛生の5つのタイミング」を、私なりに考えて育児中の家庭に置き換えてみると、次のようになりました。
【1】子どもに触れる前
→手に菌やウイルスがついたまま抱っこ・食事介助をしないように
例:外出から帰宅後、ミルクや食事の前、薬を飲ませる前、おむつ交換前など
【2】清潔な作業の前
→菌やウイルスを体内に入れない
例:鼻吸い器を使う前、目薬や軟膏を塗る前、傷などの処置前、食器を触る前など
【3】うんち・鼻水・嘔吐物など体液に触れた後
→自分への感染や家の中への広がりを防ぐ
例:おむつ交換後、鼻水を拭いた後、嘔吐物の処理後など
【4】子どもに触れた後
→自分や他の家族にうつさないために
例:熱がある子を抱っこした後、咳をしている子を看病した後など
【5】子どもの使ったものや周辺を触った後
→菌やウイルスが手に残るのを防ぐ
例:おもちゃ、食器、布団、ハイチェア、着替えた服などを触った後など
家庭ではできる範囲で手洗いを
医療現場では複数の患者さんに触れるため、あらゆる場面で手洗いは必須です。
しかし、家庭では触れる相手が限られますし、育児中のあらゆる場面で手洗いを行うのは現実的ではありませんよね。
手洗いと聞くと「とにかくこまめに!」というイメージがありますが、大切なのはタイミングだと思います。
たとえば、インフルエンザの予防なら「帰宅後」「食事前」「鼻水をかんだり咳を手で押さえた後」などのタイミングが重要です。
また、胃腸炎の子を看病中の場合は「おむつ交換や嘔吐物の処理後」の手洗いを徹底するだけでも感染を防ぐことにつながると思います。
感染リスクが高い場面を意識して手洗いする方が無理なく続けやすいと思いますし、「手洗い後に清潔な操作から始めて、汚れたら洗う」くらいを目安にしてみるとよいのではないでしょうか。
すぐに手洗いができないときに気をつけたいこと
外出中、育児や看病の最中など、手洗いをしたくても難しい場面は多いですよね。
どうしてもすぐに手が洗えない場合は、できるだけ自分の顔(特に目・鼻・口)を触らないように意識してみましょう。
菌やウイルスがついても、口や鼻などから入る前に洗い流せば感染を防ぐことにつながると思います。
また、アルコール消毒も併用すると便利です。
ただし、アルコールが効かないウイルス(ノロウイルスなど)もあるため、おむつ交換や鼻水・嘔吐物など体液に触れたときは、必ず石けんと流水で手洗いをしましょう。
子どもからの感染が辛いのは、パパ・ママが頑張っているから
子どもの看病が続くと、どうしても親の睡眠不足や疲労が蓄積して免疫力が下がり、家庭内感染を起こしやすくなります。
子どもより親のほうが重症化してしまうことがあるのも、看病疲れが原因の1つともいわれているようです。
自分自身もいたわりながら、できる範囲で感染予防を続けていくことが大切ですね。
家庭での手洗いは私も気が抜けがちですが、これからの季節に備えて手洗いのタイミングを家族で再確認していこうと思います。
家族みんなが健康に過ごせますように。
この記事を書いた人