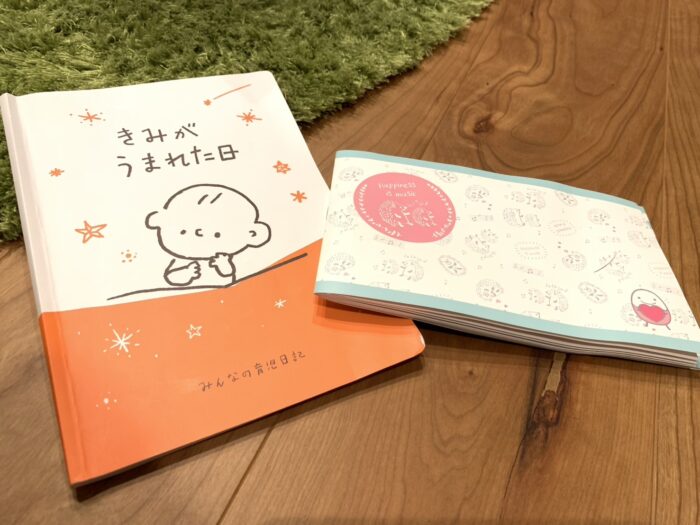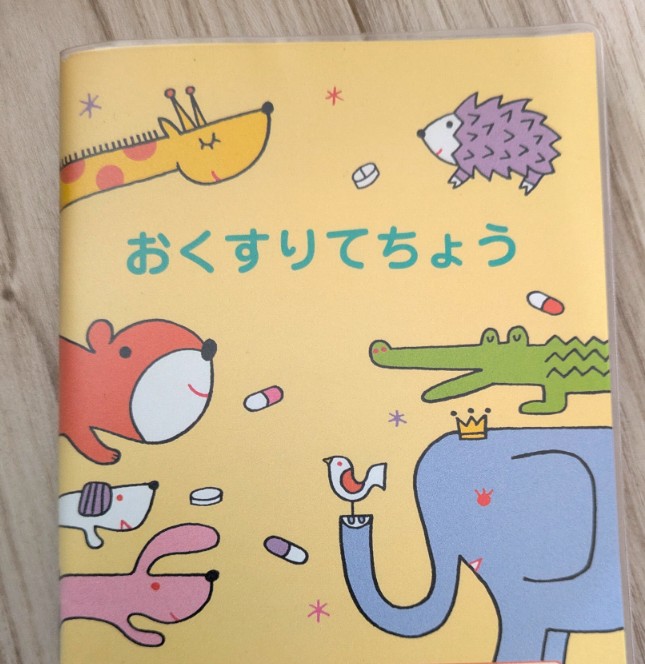公開 :
新入園・入学準備、持ち物以外のメンタルと習慣編

前回持ち物の準備について触れましたが、今回は持ち物以外の面を見ていきます。
子どもの心の準備
入園・入学を前にして、子どもの心は夢と希望と不安の入りまじった不安定な状態になっています。
少しでも安定した気持ちを抱かせるように子どもに接してください。
学校や園により、『慣らし』を実施していることもあります。
新しい環境に馴染むのが不安な場合、シミュレーションをしておくと、気持ちに余裕が出ます。
ただ実施していないことの方が多いので、その場合の気持ちや行動パターンの準備をしておくと、親子とも春からの環境変化によるストレスを軽減できるかもしれません。
今からできる準備を順番に見ていきましょう。

園や学校がどんなところか知っておく
幼稚園や保育園に入る子は、まだ話してもわからないかもしれませんが、たくさんのお友達や先生と、家では出来ない遊びや体験がたくさんできることを少しずつ伝えていくといいと思います。
小学校では、今まで以上に多くの友達や学年の子と関わること、基本的に学校には自分の足で行くこと、自分の行動に責任を持つことなど、今までと違う点を親子で把握しましょう。
説明の例としていくつか挙げると…
・大勢の友達と遊んだり、勉強したりして、楽しく過ごせるところ。
・優しい先生方、お兄さんお姉さんが親切にしてくれるところ。
・色々な勉強をして、たくさんのことがわかるようになるところ。
・友達と仲良く過ごすためのルールを知るところ。
などです。
さらに小学生になると子どもだけで外へ出る時間が多くなります。その時に向けての約束の確認や覚えておくことも最低限把握します。

あいさつ・返事
基本的なあいさつはできるようにします。
・「おはようございます」「こんにちは」「さようなら」などの挨拶をする。
・名前をよばれたら「はい」と返事をする。

身のまわりの始末
自分のことを自分でできるようにする
幼稚園の場合、入園時にまだトイレが1人でできない子もいますが、心配いりません。園の協力があれば大体夏休み前頃にできるようになる子がほとんどです。
中には家で出来ないのに園では1人でできるといった、外では頑張るけど家では甘える子もいます。あまり目くじら立てずに見守ってあげて欲しいです。後々トイトレの悩みが嘘のようにスムーズにできるようになるタイミングが来るので、大丈夫です。
その他大まかな項目としては…
・自分の身支度は自分でする。脱いだものはたたむ。
・トイレに一人で行く。
・手や顔を洗う、歯を磨く。
・次の日の準備をする習慣をつける
・持ち物を大事にし、使った物はきちんと片付ける。
・自分の物と他人の物との区別ができる。(ひらがなで記名の徹底)
食事の習慣
園や学校では、時間が決められていることがほとんどです。家では全部食べ終えるまで待っていたとしても、外では周りに足並みを揃えないといけません。お弁当や給食の時間が決まっていたら、その時間内で食べ切る習慣を意識付けすることは大切です。朝ギリギリでご飯を食べずに出るのもNGです。元気が出ませんしやる気も出なくなってしまいます。
・食事の前に手を洗う。
・20分位で食事をすませる。
・好き嫌いをなるべく減らす努力をする。
・箸を正しく使う。
・朝食は必ず食べる。
▶︎家族や自分のことを言える
近隣に一緒に登下校出来る子がいれば、早めに親同士の連絡先交換をし、お友達親子でお散歩や待ち合わせ場所・登下校練習をすると危険箇所を把握しやすいです。
中には近隣に登下校一緒になる子が居ない場合もあります。登下校で1人になる場面で何か緊急事態が起きた時に、自分の事を伝えられるかも大事です。
また、地域によっては【子ども110番の家】があります。【子ども110番の家】とは、(場所により【こども110番の家】の表記のこともあり)犯罪等の被害に遭い又は遭いそうになって助けを求めてきた子どもを保護し、警察への通報等を行う「子どもを守るボランティア活動」の一つです。「子ども110番の家」等の活動は、お子さんをお持ちの保護者や地域住民、事業者等の方々のご協力により、地域ぐるみで子どもを犯罪から守るための取り組みです。
何事もないのが1番ですが、万が一の時に助けを求めたり逃げられたりする場所があるのはとても心強いです。登下校の練習時に、そういった目印のステッカーの店舗や家があるかを把握しておくと良いですね。
それらを含めたチェックリストは
・自分の名前をはっきり言えるようにする。
・家族の名前、住所、電話番号を言える。
・「トイレに行きたい」「おなかが痛い」など、必要なことを自分で伝える。

登下校のルール
道路の歩き方を改めて教える。
横に広がってないか、信号をきちんと見ているか、信号と車の有無を再確認するなど。子どもだけで登下校すると、遊びながら・話に夢中になってルールを守れなくなることもあります。
・交通信号の見方がわかる。
・安全を確かめて、横断歩道を渡るようにする。
・通学路を覚えて、一人で学校までの登下校ができるように親子で練習しておく。
・知らない人に誘われても、ついていかない。
・防犯ブザーを使えるように練習する。
防犯ブザーは学校で支給されるもの、個人で用意するものとありますが、これは使い方(鳴らし方・止め方)が分かっていないと慌てます。特に間違えて引っ張ってしまい、止めたいのに止められなくて困ることも。これも止め方の練習をしたり、電池切れがないか確認したりする為にも、時々鳴らすことが必要です。
番外編
普段おうちの方がやっていて、1人でやったことがないことが意外と多く見落としがちな部分がたくさんあるんです。いくつか例を挙げると…
・雑巾の絞り方
・ひもの結び方(固結び・蝶結び)
・名札をつけるための安全ピンの使い方
・名札ホルダー・名札クリップの使い方
・長傘の開閉の仕方
・長傘の持ち方
・折りたたみ傘の開閉の仕方
・傘の水の切り方
どうでしょう?お子さまはできますか?そうやって書いているわが家は、まだ確認が必要な項目ばかりなんです…特に傘は扱い方によっては大怪我になることもあります。ワンタッチで開くものは、周りを気にして開いたり、急に開かないように手を添えたり、練習した方が良いものもあります。
そして学校に折りたたみ傘を置き傘にする場合は、この開閉も子どもには難しい事が多いので、出来るようになるまではレインコートで対応して、傘を持たせないという選択肢も候補に入れていいかもしれません。
また名札の安全ピンも針で、上手にできないとけがをすることが多いです。洋服の穴あきを防ぐのに名札ホルダーを使う場合も、使い方は教えておく必要があります。
親としては「それくらい出来るでしょ。」と思いがちな部分でも、子どもは意外に出来ない・知らない事が多くあります。当たり前と思わず、1つずつチェック・確認して新生活への準備をしたいです。
その他、園や学校により独特のルールがあることも多いので、入園入学後に調整も必要になります。柔軟に対応できるようにしましょう。
この記事を書いた人