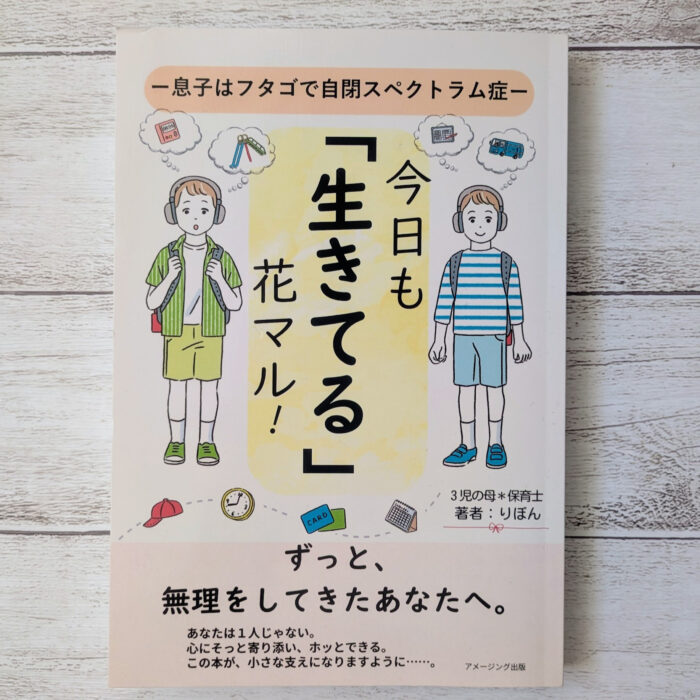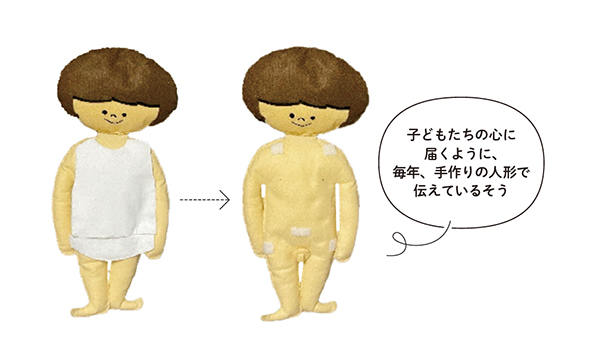「愛着障がい」ってなに?「愛着形成」に大切な“三つの基地”をやさしく解説【Part2】

近年「愛着障がい」という言葉が広く知られるようになりました。愛着に問題のある子の行動が、発達障がいの子どもの特徴とよく似ていることから「もしかしたらうちの子って、愛着障がいなんでしょうか?」、「愛着障がいにならないか心配です」という相談をいただくことがあります。今回は、「愛着形成」に関わる「三つの基地」について、スクールカウンセラー、発達凸凹コンサルタントの立場から、わかりやすくお伝えします。
関連記事:「愛着障がい」ってなに?発達障がいとの違いと「愛着形成」の基礎知識をやさしく解説【Part1】はこちら
愛着形成に大切な三つの基地
愛着とは、子どもの生涯にわたる心の土台となる重要なものです。しっかりと愛着が形成されるためには、「三つの基地」と呼ばれる大切な役割があります。
この「基地」とは、物理的な特定の場所ではなく、愛着を確固たるものにするための「心の拠点」と考えてもらえるとイメージしやすいです。今回は、愛着障がいを専門としている米澤好史教授の著書(※)を参考に、わかりやすく解説していきます。
※参考:「愛着障害は何歳からでも必ず修復できる」合同出版 著:米澤好史
それでは一つずつ説明します。
1.安心基地
三つの基地のなかでも、最も基本となるものです。
・落ち着く、ホッとする、楽しくなる、一緒にいたいと思える存在
・勇気を奪われない場所
など、「この人とならポジティブな感情が得られる」と感じられる安心の土台となるものです。
2.安全基地
・恐怖、不安、悲しみ、怒り、悔しさなどのネガティブな感情から守ってくれる
・危険に対して安全が得られる場所
怖いことが起きてもここにいたら「大丈夫」、辛い思いをしてもこの人のそばにいたら「大丈夫」と思える存在です。戻って休むことができ、エネルギーをためたり勇気がもらえる場所のことです。
3.探索基地
探索とは、探検や冒険と似たイメージです。
・基地から離れて経験したことを、報告したい場所
・経験で生まれたポジティブな感情を増やしネガティブな感情を減らしてくれる存在
これは、ベースキャンプに例えるとわかりやすいです。ベースキャンプはずっと留まっているわけではありませんよね。基地をもとに周辺を探索して、寝る時になったら帰ってくる場所です。探索基地も同じように、ここを出発点として外の世界に探索に行き、危ないことが起きたときには「逃げろ〜」と、また戻ってくる場所になるのです。
また、ただ戻ってくるだけではなく「今ね、すごく危ないことが起きて怖かったから帰ってきたんだよ」と話を聞いてもらえる場所でもあります。自分の経験したことに、共感してもらえると心には安心が生まれますよね。「大丈夫なんだ」と安心を感じるからこそ「もう一度、行ってくるね」という次の行動が生まれ、少しずつ世界を広げていくことができます。
このように、「三つの基地」とは子どもにとっての「出発点」であり「戻ってくる場所」という、大切な役割を担っています。
三つの基地が育つ順番
紹介した三つの基地には育つ順番があります。いきなり探索基地ができるわけではありません。
・最初は、「ここにいるとホッとするな〜」と感じられる安心基地
・次にできるのは、「ここにいると守ってもらえる」と感じる安全基地
・最後に、「ちょっと外に出てみよう、そして話を聞いてもらいたいな」と感じる探索基地
という順になります。「安心→安全→探索」と、覚えてもらえたらうれしいです。
この三つの基地がうまく機能していると、子どもは安心して外の世界と関わり、自信や自己肯定感を育てていけるようになります。
愛着形成の三大特徴ポイント
子どもの行動に「あれ?」と感じたり、「三つの基地が機能しているかな」と感じる時は、次に挙げるポイントを確認します。
・愛情欲求行動があったときは、安心基地を確かめる
例:赤ちゃん返りのような行動
・自己防衛があったら、安全基地を確かめる
例:自分を守るために嘘をつく、他害をする
・自己評価の低さがあったら、探索基地を確かめる
例:「どうせ自分なんて」という言葉が出てきたとき
子どもの置かれている環境や、ストレスによって求められる基地は変わってきます。子どもの行動に揺らぎがあったとき、焦らずに三つの基地の機能を思い出しながらゆっくりと向き合う時間が持てたら素敵ですよね。
愛着形成 自分に当てはめチェックリスト
大人にとっても愛着形成は大切です。自分自身のことも、チェックリストをもとに振り返ってもらえたらうれしいです。
- 「一緒にいたい、ホッとする」と思える人はいますか
- その人は、あなたを不安や悲しみから守ってくれますか
- その人は、あなたの挑戦を応援して、一緒に喜んだり、悲しみを減らしてくれますか
きっと、思い浮かべる顔があったと思います。それは、これまでにきちんと愛着を育む相手がいたという何よりの証拠ですよね。
それと同時に、「子どもにとって“基地”のような存在になるためにはどうしたらいいか」という考えも浮かんできますよね。そんな時は、自分のこれまでの経験を深掘りしてみるとヒントが見つかるかもしれません。
ここまで、愛着障がいや愛着形成について2回にわたってお伝えしました。特定の誰かとの関わりによって育まれた「愛着」には、いくつかのタイプがあるといわれています。このタイプを知っておくと、子どもの困りごとを理解したり、関わり方のヒントにもつながります。
次回は、その愛着の4つのタイプについて詳しくご紹介します。
ナビゲーター
担当カテゴリー
子どもの健康・発達
公認心理師・スクールカウンセラー・発達凸凹支援コンサルタント 西木 めい
大学教育学部(特別教育専攻)卒業。小学校の通常学級の担任を8年、特別支援学校(小学部) の担任を5年、自治体の就学支援委員会(就学相談)の調査員、特別支援教育コーディネーターを経験。
「優秀な同僚の先生たちが、保護者と揉めて心を病んで、どんどん学校を辞めていく現状」を見て、専門職であるスクールカウンセラーになることを決意。現在は、小学校と中学校のスクールカウンセラーとして、親子や先生のカウンセリング、学校内の環境調整のコンサルティング、不登校や登校しぶりの再登校のサポートなどを行う。
一方で、SNSを通じた「発達凸凹支援コンサルタント」として、これまで2300人以上のママ・パパ、先生のお悩み解決コンサルを行いながら、発達凸凹っ子のママや、子どもの不登校・登校しぶりに悩むママに向けたオンライン講座、小学校の保護者100名以上が集まる子育て講演会などを開催。特別支援教育が「教育の一番の根本」であることを啓発している。2児の母。著書に『発達障害のある子を支える担任と保護者の連携ガイド 』(明治図書)がある。