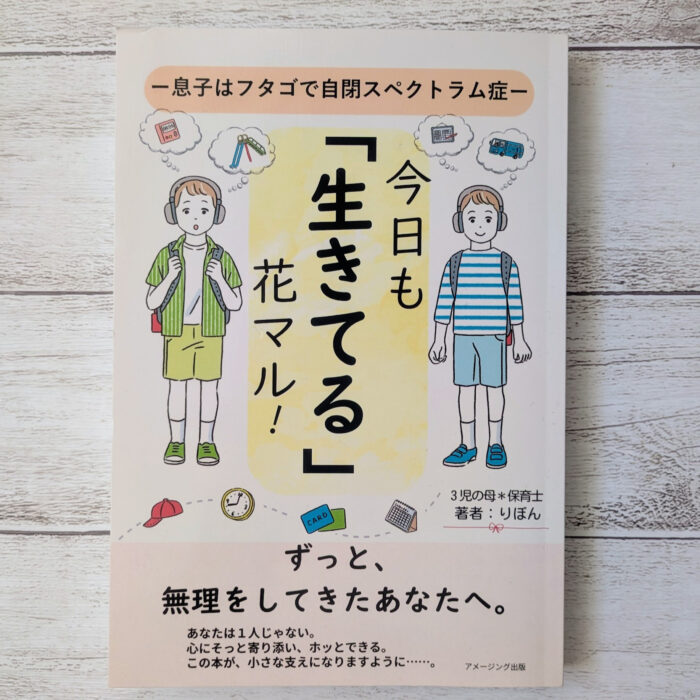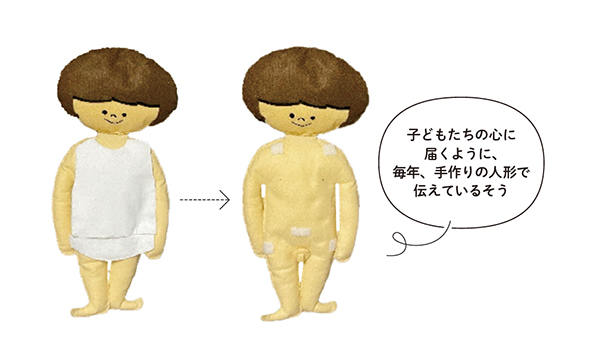園や学校の先生に質問したいとき、どうする?誤解を与えない上手な伝え方のコツ

園や学校の対応にモヤモヤしたとき、「質問したいけれど、モンペ(モンスターペアレント)と思われたくない」と悩む方が多くいます。今回は、スクールカウンセラー、発達凸凹コンサルタントの立場から、先生に誤解を与えず問い合わせるコツをお伝えします。
こんなときどうする?
ある日、園から配信された集合写真にわが子が写っていなかったらどうしますか?「あれ、この日は登園したのに?」「先生は気づけなかったの?」と心がザワザワしてしまうかもしれません。実はこれ、わが家に起こった実際のエピソードです。
園の先生に問い合わせをしたいけれど、モンスターペアレントだと思われたくないし、聞くことで先生を責めるような空気も作りたくない!でも、わが子のいない写真を買うわけにもいかず、モヤモヤを抱えたまま過ごすのも嫌ですよね。
「どうやって先生に問い合わせをしようか」と、思わず悩んでしまうような内容を伝えるときのポイントをまとめました。
ゴールを設定しよう!
モヤモヤした思いをそのまま先生にぶつけたり、やみくもに尋ねるのはオススメしません。なぜなら、納得できるような答えが返ってこなかった場合、さらにモヤモヤが溜まってしまうからです。
問い合わせをするときに意識したいことは、質問を経て「自分がどうなっていたいか」というゴールを設定することです。
例えば、先ほどのわが家のケースをもとに「どうなっていたいか」のアイデアをいくつか出してみます。
・「どうして写っていないか」という疑問が解消すればOK
・先生からの謝罪がほしい
・わが子も参加している写真に差し替えてほしい
・全体に配信しなくてもいいので、わが子もいる写真が見たい
など、いくつかのゴールが考えられると思います。
さらに突き詰めて、先生や園とどのような関係でいたいかも考えられるとよいですね。
問い合わせのポイントを3つ決める
実際に問い合わせをするときは、あらかじめ気をつけたいポイントを3つ決めるとスムーズです。話がまとまり、相手にも伝わりやすくなりますよ。
どんなポイントがよいかは、状況によって異なります。例えば、次のようなアイデアを参考に、合うものを考えてもらえたらうれしいです。
- 気をつけたいこと(語気が強くならない、笑顔で話すなど)
- 伝えたいこと(いつもの感謝を伝える、心配しがちな自分の性格のことをあらかじめ伝える)
- 聞きたいこと(理由が知りたい、代わりの対応がしてもらえるかなど)
- 提案したいこと(一緒に解決方法を探したい、連携を取りたいなど)
3つのポイントを決めるときは、自分がめざすゴールとつながっているかを意識するとよいですよ。
問い合わせの文章作り
電話で問い合わせる場合でも、お手紙や連絡帳で問い合わせる場合でも、あらかじめ文章を考えておくと、先生に伝える緊張感が少し和らぎますよね。
ここでは「わが子が集合写真にいなかった!」という例をもとに、ゴールと3つのポイントを意識した問い合わせの文章を考えてみます。
設定したいゴール
また会うとき、お互いが笑顔で話せる
ポイント
- 理由を明確に聞きたい
- 「心配している」ということをわかってほしい
- 客観視して、先手を打つ
上記の内容で、連絡帳に書く文章を作りました。
例文
園だよりを拝見しました。
いつも丁寧に伝えてくださり、ありがとうございます。
集合写真に、娘だけ姿が見当たりませんでした。
どこかでクールダウンをしていたタイミングなどでしょうか。
普段の集合写真では、お休みの子も枠外で掲載されていたので、娘はどうしたのだろうと心配になりました。
少しシンプルな文章ですが、伝えたい3つのポイントはきちんと盛り込んでいます。
例文の解説
文章のどこに、3つのポイントが込められているか少し詳しく説明します。
・理由を明確に聞きたい
「集合写真に、娘だけ姿が見当たりませんでした。」と、短く事実だけを伝え、先生を責める文章にならないようにしています。
・「心配している」ということをわかってほしい
「娘はどうしたのだろうと心配になりました」と、わが子のことが心配だという思いがあることもシンプルに伝えています。
・客観視して、先手を打つ
今回の文に、先手は2か所盛り込みました。一つ目は、冒頭の「いつも丁寧に伝えてくださり、ありがとうございます」という言葉です。この一手間は省略せず、きちんと伝えることが大切です。
そしてもう一つは「どこかでクールダウンをしていたタイミングなどでしょうか」と、わが子の行動を想像して、先手を打つ言葉です。
「わが子が写ってないのは、先生のミスですか?」と責めるのではなく「もしかして、うちの子が…」と、客観的に伝えるように意識しました。
実は…後日談
先ほどの例文を園の連絡アプリで送ってみたところ、その日のうちに先生からお返事がきました。実は、最初に配信された写真は、わが子が撮影していた写真だったのです。最初の集合写真を拒否したので、先生と一緒にみんなを撮る役目を担当し、その後みんなと一緒に集合写真を撮ることができたそうです。
先生からは、配信する写真を間違えたことの謝罪と、わが子も写っている写真への差し替え、そして今後は間違いがないように気をつけたいというとても丁寧なお返事をいただきました。
先生から真相を聞くことができ、わが子のいる写真も見ることができてホッとするとともに、「この写真をうちの子が撮っていたのか」と、わが子が写っていない写真に対する思いに変化が生まれました。
自分に返してみる
「園や学校の対応にモヤモヤする」というときは、なぜそう感じるのか、どこにショックを受けているのか、自分の過去の痛みを振り返ることも大切です。そうすることで、自分が大切にしたいことに気づいたり、過去の自分が今の不安を生み出していると気づいたり、自己理解につながります。
自分を落ち着いて見直すことができると、相手に何かを伝えるときにも、少し冷静になれるでしょう。先生に何か問い合わせるときには、今回お伝えしたコツを思い出していただけるとうれしいです。
ナビゲーター
担当カテゴリー
子どもの健康・発達
公認心理師・スクールカウンセラー・発達凸凹支援コンサルタント 西木 めい
大学教育学部(特別教育専攻)卒業。小学校の通常学級の担任を8年、特別支援学校(小学部) の担任を5年、自治体の就学支援委員会(就学相談)の調査員、特別支援教育コーディネーターを経験。
「優秀な同僚の先生たちが、保護者と揉めて心を病んで、どんどん学校を辞めていく現状」を見て、専門職であるスクールカウンセラーになることを決意。現在は、小学校と中学校のスクールカウンセラーとして、親子や先生のカウンセリング、学校内の環境調整のコンサルティング、不登校や登校しぶりの再登校のサポートなどを行う。
一方で、SNSを通じた「発達凸凹支援コンサルタント」として、これまで2300人以上のママ・パパ、先生のお悩み解決コンサルを行いながら、発達凸凹っ子のママや、子どもの不登校・登校しぶりに悩むママに向けたオンライン講座、小学校の保護者100名以上が集まる子育て講演会などを開催。特別支援教育が「教育の一番の根本」であることを啓発している。2児の母。著書に『発達障害のある子を支える担任と保護者の連携ガイド 』(明治図書)がある。