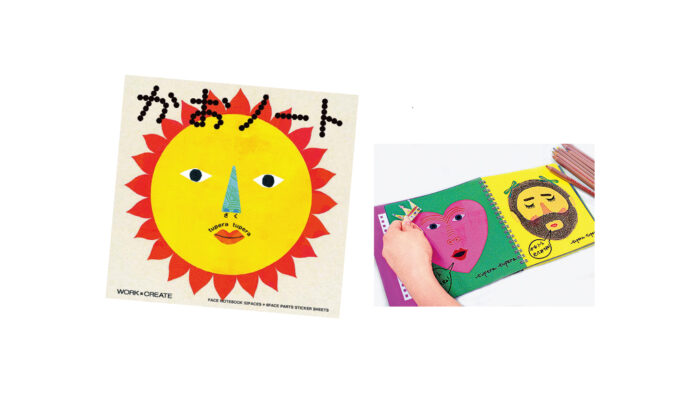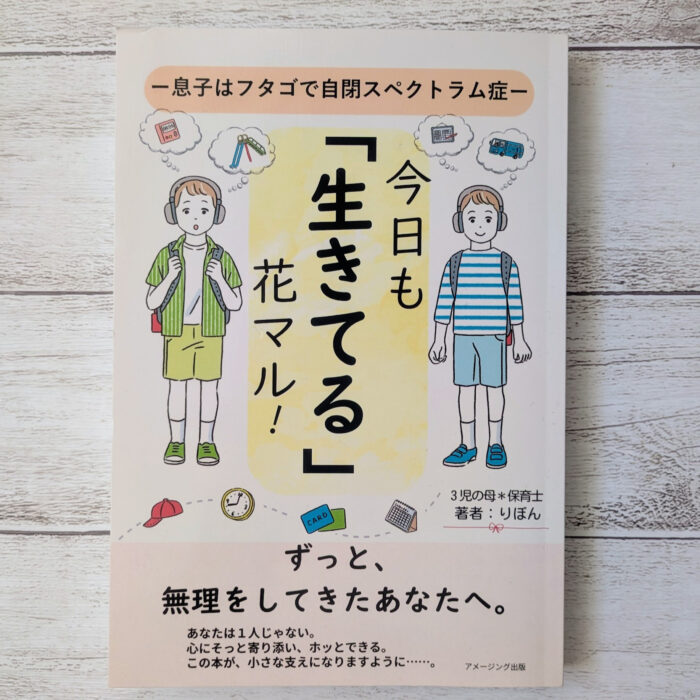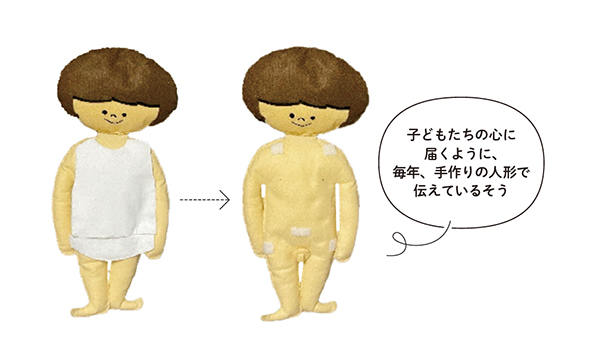更新 :
「ベビーベッド」VS「添い寝」どちらが子どもに良いの?

日本は添い寝文化が根強く、添い寝をしている家庭も多いですよね。一方で「ベビーベッドが最も安全」という情報を昨今、目にすることもあるかと思います。小児睡眠の専門家として、安全面・心・睡眠の質の3つの視点に分けて解説していきます。
安全面の視点
安全面の視点で言えば、ベビーベッドの安全性は高いです。赤ちゃん専用の寝床として作られており、親や他の家族の寝床と干渉しないように独立した空間が保たれるため、柔らかいもの(枕や掛け布団など)との接触を防ぐことができ、安全な空間を保つことができます。
また、赤ちゃんが寝ている間に突然亡くなってしまうSIDS(乳幼児突然死症候群)という怖い病気がありますが、その原因のひとつとして温めすぎ(過度な体温上昇)が関係していることがわかっています。
大人の毛布や掛け布団がかかってしまう恐れがあること、親子の体温同士が伝わって温めすぎになる可能性があり、これは添い寝におけるリスクとなります。
布団で寝る場合の安全面の解決方法として、ベビーサークルで布団を囲うという方法があります。わが家もこれを実践しているのですが、サークルの隙間から様子を見ることもできますし、手を伸ばせば触れることもできるので、添い寝の感覚は保ちつつも安全性を確保することができるおすすめの方法です。

心の視点
添い寝をしてもらうと安心して眠りやすい、という子どもは多いものです。実際に子どもの睡眠相談には「ベッドに連れてくるとよく眠ってくれる(けれども安全性が不安)」というお話をよく聞きます。スキンシップが取りやすいという面において、親子の安心感を生みやすいのが添い寝のメリットです。また、ママやパパにとっても、隣で子どもの寝息が感じられるのは安心感がある状態だと考えられます。
一方で子どもが眠ったと思った後に寝室から出てきてしまった…なんてことも。
睡眠の質の視点
ベビーベッドで寝かせている子どもが夜泣きをした場合、お世話をするのが大変というデメリットがあります。毎回抱き上げて授乳をしたり、抱っこをして揺らしたりするよりも、添い寝をしてトントンしたり添い乳してしまう方が大人の体への負担は少ないでしょう(添い乳は安全面の課題があります)。
一方で、添い寝の方がお世話しやすいゆえに、夜泣きしやすくなってしまうというケースも。すぐに反応してあやしてあげることで、子どもが自分の力で眠りに戻る習慣がつけづらくなります。また、少し成長して体が大きくなってくると寝相での干渉も睡眠の質に影響することが考えられます。
結論、どちらが良いのかは家庭次第。添い寝で体が触れ合うことを「幸せ」と感じる人もいれば「睡眠の質が下がる」と感じる人もいると思います。添い寝のままで朝までぐっすり、夜泣きなしを実現されている家庭もたくさん見てきました。
大切な赤ちゃんの安全面にだけは十分に気をつけていただきつつ、それぞれの家庭で良い形を探していただければと思います。
ナビゲーター