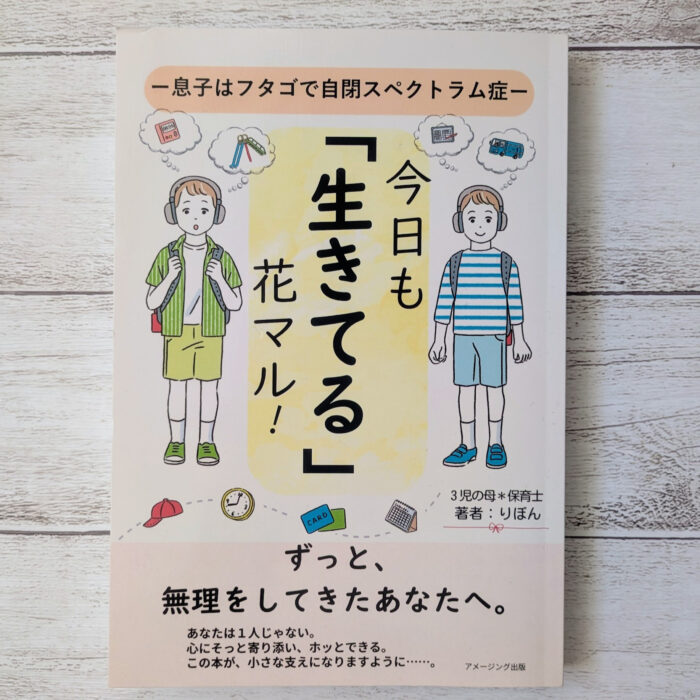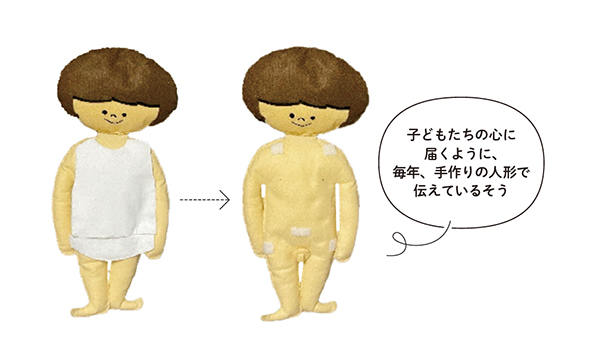更新 :
乱暴になってきた小4の息子「優しい子はいじめられる」と言います。どう対応したらいいですか?
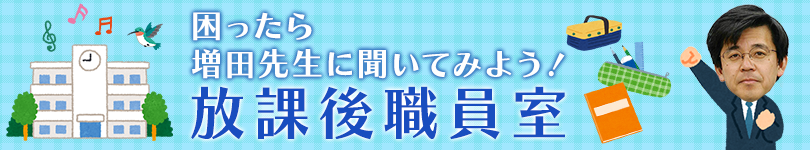
Q 友達の言葉づかいや態度をマネして、乱暴な子になってきました。どうしたらいいですか?
小4の息子が最近、まわりの友達の言葉づかいや態度をマネして、どんどん乱暴な子になってきています。人を思いやる気持ちも薄れてきていて、注意すると「みんなこんな感じだし、優しい子なんかいない。優しい子はいじめられるし、バカにされるんだよ」と言います。どう対応したらよいか悩んでいます(しず)
A 中学年が群れることと「仲間はずれ」に対する恐怖!

中学年は「ギャングエイジ」といわれ、友達同士で群れるようになります。この「群れる」という行為は、心の成長にとって欠かせないものです。もともと人間は群れをつくって生活することを好む傾向があります。このような傾向は「群居本能」あるいは「群居性」と呼ばれています。この「群居本能」があるからこそ、手段が成立するのです。
小学校中学年は「群居本能」をもとに、遊びを中心として群れを作り、意見のぶつかりあいや、楽しく過ごす経験を通して、社会性や創造性、協調性を育てていくのです。つまり、子どもにとって「群れて遊ぶ」ということは、「心のごはん」を食べているともいえるのです。
こうした群居性を成立させるためには儀式が必要です。その儀式としてよくあるのは、その集団に不可欠な行為をすることです。男の子の場合で一番多いのは、「乱暴な言葉づかい」をすることです。
ギャングエイジは自分達だけで何かを決めたり、大人に怒られそうなことをわざとやったり、自分達の集団の決まり事を作ったりします。また大人に見えない秘密を共有するようになるのです。
ですから、相談者さんのお子さんが乱暴な言葉づかいになるのも自然なのではないかと思います。そうした乱暴な言葉づかいをすることが、仲間であることの証明だからです。また、そうした仲間であることを証明しないと「仲間はずれ」になるという考えも背景にあります。
学級の担任に相談すると同時に家庭でも取り組む
ただ、人を思いやる行動や言動をすることは大切なことです。また、仲間への共有意識が強いがために人を傷つけるとするなら、それは許されることではありません。言葉は取り消すことのできない刃となって、人に突き刺さることがあるからです。
「優しい子なんていない」という言葉には、少しひっかかるものがあります。荒れた言葉が学級の中で行き交っていて、それが放置されているとするなら問題だと思います。そこには指導が絶対に必要です。
よく「チクチク言葉」とか、「ふわふわ言葉」などと言われていますが、「チクチク言葉」が多くなると、学級の雰囲気はとたんに悪くなります。また下手をすると、いじめが横行することにもなりかねません。
まずは担任の先生に、「子どもの言葉が荒いこと」「学級のみんなが思いやりをもった言葉なんて言わないとわが子が言っていること」を伝えて相談してみてください。
また家庭では、「たとえ荒い言葉をみんなが使っていたとしても、お母さんはそういうのはキライだな。まして人を傷つけることを言ったりしたら、絶対許せないな!」と話してほしいです。そして、「もし息子のあなたが、ほかのお友達にバカにされたら、相手にやり返したくなると思う。もし逆に、あなたやあなたの仲間が誰かを傷つけたとするなら、その子のお母さんはやり返したくなるほどの気持ちになると思うよ」と話してあげてください。
今の子ども達に必要なのは、相手の立場に立ってものを考えるのを教えることなのです。それが一番大切なのです。
【新刊】
新刊「子どものココロが見えるユーモア詩の世界-親・保育者・教師のための子ども理解ガイド-」(ぎょうせい、1980円)発売中。